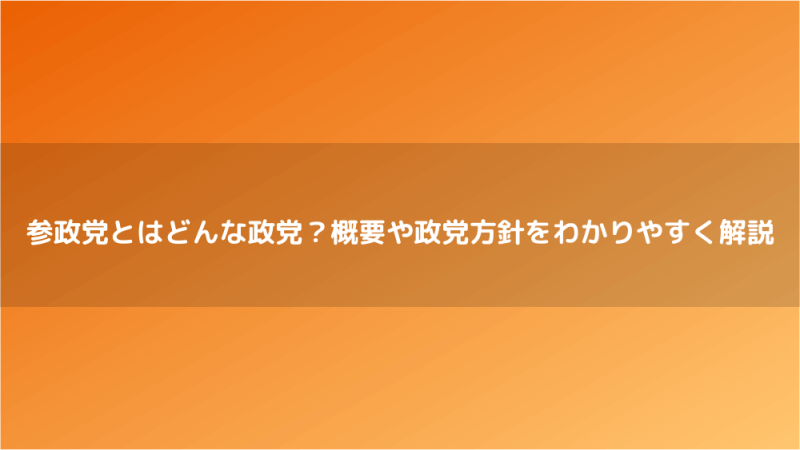三島はなぜ事件を起こしたのか
三島由紀夫は、戦後の日本文学界を代表する作家のひとりであるのと同時に、ノーベル文学賞候補に名前が挙がるなど、海外でも広くその才能が認められた作家でもありました。
少年時代からすでに持ち合わせていた才能は、川端康成や太宰治などとの交流の中で見事に花開き、「仮面の告白」「潮騒」「金閣寺」「鏡子の家」「憂国」「豊饒の海」といった作品を次々と発表。その名を広く知らしめます。
晩年は文学者であると同時に政治的な活動も活発化。現在の憲法を「国際政治の力関係によつて、きはめて政治的に押しつけられた」憲法であると批判、特に日本国憲法第9条をその内容通り忠実に遵守するならば、日本は他国から侵略されても「丸腰」でなければならず「国家として死ぬ」以外にはないと、自衛隊の国軍化を強く訴えるようになります。
また、日本はかねてから天皇をもって歴史、文化、伝統の中心として作り上げられた国とし、天皇を元首とする体制こそが政治あるいは政体の変化を超越する日本の国体と呼ばれるもので、現在はもちろん将来にわたっても天皇こそが絶対に守護されるべきものとの考えに至ります。
やがて陽明学の「知行合一」の思想のもと、自らの肉体を極限まで鍛え上げると自衛隊に体験入隊し、民兵組織である「楯の会」を結成。
1970年(昭和45年)11月25日、かねてからの計画通り、楯の会の会員4人と自衛隊市ヶ谷駐屯地(現在の防衛省)を訪れ、東部方面総監を監禁。市ヶ谷にいた自衛隊員を集合させると、バルコニーでクーデターを促す演説を行ったのち、割腹自殺を遂げました。
その目的は「自衛隊に直接呼びかけ、クーデターを起こし、自衛隊を国軍化させること」とされていますが、研究の結果、三島本人も本気でクーデターが成功するとは思っていなかったのではないかという説が有力視されています。
事件当日の流れ
事件当日、三島らは午前11時頃に自衛隊東部方面総監部玄関に到着します。
総監室に案内され、前日にアポイントを取っていた益田兼利東部方面総監に挨拶を済ませると、隊員のひとり小賀正義は総監の後ろに回り、総監の首を腕で締めるとハンカチで口をふさぎ、小川正洋らが両手を縛って椅子にくくりつけます。
総監室の異常な物音に気が付いた11名の幹部らは中に入ろうとしますが、三島は日本刀を振りかざし、「外に出ないと総監を殺す」と脅迫、室内に入った自衛官を斬りつけ追い返します。
11時30分頃、三島は「要求書がある。これを飲めば総監の命は助けてやる」と、窓ガラスから廊下に要求書を投げつけます。
この要求書で、全市ヶ谷駐屯地の自衛官を本館前に集めること、集まった自衛官は三島の演説を聞くこと、など6つの要求を行っています。
11時40分頃、自衛隊はマイクを通して市ヶ谷駐屯地内の自衛官全員に、本館前に集合するよう放送、約800名が前庭に集合しました。
11時50分頃、三島は「七生報国」のはちまきをし、日本刀を持ちバルコニーに立ちます。三島は、集合した自衛官に向かって演説を自身とともに行動し、クーデターを促す演説を始めましたが、自衛隊員のヤジと頭上を飛び交うヘリコプターの騒音で、現場にその声はほとんど届いていませんでした。
12時10分頃、演説を終え総監室に戻った三島は、「20分くらい話したんだな。あれでは聞こえなかったな」と独り言を漏らすと、総監に「恨みはありません。自衛隊を天皇にお返しするためです。こうするより仕方がなかったのです」と伝えると制服を脱ぎ、正座して短刀を両手に持ちます。
その場で三島は左脇腹に脇刀を突き刺し切腹。左後方にいた楯の会の会員の森田必勝は、介錯のために三島の頸部に2回刀を振り下ろしますが果たせず、3太刀目でも失敗。別の隊員に刀を渡すと、一太刀で三島の首を介錯しました。
三島に続き、かねてからの計画通り、森田も切腹。残った3名の隊員が、ふたりの遺体を仰向けに直して制服を掛け、両名の首を並べて合掌しました。
12時21分、残った3名の隊員は総監を縛ったロープを解き、総監室前に総監を連れ出て日本刀を自衛官に渡し、警察官に逮捕されています。
この事件は国内外に大きな衝撃をもたらしました。
事件から半世紀経った現在もなお、事件で命を落とした三島と森田の慰霊祭が続けられています。
事件当日、自衛隊員に向けて行われた三島の演説(ほぼ全文)
(「聞こえねーぞ」「もっとはっきりしゃべれ」等、演説前からヤジが続く)
私は、自衛隊に、このような状況で話すのは恥ずかしい。しかしながら、私は自衛隊というものに、この日本の……思ったから、こういうことを考えたんだ。
そもそも日本は経済的反映にうつつを抜かして、ついに精神的空白状態に陥って、政治はただ謀略、自己保身だけ。つくりあげられた体制は、何者に歪められたんだ! これは日本でだ、ただひとつ、日本人の魂を持っているのは自衛隊であるべきだ。我々は自衛隊に対して、日本人の根底にあるという気持ちを持って戦ったんだ。しかるにだ、我々は自衛隊というものに……心から……。
清聴しろ! 清聴! 清聴せい! 清聴せい!
自衛隊が日本の国軍……たる裏に、日本の大本を糺すということはないぞ、ということを我々が感じたからだ。それは日本の根本が歪んでいるんだ。それを気が付かないんだ。日本の根源の歪みに気が付かない。それでだ、その日本の歪みを糺すのが自衛隊。それがいかなる手段においてだ。
(ヤジが激しくなる)静聴せい! 静聴せい!
そのために我々は自衛隊の教えを乞うたんだ。静聴せいと言ったからわからんのか、静聴せい!
(「英雄気取りになっているんじゃない」とのヤジ)
しかるにだ、去年の10月21日だ。何が起こったか。去年の10月21日に何が起こったか。
去年の10月21日にはだ、新宿で反戦のデモが行われて、これが完全に警察力で制圧されたんだ。オレはあれを見た日に、これはいかんぞ、これで憲法が改正されない、と慨嘆したんだ。
なぜか、それを言おう。なぜか、それはだ。自民党というものはだ、自民党というものは、つねに警察権力によっていかなるデモも鎮圧できるという自信を持ったからだ。
治安出動はいらなくなったんだ。治安出動はいらなくなったんだ。治安出動がいらなくなったので、すでに憲法改正が不可能になったんだ。分かるか! この理屈が!
諸君は、去年の10・21からあと、諸君は去年の10・21からあとだ、もはや憲法を守る軍隊になってしまったんだよ。
自衛隊が20年間、血と涙で待った憲法改正ってものの機会はないんだよ。もうそれは政治的プログラムから外されたんだ、ついに外されたんだ、それは。
どうしてそれに気が付いてくれなかったんだ。
去年の10・21から1年間、オレは自衛隊が怒るのを待っていた。もうこれで憲法改正のチャンスはない! 自衛隊が国軍になる日はない! 建軍の本義はない! それを私はもっとも嘆いていたんだ。
自衛隊にとって建軍の本義とはなんだ。
日本を守ること。日本を守るとはなんだ。
日本を守るとは、天皇を中心とする歴史と文化の伝統を守ることだ。
お前ら聞け! 聞け! 興奮しない、話をしない、話をしない! 話を聞け! 男一匹が、命を懸けて諸君に訴えているんだぞ! いいか! いいか!
それがだ、いま、日本人がだ、ここでもって立ち上がらなければ、自衛隊が立ち上がらなきゃ、憲法改正ってものはないんだよ。
諸君は永久にだね、ただアメリカの軍隊になってしまうんだぞ。
諸君の任務というものを説明する。
アメリカからしかこないんだ。シビリアン・コントロール、シビリアン・コントロールに毒されてんだ。
シビリアン・コントロールというのはだな、新憲法下でこらえるのがシビリアン・コントロールじゃないぞ! どうしてそれが自衛隊……だ。
(ヤジが激しくなる)
そこでだ、オレは4年待ったんだよ。オレは4年待ったんだ。自衛隊が立ち上がる日を。
そうした自衛隊で4年待ったのは、最後の30分に……オレはいま待ってるんだよ。
諸君は武士だろう。諸君は武士だろう。
武士ならば、自分を否定する憲法をどうして守るんだ!
どうして自分を否定する憲法のため、自分らを否定する憲法というものにペコペコするんだ。
これがある限り諸君てものは、永久に救われんのだぞ。諸君は永久にだね。
今の憲法は政治的謀略で、諸君が合憲だかの如く装っているが、自衛隊は違憲なんだよ。自衛隊は違憲なんだ……。
憲法というものは、ついに自衛隊というものは、憲法を守る軍隊になったのだということに、どうして気が付かんのだ!
どうしてそこに気が付かんのだ!
そしてそこに縛られて気が付かんのだ!
オレは諸君がそれを立つ日を待ちに待ってたんだ。諸君はその中でもただ小さい根性ばっかりに惑わされて、ほんとうに日本のために立ち上がろうという気はないんだ。
(「そのために我々の総監を傷つけたのはどういうわけだ!」とのヤジ)
抵抗したからだ!
憲法のために、日本を骨なしにした憲法に従ってきた、ということを知らないのか!
諸君の中にひとりでもオレと一緒に起つやつはいないのか。ひとりでもいないんだな。よし! 武というものはだ、刀というものはなんだ。自分の使命と心に対して……それでも武士か! それでも武士か!
諸君は憲法改正のために立ち上がらないと見極めがついた。
これでオレの自衛隊に対する夢はなくなったんだ。
それではここで、オレは天皇陛下万歳を叫ぶ。
天皇陛下万歳!
(「降りろ!」「降ろせ、こんなの!」などのヤジ)
※参考資料:「決定版 三島由紀夫全集 36」/「三島由紀夫『日録』」安藤武編 、未知谷刊/「三島由紀夫事件 50年目の証言」西法太郎著、新潮社刊/「読売新聞」/「朝日新聞」

事件の第一報を伝える新聞記事(「読売新聞」昭和45年11月25日号夕刊)

七生報国のハチマキを締め、バルコニーで演説する三島(出典:「読売新聞」昭和45年11月25日号夕刊)