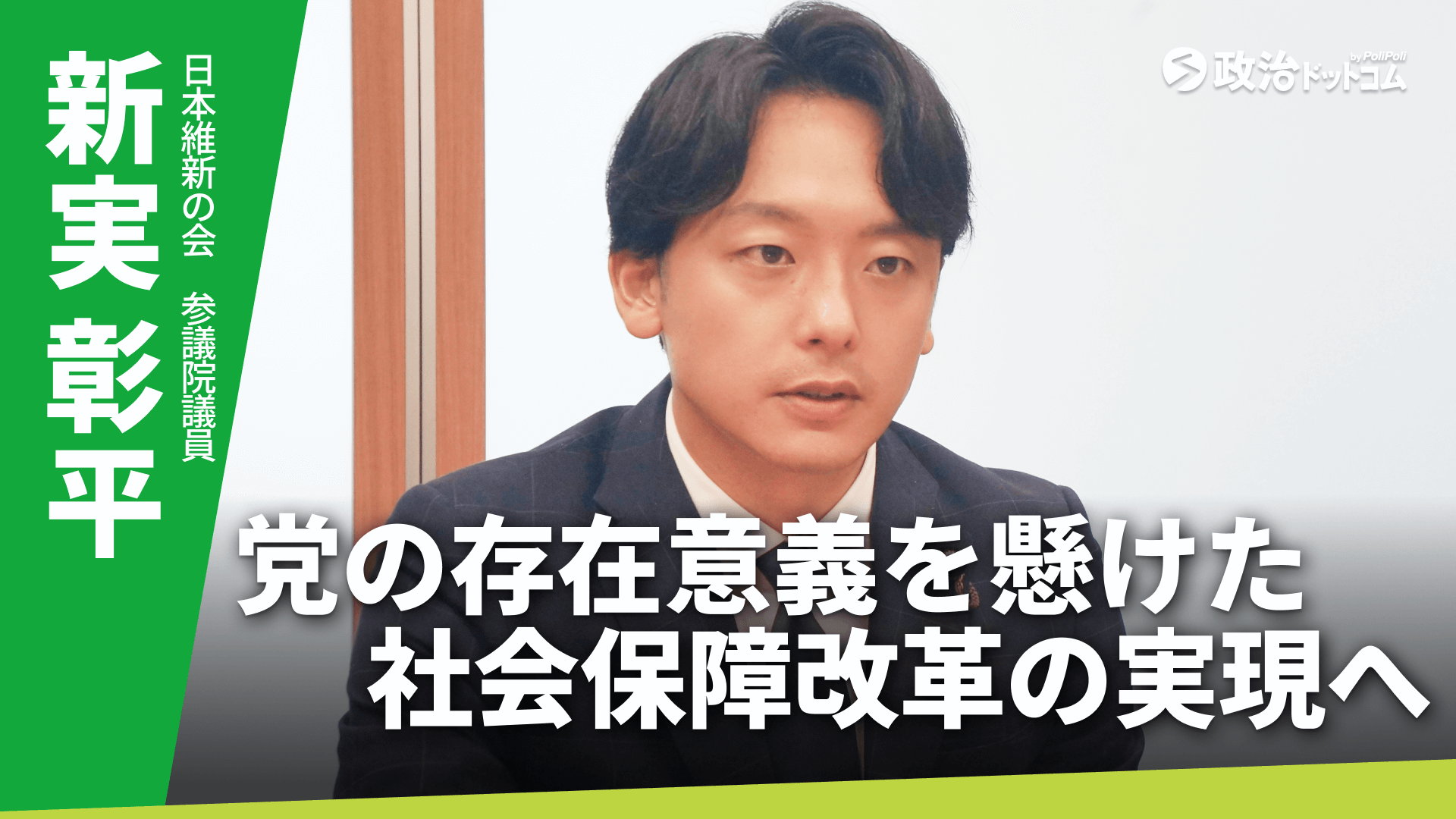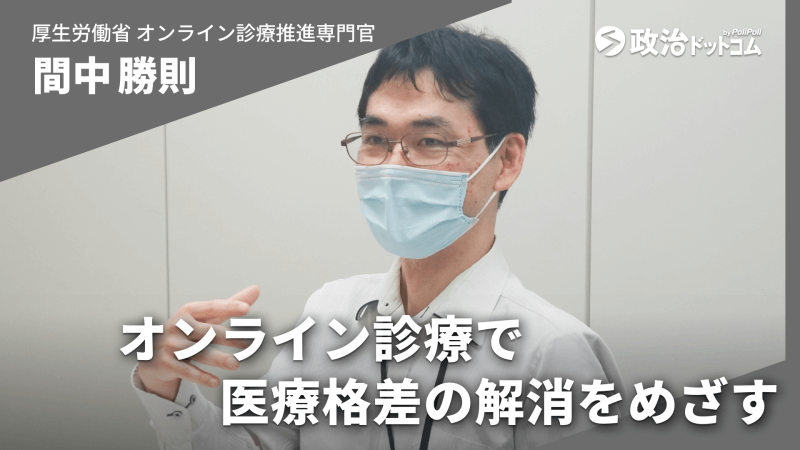新実 彰平 にいみ しょうへい 議員
1989年京都府生まれ。京都大学法学部を卒業後、関西テレビ入社。
アナウンサーとしてニュース番組やプロ野球中継に出演。
2024年に同社を退社し、日本維新の会の京都府選挙区支部長に就任。
2025年の第27回参議院議員選挙で初当選(1期)。
26年間続いた自公連立が終わりを迎え、日本の政治は新たな局面に入りました。日本維新の会は自民党との政策協議を経て、10月21日、高市総理大臣の下で「自維連立政権」に参画。政権与党として政策実現へ進むことになりました。
この歴史的な転換点の直前である10月8日、アナウンサーから政界に転身した日本維新の会の新実彰平議員にインタビューを実施しました。連立政権の一員として、今まさに実現を目指す社会保障改革や今後の展望について、当事者の言葉でお伝えします。
(取材日:2025年10月8日)
(文責:株式会社PoliPoli大森達郎)
「公に奉仕したい」がキャリアの原点
ー政治家になる前はアナウンサーとして活躍されていましたが、なぜアナウンサーを志したのでしょうか。
意外に思われるかもしれませんが、アナウンサーになりたいという夢は全くありませんでした。幼い頃から抱いていたのは「公に奉仕したい」という漠然とした思いで、大学時代は国家公務員も視野に入れていました。しかし、大学で野球に打ち込んでいたため公務員試験との両立が難しく、民間企業への就職に切り替えました。
就職活動では「公」を意識してインフラ業界を中心に見ており、テレビ局も「社会のインフラ」という視点で捉えていました。当初はディレクター職を志望していましたが、「会社の雰囲気を見るために」と何気なく受けたアナウンサー職の試験で適性を見いだしていただき、悩んだ末、アナウンサーとして入社しました。
人前に出る仕事には戸惑いもありましたが、「やってみてダメなら、異動願いを出そう」と割り切って、想定外のキャリアをスタートさせました。
ーアナウンサーとしてのキャリアを歩んでいく中で、政治家に転身されたきっかけは何だったのでしょうか。
「社会を良くしたい」という思いは常にあり、その選択肢の一つとして政治家にも関心はありましたが、入社6年目に夕方のニュース番組を担当することになり、社会課題をお伝えし、その解決を民主主義に委ねるという役割に、やりがいを感じながら働いていました。一方で、やればやるほどに、自らが直接その解決に関与しきれないもどかしさも募ってきました。そしてついに、立場を変える決意をした、という経緯です。
ー今年の参議院選挙で、日本維新の会から出馬したのはなぜでしょうか。
維新は「次世代に主眼を置いた稀有な政党」です。また、新自由主義的に見られがちですが、競争を促す前提として、きちんとセーフティーネットを整えることを重視しています。そして、理想を語るだけでなく実現するためのシビアな手段も厭わない政党である点も重要でした。理想の社会改革を実現するには、時にご批判を受けることを覚悟のうえで、丁寧な説明を尽くし、政策を断行する力強さが必要です。それができるのが維新だと考えたのです。
ー実際に政治家になってみて、以前のイメージとのギャップなどはありましたか。
激しい批判に晒されることや、衆人環視の状況は、想定の範囲内でした。前職時代に耐性ができていましたから(笑)。唯一想定外だったのは、お力添えを頂く人の多さです。選挙を戦い抜き、政策実現に近づくためには、あらゆる立場の方々にご協力を仰ぐ必要があります。
例えば、選挙でポスターを貼るだけでも、京都府内だけで6000ヶ所以上の掲示板に対応しなければなりません。当然、私一人では不可能で、何百人という支援者の方々のネットワークがあって初めて実現できるのです。そのスケールの大きさに、政治という仕事の重みと、ある種の参入障壁を感じています。

期待が失望に変わる、その緊張感の中で
ー実際に選挙戦を戦われて、どのような感想を持ちましたか。
非常に厳しい評価だったと受け止めています。維新が首長をお預かりしている大阪での政策実現への一定の評価は、私の選挙区であった京都を含む近隣府県にも波及していますが、全国的には「維新が国政で何をしてくれるのか」を明確に伝えきれませんでした。
厳しいお声もたくさん頂戴しました。特に党内の不祥事に対する非難の声が多かったように感じます。いくら良い改革を掲げても「信頼できない」という一言で全てが覆されてしまう。その言葉の重みを痛感し、反省するほかありませんでした。
その一方で、「改革者として、まだまだ頑張ってほしい」という温かい激励も頂きました。京都では維新への期待は薄いのではないか、と感じていただけに、「今こそ維新が必要だ」という声が想像以上に多かったことは大きな救いでした。しかしそれは同時に、一歩間違えれば期待が失望に変わるという緊張感とも隣り合わせです。
ー維新が掲げる「副首都構想」は、有権者に響いたという手応えはありますか。
私自身が演説で副首都構想を訴える機会は少なかったので、京都での訴求効果はまだ分析できていません。また、京都は長く都が置かれた歴史を持つ土地柄、「首都」というテーマに敏感な方もいらっしゃるかもしれません。そのあたりの府民感情は、これから丁寧に探っていく必要があります。ただ、私個人としては、日本の未来のために副首都は不可欠だと考えています。
ー国政での政策実現や、今後の党勢拡大に向けて、どのような姿勢が必要だと感じていますか。
教育無償化のように、議席をテコに政策を実現した実績はありますが、我々が本気で目指す社会保障改革は、そう簡単にはいきません。削るべきを削って、適正化を図るという話ですから、抵抗勢力も桁違いです。自民党との粘り強い交渉を通じて、一歩ずつ実現させていくしかありません。
そして、政策を実現した暁には、それによって国民の生活や次世代の未来がどう改善されたのかを、分かりやすく伝える努力が不可欠です。その積み重ねが、関西以外の地域にも維新の勢いを広げる力になると信じています。
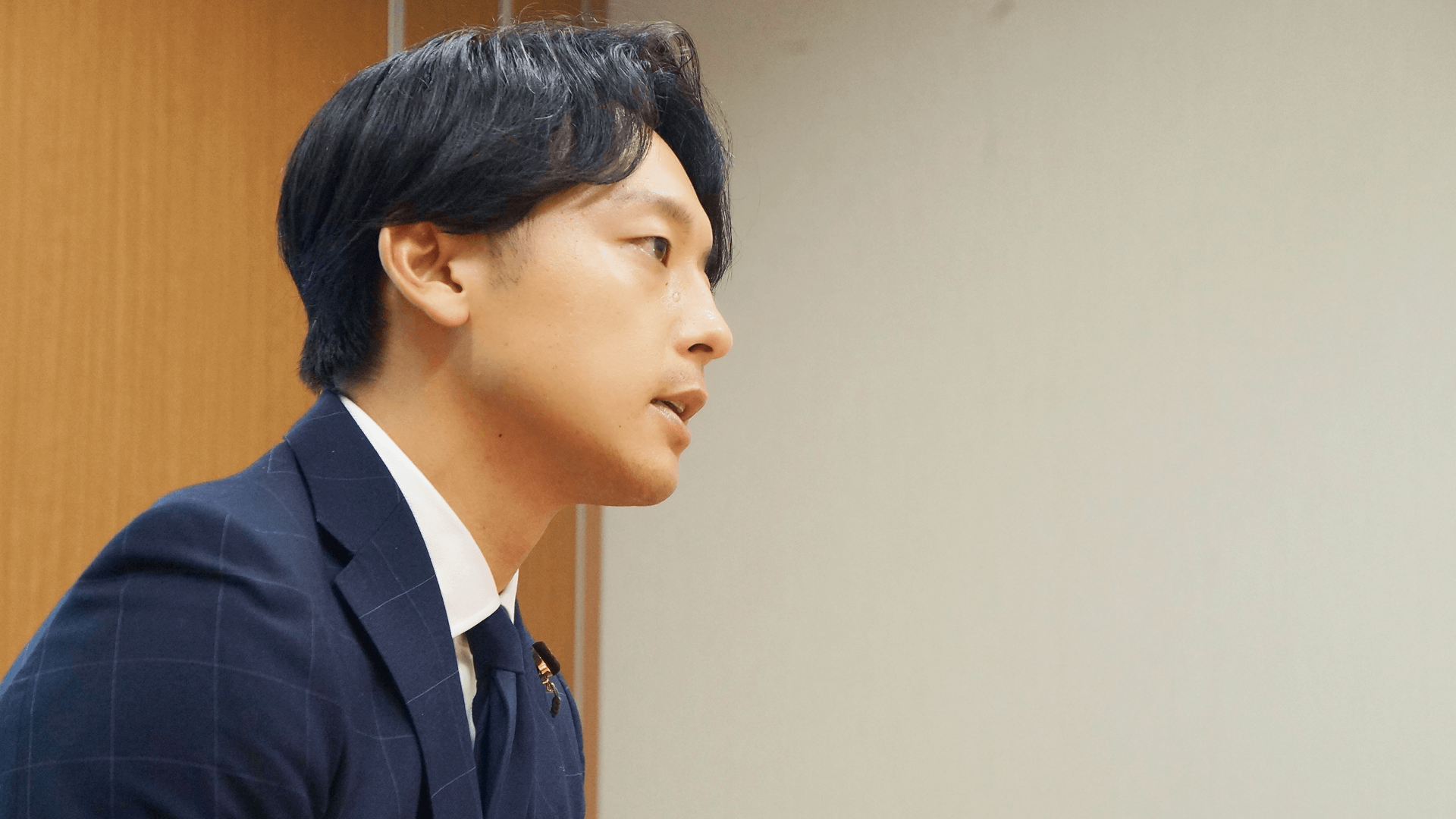
社会保障改革こそ、維新の存在意義
ー新実議員は1期生ながら国会議員団の広報局長という要職に就かれています。新人議員としての意気込みをお聞かせください。
素晴らしい先輩方が数多くいらっしゃるので、私の役割は、先輩議員が情報を発信する「場」を整えることだと考えています。政治に情熱を捧げる先輩方の言葉をいかに引き出すか。そこは、アナウンサーとしての私の経験が活かせるところです。政策とその実現への道のりを国民の皆様にご理解いただけるよう、チーム一丸となって効果的に伝えていきたいです。
ー新実議員個人として、特に力を入れて取り組みたい政策はなんでしょうか。
やはり社会保障制度改革です。これは日本の課題の縮図であり、少子高齢化が進む中で破綻に近づくことが分かりきっていながら、誰も手を付けられなかった問題です。そこに切り込める政党こそ維新であり、社会保障改革は維新の存在意義に直結する政策だと考えています。
そこには、以前から訴えている企業団体献金の禁止・見直しも、大きく関わってきます。今の仕組みが続いた方が得をする人たち、いわゆる既得権益層が、献金を通じて政治に影響力を行使して改革を阻んでいる、今の構造を変えることは、日本全体のイノベーションに繋がります。これらは密接にリンクした問題であり、両輪で突破していくことで、日本の明るい未来が拓けると信じています。

ー最後に今後の抱負をお願いします。
吉村代表も藤田共同代表も常々口にされていますが、私たちは社会課題を解決するために存在する政党です。その使命が果たせるなら、自分たちの立場がどうなろうと構わない。私もその一員として、「社会を良くするための政策を実現する」という一点のみを判断軸に、自らの行動を決めていきたいと思います。まだまだ学ぶべきことは多いですが、国政の場で与えられた責任を、全身全霊で全うしていく所存です。