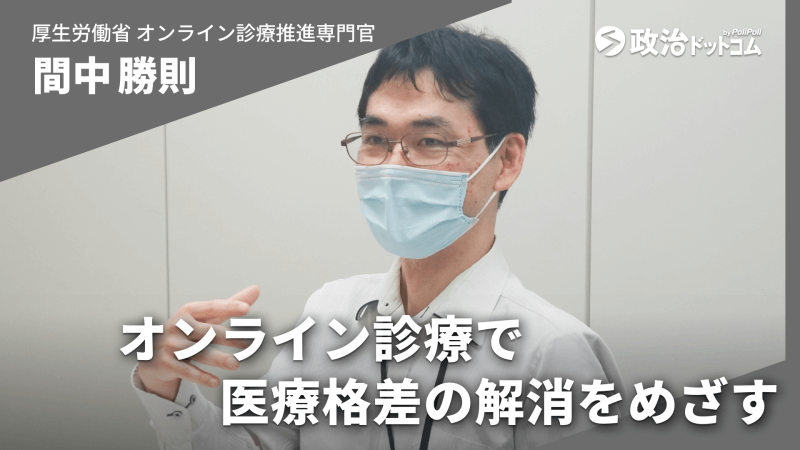福田かおる ふくだかおる 議員
1985年富山県高岡市生まれ。高校時代にアメリカの公立高校へ留学。
東京大学法学部に在学中、全国大学生環境活動コンテスト(ecocon)を
学生代表として主催。米国コロンビア大学国際公共政策大学院卒。
2008年、農林水産省に入省し2022年に退職。
衆議院議員・齋藤健の事務所秘書、法務大臣秘書官などを務め
2024年の衆議院議員選挙で東京18区から出馬し初当選(1期)。
日本人の主食である米の価格が高騰し、一時はスーパーの店頭から姿を消す騒ぎとなった「令和の米騒動」。備蓄米放出を巡る迷走や農林水産大臣の交代などの話題が連日ニュースをにぎわせ、「食の安心」に対する国民の意識も高まっています。今回のインタビューでは、農林水産省職員から政治家へ転身した福田かおる議員に、農業政策にかける思いをお聞きしました。
(取材日:2025年9月4日)
(文責:株式会社PoliPoli大森達郎)
派手なパフォーマンスよりも、地味でも粘り強い調整ができる政治家に

ー農林水産省という国家公務員としてのキャリアから、なぜ議員の側に行こうと思われたのでしょうか。
根底にあるのは「日本を良くしたい」という思いで、そのモチベーションは農水省時代も今も変わっていません。これまで20以上の国を訪れてきましたが、そのたびに「日本は本当にいい国だな」と感じてきました。働き者の方々がたくさんいて、社会も安定していて、実は楽しくて自由な国。しかし、日本に住む多くの方々が、この国の素晴らしさに誇りを持てていないことに、いつも悔しさを感じながら働いてきました。
入省間もない頃には「自分の力で社会は変えられない」と心が折れかけたこともありましたが、仲間を増やして力を合わせれば制度も社会も変えられる、ということがわかり、成果もあげられるようになってきました。
国家公務員として仕事ができるようになる中で、「省庁の枠を超えて、いろんな課題解決の役に立ちたい」という思いが湧いてきましたし、「政治が変われば、もっと社会を良い方向に変えられるのではないか」という思いも抱くようになったのです。
ー2024年の衆院選で初当選されましたが、官僚の立場も経験されている福田議員だからこそ感じる、政と官の違いなどはありますか?
政と官の役割分担が時代とともに変わってきたことを感じています。かつては政治家が大きな方向性を決めて「細部は官にお任せ」という大まかな役割分担がありました。
足元の課題解決をしているだけでは、日本の未来は切り拓けません。政治家は、大きなビジョンを描いて目指したい日本の姿を示すとともに、国家公務員の皆さんをリードしながら政策を実行していくマネジメント力も求められるようになっているのだと思います。
政策の実行は決して簡単ではありません。実行の過程では多くの調整が発生し、うまくいかなければ試行錯誤を繰り返して修正していくことも必要です。
派手なパフォーマンスではなく、地味な調整が実は政治家の大切な仕事です。私は官僚時代から「批判や提案ではなく、実行に向けた粘り強い調整もできる政治家が増えれば世の中は変わる」と考えていました。SNSの時代、政治家も発信力を求められるようになってはいますが、実務家、政策のプロフェッショナルとしての姿勢は、決して失うことのないようにしたいと考えています。
令和の米騒動は農業政策を巡る議論に火を付けた

ー米価格の高騰が大きな関心事になっていますが、農水省に勤務されていた福田議員は、どのように見られていますか。
私たちの年代で鮮烈に記憶に残っているのは1993年の米不足です。夏の冷害で収穫量が圧倒的に不足し、新米が多く出回る9月の翌月にあたる10月には、米が不足し、タイ米を緊急輸入した歴史があります。今回とは状況が違いますが、食料安全保障の観点から備蓄米の制度ができるなど、大きな転機となりました。
昨年発生した米不足は、緊急輸入が必要なレベルではありませんでしたが、政府が政策的にコントロールしてきた米の需給バランスのもろさを露呈する結果となりました。昨年8月の南海トラフ地震の臨時情報発出等に伴う突然の需要増加のようなイレギュラーな事態が発生すると、政策的に維持されてきた米の需給バランスは、ガタガタと崩れてしまうということが、浮き彫りになりました。
米の価格高騰については、「あらゆる物価が上がっているから仕方ない」とか「今までが安すぎたのでは」といった声もあります。しかし、国民の主食である米の価格が突然2倍になってしまうような事態は、やはり避けるべきでありました。この点でも、備蓄米放出の時期が遅れたこと、小売への流通が遅れたことなど、政府や政治の失敗があったと思っています。
日本の米政策は、50年以上にわたって米余り対策を主眼としてきました。日本人の米の消費量も減る中、減反や補助金による生産調整を通じて、主食用米の供給過多を緩和し、米価の下落を抑え、米農家を保護しようとしてきました。
昨年の米不足の原因の一端には、政府が需給バランスを読み誤ったことにあるという批判があります。事後対応が適切であったなら、急激な価格高騰は避けられたと考えていますが、いずれにせよ、米政策の見直しの議論が、今回の一連の出来事を契機に加速しています。令和6年の米価格高騰は、のちに農政・米生産の転換点になったと評価されることとなると考えています。
ー単純に米の増産へ舵を切れば良い、という話でもないのでしょうか。
昨年の米不足を受けて、今年は作付面積が増え、増産している状態です。忘れてはいけないのは、日本人の米の消費量は年々減少し、お米は余っている状態が続いてきた、ということです。「需給バランスなど気にせず、好きなだけ作ってください」という形にすると、価格が暴落して生産者の皆さんが困る事態になりかねません。
価格が下がったら、「補助金を出そう」とか「所得補償をしよう」ということをおっしゃる方もいますが、安易な制度設計は、さまざまな歪みを生み出します。
農業に限らず、人口減少と高齢化が急速に進み、これまでと同じことを続けていては、社会インフラの維持はできません。過去と同じことをするために、補助金等の公金をつぎ込むような政策を行ってはいけないと思っています。
稲作については、農地を集約して生産効率を上げるべきということが、1970年代から言われていました。高齢になった生産者の方々の引退も契機に、大規模化によって稲作の収益力を上げている若い生産者の方々も登場し始めています。「力強い農業経営をやっていこう」という次世代の意欲を削ぐような、安易な補助金政策は避けなければなりません。
ー「余った米を輸出する」という考え方もありますが、どのような意見をお持ちですか。
農水省時代に日本の農産物の輸出拡大をめざす政策も担当していました。イチゴやリンゴ、ブドウなどの輸出は実現・拡大してきましたが、米の輸出になると「価格的に無理でしょう」という声が多くありました。でも、海外市場を開拓している事業者の方々とお話していても、米も十分に可能性があると感じています。
実際、アメリカで水不足となった2021年の翌年には、カリフォルニア産米を埋め合わせる形で、日本からの米の輸出が増えた実績があります。こうした偶然の需要拡大ではなく、継続して輸出を拡大していくためには、規模拡大・コスト削減をして、海外のお米との価格差を縮めていく必要がありますし、買い叩かれないようにブランド価値も高めていかなければなりません。
この度の米価高騰は「従来のような生産調整は正しいのか」という議論に火を付けた側面もあります。生産量が増えれば、いずれは米価が下落していくことなります。お米の生産拡大の議論にあたっては、生産効率向上や海外販路拡大など、総合的に需給のあり方を考え直す契機にできればと思っています。
食料安全保障に必要なのは「国内生産の強化」と「戦略的な輸入」

ー福田議員が考える農業政策が目指す未来は何でしょうか。
10年後も20年後も、その先もずっと、所得に関係なく、おいしいものが食べられる、豊かな食生活が楽しめる社会を実現することだと思います。
ーその未来を実現する上での課題をどのように捉えていますか。
農業政策の複雑さをどうやって国民的理解にしていくか、ということは、いつも考えています。一つの課題が、普及しすぎてしまった「食料自給率」という指標です。特にカロリーベースの食料自給率は広く知られた指標で、38%という数字は、食料安全保障の危機感を煽るのに使いやすい側面があります。農林水産省も、かつて予算要求にあたって、説明に便利な指標として使ってきた側面があります。しかしながら、食料自給率は、日本の農業の課題を上手に表す指標とは言えないと考えています。
例えば、カロリーベースの食料自給率を上げたければ、野菜や果物などの低カロリーなものは作らず、とにかく米や芋といった高カロリーの作物を作れば良いのです。実際、農林水産省も、本当に食料安全保障の危機が発生した場合は、米や麦、芋などに作付けを変えて対応するというシミュレーションをしています。
しかし、平時において、米や芋だけを食べる生活は、望ましい食生活と言えるのでしょうか。ラーメンも食べたい、パンも好き、お肉も食べたい。誰もが日本の多様な食生活を楽しめる。しかも所得に関わらず食べたいものを食べられるような環境を維持していく。平時に考えなければならない食料政策の課題というのは、カロリーベースの食料自給率では表現できない課題なのです。
平時の食料供給を考えるに当たっては、「国内生産の強化」と「戦略的輸入」の両方を、同時に考える視点が必要です。
「国内生産の強化」を考えるに当たっては一つ重要な視点があります。それは、品目別に考えるということです。一言に農業と言っても、稲作と、野菜などの畑作と、果物で抱えている課題は全く異なります。例えば、先ほどお話したお米については、いかに大規模化をして生産効率をあげていくということが、長年の最重要課題です。食料自給率を高めるために、「稲作農家に補助金をつけてもっと農家を増やさなければ」とおっしゃる方がいます。これは全く逆で、安易な補助金政策で農地の集約が遅れれば、元気な稲作農家を苦しめることになるのです。
一方、大規模化が必ずしも有効打にならない場合もあります。特に大きいのは労働力の問題で、労働投入量が比較的少ないお米と異なり、野菜や果物はずっと多くの人手が必要になります。しかも、年間を通してずっと労働力が必要なわけではなく、特定の期間だけ人手が必要になる品目も少なくありません。だから、スポット的な人材の需要に応える仕組みをどう作るか、農閑期に労働力をどのように活用するか、という視点が「国内生産の強化」のために重要になってきます。
次は「戦略的輸入」についてです。農地があればなんでも作れる、とお考えになる方も少なくないのですが、作物にはやはり適地というものがあります。「パンやラーメンを食べたい」と思っても、日本では十分な量の小麦や大豆を生産できません。品種改良を重ねて国内でも品質の良い小麦や大豆の生産拡大にチャレンジしている方はいらっしゃいますが、国内の需要を満たすためには大部分をやはり輸入に頼らざるを得ないのが現実です。
輸入に依存しているのは農産物だけではありません。農業に必要な資材、例えば肥料の主要な原料である尿素、りん酸アンモニウム、塩化カリウムなどは、鉱物資源であり、そのほとんどを輸入に頼っています。2021年から2022年にかけ、肥料原料の多くの輸入元国である中国で、肥料原料の輸出検査が厳格化されたことを受けて、日本国内でも肥料供給の不安定化、価格高騰といったリスクが顕在化しました。
食料だけでなく、肥料やえさなどの農業資材もほとんど輸入に頼っている中、「戦略的輸入」については、安定的な輸入を継続できるよう、戦略を持って輸入元を多角化していくことが重要です。
「国内生産を強化する」という命題がある中で、政策として輸入のことを考えることは、タブー視されてきた部分もあったように思います。昨年の食料・農業・農村基本法の改正で主要課題と位置付けられ、「戦略的輸入」の政策検討は、やっと入り口に立ったところです。
輸入元を多角化・確保する際には、農業分野だけで不利な交渉をするのではなく、農業以外の製品・分野も含めてパッケージで俎上にのせて、交渉することが重要です。農業分野の主要輸入相手国との関係性を作りつつ、分野横断的な通商交渉を日頃から展開することが重要であり、経済安全保障の文脈の中に、農業分野も主体的に参画していくことが必要です。
ー食料政策は全国民の生活に影響するテーマだと思いますが、私たちが考えるべきことは何でしょうか。
できるだけ「幅広い」情報に触れていただければと思います。食料政策は、消費者である私たちの生活、農林水産業を営む方々の生活、そして製造や流通に関わるたくさんの方々の生活に関わる政策分野です。まさに、日本の社会構造を紐解いていくような政策分野だと理解しています。
農水省入省後、同期とともに、全国各地を回って、生産者さんや農業関係者の方々の話を聞いてまわりました。さまざまな立場の方から異なる意見を伺う中で、課題の複雑さやボトルネックが、社会の仕組みの一部として、少しずつ理解できるようになっていきました。
今はネットメディアを通じて多くの情報が飛び交っており、ニュースや政治家の発信だけでなく、生産者さん自身の作物や経営に対する思いなどの発信にも触れることができます。良いと思った意見があれば、反対意見も必ず確認するなど、意識的に異なる情報を取り入れていただき、いま、どのようなことが起こっているのか、何を改善しようとしている政策なのか、その政策の是非はどうなのか、判断いただくことが大切だと思います。
また、毎日の消費行動そのものが、日本の農業の支えとなります。「この農家さんを応援したいから、買ってみよう」「おいしかったので、少し高いけど、もう一度買おう」といった行動のひとつひとつが、日本の農業生産の未来につながることになります。
暗い展望を反転させ、日本に自信を取り戻す

ー最後に政治家として描かれているビジョンや、今後の目標を教えてください。
これから日本では急速に人口構造が変化していきます。急激な変化によって、制度や現場にさまざまな歪みが出てくると思います。安全保障のリスクの増大や、大規模災害の発生などへの懸念の声もあり、厳しい時代が待っていると予感している方は少なくないと思います。
ただ、この状況はいずれ必ず反転します。農業の構造転換、医療や年金といった社会保障制度の改革など、先送りになっている問題に、粘り強く取り組み、安定した社会を次の世代につないでいく。本来、日本はとっても自由で楽しい国です。明るい展望が描ける社会へとつなぐこと、将来にむけて時代に合わなくなった仕組みを一つずつ直していくことが、私の使命だと思っています。最初にお話しした「地味な調整役」をしっかりこなし、ひとつずつ課題を解決していきたいと考えています。