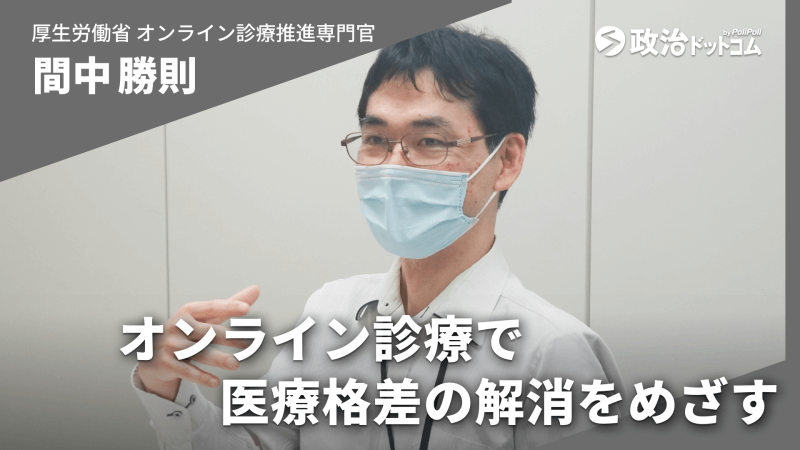井上信治 いのうえ・しんじ 議員
1969年 東京都出身 東京大学法学部を卒業後、建設省(当時)入省
2003年 衆議院議員選挙に自由民主党公認で立候補し初当選(8期)
2012年 第2次安倍内閣で環境副大臣と内閣府副大臣に任命
2020年 初代国際博覧会担当大臣、内閣府特命担当大臣として入閣
世界経済フォーラムの試算によると、宇宙産業の世界市場は2035年に1兆8000億ドルまで拡大すると予測されています。参入する国家の顔ぶれが多様化する一方、国家主導で進めてきた宇宙開発は民間企業が主役の時代へ。今回のインタビューでは、特命担当大臣として宇宙開発に力を注いできた井上信治議員に、日本の宇宙戦略の展望をお聞きしました。
(取材日:2024年9月26日)
(文責:株式会社PoliPoli 河村勇紀)
目の前の一人だけではなく、より多くの人を幸せにしたい

ーまずは井上議員が政治に興味を持たれたきっかけを教えてください。
実をいうと私は医者の家系の生まれで、両親もきょうだいも眼科医です。だから私も子ども時代は漠然と医者になる夢を持っていました。そして高校時代に具体的な進路を考えたとき、「医者になって多くの人を救いたい」と思う一方で、「目の前の患者さんしか救うことができないのでは?」という葛藤がありました。
もちろん、目の前の一人を救うことは非常に貴重なことですが、やはり「一生かけて何人の人を救えるんだろう?」という疑問が消えませんでした。「より多くの人を救って幸せにするには?」と考えたときに、政治家になって国づくりをすべきだと思ったわけです。
ー高校生の頃にはもう政治家を志していたのですね。卒業後は東京大学を経て当時の建設省に入られていますが、どのようなロードマップを描かれていたのでしょうか。
家族はみんな医者で政治家は1人もいませんから、政治家になる方法がわかりませんでした。ただ、当時は「政治家になるために、まず役人になる」というルートが一般的だったので役人をめざしたわけです。特に日本は政治と行政が非常に近いので、勉強になると思っていました。2001年に建設省が国土交通省に変わり、その2年後の2003年に退官して衆院選に立候補することになりました。さまざまなご縁があって東京25区から出馬しましたが、国会議員になるとはいえ「地元を大切にして、地元を良くしたい」という思いが強くなったのを覚えています。
ー2003年に初当選されましたが、政治家として大切にしてきたポリシーは何でしょうか。
最初は、医師の家系出身ということもあって社会保障を中心に活動していましたが、できるだけ幅広い分野に関わるようにしてきました。単なる一分野の専門家になるのではなく、「どんな分野でも困っている人をなるべく多く助けて幸せにしたい」という思いが原点にあり、ずっと貫いてきたポリシーです。
追い越された日本…官民一丸で宇宙ビジネスに挑戦を

ー井上議員は2020年に入閣された際、宇宙担当の特命担当大臣を務められました。今回のインタビューでは宇宙政策について深掘りしたいと思います。
それまで宇宙関連の政策にあまり関わってこなかったのですが、いざ関わってみると宇宙は非常にポテンシャルの高い重要な分野だと実感しました。日進月歩で技術もどんどん進化しています。宇宙はもともと、科学探査という科学の分野からスタートしましたが、いまや安全保障、防災、交通、農業、建設、通信もそうですし、生活にかかわる様々な分野で重要な役割を果たしています。
5月に「宇宙ビジネス新時代での官民一丸となった挑戦に向けた提言」を提出し、そこでは民間企業と密に協力しながら宇宙の活用方法を広げていく方針を掲げています。ご存じのように、アメリカではスペースXのような革新的な企業が宇宙開発をリードしています。日本ではこれまでJAXAが宇宙政策の実行を担っていましたが、それだけでは限界があるので、スタートアップ企業などのすぐれた技術をもっと生かすための提言を盛り込んでいます。
提言の中には、宇宙開発で得られた知見を研究や産業創出だけでなく、安全保障や防災にも活用するデュアルユースの考え方を盛り込んでいます。今はアメリカだけでなくヨーロッパやインド、中東なども宇宙に力を入れているので、日本も重点施策として進めていく必要があります。
ー日本は宇宙開発で「遅れている」と言われることもありますが、この点はどのように見られていますか。
「遅れている」というよりもむしろ「追い越された」という感覚ですね。それだけ、ここ数年の各国の動きが速いのだと思います。民間企業の意思決定も非常に速いので、日本もキャッチアップしていかないと厳しい状況になると思います。
ー日本が宇宙競争で勝つために力を入れるべき分野はありますか。
ひと言で「宇宙」といっても非常に幅広く、最終的にはすべてに力を入れる必要があります。その中でも先行しているものを挙げると、有名なのは「はやぶさ」のサンプルリターンですね。あれは世界でも画期的なことです。他には「スリム」(※SLIM=Smart Lander for Investigating Moon)というピンポイントの月面着陸技術。来たるアルテミス計画では、日本は「有人与圧ローバー」といって宇宙飛行士が乗り込んでローバー内で生活しながら、天体表面を探査することができる探査車を担当します。またスペースデブリの処理においては日本企業がトップを走っています。
逆に、これから力を入れなければならないのが、ロケットの打ち上げ技術です。官製ロケットではJAXAが実績を作ってきましたが、民間ロケットがまだ少ないですよね。昨年の統計では世界で253回の打ち上げがありましたが、そのうち日本は5回のみです。スペースXだけで130回くらい打ち上げていますよ。打ち上げは海外に頼り、そのロケットで運んでもらう形でもいいのですが、やはり日本のロケットで日本の衛星を打ちあげたいですよね。
ーそのためには、どのようなインフラが必要なのでしょうか。
やはり発射場です。現在はJAXAの発射場が2か所ありますが、これでは本格的に打ち上げ回数を増やすことはできません。北海道や和歌山など、民間企業や地方自治体が発射場を作っているケースもありますが、財政的に厳しいのが現状です。やはり、このようなインフラ整備は国が支援する必要があるでしょう。
国が本気を見せないと民間企業もチャレンジできない

ー民間の宇宙ビジネスを活性化させるためには、どんな施策が必要でしょうか。
やはり「国は宇宙政策を本気で推進するんだ、俺たちのことを支援してくれるんだ」っていうことを分かってもらうことですね。アメリカのスペースXが成長した背景には政府調達があります。民間のために国が発注して資金を流していく仕組みは非常に有益で、そのために日本でも総額1兆円の宇宙戦略基金を設立しました。毎年度の予算も1兆円を目指しています。本当にそれくらいの規模が必要です。
また組織面では、将来的に「宇宙庁」の設立を考えています。これは以前から自民党が唱えていることですが、やはり大きな産業を動かすには司令塔が必要です。今も内閣府に宇宙事務局があり、職員の皆さんが本当に頑張っておられますが、文科省、経産省、防衛省などの取りまとめ役になっているのが現状です。それではスピード感が生まれません。
そして、もっとも重要な施策といえるのが法整備です。この先、有人宇宙探査や宇宙旅行など、宇宙との関わり方も多様化していくと思います。それらの法的環境を整えるのは立法府の責任です。資金、組織、法律という3つの環境整備を国が推進し、「本気で宇宙事業をバックアップする」という姿勢を示せば、民間企業も思い切ってリスクテイクすることができるのではないでしょうか。
ー日本は、国際的な舞台でどのような役割を果たしていくべきでしょうか。
宇宙の分野は、国際的に成熟してないため国際的なルールづくりをしなければいけません 。スペースデブリの問題もそうですし、宇宙の資源をどうするのか、例えば月には我々が知らないような資源があって、本当に宝箱のような場所かもしれません。その資源を早い者勝ちでいいのかと。また、衛星の破壊実験など平和安全の面でもルールが必要です。開発を促進するためにもルールがあっての国際競争だと思います。そういう世界の公平なルール作りで日本は主導的な役割をはたしていくことができると思います。
子どもたちに夢を「宇宙は最後のフロンティア」

ー宇宙政策を推進する上で、将来的な展望をどのように描かれていますか。
私が所属している党の委員会は「宇宙・海洋開発特別委員会」といって、宇宙だけでなく海洋も含んでいます。宇宙と海洋というのは「人類に残された最後のフロンティア」です。このポテンシャルを十分に生かすことを考えなければなりません。
それに加えて、大切なのは、「子どもたちに夢を与えること」です。昔は子どもたちが将来なりたい職業の中で「宇宙飛行士」は定番でした。これからのポテンシャル考えたら、今の子どもたちにもそうに思ってもらいたいんです。画期的なこととして、アルテミス計画で、2020年代後半、2030年までに日本人の宇宙飛行士が月面着陸をすることをアメリカと約束をしました。これを絶対に実現して、それを見た子どもたちが感動して、宇宙に興味を持ってもらいたいです。今、将来的に夢のある楽しい話がなかなかない時代だからこそ、私は、宇宙には大きな夢がある、そう思って力を入れています。
ー壮大な宇宙の夢を実現するためにも、政治がしっかり機能することが重要だと思います。最後に、めざすべき政治のあり方についてご意見をいただけますでしょうか。
今、特に物価高で国民の暮らしが厳しいから、どうしてもこの目の前のことを政治はやらなければいけない。予算もそこにかけなければいけない。暮らしを守るのは政治家にとって、とても大切なことです。
一方で、宇宙をはじめとする科学技術分野は、短期的にリターンが見えにくい、長期的でリスクもあります。そういう意味では、国民に対して、何がメリットかを分かりやすく説明していくことが政治の役割だと思います。インターネットもGPSも宇宙技術です。あれがなかったら今の社会は全く違いますよね。それぐらい宇宙の技術は、世の中を変えるポテンシャルがあるわけです。これから、自動運転やスマート農業だとか、防災でも能登半島地震の際に衛星の画像をもとに様々な対策をとりました。
そういったことは目に見えないから、分かりにくいけれども、必要性や重要性を丁寧に説明して、国民の理解をいただく努力をしなければいけないと思っています。そういう分野だからこそ国が応援しなければいけないし、政治家は、長期的なスパンで、国の未来、世界の未来を考えた時に、何が必要なのかを見極めて、国民に夢のある話をしたいという思いがあります。