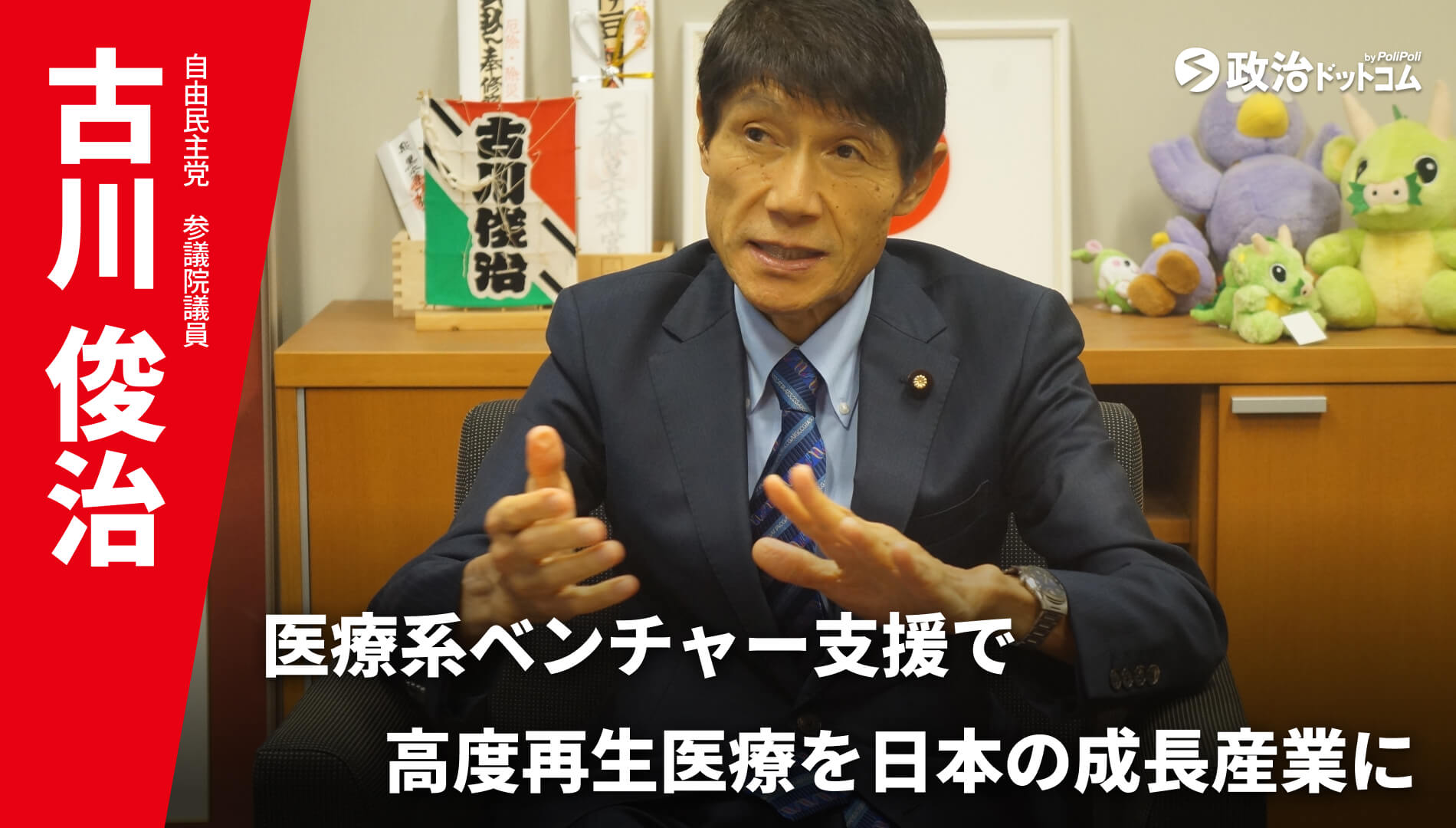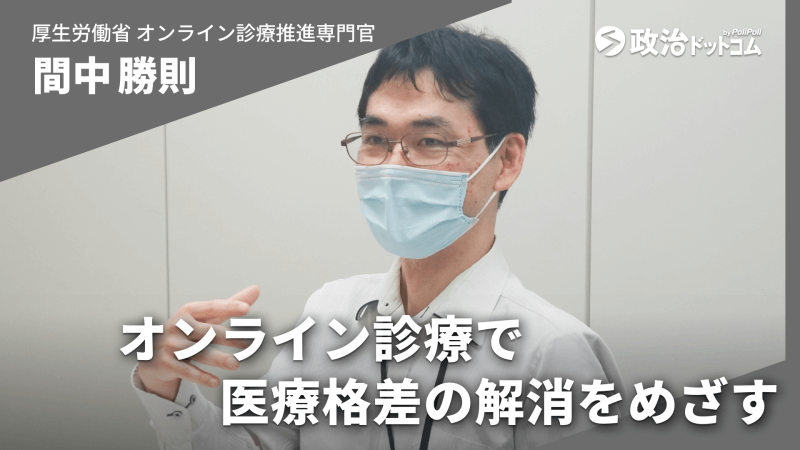古川俊治 ふるかわ・としはる 議員
1963年 埼玉県出身 慶應義塾大学医学部を卒業後、1994年 医学博士
1996年 同大学法学部を卒業し、司法試験に合格
医療ベンチャーの設立や先端医療手術の開発などに尽力
2007年 参議院議員選挙で初当選(4期)
自民党厚生労働部会長、法務部長などを歴任
iPS細胞の研究開発で先行しながらも、再生医療や創薬の分野を成長産業にまでつなげられていない日本。一方、足元では少子高齢化に伴い、社会保障制度の土台が揺らいでいます。今回のインタビューでは、医師であり弁護士でもある古川俊治議員に、医療産業の課題、再生医療を中心に今後の日本が描くべき成長戦略をお聞きしました。
(取材日:2024年9月22日)
(文責:株式会社PoliPoli 河村勇紀 )
医療の世界で抱いた倫理と法律への問題意識

ー古川議員は医学部を卒業後、司法試験にも合格されていますが、当初はどのようなキャリアを思い描いていたのでしょうか。
医学部を出た後は慶応義塾大学病院の外科専門医として修行を積んでいましたが、だんだん生命倫理や法律について悩むことが多くなってきました。例えば臓器移植。当時の日本では脳死が認められていなかったために臓器移植ができませんでした。だから移植が必要な人は海外に行くしかなかったわけです。
日本には十分な移植技術があるのに、海外に行かないと手術を受けられないなんておかしい。そんな思いを胸に解決の道を探っていたら、倫理や法律を学ぶ必要が出てきたのです。それで外科医と並行して法学部の学位も通信課程で取ることにしました。
ー弁護士資格を取得したのはどんな思いからなんでしょうか。
法律を学んだ際に、知識として「知っているだけでなく、実務を身につけないと意味がない」ということを感じたのです。当時、アメリカでは新しい医療技術に関して弁護士が干渉するような事例もあったので、私も同じレベルで法律を扱えるようになりたいと思ったわけです。それで司法試験を受けた後、弁護士事務所で一定の実務経験を積みました。
ーその後、政治家になるまでの期間は幅広い活動をされています。
そうですね。1999年に弁護士登録したのですが、その後は大学の医学部に戻り、後進の指導や新しい医療技術の開発に関わっていました。ちょうど「ダヴィンチ」という手術支援ロボットが日本に導入されようとしていた時期で、日本初のダヴィンチでの手術を私が主導することになりました。
このダヴィンチは遠隔での手術を可能にするロボットで、例えば日本にいながらアメリカの患者さんを手術することもできます。実際に、アメリカにいる医師がフランスの患者を手術した事例もあります。ただ当時の日本では医療事故が世間の耳目を集めていたこともあり、「これで事故が起こったら法的な責任はどうなるのか?」といった問題もありました。医療にも法律にも詳しい、ということで私もいろいろな場に呼ばれ、制度設計に関わりました。
そんな中、地元埼玉で医師から国会議員になった方が引退する、という話があり、後任の候補も「医師がいい」とのことで私に出馬の依頼がありました。アメリカに比べて基礎研究が遅れていることや、医師不足の問題など、私も日本の医療と法律に対してさまざまな課題感を持っていたため、政治家をめざすことになったのです。
再生医療の普及にはバイオベンチャー成功が不可欠

ー政治家になる前に、再生医療を含む技術開発のベンチャーを設立されていますが、日本における再生医療の可能性について、どのように見られていますか。
これまでに再生医療関連のベンチャーを3社立ち上げています。再生医療の研究者、そして実用化を推進する事業家という立場から見ると、いかに再生医療を推進するための政策のパーツが足りていないかがよくわかります。
再生医療と言っても、細胞医療やiPSを使った臓器再建などいくつかに分類されます。細胞医療というのは、細胞から出てくる何らかの因子によって体の回復させる治療方法です。患者の細胞を培養して戻してあげると、いろんな数値が改善するという研究がたくさん出ています。もう一つが文字通り臓器を再生する方法で臓器再建型。これは脊髄損傷やアルツハイマーなどの患者さんに対して、神経細胞を再生することによって回復を目指す方法も臨床試験が行われています。
一方で、リスクが高い研究に対しては、大手の製薬会社はなかなか手を出せない部分もあります。再生医療では次々とバイオベンチャーが出てきて研究開発をしていますが、新しいベンチャーを生む流れを止めないことが重要です。そのためには、ベンチャーを作るだけではなくて、出口まで行くことが大切です。つまり、しっかり成功させて産業化させて行かなければなりません。
ーバイオベンチャーを成功させる上で課題や障壁はなんでしょうか。
ずばり、資金調達です。今は大学でベンチャーを支援する仕組みも増えていますが、創薬の分野で最終試験まで到達するには100億から200億円くらいの研究開発資金が必要になります。残念ながら日本の市場では、ベンチャー投資に対してそこまでのパワーがありません。アメリカではM&Aが一般的ですが、日本は勇気のある事業会社が少ないので、バイオベンチャーが大きな資金調達をしようと思ったら、苦し紛れにIPO(新規上場)することになります。これでは、リスクの大きい医療や創薬の分野でベンチャーがなかなか育ちません。
特に、上場前に企業価値が10億ドルを超える「ユニコーン」には、国内市場だけを見ている限り到達しないでしょう。日本だけでは市場が小さすぎるからです。最初から海外展開を見据え、北米とヨーロッパの市場を開拓して初めて500億から1000億円の企業価値になるのです。

ー日本はiPS細胞の分野で先行しているので、海外でも勝てそうなイメージがあります。
ただ、多くのベンチャーが海外での開発計画や方針を持たないままIPO(新規上場)してしまっています。その点を克服できるような支援体制を整えようと、いま動いているところです。進出した先での事業展開の目途が立ち、現地の投資家からの資金が得られるようになれば、勝てる見込みは大きくなるでしょう。
くわえて、海外から日本への投資を呼び込むことも必要です。日本のベンチャーキャピタルの規模感では、薬の開発に必要な資金は集まりません。そこが一番の問題かもしれません。
ー確かに、スタートアップ投資の規模感を見ると、アメリカは日本よりケタが1つも2つも多いですね。
ベンチャーキャピタルの投資のスパンが基本的に10年で、その間に投資を回収してリターンを出さないといけません。でも10年では難しい。一方でアメリカではセカンダリー取引が普及しているので、もう少し長いスパンで成長戦略を描けるのです。日本でもこの制度を根付かせる必要があります。あとは事業会社によるM&Aの支援も打開策のひとつになると思いますが、まだまだこれからです。
ー日本は医療機器や薬事の承認にすごく時間がかかるイメージがあるのですが、その点もベンチャー育成の障壁になっているのでしょうか。
いや、本当にすぐれた製品が生まれれば、それなりのスピードで市場に出ると思います。確かに臨床試験に割と時間がかかる側面もありますが、どちらかといえば、本当にすぐれた製品が生み出せないことが要因です。
経済成長の鍵は再生医療の輸出産業化と高齢者活躍

ー日本は医療や社会保険の分野で進んでいると言われますが、古川議員の目にはどのように映っていますか。
これまでは「進んでいる」と言われてきましたが、ご存じのように今は若い世代の負担が増えすぎている状況です。「これ以上、税金も社会保険料も払いたくない」という人も多く、徐々に社会保険制度そのものが成り立たなくなっていく可能性もあります。そうなると、必然的に患者さんの自己負担を増やしていく必要があります。
再生医療も、保険適用でやるとしても高い価格がつかなければ、みんなビジネスをやめてしまって、誰も開発できなくなってしまいます。
これは国民的な議論をしっかりしないと、誰もこの負担からは逃げられません。医療機器を作るにも薬を作るにも巨額の投資が必要なので、販売価格が安ければ事業が成り立たない、という現実も考慮する必要があります。今の制度を維持しようとすれば現役世代の負担が増えるし、負担を減らせば治療を受けられなくなる高齢者が増えます。この二極対立を調整できないまま今に至っているのです。
自己負担を増やせば厳しい社会になってきます、そこを是とするかどうか。再生医療を受けられる人は一部になる、本当はそれでいいのかどうか、今後考えなればいけない。
日本の中でも、これから新しいものを作っていく、例えば、創薬力などを強化しようと思えば当然、新しい研究開発や技術には資金がかかるので、利用する方にとって価格は高くなってしまいます。それでも最終的に、輸出産業として日本の経済成長につなげていくためには、そこは高い価格になったとしても踏ん張って、再生医療を発展させていきたいという思いがあります。
ー社会保険制度が揺らいでいる背景には少子高齢化もありますが、これからの日本の成長戦略をどのように考えておられますか。
まずは、医療や創薬を日本の輸出産業にする必要があると思っています。せっかく苦労してiPS細胞を実用化させたわけですから、これを外貨獲得の手段として経済成長に結びつける戦略は間違いなく必要ですね。
また、これからロボティクスが発達する中で、高齢者が働ける期間も延びると思います。在職老齢年金を見直し、高齢者にもどんどん社会で活躍していただいて生きがいを持ってもらう。その仕組みを整えれば、今後アジア全体の高齢化が進む中で日本が先行モデルとなり、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性もあるのです。
ーそのような未来を実現するためにも、これから注力すべきことを最後に教えてください。
やはり半導体とAIではないでしょうか。自前の半導体、自前の生成AIを開発し、日本中みんなで使えるようにしていくことです。それでバックオフィス業務がどんどん自動化され、人間は人にしかできないフロントの業務に集中して生産性を上げることができます。
これは、先ほど申し上げた高齢者の労働も可能にします。さらに、創薬の基礎研究に必要な分子構造の解析も、AIを使えば大幅に期間を短縮できます。日本は技術立国で成長してきた国なので、やはり技術に賭ける姿勢が必要ではないでしょうか。