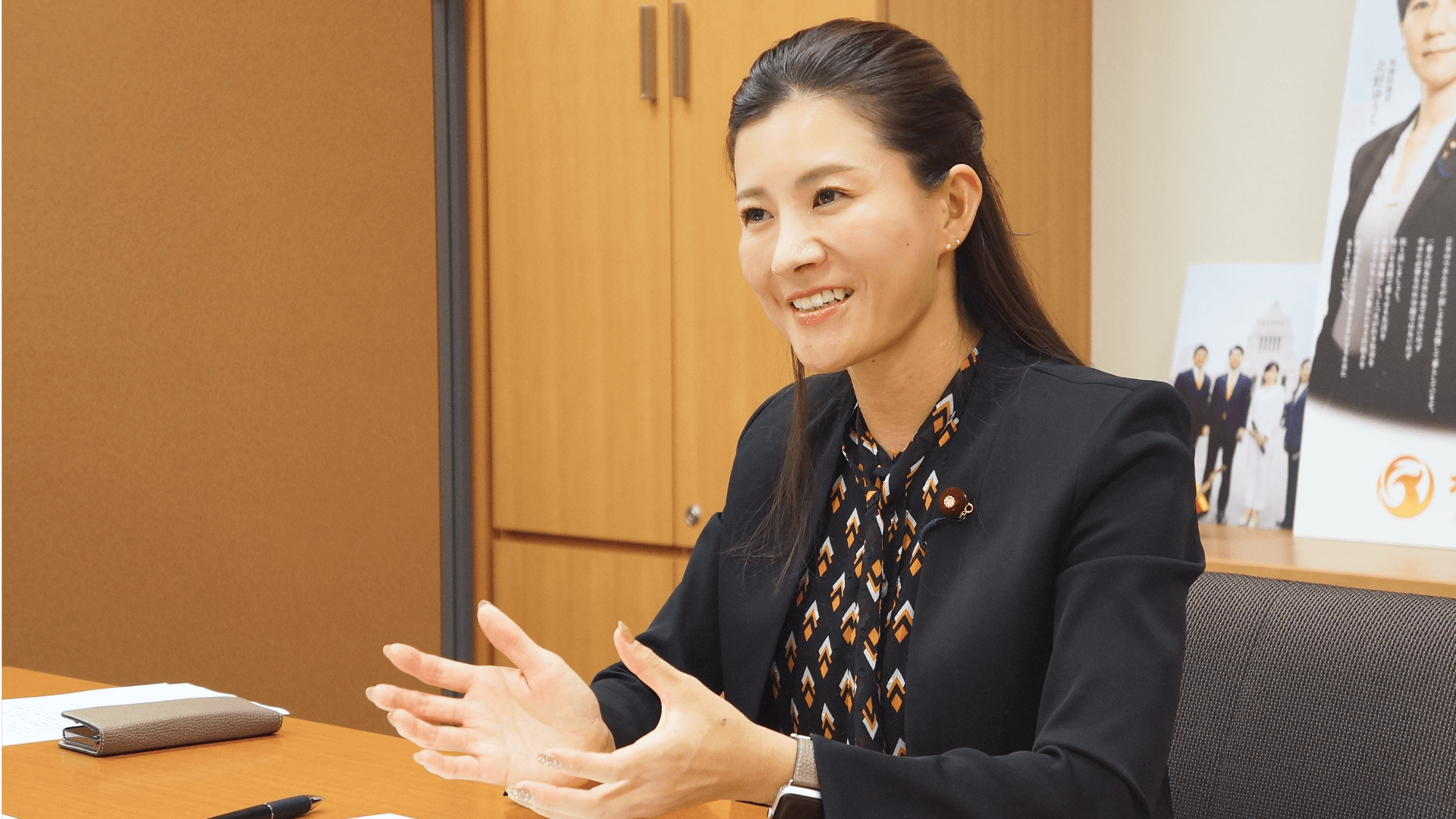
吉川 里奈 よしかわ りな 議員
1987年大阪府出身。大阪府立大学看護学部を卒業後、
大学病院の看護師として約8年間勤務。
2024年の第50回衆議院議員選挙に立候補し初当選(1期)。
2025年9月、参政党副代表に就任。
2025年7月の参議院議員選挙で14議席を獲得し、政界の注目を集めた参政党。国会での存在感を増し、党としてさらなる飛躍を目指しています。今回は、党の副代表を務める吉川りな議員に、政治家への転身の経緯から党の理念、そして今後の目標について、深くお話を伺いました。
(取材日:2024年10月7日)
(文責:株式会社PoliPoli大森達郎)
「守られるべきものが守られてない」という現実への共感
ーもともと医療の現場で活躍されていましたが、どのような経緯で政治の道へ進まれたのでしょうか。
子どもの頃の病気の経験がきっかけとなり、私は医療の道を志し、看護師になりました。大学病院では先進医療の現場に立ち会い、「患者の命を救う」という強い使命感のもと、充実した日々を送っていました。私生活では3人の子どもに恵まれ、仕事と育児に奮闘する毎日。夫とは週末婚生活が長く、子育ての多くを一人で担う慌ただしい日々の中で、母としての責任と向き合い続けてきました。
出産を機に、「食と健康」への意識はさらに高まりました。添加物や農薬、予防接種など、これまで当たり前と思っていたことを一つひとつ考えるようになったのです。30代を迎える頃には、育児をしながらこのまま大学病院でキャリアを積んでいくのか、自分の生き方に葛藤するようになりました。そんな中、自身の経験と医療スキルを活かせる道として、アートメイク看護師へと転身。美容医療の世界で新たな一歩を踏み出しました。
そして、個人事業主として独立したことで、初めて税金や国民負担率と向き合うようになりました。看護師時代には天引きされ、深く考えることのなかった税金。日々の忙しさから「仕方がない」と受け流していたことが、実は「政治が私たちの暮らしを守っていないのではないか」という気づきへとつながったのです。
この“気づき”こそが、私が政治の世界へ一歩踏み出す原点になりました。

ーその問題意識が、最終的に政治家を志すことにつながったのでしょうか。
夫が先に参政党で活動していたため、4年ほど前からその存在は知っていましたが、当初はどちらかといえば一歩引いた、懐疑的な目線で見ていました。
そんな私の意識が大きく変わったのは、新型コロナによるパンデミックの頃です。医療従事者の友人たちと同じく、ワクチン接種には慎重な立場をとっていた私にとって、医療のビジネス化という“タブー”に真正面から切り込む参政党の姿勢は、衝撃的であり、大きな勇気を与えてくれるものでした。
政策を知るうちに、教育・食・健康といった生活の根幹に関わる分野においても、深く共感する点が次々と見つかりました。そして、「本来守られるべき国民の暮らしが、今は守られていない」という党の訴えは、私自身が感じていた違和感そのものだったのです。
さらに、2023年の「LGBT理解増進法」が拙速な議論で成立したことに強い違和感を覚えました。国政政党の中で唯一、明確に反対の声を上げていた参政党の存在を、もっと多くの人に知ってもらう必要があると強く感じ、入党を決意しました。
ー人前で話すのは苦手だと伺っていますが、国政選挙に立候補するという決断は、大変な覚悟だったのではないでしょうか。
そうですね。私自身、「自分にできることがあれば」という思いで参加したのですが、当時は党としても当選を前提に候補者を探していたわけではありませんでした。だからこそ、「誰もやる人がいないなら、自分がやってみようかな」という、軽い気持ちが出発点でした。
実際に引き受けてみると、人前で話すことが本当に苦手で、「やめておけばよかった」と何度も後悔しました。神谷代表から「挨拶くらい、しっかりしてください」と叱られたこともあります。
それでも、党員の皆さんの「一緒に頑張ろう」という励ましに支えられ、参政党として初めて挑んだ衆議院議員選挙である東京15区補選では、表に立つ覚悟と政治の厳しさを学びました。その悔しさこそが、今の私を突き動かす力になっています。
子どもを持つことが「デメリット」にならない社会へ
ー具体的な政策について伺います。まず、吉川議員が訴えておられる子育て政策の課題をどのように捉えているのでしょうか。
少子化が危機的な状況であるにもかかわらず、現代は出産が女性の人生において必ずしも重要視されない風潮があります。「女性の社会進出」という言葉は華やかですが、実際には「子どもを産みたい」と心から思える環境は整っていません。子育てしやすい環境の整備はもちろんですが、それ以前に「家族を持ちたい」と思える社会を政治の力で作る必要があるのではないでしょうか。この最も重要な点に光が当たっていないことに、強い危機感を覚えています。
ー結婚や出産を前向きに感じていない感覚の人は多いのかもしれませんが、何から改善すべきなのでしょうか。
参政党は、経済政策の抜本的な立て直しが必要だと訴え続けています。この「失われた30年」で実質賃金は上がらず、国民負担率ばかりが増加しています。これでは自分の生活で精一杯で、結婚して家族を持つ未来を描くのは困難でしょう。
その解決策として、私たちは減税と積極財政を掲げています。さらに、0歳から15歳までの子どもに子育てや教育のために使える月10万円の給付制度で、経済的な不安を軽減し、子どもを持つことが「デメリット」だと感じさせない社会を目指すべきです。

ー所属の法務委員会でも家族に関する質疑をされていました。選択的夫婦別姓に対してどのような思いを持っているのでしょうか?
この政策は、法務委員会に所属してから深く調査研究を行ってきましたが、考えれば考えるほど「今、最優先で議論すべきことなのか」という疑問が強くなりました。高市総裁が総務大臣時代に旧姓の通称使用が大幅に認められ、社会生活上の支障はほとんどなくなっているはずです。
むしろ、別姓を選択した家庭で育つ子どもの視点に立つべきです。親と子の姓が異なることに違和感を覚えるのは自然なことであり、もっと丁寧な議論が必要です。推進派は「離婚家庭もあるのだから問題ない」と言いますが、それは本質的な答えになっていません。
また、この議論の根底には「戸籍制度は不要」という考え方があります。戸籍制度は今や世界でも珍しく、日本国民の家族関係を証明する唯一の公的な仕組みです。この「日本らしさ」を守ることも多様性の一つであり、「世界標準に合わせるべきだ」という考えには賛同できません。

参政党を拡大し、国益に資する政治を取り戻す
ー参政党は7月の参院選で大きく議席を伸ばしましたが、今後の成長に向けて課題を挙げるとすればなんでしょうか。
おかげさまで参議院では法案提出が可能となり、公約実現に向けた「日本人ファーストプロジェクト」を立ち上げました。具体的には「外国人問題対策」「スパイ防止法の制定」「新型コロナウイルス感染症対策およびmRNAワクチンの検証」「国民負担率35%の実現」の4つのチームで活動しています。
これらの政策を法案として形にするには、裏付けとなるデータやエビデンスが不可欠であり、専門家の方々の協力が欠かせません。スピード感という点ではまだ課題がありますが、プロフェッショナルなメンバーが続々と仲間に加わったことで、大きく前進すると確信しています。
そして何より、国を動かすためにはまだ議席が足りません。引き続き、国民の皆様に政策を力強く訴え、世論を喚起していく必要があります。
ー今後、吉川議員が力を入れていきたいことは何でしょうか。
まずは、法務委員会の一員として、引き続き外国人問題の提起に注力していきます。
このテーマは、自民党総裁選でも大きな争点となり、私たち参政党の訴えが一定の影響を与えたと感じています。
高市早苗新総裁も問題意識を共有しており、今後の議論の深まりに期待しています。
また、継続審議となっている選択的夫婦別姓については、「制度として導入する必要はない」という立場を明確にしています。
私が重視しているのは、家族の在り方、そして子どもの視点を守ることです。そのうえで、旧姓の通称使用の拡大こそが、現実的かつ柔軟な解決策であると考えています。
国会でも世論に対しても、筋の通った主張を続け、日本の社会基盤を守るために全力で取り組んでまいります。
ー最後に、ご自身の抱負も踏まえてメッセージをお願いします。
ふとしたきっかけで日本の未来について考えるようになりました。
日々の生活に追われ、自分のことで精一杯だった私が、たった一つの気づきでここまで変わることができるとは思ってもいませんでした。だからこそ、皆さんに伝えたいのです。何歳になっても、気づいたその瞬間から人は変われるということ。
学び続けること、そして一歩踏み出してチャレンジすることの大切さを。
参政党に参加してから、日本がいかに素晴らしい歴史や伝統、文化、そして安心安全な社会を持つ国であるかを改めて知ることができました。「日本に生まれてよかった」という誇りは、同時に自分自身への誇りにもつながります。
私のような普通の主婦にもできることがある。
その姿を通して、「一緒にやってみよう」と立ち上がる仲間を日本全国にもっと増やしていきたい。参政党を国政の中心を担う政党へと成長させ、「真に日本の国益に資する政治」を取り戻す。
その一心で、これからも全力で走り続けます。



















