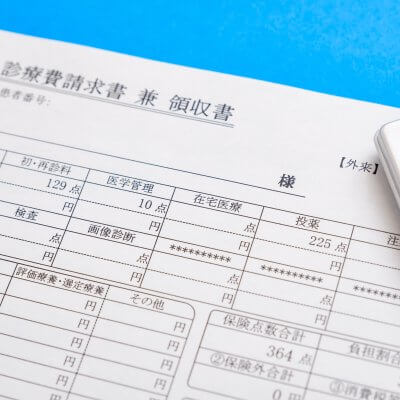食料危機の恐れがある場合に政府が農家に生産拡大を要請できる「食料供給困難事態対策法」が2025年4月1日に施行されます。
異常気象などの地球環境問題や、ウクライナ戦争など地政学的リスクに加え、コメ価格の高騰をもたらした「令和の米騒動」など、食糧生産および供給が不安定化する中で、その対策として注目が集まっています。
以下では、食料供給困難事態対策法の概要や制定までの背景、議論されている内容についてわかりやすく解説します。
1. 食料供給困難事態対策法とは?
「食料供給困難事態対策法」は、国民生活や国民経済に影響を及ぼす事態を防ぐため、政府が一体となって早期から必要な対策を講じることを目的とした法律です。令和6年の通常国会で成立しました。
農林水産省によると、この法律は近年高まる世界的な食料安全保障上のリスクを踏まえ、不測の要因による食料供給不足の防止や早期解消を図ることで、国民生活や国民経済への支障を防ぐことを目的としています。つまり、食料供給が不足する兆候が現れた段階から、政府が一体となって供給確保の対策を進めるための法律といえます。
引用:農林水産省
2. 食料供給困難事態対策法の具体的内容
食料の安定供給を確保することを目的とする食料供給困難事態対策法は、具体的にどのような場面で、どのような対応が取られるのでしょうか。
この法律では、食料供給が不足する事態を以下の3つの段階に区分し、それぞれの基準を設定しています。
(1)食料供給困難兆候
異常気象や動植物の疾病などにより特定食料(米穀や小麦、大豆等)の供給が大幅に不足する兆候が見られる段階
(2)食料供給困難事態
特定食料の供給が大幅に不足している段階
(3)国民が最低限度必要とする食料の供給が確保されないおそれ
食料供給困難事態において、国民が最低限度必要とする食料の供給が確保されず、又は確保されないおそれがある段階
さらに、上記の事態に対応するため、政府は食料供給困難事態対策本部を設置し、食料の需給状況や価格動向などの情報収集・分析、事業者への出荷販売の調整、輸入の促進、生産の促進などの対策を段階的に実施することが明記されています。
特に、供給が大幅に不足する「食料供給困難事態」の段階では、政府は必要に応じて生産計画の届け出を事業者に指示します。これに従わない場合、20万円以下の罰金が課せられることがあります。
さらに、供給が著しく不足する「国民が最低限度必要とする食料の供給が確保されないおそれ」の段階においては、必要に応じて増産などの計画変更指示が出され、これに従わない場合は氏名の公表が行われます。また、物価統制令に基づく価格統制や、国民生活安定緊急措置法や食糧法に基づく割当て・配給の実施も検討されます。
引用:農林水産省
参考:ABEMA Prime
3. 食料供給困難事態対策法に関する議論
食料供給困難事態対策法には賛否があり、その議論は多岐にわたります。
賛成の意見では、主に有事法制の遅れが指摘されています。日本では食料に関する法整備が遅れているため、周辺国の不安定な情勢を考慮すると、食料供給体制の強化が今後の安全保障にとって重要だとされています。
一方、反対の意見では、罰則の厳しさや農業の実態に合わない点が問題視されています。
立憲民主党や共産党は、法案審議段階から、過度な罰金刑が農業経営を圧迫するとして反対しています。
また、高齢化や後継者不足といった農家が抱える構造的な問題への対策が不足していると指摘されています。これらの潜在的な問題を踏まえると、国内の農業基盤が脆弱であるため、法案が実効性を発揮するかについて懐疑的な意見も出ています。
さらに、SNSでは食料供給困難事態対策法に関する誤った情報が広がっています。例えば、「花や果樹農家にコメやイモの生産を強制する」といった虚偽の情報が拡散され、注目を集めました。食料や生命に関わる問題に対しては特に関心が高いため、誤情報は民主主義の根幹を揺るがす可能性が指摘されています。そのため、政府をはじめとする関係者は、正確でわかりやすい情報提供が一層求められています。
参考:日経新聞、ABEMA Prime
まとめ
「食料供給困難事態対策法」は、異常気象や地政学的リスクなどによる食料供給不足の事態に対し、政府が迅速に対応するために制定された重要な法律です。これにより、供給不足の兆候が見られる段階から、政府は段階的に対策を実施し、最終的には国民生活に深刻な影響が出る事態を防ぐことが目指されています。しかし、罰則や農業現場の実情を考慮した対策の整備が求められており、議論は続いています。国民の食料安全保障を確立するとともに、予期せぬ事態にも柔軟に対応できる体制の構築が期待されます。