2024年10月の衆議院選挙、2025年7月20日の参議院選挙の結果、与党・自民党と公明党の連立政権が両院で過半数を維持できない事態となりました。この結果、政権運営はこれまで以上に複雑化し、野党や他党との調整が不可欠になっています。
こうした状況の中で注目されるのが「連立」という仕組みです。連立とは、単独で過半数を確保できない政党が他党と協力し、政権を担う形態のことです。
過去の歴史や海外の事例を見ても、連立は民主主義国家において重要な政権運営の手段といえます。本稿では「連立とは何か?」をわかりやすく解説し、今後の日本の政治の見通しについて考えます。

1.連立とは
「連立」とは、複数の政党が協力して一つの政権をつくることを指します。単独の政党では国会で過半数の議席を確保できない場合や、より安定的な政権運営を目指す場合に行われます。
例えば、日本の衆議院で過半数を確保できない政党が、他党と組むことで政権を担える仕組みです。政治に詳しくない方にわかりやすく言えば、「一つの政党では人数が足りないので、他の政党とチームを組んで政権を運営する」というイメージです。
2.なぜ連立が組まれるのか
連立が組まれる理由は主に二つあります。第一に「数の確保」。国会で法律を成立させるには一定の議席数が必要であり、単独政党では難しい場合が多いためです。第二に「政策の実現」。価値観の近い政党同士が組むことで、互いの政策を政権の中に盛り込むことができます。
3.日本の政治における連立政権の歴史
(1)戦後の連立政権の事例
戦後日本では、1955年に自民党が結成されて以降「55年体制」と呼ばれる長期の自民党一党優位体制が続きましたが、必ずしも常に単独政権だったわけではありません。特に参議院では過半数を割ることが多く、他党と協力せざるを得ない状況が繰り返されました。
1993年には細川護熙首相の下で、自民党を除く8党派が集まった「非自民・非共産」の連立政権が誕生。これは日本で初めて自民党が野党に転落した歴史的な出来事でした。その後も村山富市内閣(社会党・自民党・新党さきがけの連立)や、民主党政権下での社民党との連立など、多様な組み合わせが生まれています。
(2)自民党と公明党の連立の背景
現在の日本政治における代表的な連立といえば、自民党と公明党の連立政権です。1999年に発足したこの枠組みは20年以上続いており、戦後最も安定的な連立政権といえます。
背景には、自民党が単独で過半数を確保できない局面を補う戦略と、公明党が国政に影響力を持ちたいという双方の利害が一致したことがあります。また、公明党が持つ組織票(創価学会を支持母体とする選挙支援)は、自民党にとって選挙戦を戦う上で大きな強みとなってきました。一方で、政策調整の過程では自民党が譲歩を迫られることも少なくなく、教育、福祉、外交・安全保障などの分野で双方の主張をすり合わせながら政権運営を行っています。
4.連立のメリット・デメリット
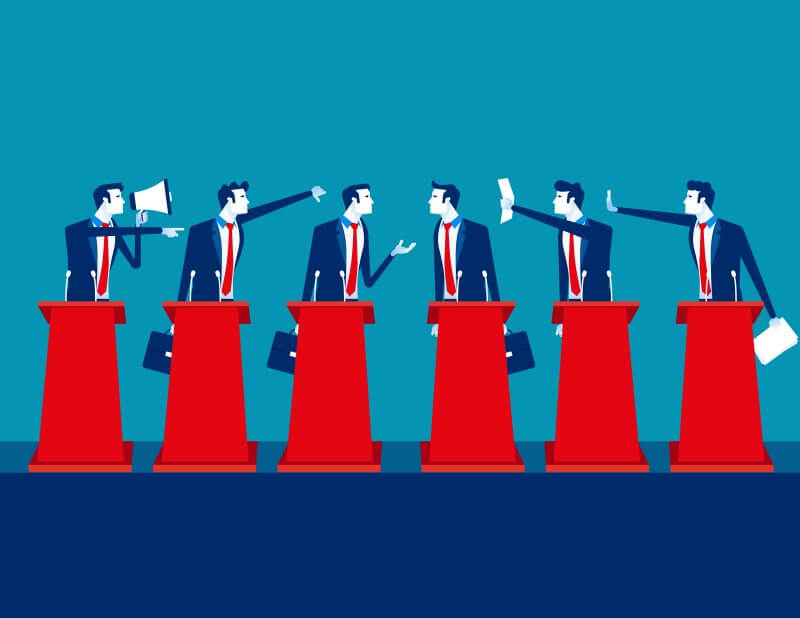
メリット(安定多数の確保・政策実現)
連立の最大のメリットは「議席の安定確保」です。単独で過半数に届かない政党も、他党と手を組むことで法案成立に必要な数をそろえられます。特に日本のように衆議院と参議院の二院制がある場合、両院での安定的な政権運営基盤を確保するために連立はしばしば有効な手段となります。また、連立は政策実現の場でも効果を発揮します。
与党間で政策協定を結ぶことで、単独では実現が難しかった施策を盛り込み、国民への支持基盤を広げられるからです。例えば自公連立政権では、自民党が重視する経済・安全保障政策と、公明党が重視する福祉・教育政策が組み合わさり、幅広い層に訴求できる政策パッケージが形成されています。
デメリット(政策調整の困難・妥協の多さ)
一方で、連立にはデメリットもあります。まず挙げられるのは「政策調整の難しさ」です。複数の政党が参加するため、それぞれの政策優先順位が衝突することは避けられません。その結果、妥協を重ねた政策に落ち着き、スピード感が失われる恐れもあります。
また、選挙での公約を連立協議で修正せざるを得ない場合、有権者から「約束違反」と受け止められるリスクもあります。さらに、連立が解消された場合には政権基盤そのものが不安定になり、政治の混乱を招く危険も伴います。つまり、連立は「数の力で安定を得る」一方で「調整コストを常に抱え込む」性質を持つのです。
5.海外における連立政権の例
ドイツ(メルケル政権など)
ドイツは典型的な「連立型政治」の国です。比例代表制を採用しているため、単独過半数を獲得する政党はほとんどなく、複数政党の連立が前提となります。長期政権を築いたアンゲラ・メルケル首相(キリスト教民主同盟=CDU)も、社会民主党(SPD)や自由民主党(FDP)といった他党との連立を繰り返し、政権を安定させました。このようにドイツでは、選挙後に「どの政党と誰が組むのか」が最大の政治的焦点となり、連立交渉自体が政治プロセスの中心を占めています。
イタリアやイスラエルの事例
一方、イタリアやイスラエルでは連立が頻繁に組み替えられる不安定さが特徴です。イタリアは戦後70年以上の間に60回以上も政権交代が起こっており、ほとんどが短命の連立政権です。政党間の政策的な違いだけでなく、指導者間の対立や選挙制度の影響で、連立が崩壊しやすい構造を持っています。イスラエルも小党乱立のため、与党が連立を組まなければ政権運営が不可能であり、そのため政治的駆け引きや政局の流動性が非常に高い国として知られています。
日本との比較
これらの国々と比べると、日本の自公連立は例外的に長期安定しているケースといえます。比例代表中心の欧州や中東に比べ、日本は小選挙区比例代表並立制を採用しているため、大政党が優位に立ちやすく、結果として連立が長期的に安定的になりやすい、という分析もあります。
6.連立政権と単独政権の違い
単独政権とは、ひとつの政党が国会で過半数の議席を獲得し、自力で政権を運営できる形態を指します。日本では自民党が長らく単独政権を担ってきた例が代表的です。単独政権の強みは、意思決定のスピードと政策の一貫性です。複数党間の調整が不要なため、首相や与党執行部のリーダーシップの下で政策を迅速に実行できます。また、有権者にとっては「誰が責任を持って政治を進めているのか」が明確で、説明責任の所在も分かりやすいのが特徴です。
一方、連立政権は複数政党が共同で政権を担うため、幅広い民意を反映できるメリットがあります。少数政党の意見も政策に盛り込まれることで、多様な価値観に対応した政治が可能になるのです。しかしその反面、政策決定までの調整に時間がかかり、妥協の産物として曖昧な政策が打ち出されやすいという弱点もあります。責任の所在がぼやけ、「どの党が主導した政策なのか」が有権者から見えにくい場合もあります。
要するに、単独政権は「迅速で明快だが一つ政党のみが政策の意思決定に反映される」、連立政権は「多様な意見を意思決定に取り込むことができるが調整に手間がかかる」という対照的な特徴を持っています。国の制度や社会の多様性に応じて、どちらが適しているかは異なります。
7.今後の日本政治における連立の行方
日本の政治における連立のあり方は、今後も重要なテーマとなります。現在の自民党と公明党の連立は20年以上続き、事実上「固定連立」となっています。
しかし、両党間の利害は必ずしも一致しておらず、防衛費増額や憲法改正などの大きな政策課題ではしばしば意見の違いが浮き彫りになります。公明党は平和主義や福祉政策を重視する一方、自民党は安全保障や経済成長を優先する傾向があり、今後の政権運営でどこまで歩調を合わせられるかが課題です。
2024年の衆議院選挙と2025年の参議院選挙の結果、自民党・公明党の議席数は両院で過半数を下回りました。これにより、自民党・公明党以外の連立の組み合わせが現実になる可能性もあります。自民党・公明党と日本維新の会、国民民主党などの野党との、全面的な連立ではなく、政策ごとの「部分的な連携」も考えられます。
海外のように政党が乱立しやすい制度設計ではないため、ドラスティックな組み替えは起こりにくいものの、選挙制度改革や政党再編が進めば、新たな連立パターンが生まれる可能性は否定できません。
少子高齢化や気候変動といった複雑な課題に対応するため、今後は複数の政党が協力する連立政権の重要性が増していきます。これからの連立は、単に議席数を確保するための「数合わせ」ではなく、多様な国民の意見を調整し、政策に反映させる「協働の場」としての役割が期待されます。


















