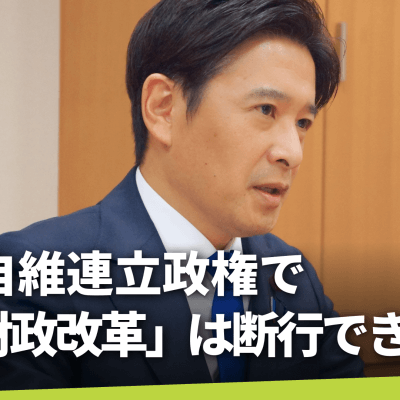河合宏一
1994年自治省(現:総務省)入省。大臣官房企画室、下関市総合政策部長、総務省自治行政局国際室国際協定専門官などを歴任。2006年からは3年間、在英国日本国大使館一等書記官を務め、イギリスの政治状況を調査研究する。その後、総務省消防庁地域防災室長や総務課長などを経て現職。
石破政権下で防災対策が目玉政策として推進されています。防災と一言で言っても、避難所環境の改善や防災教育の強化、防災DXなどカバーする範囲は多岐に渡ります。
今回は防災施策や防災庁設置準備を担当する、内閣府・河合宏一 審議官にインタビュー。これからの時代に必要なのはどのような防災政策なのか。また現在、準備を進めている防災庁設立のロードマップについて伺いました。
命を救うためには事前防災こそが大切
ー現在の日本の防災政策に関してどのように捉えていますか。
防災政策は今まさに歴史の変わる瞬間を迎えています。防災庁設置を公約に掲げて自民党総裁選に出られた石破さんが総理になり、防災庁設置準備担当大臣というポストが生まれました。
2024年1月に起こった能登半島地震での災害対応は100点満点とは言えません。南海トラフ地震や首都直下地震がもし今起こったとして、100点満点の対応ができると言い切れる人は誰もいないでしょう。しかし一歩ずつでも100点に近づいていかなければいけないので、やるべきことがたくさんある状況です。

ー改めて、防災庁を設置する背景や意義について教えてください。
現在、国が綿密に計画を策定して対応しようとしている災害は4つあります。1つ目は南海トラフ巨大地震。現時点での想定死者数は最大約32.3万人にのぼります。東日本大震災での死者が1万9,775人だったことを考えると、とんでもなく桁違いの災害が待ち構えていることがご理解いただけると思います。
2つ目は富士山噴火。こちらは多数の死者こそ想定されないものの、火山灰が降り続けることが首都圏一帯を含む広域に大きな影響を及ぼします。電車が動かなくなったり、電気や水道が止まったりして生活が麻痺する可能性があります。
3つ目は首都直下地震で、死者数は最大約2.3万人、避難者は約290万人に達することが想定されます。4つ目は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震。こちらは北海道・東北地方の人口が比較的少ないエリアですが、最大約19.9万人の死者が出る想定です。特に津波の被害が懸念されています。これら4つの災害については、全省庁を挙げて取り組むレベルで対策を練っています。
このような大きな災害へ対応するには、今の体制はあまりにも貧弱です。そこで防災庁を設置して体制を強化しようと取り組んでいるのです。
ー防災庁設立までのロードマップは。
2024年11月に防災庁設置準備室が発足し、2025年1月には防災庁設置準備アドバイザー会議がスタート。現在は20人のアドバイザーが、政府として強化すべき防災施策の方向性とそのために必要な組織体制のあり方について議論を重ねています。夏頃までに検討をし、2026年度中には防災庁を立ち上げる計画です。
災害対策には大きく事前防災と災害対応の2つの方向性があるのですが、極めて重要になるのが事前防災です。災害が起こってから人命を救うことには当然全力を注ぎますが、災害が起きてから数十万人を救うことは現実的に難しいわけです。一方で、事前防災にはもっと大きな可能性があります。極端に言えば、南海トラフ巨大地震の死者32.3万人をゼロにできるかもしれない。
津波が来たら、すぐに高いところに逃げることを住民全員に徹底させる。津波避難タワーをつくる。場合によっては町ごと移転する。そうした政策を行うことによって多くの命を救うことができます。ですので、事前防災に徹底的に取り組んでいきます。
防災庁が設立されるまでは、防災政策は変わらないのでしょうか。
防災庁設立は2026年度を目指していますが、それ以前にできることはどんどん進めていきます。2025年度から、これまで110人だった内閣府の防災担当職員の定員が220人に増えます。省庁における人員倍増は歴史的にもありえないレベルの増え方。能登半島地震などの昨今の状況を踏まえて、石破政権の政治主導での政策です。
能登半島地震が発生した際には。110人の全員が災害対応にかかりきりになってしまいました。結果として、南海トラフ巨大地震などの事前防災の業務が止まってしまった。職員を倍増させることで、事前防災と災害対応を並行して行えるようにします。
加えて、新たに地域防災力強化担当を創設。47都道府県の担当職員を配置し、地域の防災力を強化していきます。また、災害対応全般の司令塔として事務次官級の「防災監」も創設し、縦割りにならずに組織をうまく機能させていきます。いわば防災庁の先取りのようなポストですね。

マイナンバー活用で、適切な避難所運営に
ー災害対策において、私たちが考えておくべきことを教えてください。
一番大事になってくるのは、意識改革だと思います。内閣府で立ち上げた南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループで議論を続けているのですが、そこでよく有識者の先生方がお話しされるのが「自助・共助・公助」の考え方をより多くの方々に理解していただこうということ。
行政の役割は公助にあたります。災害時には国や都道府県がやるべきことはたくさんありますが、行政で解決できることに限界があるのもまた実情です。行政は役割を果たしつつ、自助や共助も大切になってくる。その意識を多くの人に持ってもらいたいんです。
災害対応は民間企業やNPO・ボランティアの方々も含めた総力戦です。防災においては、どこから叩かれてもほこりが出ないような完璧な体制を役所の世界で築くことが必ずしも正解ではありません。そのことを有識者の方々からもご指摘いただいています。官民の連携をとっていくことが非常に大切です。
ー具体的には、どのように官民の連携をとっていくのでしょうか。
様々な取り組みを行っていますが、たとえば、「被災者救護協力団体」の登録制度を創設します。NPO・ボランティアの災害に強いスタッフがどこにどれだけいらっしゃって、どういった専門分野をお持ちなのか、これまで行政にはあまり情報がありませんでした。国とNPO・ボランティア団体の皆様が普段から顔の見える関係を構築することで、災害時にも連携が取りやすくなりますし、共同で事前防災に取り組むことも容易になるかと思います。
また、2021年に「防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム(防テクPF)」を設置。防テクPFは、災害対応を行う地方自治体のニーズと、民間企業が持つ技術・サービスのマッチングを行う場です。Webサイトを通じてオンライン、現地を問わずお互いのマッチングを支援。登録数は伸び続けており、2024年10月時点で129件のマッチングが成立しています。
防テクPFが行ったアンケートによると、全国の自治体の約8割が災害対策に民間テクノロジーを活用したいと考えています。ですので、今後はさらに両者のマッチングを強化していきたいと思います。
ー民間企業のどんな技術が実際に活用できるのでしょうか。
能登半島地震では、ドローンが災害事象の早期覚知・被災状況把握に活躍しました。他にもエアーテントの活用による緊急消防援助隊の活動環境の整備、医療機能を運搬可能にする医療コンテナの活用など、36の技術が有効なことが明らかになりました。
ー災害時には誤情報が出回ることもあるかと思います。正確な情報をどのように管理するのでしょうか。
昨年リニューアルした「新総合防災情報システム」で情報を管理し、国や各自治体で連携を図ります。これは地図上に様々なデータを重ねて表示でき、天気や断水情報、道路通行規制状況などを一括で見ることができるシステムです。
旧システムは手動操作が多く手間がかかったり、表示できる地図情報が少なかったりといった課題がありましたが、今回のリニューアルで操作性・データ量を大幅に強化。これまでは国の関係省庁のみしか閲覧できなかったのですが、新たに地方自治体や電気、ガス、通信、運送などを担う指定公共機関も利用できるようになりました。たとえば、避難所情報、物資拠点情報、道路状況を重ね合わせて表示することで、物資拠点から避難所までの輸送ルートの検討に活用できます。
なるほど。防災においてデジタルの活用も大切ですよね。
2022年度からは「クラウド型被災者支援システム」の運用を開始しています。避難所の入退管理などにマイナンバーを活用する制度です。これまでは避難所に来た被災者に一人ひとりお名前を書いてもらって、職員がパソコンで打ち込んで避難所名簿をつくっていました。
マイナンバーカードをリンクさせれば、瞬時に情報を読み取り避難所名簿が完成。被災者がどんな持病を抱えているかなどの情報も確認できるようになるため、より適切で効率的な避難所運営が可能となります。システムはすでにできあがっており、現在は各自治体に順次導入いただいている段階です。デジタル庁等とも連携しながら、今後さらに防災DXを進めていきます。

日常生活に防災を織り交ぜる
ー避難所の環境整備についてはどのようにお考えですか。
避難所ではトイレ、キッチン、ベッドの「TKB」の環境改善が最大の課題になっています。2024年12月に避難所に関するガイドラインを改定。国際基準であるスフィア基準に照らし合わせて、トイレを20人に1基用意すること、キッチンカーを活用して温かくて栄養のある食事を提供することなどを定めました。
また、これまで国による支援に使う資機材を置く備蓄拠点は東京の立川防災合同庁舎1カ所のみ。全国津々浦々の被災地へ送るには時間がかかってしまいます。そこで2024年度の補正予算で、備蓄倉庫を新たに7カ所追加。今後は全国8拠点で災害用の物資の確保に努めます。被災者が少しでも良い状態で過ごせるように、環境整備を早急に進めています。
ー日本は災害大国で、誰もが災害と無縁ではありません。最後に、国民に対してメッセージをお願いします。
「自助・共助・公助」において公助には限界があるということを改めてお伝えしたいです。行政の立場としてこれを言うのは申し訳ないことではありますが、現実としてそこは言わざるを得ません。ですから皆さんには自助・共助を頑張っていただきたいです。
大きな災害が起こったときには防災への意識が高まりますが、普段は防災について考える機会は多くないと思います。「防災のセミナーをやるので来てください」と言われても、なかなか行かないですよね。それは仕方ないと思うんです。
だからこそ重要なのは、防災をいかに日常生活に織り交ぜていくか。災害時のために防災グッズをつくるのではなく、日常で使うモノやサービスを災害時にも役立つようにする「フェーズフリー」という考え方があります。商品をつくるにしてもサービスを提供するにしても、普段から使えて、かつ災害時にも役立つような使い方ができたらいいと思うんです。
平時の使い方としてはどちらでもいいのなら、災害時にはどちらが適切かを考えてみる。そんな意識を一人ひとりに持ってもらいたいです。勉学にしろ仕事にしろ、個人の生活で防災について考えられることがあるのではないでしょうか。その積み重ねが、より良い防災対策につながっていくと思います。