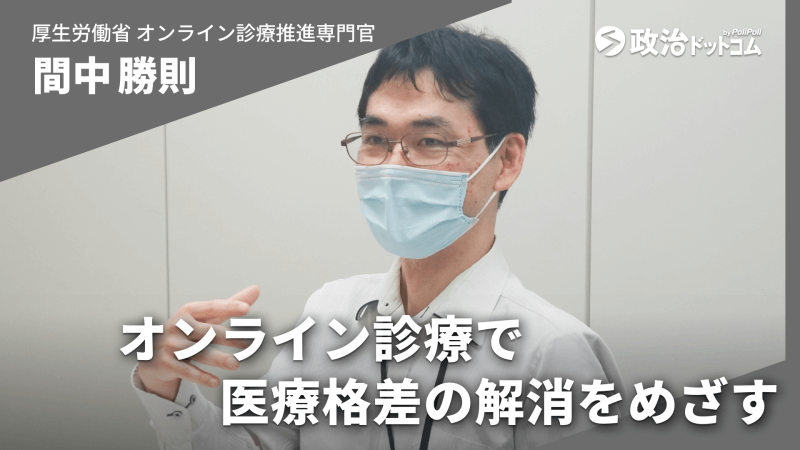吉良 州司 きら しゅうじ 議員
無所属(6期)、院内会派「有志の会」代表
1958年生まれ。大手総合商社で22年、ニューヨーク駐在やブラジル留学などを経験。
民主党政権時には外務副大臣、外務大臣政務官を歴任。
額縁の書は「熱心な素人は玄人に勝る」
院内会派・有志の会の代表を務める吉良州司議員は「生活者主権の政治」を掲げています。多数決の原理がはたらく民主主義の中において、無所属の立場から政策づくりに奔走する吉良議員が目指す、これからの日本の姿についてお話をお伺いしました。
(聞き手・文責:株式会社PoliPoli 秋圭史)
(取材日:2024年3月27日)
(1)「何を為すか」を考え、将来世代のために行動することを決断
ー商社で22年間働いたのち、政治家になる決断をされました。大きなキャリアチェンジだったと思います。
「政治家」に「なる」ということは考えたことがありません。『「既存の職業」を前提に何々に「なる」という小さなことを考えるな。人間、何を為すか考えろ。』という高校時代の恩師の言葉が今でも心に残っています。例えば「医者になる」のではなく、「人の命と健康を守る」のです。
子どものころから世界地図を穴があくほど見ていましたので、将来は世界中を飛び回りたいと考えていました。そして、社会人人生の前半は商社で世界を相手に経験を積み、後半は「世界は広く面白い。夢を持って思いっきり羽ばたけ」と子どもたちや若者に元気を与えることがしたいと考えていました。22年間の商社勤めの中では先進国のニューヨーク駐在、新興国のブラジル留学、また、100回を超える中南米出張など数多くの途上国を訪問し、世界の面白さ、世界の多様性を実感してきました。同時に海外から日本を見る目も持てるからこそ、日本が抱える課題も見えるようになってきました。
最大の課題は「業界主権の政治」の横行と将来世代への負担の先送り問題です。日本では政治家に対し各業界団体がお金と票出しの見返りとして、予算や法律制定を働きかける一方、その財源は将来世代に先送りして負担させる政治が日常的に行われています。
これはいわば、子どもたちが無邪気に遊んでいる時に、親である大人たちが子どもたちを連帯保証人にして借金を背負わせているようなものです。
このような政治を変えていくためには、選挙権のない子どもたちの声を代弁しなければならないと考え政治の世界に飛び込みました。
政治家としての最初のスタートは2003年の大分県知事選挙です。共産党を除くすべての政党や業界団体が他の候補者を推薦・応援する一方、徒手空拳の私は弟と2人だけで立ち上がり、全県中を回りながら、街頭に立って思いを訴え、一人ひとりに向き合う草の根選挙を展開しました。
結果は2か月の全県選挙で32万2千票対29万5千票の惜敗。同年行われた衆議院選挙に、県知事選挙で応援してくれた多くの人々の勧めもあり、地方の元気を日本の元気にするという思いで出馬。衆議院選挙でも無所属の草の根選挙で闘い、与党・自民党候補を破り初当選することができました。
ー大手商社で働いていた経験は政策作りにどんな影響を与えていますか?
世界中を飛び回る中で、あらゆる価値観や正義は相対的なものだと実感しました。日本で正しいと言われていることも外国ではそうではないことが山のようにあります。
人々の生き方や考え方はそこの地理的環境や気象条件に大きく影響されます。砂漠に住む人たちに熱帯雨林気候に住む人々の生活様式が通用しないことは容易に想像できると思います。その地理的環境、気象条件の中で生きる知恵が文明を発展させ、それぞれの民族の文化、伝統、歴史、考え方を紡いでゆくのです。
つまり、私たちが今正しいと考えていることは、2024年3月27日という時間軸と日本の東京という空間軸の接点だけで通用する考え方であり、時間軸を100年前や50年後に移動させたり、空間軸をキエフやモスクワやガザやエルサレムに移動させれば、全く違う考え方や正義があるのです。
このことは日本の文化や自分の感性を否定することを意味しません。異なる考え方や価値観が存在すること、その多様性に思いを馳せてもらいたいと思います。
政策づくりを行う上でも同じです。すべての議員がそれぞれの立場から最善と考える案をぶつけ合い議論します。折り合いをつけるには、相手の考え方にも一理あるという前提で相手の案にも敬意を払い、お互いが異なる立場を乗り越えて落としどころを探る努力と度量が必要なのです。

(2)「有志の会」で行う長期的視点の政策づくり
ー吉良議員は院内会派の「有志の会」を結成し活動を行っています。どのような考えをもとに政策作りをしているのでしょうか?
そもそも国会内において各議員は、政党ではなく院内会派を中心に活動しています。それぞれの院内会派は国会に提出された法案に対し、原則まとまって賛成や反対のスタンスをとり、修正の提案をします。国会内では会派があたかも政党のようなものです。
「有志の会」は無所属の立場で活動する議員4名から成る衆議院院内会派です。特定の組織や政党に依存しないメンバーの集まりです。
今の内閣や与野党ともに政党は支持率を気にしすぎています。短期的な視点から国民の耳ざわりのよい政策を打ち出すことに汲々としてしまっているんですね。その点、我々無所属だと、しがらみフリーですから、長期的視点からストレートに現在・将来の国民と国のためになる政策を打ち出すことができます。日本の政党には党議拘束があり、基本的には党で決定した方針に個々の議員は逆らうことはできません。それぞれの議員が政策に対して個人的には独自の意見・提言がある中で、言動が制限されてしまいます。
将来世代への投資を実行していくためには、短期的な視点だけを考えてはいけません。自由な風通しのよい立場から是々非々での政策づくりに挑んでいます。
(3)吉良議員が掲げる理念「生活者主権」とは
ー吉良議員は「生活者主権」の政治を掲げています。このフレーズを掲げた背景にある問題意識はどのようなものですか?
「生活者主権」は「業界主権」の対比としての言葉です。
「業界主権」は自民党政治の基本です。敗戦後の焼け野原から復興を果たし、国民が食うに困らない生活水準を実現するには自国産業の育成が急務でした。そのような貧しく苦しい戦後の社会環境の中、自民党は国内産業を育成するため、重要な産業に予算分配を行い、産業を育成していくという「業界重視」の政治を行ってきました。その結果として高度成長を実現し、一時は世界第二位の経済大国へと押し上げた自民党政治には感謝しています。
しかし、先進国の仲間入りを果たし、ある程度の豊かさを実現した日本に必要な政策が貧しかったころのものと同じでよいはずがありません。今の業界重視、業界主権政治は、成功体験として脳内に深く刻まれた高度経済成長時代の蜜月関係を前提に、お金と票を出してもらう見返りとして、業界が望む予算配分と法律制定をする、という時代遅れ、時代錯誤の政治です。業界とのつながりはしがらみを生み、自由主義経済の一番重要な新陳代謝を阻みます。
これまで継続してきた産業政策を冬物オーバーコートとしましょう。そして、新しい時代が要請する新しい産業政策を新しいTシャツとしましょう(例えばデジタルやGX(脱炭素)など)。普通、オーバーコートの上から新しいTシャツを着ることはできません。しかし、新しいTシャツを着たいのに、しがらみの関係でオーバーコートを脱ぐことができず、強引にオーバーコートの上からTシャツを着ようとして不具合が起こってしまう、それが今の業界主権政治なのです。
ガソリン価格をめぐる政策はその象徴と言えるでしょう。現在のガソリン価格を抑えるための政策ではガソリンスタンドに卸す元売り業者に補助金を出し、業界の裁量で価格を抑えています。これが「業界主権政治」が採用する政策です。
この政策が国民の生活を支えるための手段として有効なのか、とても疑問です。元々「暫定的に」上乗せされていたガソリン税の暫定上乗せ分を減税すれば直接ドライバーさんなど生活者一人一人に直接還元されることになります。これが「生活者主権」が採用する政策です。
ー誰に対して支援をするか、という視点が政策のあり方も変えるわけですね。
そうです。国民一人ひとりを生活者として支援していく「生活者主権政治」が私の目指す政治です。私のいう「生活者」とは「家庭人」と言い換えることができます。経済界の頂点に立つ経団連の会長も家庭に帰れば一人の夫やお父さんやおじいちゃんです。ですから、「業界人vs生活者」は本来的には敵対関係ではありません。一人ひとりが持つ職業人の顔と家庭人の顔の内、家庭人の視点から、生活を考え、子どもたちの教育や将来を考え、仕事を考え、老後を考えていく政治です。時には「業界や職業人の立場」と「家庭人の立場」が対立することもあります。その際も原則として家庭人の立場からの政策を優先する政治です。
たとえば、足元で進む円安のメリットを強調する人がいます。円安は輸出企業の利益を大きくするからです。しかし、海外工場をつくり海外で生産することが多くなっていたり、世界中にサプライチェーンを構築している現在の輸出産業は、円安になったからといって、それ以前のようには、輸出数量は増えておらず、日本の中小企業への部品発注件数が増加するような産業構造になっていません。むしろ円安の進行により、原材料の値段が上がることで中小企業も痛手を被ったり、生活者の視点からは輸入物価が上がり、電気代、ガス代、ガソリン代はじめ身近なうどんやパンなどの値段が上がって一人一人の国民が困ってしまっているのです。

(4)吉良議員の今後の展望
ー今後、特に力を入れて取り組みたい政策分野や注力したい取り組みを教えてください。
「生活者主権政治」の実現と同時に、「将来世代優先政治」、「国民一人ひとりの幸せ感を重視する政治」の実現に注力して取り組んでいきたいと考えています。
まず、将来世代優先の観点から、財政健全化の必要性を考えてみます。冒頭、子どもたちは遊んでいる内に大人の借金を背負わされていると言いました。現在の国の借金は1200兆円以上となり、GDPの2倍以上の借金を抱えた状態です。それでも尚毎年毎年30兆円を超える借金を続けており、その借金返済は将来世代が担わざるをえないのです。
家計でいえば毎月30万円の収入なのに、毎月50万円の支出をし続けているのと同じ状況です。しかし、実際の国民の家計は、収入が30万円であれば、借金をしてまで50万円の生活を続けようとは思いません。お父さんの飲み代を減らすなど何とか節約をして支出を減らしつつ、子どもへの投資は確保しようとするはずです。国家の運営も同じです。若者や将来世代に対する人的投資を国家の優先順位として予算はじめ国家の経営資源を集中配分すべきだと考えています。
実は日本には個人の現金預金が1100兆円ある。そのうち7割は60歳以上の人たちが抱えているんです。たとえば異次元の金融緩和などの愚策を止め、金利を正常に戻していけば、この眠っているともいえる1100兆円のお金は高齢者の金利収入として、余裕のなかった年金生活に少しばかりの可処分所得増をもたらします。それが消費へ回り、消費税収を押し上げることにより、将来世代への投資に回すことができるようになります。
もうひとつ私は国民一人ひとりの幸せ感を重視する政治を掲げています。過去の高度経済成長期の成功体験があるので、現在の政治は、所得が増えたら幸せであるという論理のもとにGDPを増やして国全体が豊かになることを第一に考えて行われています。途上国的発想です。
GDPは個人消費+民間設備投資+政府支出+純輸出の総和ですから、個人消費以外が伸びてもGDPは増加します。でもそれで、家庭人、消費者としての国民一人ひとりは幸せでしょうか。過去30年のように日本円ベースのGDPは少しばかり増加しても、私たち一人ひとりの可処分所得、実質賃金は下がってきました。
人は、欲しかったものがようやく買えた時、旅行のようにお金はかかるけど好きで楽しみにしていたことが実現した時などに小さな幸せを感じます。個人消費が伸びなければ一人ひとりの幸せ感には結びつきません。
また、何が欲しいか、何がしたいかは一人ひとり異なります。これからの政策づくりは一人一人の幸せが多様なものであるとの認識に立ち、将来不安をなくし、国全体もさることながら、国民一人ひとりの可処分所得を増やしながら、一人ひとりの幸せ感を追求する政治でなければなりません。
生活者優先、将来世代優先、国民一人ひとりの幸せ感を重視する政治を実現していきたいと思います。