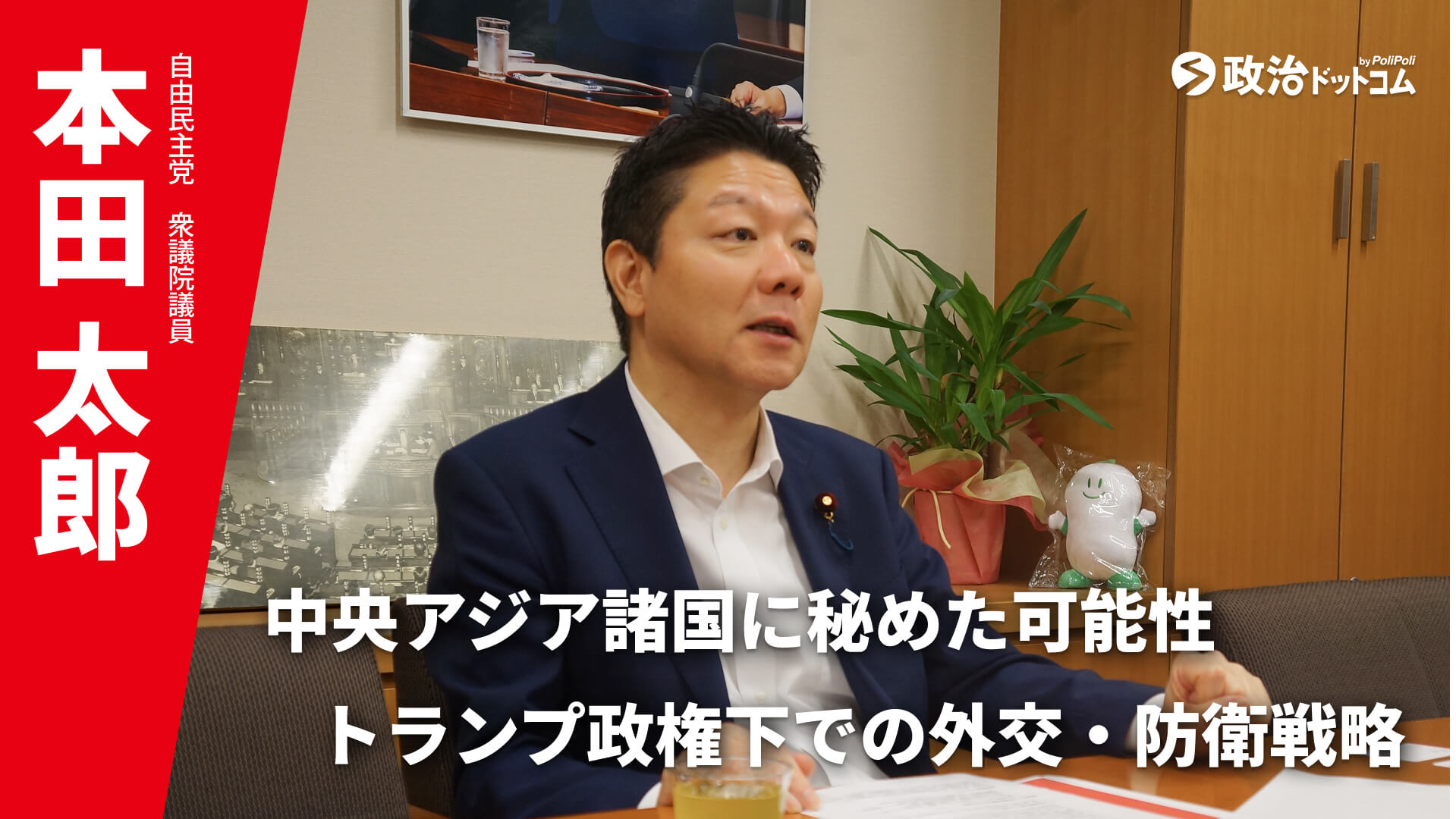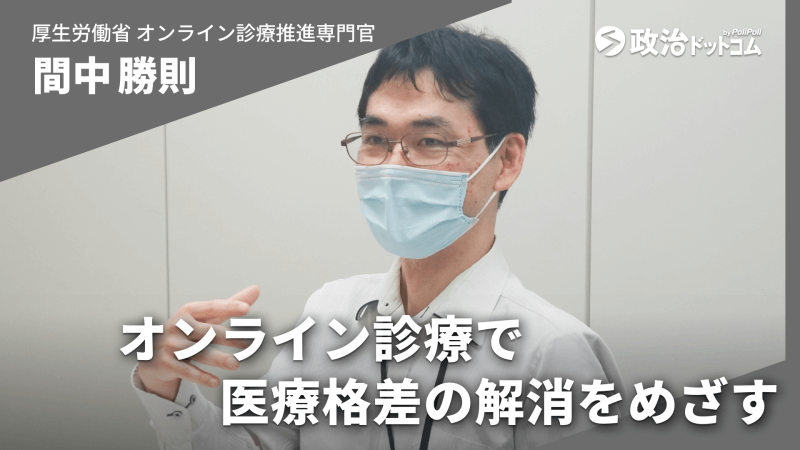本田太郎 ほんだ・たろう 議員
1973年 京都府向日市出身 東京大学大学院卒
2008年(外資系証券会社などを経て)弁護士に
2017年 衆議院議員初当選(京都5区、3期目)
2021年 外務大臣政務官 2024年 防衛副大臣
弁護士から政治家に転じた本田議員。外務政務官として中央アジア各国との外交を担当し、現在は防衛副大臣を務めている外交・防衛に通じた政治家です。ロシア、中国と近い中央アジア各国の地政学的な重要性。また、防衛と地域の安心とのバランスをどうとるべきか。そして、政治家として、法律の影響を受ける当事者ひとりひとりにどう向き合うべきか、うかがいました。
(取材日:2025年9月11日)
(文責:株式会社PoliPoli 河村勇紀)
「法律に感じた矛盾を変えたい」弁護士から政治家へ
ー弁護士から政治家になりましたが、そのきっかけを教えてください。
弁護士は法律に従って仕事をするわけですが、その法律自体が果たして日本の社会に合っているのかなと疑問を抱くことがありました。
カルテルで摘発された企業と海外の独占禁止法当局との交渉などを行っていましたが、日本の独占禁止法はアメリカの法律をもとにしています。でも、アメリカの資本主義は、競争して勝ち残った人が全部を勝ち取る社会。一方で日本は、共存共栄みたいな部分もあって、地域や社会も含めてうまく回していたわけです。そこに突然、資本主義的の極みたいな法律が入ってくると、大企業ですらうまく適応できなかったり、従業員など関係するステークホルダーも痛い目に遭ってしまう。でも、法律家である以上は法律に従わざるをえない。そこに矛盾を感じていました。それならば、法律そのものをより良いものにしようと、それが政治家になったきっかけです。
ー政治家として法律を作る立場になって感じた難しさはなんですか?
法律やルールを変えると「得する人、喜ぶ人」と「損する人、悲しむ人」が必ず生まれます。変更によって不利益を受ける人たちの理解を得るのは、本当に時間が必要です。
例えば、危険運転致死傷罪がなかなか適用されない、という問題に私は取り組んでいますが、被害者からすれば、こんな危険な運転をしておきながら、なぜ危険運転致死傷罪が適用されないんだと。そのストレートな感情は大事にしなければいけない。他方で、法適用の面から見ると、かわいそうだからと言って法律の解釈を変えていいとはならない。それは駄目だよという法学者の意見もあるわけです。また、経済に関する法律なら、変えることによって、こっちの人は儲かるけど、じゃあそれでいいのかと。そういう意味で、関係する人たちへの理解をどう得るのかということが、政治家としてとても大切で、そのための時間や労力を惜しまないようにしています。

外務政務官として感じた「中央アジア」の地政学的重要性
ー外務政務官として「中央アジア」を担当されていましたが、日本にとって中央アジア各国と関係を深めることはどんな意味を持つのでしょうか?
中央アジア各国に西側諸国の方に向いてもらう、特に日本に向いてもらうということが極めて重要です。というのも、中央アジアの国々は旧ソ連の構成国ですが、ロシア依存から、彼らなりに脱却したいという思いがあります。しかし、現実には軍事的にも経済的にもロシアと深いつながりがあるので、なかなか一筋縄ではいかない。かつ、中国も隣にあって触手を伸ばしてきていて、要するに、中央アジアは、中国、ロシア、ヨーロッパ西側諸国が地政学的に取り合っている重要な地域です。
日本は、中央アジア5カ国との会議体を中国より先につくっていて、私はそれをもっと深めて、場合によっては防衛協力なども将来的には検討しうる関係を構築したいと考えています。また、経済協力、特にハイレベル人材が中央アジア各国から日本に来ていただけるような機会が作れたらと思っています。中央アジア各国との友好関係を深めることによって、日本も得られるものがたくさんあります。
ー具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
例えば、カザフスタンは国土が広い資源国で、資金もある反面、IT化が進んでおらず、IT化を進めたいとの意向があって協力できる部分は多いです。ウズベキスタンは日本から観光客がもっと来て欲しいと思っていて、日本から直行便を飛ばすニーズがあり、今年4月からやっと運航が始まりました。キルギスタン、タジキスタンの場合は、まだ経済発展が遅れていてODAのような支援を求めています。それぞれの国のニーズに応える形で、日本が協力できることは多いです。
多くの国と連携をして、様々な局面で、同盟関係や友好関係が活かせるようにすることで、例えば、今回の関税交渉で日本はなんとか成果を出せましたが、そうでなかった時に、日本が他の国と広く手を組むことによって、アメリカもある程度妥協せざるを得ないような形に持っていく。アメリカの意向だけをくむのではなく、超大国アメリカにもきちんと対峙できるようなスタンスを日本自体が持っておくことが重要なのです。

変化する日米関係 防衛面での日本の新たな役割とは
ー第二次トランプ政権で日米関係も変化を余儀なくされています。日本の新たな役割について、どのようにお考えでしょうか?
第二次トランプ政権となり、自分の国は自分で守れ、という方向性が明確です。世界の警察官を自認していたアメリカですが、アメリカが普通の国になるのと同時に、日本も自分の国は自分で守る普通の国になる過渡期にあると思っています。その流れで考えれば、過剰反応は必要ありません。ただし日本は過去の戦争の経緯もありますし、アジアでは中国に次ぐ防衛大国です。防衛力強化はあくまでも自国防衛のためであり再軍備の意図はない、ということを外交でしっかりアジア各国に説明する必要があります。
日本は現在、フィリピンに海上保安庁の警備ノウハウや装備を提供するなどしています。このようなコツコツとできることを続ければ、いざという時は一緒に協力して守ろう、ということができると考えています。多国間で貿易、経済はもとより海上保安や防衛分野でもできることを誠実に実行して、日本との信頼関係を築いている、という状態を作るのが、アジアの中における日本の役割として一番よいのではないでしょうか。アジアの中での信頼を軸に、日本がそう言うなら協力してみよう、という関係を築くことが重要だと思っています。
ー現在は防衛副大臣を務めています。災害対応でも重要な自衛隊の隊員数が減少しているが
自衛隊に限らず、少子高齢化が進む日本では民間企業も含め人手不足です。しかし、処遇改善を含めて、少し改善の兆しが見えてきています。また、自衛隊は装備品の高度化により省人化がかなり進んでいます。大型の部分では、最新型の護衛艦はこれまでの120人体制の運用が90人で運用できるようになりました。またドローンの発達が目覚ましく、戦闘機や潜水艦の代わりにドローンが無人で任務を行えるようになりつつあります。日本でのドローン開発も進めますが、そういった装備品をどうやって海外から安全に有事にトラブルなく使えるようなものを準備をして、配置をしておけるかということが、これからの防衛にとっては、極めて重要だと思います。もちろん、マンパワーは依然として必要ですが、今、防衛分野でのDX化は驚くほど進んでいます。
ー防衛力の強化と地域の安心・安全とのバランスのついてはどのようにお考えですか?
それは私もとても意識している部分です。例えば、災害対応では、目の前で発生した危機への対応なので、やればやるほど住民の皆さんに感謝していただけます。一方、防衛はやればやるほど地域の方々への負担がかかってしまいます。
防衛と地域の安全について、現在まさにスタンドオフミサイルの配備がその課題に直面しています。ミサイルが配備される地域の住民の方からは当然、有事があれば狙われるのではないか、という心配が持ち上がります。実際にその可能性はゼロではありません。では、日本のどの地域もミサイルの配備を受け入れなかったら、どうやって国を守るのかということになります。狙われないような警戒態勢はどうするのか、騒音もできるだけ生活や学校に影響が出ないように対策をやりますと、自治体とも話しながら説明を重ねて、住民の方の不安をひとつひとつ解消するしかありません。それでも人間のやることなので、ミスや見落としがゼロにはならないかもしれません。その現実の中で、住民の方の不安とリスクを最小限にする努力を怠ってはならないと思います。

理想は「政治の存在に気づかず暮らせる社会」
ー最後に本田議員が目指している理想の社会はどういう姿でしょうか?
生活している人が「政治の存在に気づかない」というのが、ある意味すごくいい社会だと思います。
政治がうまく機能していて、みんなが自分の生活に満足して、安心している社会だったら、政治に対して「こうしろ、ああしろ」っていう不満も出ないじゃないですか。もちろん、不満を生じさせている大きな原因は、政治であることは間違いないので、そこは真摯に受け止めなければいけないですが、逆に国民が政治のことを意識しなくて済む社会というのは、ものすごく幸せな社会だと私は思います。
だから、政治というのは、はっきり言って裏方で、われわれ政治家が粛々とやるべきことを真面目にやって、政治も経済も社会も安定して、国民がそれぞれ、自分の生活や仕事のこと、家族のこと、友人のことを考えて、それに邁進できる社会。政治家が裏方として人知れず汗をかいてる、そういう政治を目指したいと思っています。