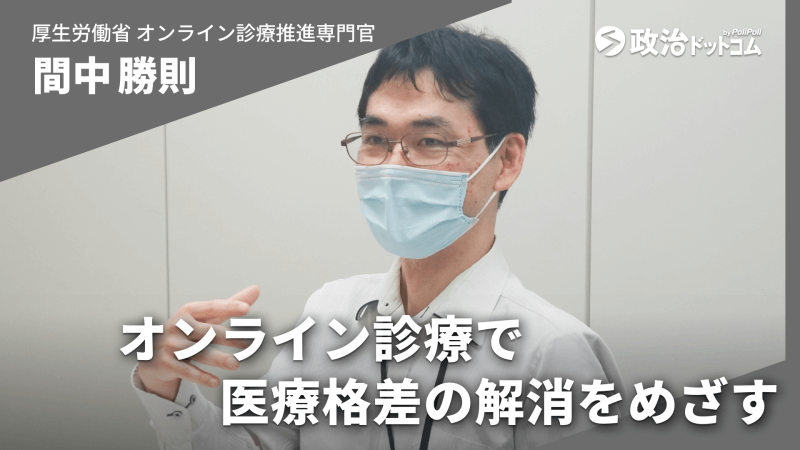佐々木さやか ささき さやか 議員
1981年生まれ。創価大学法学部卒業、同大学法科大学院修了
2006年司法試験合格、2007年弁護士登録(横浜弁護士会)
2013年参議院議員選挙初当選(現在2期目)
弁護士を経て参議院議員となった公明党・佐々木さやか議員は、議員生活12年目を迎えています。弁護士だった佐々木議員が参議院での出馬を決意した理由、そしてこれまでライフワークとして携わってきた子育て支援について印象に残る政策などについて伺いました。
(取材日:2025年2月20日)
(文責:株式会社PoliPoli 大森達郎)
法律の限界に直面、制度の谷間にいる方を救うために政治家へ
ー佐々木議員は弁護士として活躍された後、政治家に転身されています。どのような経緯で政治家を目指されたのでしょうか。
私は2006年に司法試験に合格し、翌年から弁護士としての活動を始めました。困っている人を助けたい、法律を活用して悩みを解決したいという思いが、この道を選んだ理由です。実際に、相談者の問題に対してアドバイスを行い、問題が解決して喜んでいただける弁護士としての仕事にやりがいを感じていました。しかし、次第に弁護士としてできることの限界も痛感するようになりました。
現行の法律では相談者の抱える課題に十分に対応できないケースが多々あります。本当に困っている人の力になるためには、法律そのものを変える必要があるのではないか。そのような思いを抱きながら弁護士としての日々を過ごしていました。
特にその限界を突きつけられたのが、2011年3月の東日本大震災でした。戦後最大規模の被害に直面し、私は被災地で法律相談のボランティアに参加。給付金や支援金について相談を受けましたが、当時の制度では被災者の生活を根本的に支える仕組みは十分ではありませんでした。
「国会で制度の見直しが進められているので、その動向を見守りましょう」と伝えるしかない状況に、もどかしさを強く感じました。
そんな葛藤の中、公明党から「政治家として立候補しないか」とお声がけをいただいたのです。

ーどのような過程で政治家になることへの決意に至ったのでしょうか。
正直に言えば、自分が政治家になるなんて考えたこともありませんでした。私は人前で自分の意見を話すのが得意ではありませんし、政治家は積極的に発信できるタイプの人がなるものだと思っていました。そんな仕事を自分にできるのかと、2週間ほど本当に悩みました。
それでも、決断に至ったのには、大きく2つの理由があります。
1つ目は、先ほどもお伝えした弁護士としてできることの限界を痛感したからです。
震災だけではなく、私たちの日常においても多くの法律の限界があります。たとえば、消費者金融で苦しむ方の相談を受けても、弁護士として関われるのは法的な解決まで。ですが、その後の生活再建や仕事の支援は行政の領域であり、弁護士としては関われません。政治家になれば、震災支援や格差問題、そのほかの社会的課題など、制度の谷間にいる人たちを救うための仕組み作りができるのではないかと考えました。
2つ目は、さまざまな国民の声を届ける存在になりたいと思ったからです。政治家は人前で話すことが得意な人ばかりではなくてもいい。世の中には言いたいことがあっても声を上げられない人がたくさんいます。だからこそ、私のような人間が政治の場に立つことで、言いたくても言えない人の声を代弁できるのではないかと考えました。
結果として、多くの悩みを抱えた人々の力になれる道は政治の世界にあると思い、決意を固めました。
一人の母親として取り組んだ子育て支援政策
ー参議院議員となり12年が経過しました。関わってきた政策の中で、どのような政策が印象に残っていますか。

1つ1つの政策にとても思い出があります。その中でも、子育てに関する政策に注力していることもあり「通園バスの安全装置の義務化」と「こども誰でも通園制度の創設」の2つが特に印象に残っています。
1つ目の「通園バスの安全装置の義務化」は、2022年の9月、認定こども園で3歳の園児が通園バス内に置き去りにされ亡くなるという痛ましい事故が発生しました。このニュースを知り、怒りと悲しみで胸がいっぱいになったのを覚えています。前年にも同様の事故があったにもかかわらず、早期に対策が取られなかったことに強い悔しさを感じました。この状況を受け、公明党として政府に提言を行い、私自身も参議院予算委員会で岸田総理に対し、全ての通園バスに安全装置を義務付けることと、そのための予算措置、そして早期の実現を強く訴えました。
ー通園バスの安全装置義務化について、スピーディーな対応をしたと記憶しています。
岸田総理は、参議院予算委員会で安全装置の義務付けに前向きな姿勢を示し、事業者の負担を実質ゼロにする財政措置の実施と、迅速な対応を約束しました。
その結果、翌年4月からハード面での義務化が実現し、ソフト面でも点呼による人数確認の義務化が進められました。安全装置の義務化は、多くの子どもたちの安全確保につながったと感じています。
ーこども誰でも通園制度の創設についても教えてください。
印象に残っている2つ目の政策、「こども誰でも通園制度」は、全ての子育て家庭が就労要件に関係なく、時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付制度です。
これまでの子育て支援は、ワーキングマザーやシングルマザーなど特定の層への支援が中心でしたが、専業主婦や産休中の母親も0〜2歳児の育児に大きな負担を抱えています。私自身も子育ての幸せな時間を感じる一方で、母親が一人で子育てをすることの大変さを実感しました。産後うつや虐待といった問題が生じる背景には、育児の孤立があります。
子育てをしている人が、安心して子どもを預けられる環境は絶対に必要です。そのため、「こども誰でも通園制度」によって、働く人だけでなく、家庭で育児をしている方々も安心して子どもを預けられる環境を整備したいと考えました。この制度は2026年度から全国の自治体で本格的にスタートします。
公明党が掲げる「子育て応援トータルプラン」とは
ー各党が子育て支援政策を掲げる中、公明党は「子育て応援トータルプラン」を掲げています。どのような考えなのでしょうか。
「子育て応援トータルプラン」は、公明党が2023年3月に政府に提言した2030年の実現を目指す包括的な政策計画です。
子育ては、妊娠・出産から子どもが社会に巣立つまで、さまざまなライフステージがあり、それぞれに適切な支援が求められます。支援の隙間をなくすため、公明党はライフステージごとに切れ目のない支援を行う必要性を訴えています。特に2023年から2030年までの7年間を「次世代育成を最優先する7年」と位置付け、財源を確保しながら国を挙げて取り組むよう提案しました。
本プランは、子どもだけでなく、関わるすべての人への支援も重視しています。女性の支援に加え、男性の働き方改革や公共空間での子育て環境の整備なども重要なテーマです。公明党は現場の声を大切にし、育児の現場で生まれる小さな課題も丁寧に拾い上げ、政策に反映させています。
ー少子化が進む中で、子育て支援制度の整備のみならず社会の意識の変化も必要と言われています。
確かに、現在の社会はまだ「子育てしやすい社会」とは言えません。この状況を変えるためには、省庁の啓発活動の推進や、大企業などでの働き方改革が重要です。一人ひとりが、自分にできる取り組みを積み重ねていくことが意識変革の鍵になると考えています。
社会の意識は変えられると信じています。私が議員になった12年前、女性議員が出産すると記者会見を開き、「議員として仕事を続けます」と説明するのが当たり前でした。しかし今では、そうした会見は不要となり、社会は少しずつ変わってきています。ただ、理想と現実のギャップはまだ存在しています。
このギャップを埋めるには、政治の役割が大きいですが、民間の取り組みも欠かせません。官民が連携しながら、より良い社会を築いていきたいと考えています。

地域や社会全体で子どもの成長を喜べる社会に
ー今後注力したい政策分野について教えてください。
喫緊の課題としては、物価高への対応が必要だと感じています。私自身も日々スーパーで買い物をしていますが、5年前と比べて同じ商品が1.5倍の価格になっていると実感しています。特に賃金の上昇が限定的な中で、子育て世代をはじめ多くの方々が物価高の影響を直接受けています。
根本的な解決策としては、やはり賃金アップが重要です。賃上げのための環境整備はもちろん、減税などの対策も検討しながら、国民の皆さんが「安心して生活できる」という見通しを持てる社会の実現が急務だと考えています。
また、教育無償化政策にも取り組んでいます。授業料の無償化は大きなテーマですが、中高生になると塾代や食費の負担も増えます。近年ではタブレット端末も必需品となり、教材費の負担も大きい状況です。
こうした授業料以外の負担についても軽減策を進めており、家庭の経済的な負担が少しでも軽くなるよう、議論を深めています。
ー今後のビジョンを教えてください。
子育て支援は私のライフワークです。子どもの成長を親御さんだけでなく、地域や社会全体が喜び合える社会を目指しています。子どもたちが安心して笑顔で過ごせる環境を整えるためには、お母さんやお父さん、学校の先生、保育所の先生など、関わるすべての大人たちが笑顔でいられることが大切です。
誰もがかつては子どもだったことを思い返しながら、子育ての現場に立つ方々と共に、より良い社会を築いていきたいと考えています。この原点を忘れず、今後も取り組みを進めてまいります。