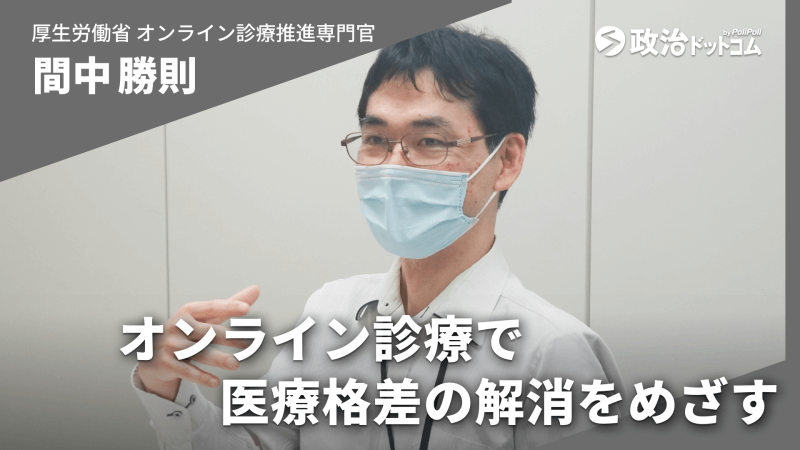藤井比早之 ふじい ひさゆき 議員
自治省(総務省)を経て、秋田県・岐阜県・滋賀県彦根市などに勤務。
元彦根市副市長。2012年衆議院選兵庫4区当選(現在5期目)。
初代デジタル副大臣、内閣府副大臣などを歴任し、2024年外務副大臣に就任。
趣味はB級グルメの食べ歩き、ドラマの視聴率チェック、いきいき体操でダイエット。
戦争や紛争の中で弱い立場に置かれる女性たち。しかし彼女たちは持続的平和の鍵を握る重要な担い手でもあります。今年2月、そんな女性の力に焦点を当てたWPS(Women, Peace and Security:女性・平和・安全保障)フォーカルポイント・ネットワーク会合が東京で開催されました。
外務副大臣としてWPSを推進する藤井比早之議員に、現在の国際情勢、そしてWPSの取り組みの意義を聞きました。
(取材日:2025年3月6日)
(文責:株式会社PoliPoli 井出光)
地方振興の限界を超えるため、自治省から政治家に転身
ー藤井議員はなぜ、自治省(現在の総務省)から政治を志したのでしょうか。
私は兵庫県の中山間地域の西脇市出身です。高校を卒業するのと同時にJRの路線が廃線になり、地方の衰退を肌で感じていました。「故郷の衰退を止め、どのように守っていくのか」を考え続け、地域振興や地方自治で最も活躍できる場所を探したとき、自治省しかない、と入省しました。
しかし、自治省に入り実際にさまざまな地方の現場を経験すると、日本そして地方の人口減少への対応は行政だけでの対応には限界があると痛感しました。この限界を突破するには政治を変える必要がある、と確信し、14年前に地元に戻って政治家の道を歩み始めました。
 彦根市副市長時代は「ひこにゃん」プロジェクトを主導。
彦根市副市長時代は「ひこにゃん」プロジェクトを主導。
ー政治でなければ変えられない、というのは具体的にはどういうところでしょうか。
前提として行政は、法律や制度があってそれを執行する立場です。法律をはじめとする根本的な部分は行政では変えられません。また行政は省庁毎に縦割りで仕事が進むため、省庁の壁を乗り越えて仕事を進めるなら、政治が動かなければ前に進みません。
たとえば現在、米不足が問題となっていますね。農業の問題、米を作る農地の場所をどうするか、調整区域の話は確かに農水省が管轄ですが、土地利用全体をどうするか、都市計画の話になると国土交通省、自治体が関係する話になると総務省、農家であっても兼業農家の仕事、産業全体の話は経済産業省、さらに地方の人口減少、少子化対策、子育てまで絡めると厚生労働省、こども家庭庁や文部科学省の管轄になります。さまざまな省庁の縦割りを乗り越えて何かを動かすには、政治が動くしかありません。
ー地方創生は石破内閣の政策の一つの柱となっています。
石破総理は日本で一番人口が少ない鳥取県のご出身で、私は隣の兵庫県出身です。地方を何とかしたい、という石破総理の思いは、地方創生の追い風になっていると思います。
ただし“地方”とひとくくりにしても、私の選挙区のように、同じ地域でも児童1500人以上の小学校がある一方で、20人しかいない小学校もある状態です。そのため、地域毎にどのようにすべきかをオーダーメードで進めていく必要があり、これが私の政治家としてのライフワークです。
その中で、新たな列島改造計画のようなものが必要ですし、何よりも若い方の収入を増やさねばなりません。新たな所得倍増計画が必要で、地方や地域を守り発展させるための政策を進めていきます。
外務副大臣として見る現在の国際情勢
ー藤井議員は昨年11月に外務副大臣に就任しました。現在の国際情勢についてどのようにお考えでしょうか。
今年1月にアメリカでトランプ政権が発足して、世界はまさに様々な変化の渦中にあります。国際社会が分断状態にあり、国連の機能不全が顕著になっています。
トランプ大統領は多国間主義に懐疑的な姿勢を示していますが、日本にとっては多国間での外交が依然として重要です。今後は2国間や3国間での個別関係の積み重ねが、より一層意味を持つのではないでしょうか。
まず日米同盟を基盤として、日米豪、日米英、日米韓、日米比、日米豪印の推進、NATOやAUKUSとの連携など、一つ一つの関係構築が重要です。「自由で開かれたインド太平洋」を推進する。日米英のみならずフランスやドイツも含めた枠組みを強化する同志国連携が非常に大事であり、このような視点で外交を進めていきたいと考えています。
国際社会が分断に向かう中、ロシアのウクライナ侵略などが継続しています。これらは国際秩序に対する力による挑戦の表れです。力による一方的な現状変更の試みは決して許されません。国際秩序の回復と安全保障の強化に取り組んでいく必要があります。

ー厳しい外交情勢にありますが、今年2月にWPS(Women、Peace and Security:女性・平和・安全保障)フォーカルポイント・ネットワークの会合がアジアで初めて東京で開催されました。日本の外交をめぐり、WPSが平和構築のための新たなキーワードとして注目を集めているようですね。
女性の視点での平和や安全保障に対する取り組みが必要とされている今、女性・平和・安全保障(WPS)アジェンダは極めて重要です。このアジェンダは、和平交渉や平和構築、平和の持続性を高めるために女性の視点や参加を促進することを目指しています。
日本は戦後永く戦争を経験していませんが、防災や復興という点では世界的な先行ランナーです。自然災害の被災地における対応においても、女性の視点は不可欠であることが明らかになっています。これらの経験は、より広範な平和構築の取り組みにも活かせるものです。
ー藤井議員ご自身も、阪神淡路大震災の際はボランティアに参加したと拝見しました。
避難所生活では、女性の視点は非常に重要だと阪神淡路大震災で実感しました。生理用品の確保や、避難所における清潔さの維持、プライバシーの保護といった極めてナイーブでデリケートな課題は、実際のところ男性の視点からは見落とされがちです。だからこそ女性の視点が必要なのです。特に避難所のような極限状況にあるときにこそ、女性の視点と女性の意見の反映が不可欠だと考えています。
阪神淡路大震災や東日本大震災という大規模災害を経験した日本は、ボランティア活動を含む被災地での対応に関する豊富な経験と知見を有しています。このような日本の災害対応の経験や知見は、世界の様々な危機管理や復興の場面でも大いに役立つものではないでしょうか。

ー今年は日本がWPSフォーカルポイント・ネットワークの議長を務めるそうですね。
そうです、2025年は、ノルウェーと一緒にWPSフォーカルポイント・ネットワーク(FPN)共同議長を務めます。
今年2月に東京会合が開かれましたが、この先1年間、しっかりと共同議長としてWPSアジェンダの推進に取り組んでいきます。2024年11月時点で93の国を含めた103のメンバーが参加するFPNでは、各国がWPSのコミットメント促進に役立てることを目的として、教訓や好事例を紹介し共有するのが重要です。日本では自然災害の観点で被災地の経験、災害復興、応急対策について、女性視点の事例を紹介し、世界の議論をリードしていきたいですね。
2月FPN東京会合では、防災、AI、サイバーセキュリティ分野におけるWPSアジェンダの展開という点が議論のポイントの一つになりました。
2024年1月には、当時の上川陽子外務大臣の下で外務省内にWPS(女性・平和・安全保障)タスクフォースが立ち上がりました。まずは外務省内での部門横断的な連携や情報共有を優先的に進めています。外務省は、特に在外公館からの情報が各国ごとに分断されることなく、リアルタイムで共有されるよう、チャットシステムなどを活用したオープンでフラットなプラットフォームの構築に取り組んでいます。
さらに、タスクフォースを通じて、内閣府、復興庁、消防庁、防衛省から、防災や災害対応・復興分野における取り組みについて説明を受けるなど、省庁間の情報共有も着実に進展しています。これにより、国内の災害対応経験をWPSの国際的な取り組みに活かす基盤が形成されつつあります。
若者が生き生きと過ごしていける社会を目指して

ー藤井議員が今後力を入れていきたい政策分野について教えてください。
日本の人口減少が続く中、若い世代が生き生きと過ごせる社会の構築が急務です。現在の最大の問題は、若者が希望を失っている点にあると感じています。先日外務副大臣として訪問したタンザニアとケニアでは、平均年齢がそれぞれ18歳、19歳でした。
世界を見渡すと、このように若々しい国々がある一方で、かつて「Japan as No.1」と称賛され、世界中で若い日本人の姿が見られた時代と比べ、現在は国際舞台での日本人の存在感が著しく低下しています。この状況を看過してよいのでしょうか。
先にお話した私の選挙区の小学校は、統合され、廃校となった小学校が、かつてはマンモス校と呼ばれるほどの規模を誇っていました。これは真に危機的な状況として捉え、早急な対応が必要です。しかし、この問題は単純にすぐ解決できるものではありません。人口減少と若者の希望喪失という現実を日本社会全体の危機として認識し、その対策に全力で取り組まねばなりません。
ー最後に読者へのメッセージをお願いします。
今の若い世代は政治に対して大きな興味を持っていると感じています。SNSやYouTubeが政治に影響を与えつつあるのは、その一端を示しています。従来のメディアでは得られなかった多様な情報が、SNSやYouTubeを通じて入手できるようになりました。日本の政治も若い世代を中心に変革の兆しが見え始めており、現在はまさにその過渡期にあるのではないでしょうか。
一方で、SNSをはじめとするインターネット上には、あまりにも膨大な情報があふれているという課題も存在します。SNS上の情報はまさに「玉石混交」であり、日本社会を混乱させる方向へ誘導しようとする情報も少なくありません。『政治ドットコム』のように直接取材に基づいて情報発信する媒体は、この状況において重要な役割を担っています。若い世代の皆様には、様々な情報に踊らされることなく、物事の本質を見極める目を養っていただきたいと思います。