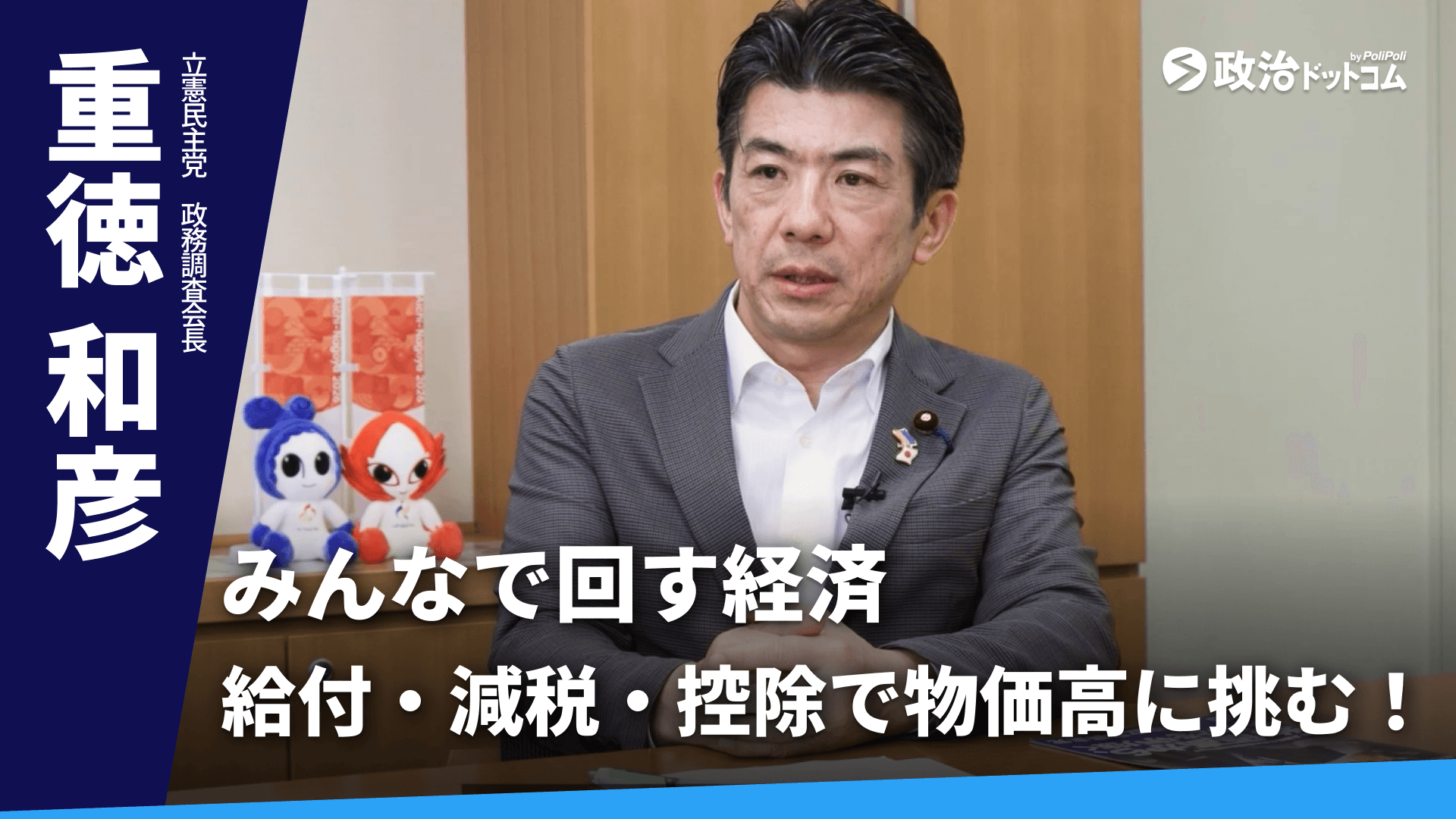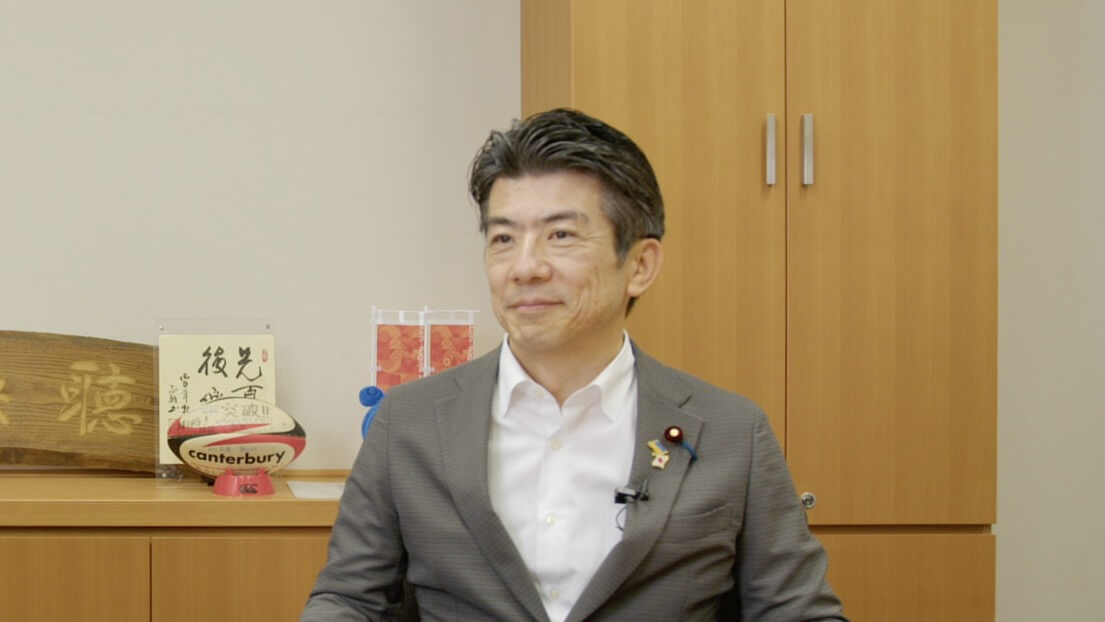
重徳 和彦 しげとく かずひこ 議員
1970年生まれ。総務省を経て、2012年衆議院議員総選挙で初当選(5期)。
立憲民主党の中堅・若手の政策グループ「直諫(ちょっかん)の会」会長。
2024年9月の立憲民主党代表選挙後、政務調査会長に就任。
趣味はラグビー観戦。
7月20日に第27回参議院議員選挙が迫っています。
株式会社PoliPoliでは、参議院議員選挙の主要な政策上の争点を明らかにし、各党の政策を分かりやすく有権者に届けるための特集企画を実施します。今回は、立憲民主党で政務調査会長を務める重徳和彦議員に、立憲民主党の選挙公約に込めた思いや公約のポイント、そして今回の参議院議員選挙の位置付けなどについてお伺いしました。
(※所属する国会議員が5人以上または直近の国政選挙での得票率が有効投票総数の2%以上という公職選挙法上の政党要件を満たす、すべての政党にインタビューの打診をしております)
(取材日:2025年7月2日)
(文責:株式会社PoliPoli 中保友里)
給付、減税、給付付き税額控除の3本柱で物価高に立ち向かう
ー今回の参議院議員選挙に向けた党内のムードはいかがですか。
今回は参議院選挙ですが、私たちは「政権選択のタイミング」と位置づけています。本来、政権選択は解散総選挙の際に語られることが多いのですが、すでに前回の衆院選で自公を少数に追い込んでいますので、今回は参議院でどこまで追い込めるか、が焦点になります。
そのため公約に関しても3月頃から何度も党内で議論を重ねてきました。ゴールデンウィーク前には食料品の消費税を0%にする計画を発表し、それに向けた財源などのプランも5月上旬に発表することができました。
ー今回、特に重要な争点として物価高対策がありますが、立憲民主党は給付と減税の両方を掲げていますね。
そうですね。現実的に考えると、消費税の減税はどれだけ急いでも来年の4月になると思います。「では今年度はどうするのか」という議論から、前倒しで1人あたり2万円を給付する計画を盛り込みました。ただし高所得者の方々については給付金も課税対象とし、後で国に返していただくことで所得に応じた給付となる仕組みです。
そして来年4月から消費税減税を最長2年の期限付きで行い、その先には「給付付き税額控除」という独自の施策を行う計画です。この3段階で適切に所得の再分配を行っていく考えなので、単なる2万円のバラマキではないのです。
最後の「給付付き税額控除」は少しわかりにくいのですが、もともと消費税には低所得者ほど負担が重くなる「逆進性」の問題が指摘されてきました。食料品だけ8%の軽減税率がありますが、これは逆進性対策としての効果は非常に小さいと言わざるを得ません。
だから立憲民主党としては最初からこの軽減税率という方法を疑問視しており、まずは一律給付するけれども、後から税で調整する仕組みを考えてきたわけです。これが「給付付き税額控除」で、細かい制度設計はまだ議論中ですが、私はこれを「究極の所得再分配システム」と呼んでいます。
ー物価高対策においては、社会保険料も重要なテーマですが、立憲民主党は中小企業に絞った対策を掲げています。
社会保険料の負担は重たいと感じる方が多いと思いますが、一方で恩恵があることも忘れてはなりません。医療が一番わかりやすいと思いますが、日本は誰もが少ない負担で医療を受けられる国で、それを支えているのが社会保障制度です。負担軽減のために保険料を下げると恩恵も減ることになるので、そこは慎重に考える必要があります。
むしろ問題は保険料を負担することすらできない非正規雇用の方々が多いことで、これを解消するには非正規雇用の従業員を正規化するよう企業に促していく必要があります。ただ、正社員化する際に企業の社会保険負担が増えるので、中小企業に関してはこれを軽減できるよう支援するのが私たちのプランです。
当面は政府がこの社会保険料を補助する形になりますが、長期的な視点で見れば、正規雇用の方々が増えることで社会保険料を納付する人が増えるので、社会保障全体が安定することになるのです。世の中では「賃上げ」が叫ばれていますが、肝心の労働者が非正規でいつでも解雇できる状態では、賃上げの恩恵も広がりません。まずは雇用を安定させることから社会保険料の問題にアプローチしていきたいと考えています。
ー減税の話になると必ず「財源」の問題が出てくると思いますが、食料品の消費税を0%にする際の財源は、どのように確保されるのでしょうか。
我々がずっと指摘しているのは過剰に積まれた「基金」です。これは使途が必ずしも決まっていない政府の資金で、7.8兆円はあると我々は見ています。一応、政府の中に「3年間の使途および成果を見て、その後の積み増しを検討する」という自主ルールがあるのですが、明らかに3年経っていないのに積み増した過剰な基金があります。それをすべて財源に充てるわけではないですが、半分くらいは活用できると考えています。

賃上げを消費の拡大につなげるには、長時間労働の是正も必要
ー物価高対策や、そのための財源確保には経済成長も欠かせないと思いますが、そのビジョンを聞かせてください。
我々の経済政策として、例えば脱炭素や健康・医療分野の技術開発、地方の活性化、デジタル化など、明日の飯の種となる産業への投資を政策として打ち出しています。ただ、これまでずっと言われてきた「経済のパイを大きくすれば税収増になって跳ね返ってくる」という主張については、検証が必要だと思っています。
企業の生産性はこの30年で約30%増加していますが、一方で、この増加分の多くが株主への還元に使われており、実質賃金は伸びないまま、という現実があります。もちろん株主への還元も大切ですが、もっと賃金に回していかないとこの問題は解消しないでしょう。だから私たちは企業の利益が真っ先に賃金に回るような誘導策を打ち出していく予定です。
同時に考えなければならないのが、労働時間の問題です。バブルの頃は「24時間働けますか」と長時間労働が当たり前の風潮がありました。長時間労働の慣習は今も相当残っていますが、今は夫婦共働きの世帯が増えているので子育てとのバランスが取れず、結果的に少子化を加速させている。そして家族と過ごす時間が取れず、お金があっても消費する時間がない、という状況を招いています。
賃上げを消費の拡大と経済成長の好循環につなげていくためには、働く人たちが「自分の時間を持つ」という状況も作っていく必要があるのです。高所得者や大企業からのトリクルダウンを期待するのではなく、雇用のあり方についてもしっかりと目を向けて「みんなで回す経済」を作っていきたいと考えています。

野党の議員外交が良好な国際関係の下地を築く
ーアメリカの関税や緊迫する中東情勢など、外交や安全保障に対する関心も高まっています。この点については党としてどのような方針なのでしょうか。
外交は政権与党が担うものなので、野党がどのように取り組んでいるのかは見えづらい部分があります。しかし、立憲民主党は「党外交推進本部」を立ち上げて議員外交の強化に取り組んでいます。
今般の関税についても、米国の連邦議会議員団が私たちに面会を求めてきたので、党本部で意見交換をさせていただきました。ディスカッションを通じてトランプ氏に近い共和党の議員から政権の真の狙いを探ったり、日本の要望を伝えたり、そしてそれらが両国政府に伝わっていくことで外交の下地を作る。そのような議員外交も野党にできる重要な取り組みだと考えています。
ー地理的に重要なアジアにおいては、どのような議員外交に取り組まれていますか。
日本は中国、北朝鮮、ロシアという核保有国に囲まれているので、安全保障上、常に緊張状態にあると考えています。その中で、もっとも大切にすべき国は韓国だと考えています。立憲民主党としても、2023年に独自に「日韓友好議員連盟」を設立し、私は2025年より会長を務めています。尹錫悦(ユンソンニョル)前大統領が弾劾された際も、韓国の与野党両方の議員と密にコミュニケーションを取り、政権交代後も友好な関係を維持できるよう準備してきました。
6月に李在明(イジェミョン)政権が誕生しましたが、その前に議員外交で関係を築いていた議員の一人が大統領府の安全保障室長になりました。今後このパイプが両国の関係維持に役立つことは言うまでもなく、これがまさに議員外交の成果なのです。今や日本と韓国は年間1000万人がお互いに行き来する仲です。民間で築いた良好な関係を政治も支えていく必要があり、そのために私たち野党の議員外交も重要な役割を果たしているのです。

インターネット投票で現役世代の政治参加を促す
ー最後に、このメディアの主な読者である20~40代の現役世代に向けてアピールしたいことはありますか。
今、インターネット投票の実現に向けて取り組んでいます。私が政治の世界に入った当時、政治に興味がなかった地元の同級生も、「重徳が出るなら応援しようかな」と言ってくれました。やはり政治との距離は「そこに当事者として入れるかどうか、入りやすいかどうか」に左右されることを痛感しました。
だから、投票所まで行くのが面倒な人でも、毎日使っているスマホで投票が完結すれば参加するハードルが下がります。さまざまな課題が指摘されてきましたが、技術的にはほぼクリアできている状態です。もちろん、インターネット投票によって投票率が劇的に上がるとは言い切れませんが、若い人たちが政治に関心を持つ大きなきっかけになると信じています。