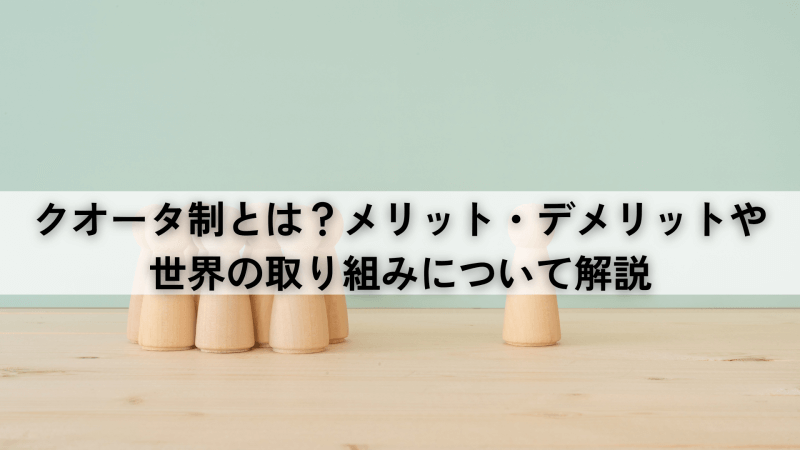憲法89条の条文
第八十九条〔公の財産の用途制限〕
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
引用:日本国憲法
憲法89条をわかりやすく説明
憲法89条は公の財産の支出について書かれている条文です。
国民の税金を、宗教団体や国が管理していない慈善事業や教育事業、またはその団体に使わせてはいけないと示しています。これは、憲法20条に記されている政教分離の原則を、財政の面でも制限していることになります。
政教分離とは、国家と宗教が分離され、政治的な権力と宗教的な信仰が分離されている社会のことを指します。国家が宗教に対して中立的であり、宗教による政治的な支配や介入がない状態を意味します。
そして公の財産における政教分離に関して、初の違憲判決となった事例が愛媛県靖国神社の玉串料訴訟です。当時、愛媛県知事が靖国神社への玉串料を公費で支出していたため、これが憲法20条、89条に違反すると判決を下されました。
また、私学助成も違憲ではないかという声が挙がることもあります。国は、国立・公立の学校だけでなく、国の機関ではない私立の学校にも助成金の援助をしているためです。
しかし、私立の学校も教育に関する公の規則を守っているため、国の支配に属すると解釈ができるとし、違憲とはなっていません。