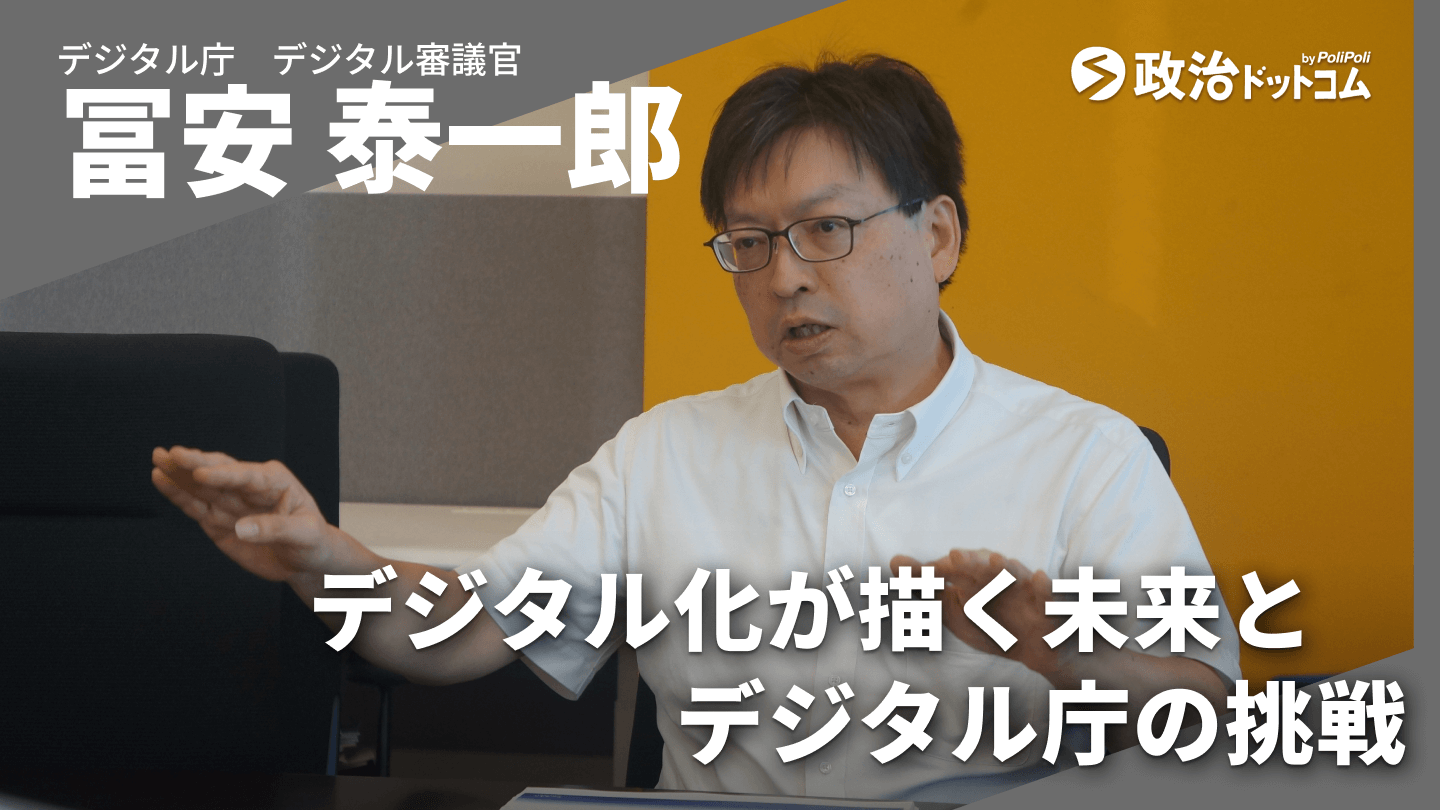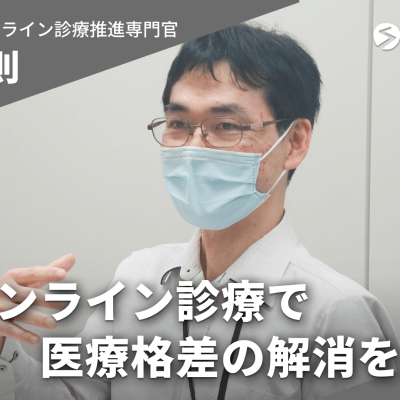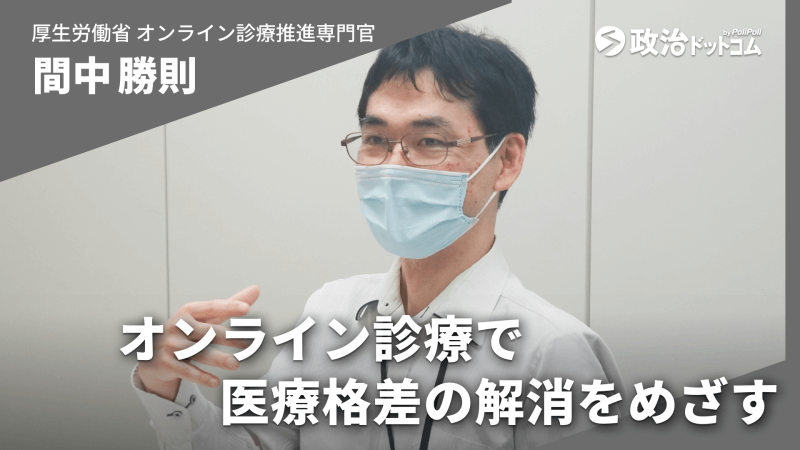生産年齢人口の減少、行政サービスの維持、そして国民の利便性向上。デジタル庁は、日本が直面する多くの社会課題に対し、デジタル技術による解決を目指しています。今回のインタビューでは、デジタル庁の設立以前から現在に至るまで、デジタル改革の最前線を走り続ける冨安デジタル審議官に、行政のデジタル化に向けた取り組みを詳しくお聞きしました。
(取材日:2025年10月2日)
(文責:株式会社PoliPoli 秋圭史)
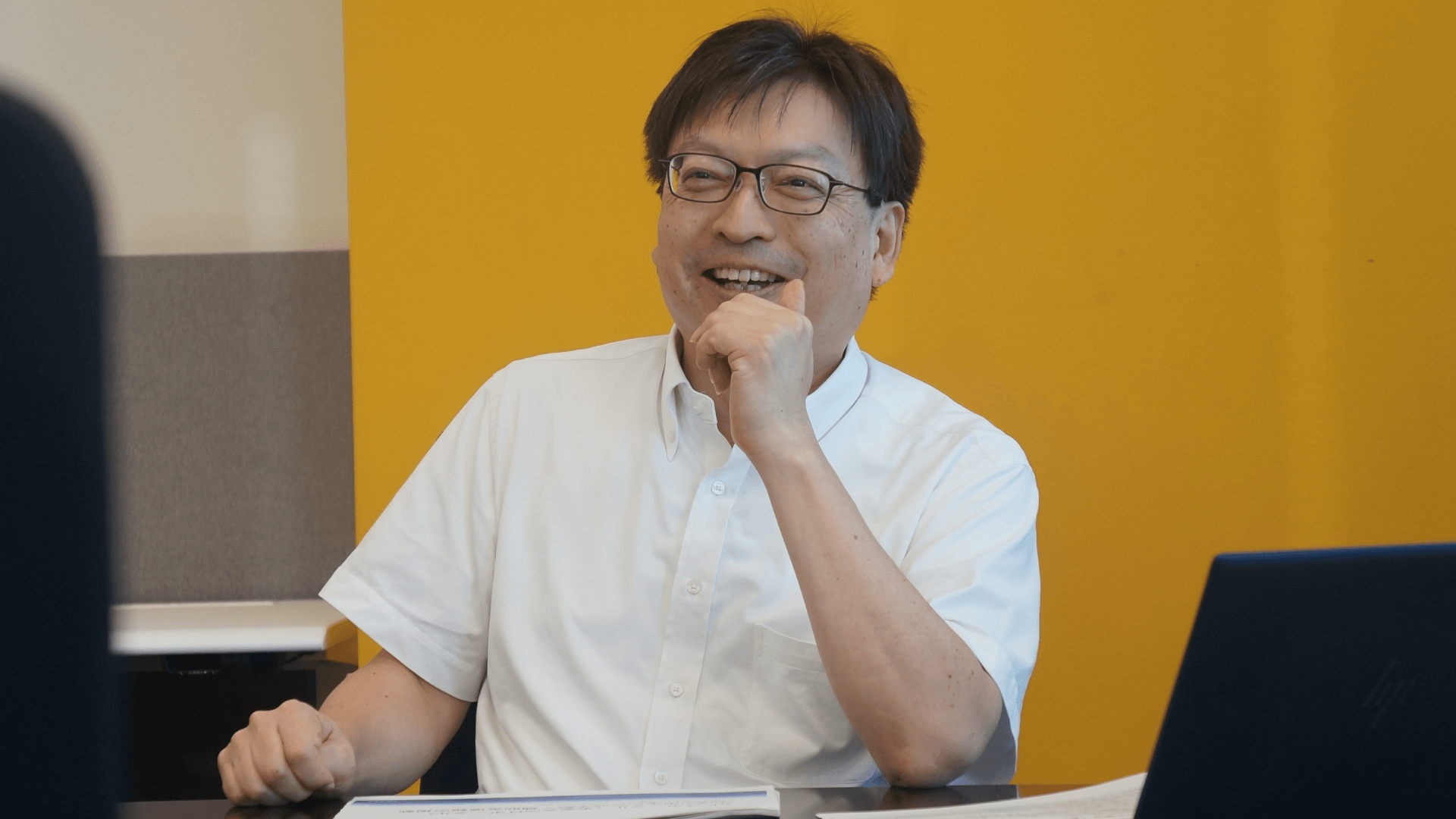
冨安泰一郎(とみやす たいいちろう)デジタル審議官
1968年福岡県出身。東京大学法学部を卒業後、大蔵省(当時)入省。
主計局主計官、財務総合政策研究所総務研究部長などを歴任。
2020年よりデジタル庁設立に関わり、発足後は同庁統括官に就任。
2025年7月、デジタル審議官に就任。
コロナ禍で露呈したデジタル化の遅れを取り戻す
ー2025年9月1日で発足から4年が経過しましたが、改めてデジタル庁設立の目的や意義を教えていただけますでしょうか。
コロナ禍を経て「デジタル化しているつもりだったけど、なかなかうまくいかなかった」という課題が露呈しました。デジタル化を進めるには、民間企業も行政機関も覚悟を持って投資することが必要です。デジタル庁の設立は、政府として「確実にデジタル化を進める」というコミットメントの表れです。
世の中のデジタル化はどんどん進むので、各省がキャッチアップすることも重要ですが、バラバラに追いかけるのは非効率です。デジタル庁がトレンドをしっかりと汲み取り、それを各省や自治体に展開することで行政府全体として効率化することができます。もちろん最終的な目的は国民や事業者の皆様の利便性の向上で、その手段としてデジタルサービスの向上や行政システムの最適化・効率化を推進しています。
ー発足から現在まで、具体的にどのような成果事例がありますか。
ひとつはマイナンバーカードの普及です。さまざまなデジタルツールがある中、これはもっとも厳格な本人確認手段です。今後ますますデジタルでの取引や手続きが増えますが、既に国民の約8割にあたる1億人ほどの方が保有されていて、これは諸外国と比較しても一番の強みだと思います。なりすまし防止効果が高いため、金融機関などの民間事業者の方も、年齢確認や転売防止といった目的で活用を広げています。
もうひとつはアナログ規制の見直しで、各省の協力の下、人や紙の介在が必要な規制を見直しています。目視や常駐規制など、デジタル技術の活用を妨げる手続きを見直しましたが、所管する役所が一つひとつ見直すのは非効率です。従って、デジタル庁が中心となって各府省と一緒に該当する規制を洗い出し、見直しの方向性を提示しました。現在、見直しの対象となった約1万条項の手続きの約98%が完了しています。
そして、これからは便利になった手続きを利用してもらう局面です。例えば、ある自治体では、従来は人が行っていた農業の作付面積の確認に衛星画像の活用を可能とすることで大幅に省力化できるようになりました。このように、人手不足への対応や投資の促進という効果が出てきていますので、見直し結果を活用しデジタル技術をどんどん導入してほしいと考えています。
ーこれらの施策を通じて、特にアプローチしたい社会課題は何でしょうか。
直面する最も重要な課題は、やはり人口減少です。生産年齢人口が大幅に減少するのは確実で、経済面では当然ながら供給制約になりますし、行政機関や民間事業者のサービスをこのまま維持していくことも困難になるおそれがあります。今は問題が顕在化していなくても、各組織のリーダーが中長期的な視点に立って今のうちからデジタルの最適な形での活用を模索し、判断していく必要があります。
ーデジタル化を進める中で、データの利活用も重要な視点になると思いますが、どのような方針をお持ちですか。
データ活用はニーズの発見や付加価値の創出につながるので、行政も民間も確実に取り組まなければなりません。民間企業は新しい顧客体験の創出やビジネスモデルの変革につなげられますし、行政機関は個別最適な行政サービスを提供できるようになるでしょう。当然ながら、今後のAIの活用においてもデータを揃えることがセットで求められることになります。
データ活用の効果を高める上で欠かせないのがデータの「連携」で、業務がデジタル化してもデータは部門内での活用にとどまり、他部門や他主体との共有や連携による利活用や価値創出にまで至っていないのが現状です。特に主体間のデータ連携の推進のためには、信頼性の確保や安心してデータを提供いただくための仕組みをどうしていくかなど検討が必要です。大きな方向性としては、データは資源であり、データの連携・活用によって付加価値の創出を目指していくことに変わりありません。
ーデジタル化やデータ活用による課題解決が求められる分野の例を教えていただけますでしょうか。
例えば、医療・福祉はデジタル化によって将来的に大きなメリットが見込まれる分野で、公的機関のデータ連携になりますが、厚生労働省と一緒に進めているのがPMH(パブリック・メディカル・ハブ)です。医療費助成・母子保健・予防接種・介護保険等において情報を共有し、紙での情報連携を減らし、子育て世帯の受診手続きをスマホで簡単にできるようにするなど利用者の利便性向上を図る取り組みです。現在、多くの自治体と実証を始めています。
また、診療報酬改定のDXも重要です。2年に一度の改定の際にシステム改修の膨大な作業が発生し、医療機関の皆様が大変苦労します。これをデジタルの力で平準化させ、負担を軽減していきたいと思います。
事業者と自治体の双方にメリットのあるデジタル施策を推進
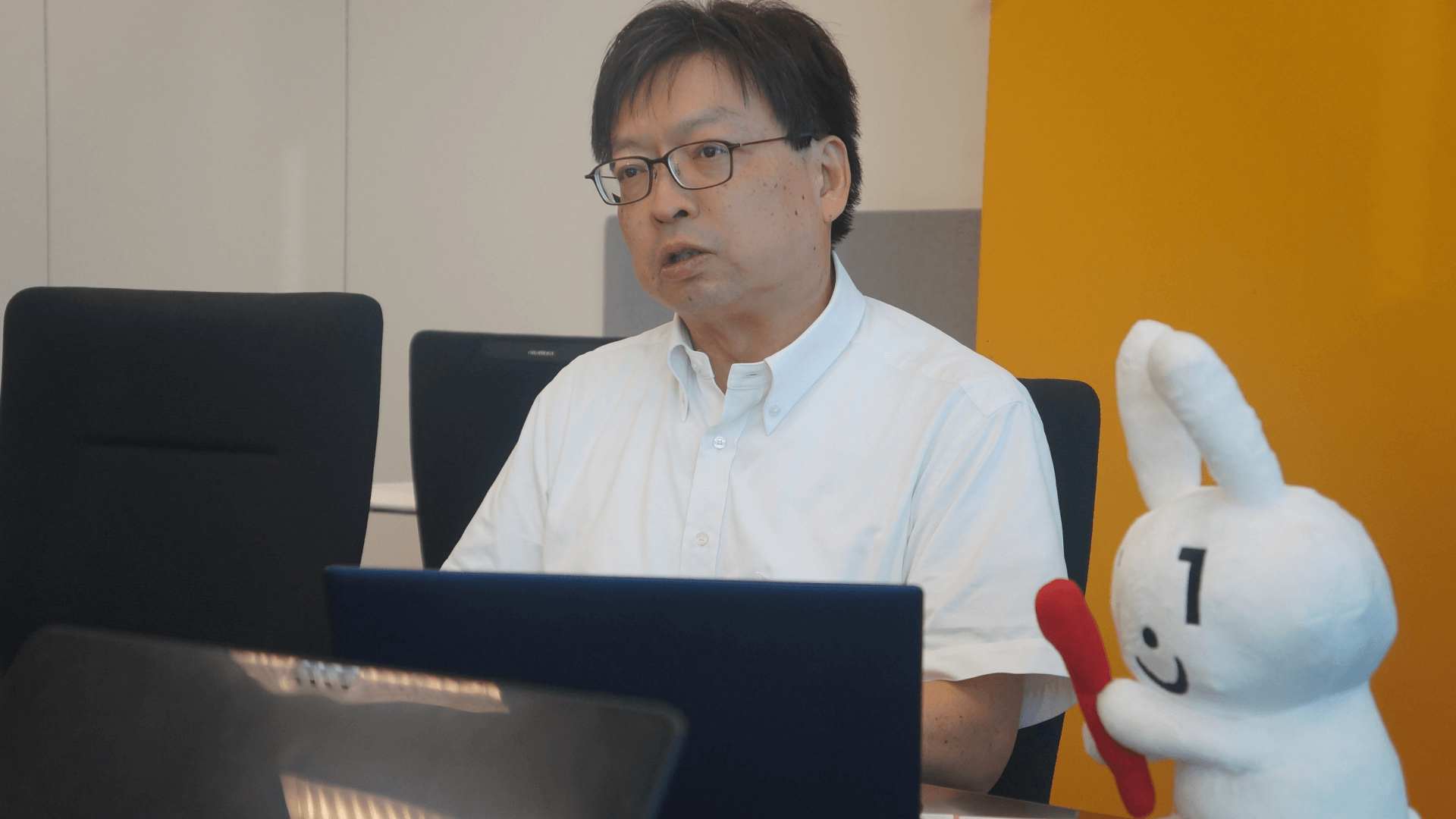
ー現在、進められている事業者向けのポータルについて、具体的な構想を教えてください。
いわゆる「Gビズポータル」ですね。個人の行政手続きが「マイナポータル」で、その事業者版を「Gビズポータル」として位置づけています。これには「手続きの検索」「電子ロッカー」「手続きジャーニー」という3つの機能を盛り込む計画です。1つ目の「手続きの検索」に関しては、事業主に必要な行政手続きを1か所で横断的に検索できるようにします。手続きだけでなく、補助金情報も探せるようにします。
2つめの「電子ロッカー」とは、申請書類などを個別システムではなく共通のロッカーに入れてもらう仕組みです。当局もアクセスして閲覧できるようにする他、場合によっては行政書士なども閲覧可能にして、汎用的なプラットフォームにしたいと考えています。
3つめの「手続きジャーニー」は、事業を始めるときなどに「どの役所が関係しているのか、どんな手続きがあるのか分からない」という問題を解決するための仕組みです。「カフェの開業」など具体的な業種別に、必要な手続きのジャーニーマップを示すものです。
2026年3月に実証版のリリースを予定していますが、事業者の皆様の利便性を高めていけるよう、対応する手続きをこれから増やしていきます。
ー自治体側の業務効率化に関しては、どのような取り組みをされているのでしょうか。
今年3月にスタートした施策として「デジタルマーケットプレイス」があります。自治体や行政機関が業務改善のためにSaaSの導入を検討する際、ベンダーに一社一社問い合わせて比較検討するのは大変です。そこで、複数のSaaSが登録されているデジタルマーケットプレイスで効率よく探せるようにしました。ベンダー側も、ここに登録しておけば一つひとつの自治体に営業をかける必要はなくなります。運用効果を高めるためには多くのSaaSを登録していただく必要があるので、認知拡大に力を入れていきます。
ー財政的に厳しい地方自治体がデジタル化に取り組む上で、デジタル庁がサポートできることは何でしょうか。
今、地方自治体の基幹業務のうち20業務に関してシステムの標準化をお願いしていますが、まず、この20業務については国の方で標準仕様を作ります。また、標準化に併せて、自治体情報システムをデジタル庁が整備するガバメントクラウドへの移行に取り組んでいただいています。セキュリティレベルの高度化、災害への対応強化、システム開発などに柔軟に対応できる、などのメリットがあります。デジタル庁では都道府県ごとに標準化リエゾンを設置するとともに、事業者協議会を設置して円滑かつ安全な移行に向けて密にコミュニケーションをとっています。さらに、運用費について、ガバメントクラウドの利用料低減に取り組んでいるほか、見積の精査には限界があるとの自治体のご意見も踏まえ、見積り精査の支援もしています。標準システムへの移行は2026年3月末を期限にお願いしていますが、市町村ごとの事情もありますので、一定の理由により移行が2026年度以降にならざるを得ないことが具体化した場合には丁寧にデジタル庁、総務省でお話を伺い、概ね5年以内に移行できるよう支援することとしています。
デジタル庁が率先してAIを活用し、社会実装の旗振り役に
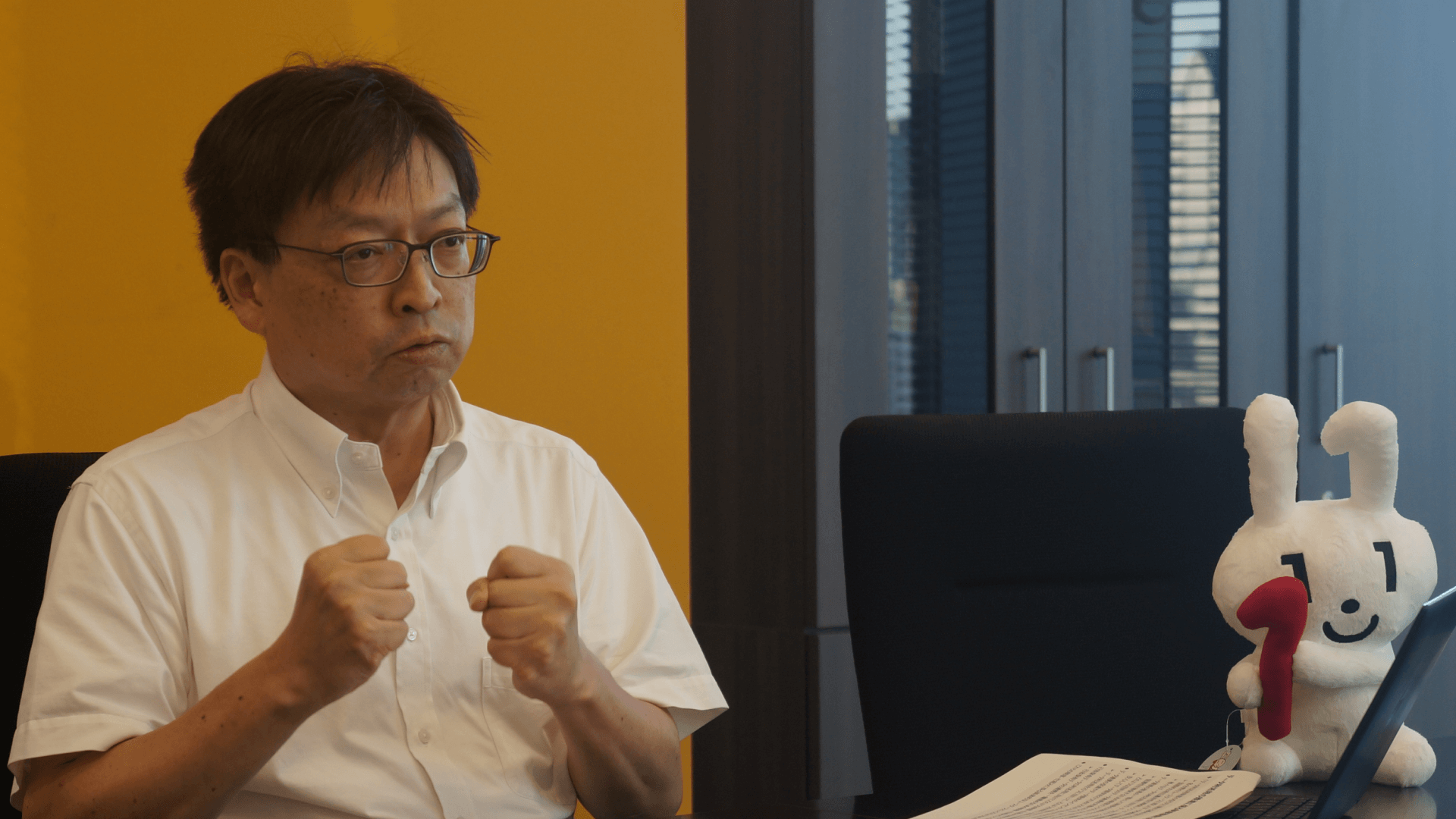
ーこれからのデジタル化にはAIの活用が不可欠だと思いますが、政府内でのAIの位置づけや活用の方針について教えてください。
政府もAI活用は重視しており、今年の9月には「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」が施行されました。AIの利活用を強化する中で、政府内で生成AIを実装していく旗振り役をデジタル庁が担っています。
今年の5月にはデジタル庁が内部開発するAI基盤「ガバメントAI」の一環として、庁内職員が利用できる生成AI利用環境を構築しました。このプロジェクト名は「源内(げんない)」で、平賀源内に由来し、Generative AIの「Gen」と「AI」を掛けた言葉です。
ー「源内」のプロジェクトで具体的に進めている取り組みを教えてください。
汎用的なAIであるチャットや要約、文章作成に加えて、行政実務用のAIアプリも作っています。例えば分かりやすい国会答弁の検索や、役所にありがちな公用文をチェックするチェッカー機能等があります。
また、「法令×デジタル」ハッカソンの中で、ある政策について質問すると、レポートと併せて法令や政府の公式文書の根拠を示す作品が開発され、これは事務の円滑化に役立ちますので、「源内」でも採用しました。他にも旅費の精算など細かい事務作業の効率化に活用していますが、これは旅費精算の際に出る不明点を会計担当に質問する前に生成AIに聞くことで、担当者の負担軽減を狙っています。
ー今後、各省庁にも活用を広げていく上で、運用ルールなどを決める必要もあるのではないでしょうか。
その通りです。「源内」の取組とは別になりますが、各省庁における生成AIの活用を推進するために、デジタル庁ではガイドラインを作成しました。安心してAIの利活用を進めるため、例えば、想定される活用方法がリスクが高いと考えられるケースに該当する場合は、デジタル庁に設置したアドバイザリーボードに相談いただくことにしています。良い事例が出たら各省間で情報共有をします。また、各省にもAIガバナンス体制を確立してもらうため、CAIO(AI統括責任者)を置いてもらうよう要請しました。
国の存続を脅かす課題にデジタルで解決策を出す
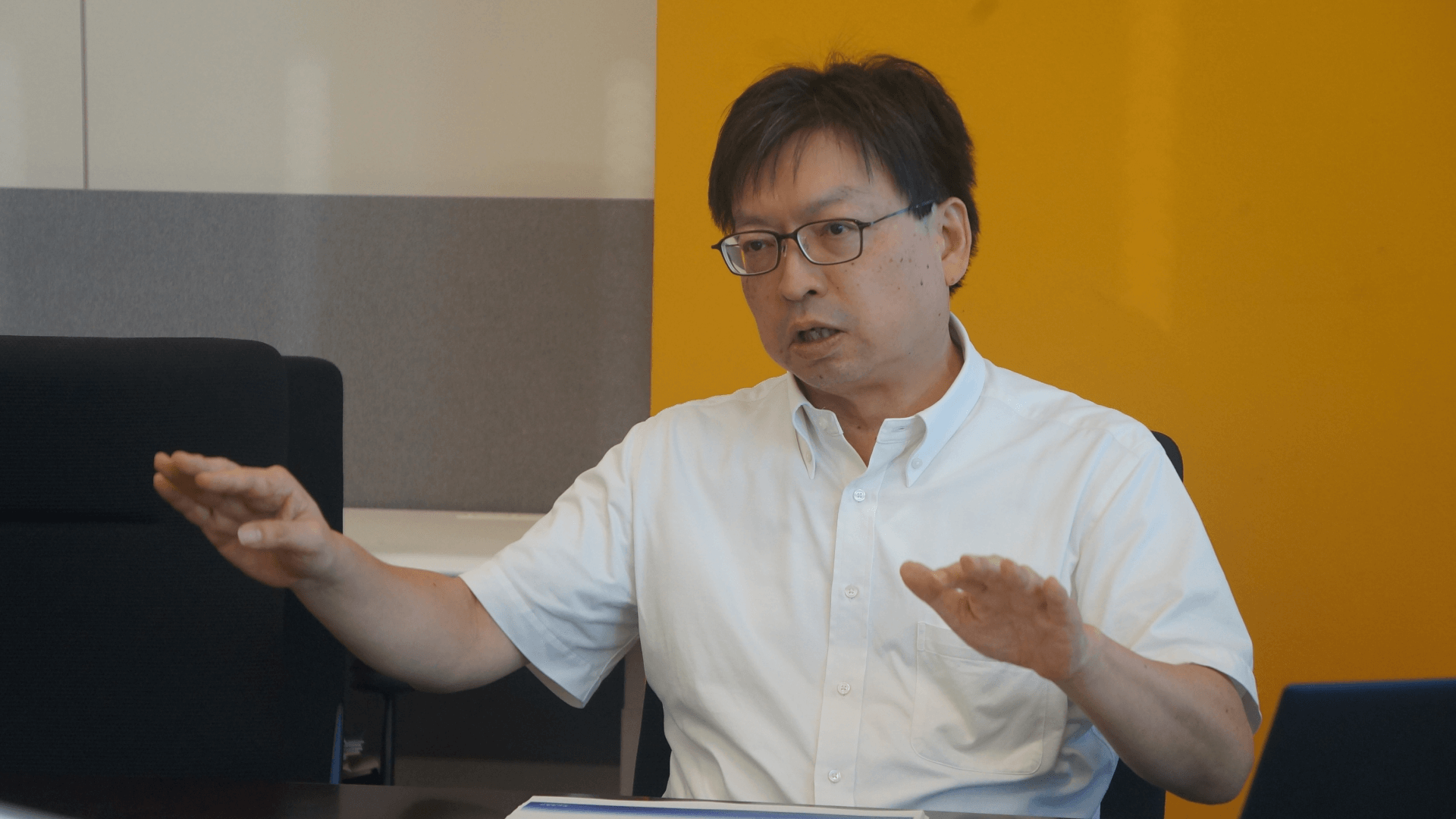
ーデジタル庁が描く将来の展望を教えてください。
もともとコロナ禍で露呈したデジタル活用の遅れを一気に取り戻そうということで、目の前の課題をすべて解消するため、多くのアジェンダが設定されました。加えて、データ戦略の司令塔機能も果たしていく必要があります。これらと向き合う上で必要なのは、人を増やすことです。
その上で、庁のミッションにも掲げている「Government as a Service」と「Government as a Startup」を体現していきたいですね。私なりの解釈ですが、前者はデジタル化はデジタル庁だけでなしえることではなく、各府省や自治体、事業者の皆さんと一緒に実現することなので、デジタル庁が一緒に協働する皆さんの「役に立つ」組織になるということ、後者はデジタルを取り込むため、絶えず「変革」に取り組む、或いは、「新しいこと」に取り組む組織になるということを表していると考えています。
まだまだ道半ばですが、人口減少や自然災害など国の持続性に脅威を与える可能性のある課題に対し、デジタル庁は各府省とともに政府全体でデジタルを活用して解決策を出していきます。「デジタル化」については、国民の皆さまの中にはためらいをお持ちの方もおられると思いますが、地道に課題を解決していくことで「デジタル化を進めてよかった」と思っていただければ本望です。