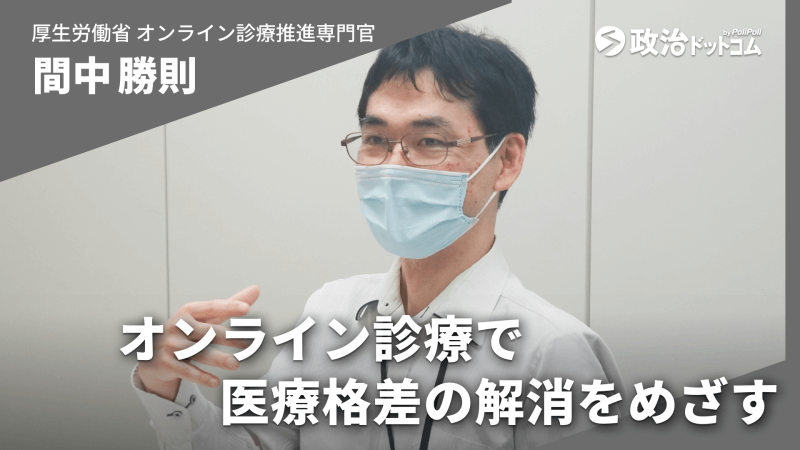三谷英弘 みたに・ひでひろ 議員
1976年 神奈川県生まれ。東京大学在学中に司法試験に合格
2001年 第二東京弁護士会に弁護士登録
2012年 衆議院議員選挙にみんなの党から立候補し初当選
自民党に入党後に文部科学大臣政務官、国会対策副委員長などを歴任し
現在、法務副大臣を務める
海外人気の高まりを受け、日本のコンテンツ産業の輸出額は2023年に5.8兆円を記録。鉄鋼や半導体を超える基幹産業に成長しています。一方で国内では制作現場の疲弊や資金難、世界では権利問題や生成AIへの対策など、課題も少なくありません。今回のインタビューでは、著作権関連に詳しい弁護士出身の三谷英弘議員に、日本のコンテンツ産業が世界で飛躍するための戦略をお聞きしました。
(取材日:2024年9月24日)
(文責:株式会社PoliPoli 河村勇紀 )
アメリカで感じたコンテンツ産業めぐる日本との決定的な違い

ーもともと弁護士をされていた三谷議員が政治家に転身された経緯を教えてください。
私は弁護士の中でも「エンタメロイヤー」と呼ばれるジャンルで、アニメやゲームなどのコンテンツ産業における著作権を主に扱っていました。仕事そのものは楽しかったのですが、メディアやビジネスの仕組みが進化する中で法律がなかなか追いつかない状況を何度も経験していました。
弁護士は社会が変化する中においても基本的には「法律の中でできること」を探すものですが、アメリカの弁護士を見たときに少し考えが変わりました。2007年にワシントン大学のロースクールへ留学したのですが、ワシントン大学のあるシアトルはマイクロソフトなどITの街だからでしょうか、「社会の制度を変えよう」というマインドを持った弁護士が多くいらっしゃいました。
法律に関しても受け身ではなく、法律に限界があるなら、法律そのものを変えていけばいい。そんなマインドに触れたことで、法律そのものを作る政治家への転身を考えるようになりました。
ー具体的に日本とアメリカの違いを実感したエピソードなどはありますか。
僕が留学していたロースクールの卒業論文で書いたのは、アニメやゲームの表現の自由についてなんです。ちょうどアメリカで暴力的なゲームを巡る裁判がありました。ゲーム内に出てくる過激な描写への規制と表現の自由との間で、裁判所が、一度でき上がった法律を表現の自由を侵害するものだとして取り消す、という動きが次々と展開されていました。ちなみに、同時期に日本でもゲーム規制の動きがありましたが、日本では一度成立した法律や条例が違憲で無効になることはほとんどありません。法律を成立させることは大変ですが、一度できてしまった法律を元に戻すことは非常に困難なのです。
だから、表現の自由を一度規制してしまうと「もう戻らない」という危機感があります。アメリカでは規制と緩和が割とアクティブに変わり、それが社会の変化に迅速に対応するアメリカの強みになっています。一方で、一度できたら厳然として動かないのは日本の安定性の証でもありますが、変化の速い世の中にアジャストする上では障壁になっているかもしれません。
クリエイターの地位向上で利益が得られる仕組みを

ー日本のアニメやマンガが世界的に有名になる一方で、コンテンツ産業が爆発的に伸びているとは言い難い側面もあります。
必ずしも利益を生んでいないわけではありませんが、もっと海外に出ていく必要があるとは思います。今後、外貨を稼ぐ産業として鉄鋼産業や半導体産業が期待されていますが、それらと並んでコンテンツ産業も軸になっていくでしょう。まだまだ伸びしろはあります。
ー人材不足や長時間労働など、コンテンツ業界の働き方を巡る問題についてはどのようにお考えですか。
子どもが「アニメーターになりたい」と言ったら反対する親はまだ多いでしょう。もちろん、下請法や最低賃金の規制などもあって問題点は徐々に改善されてきています。しかし、やはり「稼げるか、稼げないか」という視点で見ると、安心してめざせる業界とは思われていません。この状況を打破する上で参考にすべきは、かつて日本のプロ野球史上初の1億円プレーヤーになった落合博満さんの存在です。球団としっかり交渉し、実績に見合った報酬を得ることで後の選手たちの年俸も一気に上がりました。コンテンツ業界でも実績を残しているクリエイターに対して高額の報酬が支払われるようになることが、アニメ業界がより多くの収益を上げられるような仕組みを作っていくことに繋がって参ります。
ただ、そこでボトルネックになるのがアニメの制作会社の立場が弱すぎるという点です。一般的にアニメを製作する場合には何社かが集まって製作委員会を組織するのですが、多くの制作会社はリスクを取るだけの体力がないので、最初にお金を出し合う製作委員会に入れません。そのため、アニメの制作会社は例えば、1億円なり10億円なりの制作費をもらってアニメの制作を進めるわけですが、他の会社に比べて少しでもいい作品を作るために、いい機材を入れたり、アニメの原画の枚数を増やしたりして、もらった制作費を人件費に回すことがなかなかできません。クリエイターには意地があるので、自分が儲けることよりも、いいものを作るためにお金を使ってしまう面があるわけです。しかも、できた作品が世界で大ヒットして製作委員会には利益が落ちていく場合でも、制作会社は下請けとして最初に決まった制作費をもらって終わりになってしまうので、クリエイターに利益を還元することができません。
ーこのような状況に対して政府ができることは何でしょうか。
やはり、まずは、アニメ制作会社を単なる下請けで終わらせずに、その地位を上げて作品が売れたら売れた分だけ制作会社に収益が入る仕組みを作る必要があります。そのためには、最初に製作委員会にはいり、あるいは単独でアニメ製作をできるだけの体力が必要ですし、それを可能にするための資金調達も考えなければなりません。政府としては、アニメ制作会社に対する税制優遇や低利融資などを通じて資金的なリスクを小さくする手助けができると思います。

ー海外市場を開拓するためには、権利関係の問題もクリアする必要がありますね。
コンテンツビジネスというのは、基本的に権利ビジネスです。その権利を守るのが法律なので、法に則って権利許諾を扱う作業は非常に重要です。その視点で考えると、日本の企業はリーガルがまだまだ弱すぎると思います。契約・法務部門にもっとコストをかけ、契約などの手続きは「法務に任せろ」と力強く言えるチームを作るべきです。結局は、その許諾が利益を生むわけですから。
海賊版などの対策にも法律の力が必要です。問題のあるサイトにアクセスできなくする「サイトブロッキング」の是非を巡り、通信の秘密を侵害するとして「憲法違反だ」という声もありますが、理解を深めればこの壁は越えられると思っています。行政の判断ではなく、裁判所が許可した場合にサイトブロッキングができる、という仕組みを作ることで、海賊版などの被害は大きく減らすことができるのです。
また、アニメや漫画の分野ではありませんが、音楽の分野で乗り越えないといけない障壁のひとつに「レコード演奏・伝達権」という権利がないという問題があります。例えば、あるアーティストの楽曲が海外の喫茶店等で演奏されたとき、通常はアーティストやレコード会社に使用料が支払われます。ところが日本にはこの権利が存在しないため、たとえ海外の公の場で曲が流れてもアーティストたちに収益が生まれないのです。
この権利は世界で150カ国近くが持っているのに日本は持っておらず、アーティストやレコード会社の海外進出のモチベーションを下げてしまっています。今、この法改正に向けて努力しているところです。補助金も大事ですが、アーティストが自発的に海外に打って出る仕組みを作ることで、自発的な外貨獲得につなげていきたいと思います。
予算の集中投下でコンテンツ産業を日本の成長産業に

ーグローバル展開を考えたときに、日本のコンテンツの最大の魅力はなんでしょうか。
いわゆる「アメコミ」を例に挙げると、キリスト教的な善悪二元論的な面があって、いわばデーモンにあたる悪役を、いわばゴッド側の主人公が征伐するといった世界観があるわけですが、日本の作品の良さというのは、そういった宗教的、社会的な制約があまりないことだと思っています 。
例えば、ガンダムでは、連邦側にも悪い人物がいるし、ジオン側にも良い人物がいて、どっちが正しいとは言い切れない。複雑に人間関係が絡み合って、必ずしも悪い人が悪いだけではありません。最近で言うと、鬼滅の刃でも、鬼の側にも色々な背景や事情があったりして憎み切れないキャラクターを丁寧に描くことが人気につながっています。そういった深みのある登場人物やストーリーが日本のコンテンツの良さの一つだと思います。
しかし、海外に日本のコンテンツを輸出して、様々な文化や社会の中で広めていくときに、どうしても直面するのは表現の自由をどこまで尊重するかという問題です。わかりやすい話だと、日本のアニメや漫画ではタバコを吸っているキャラクターが、アメリカではタバコ吸っていなかったりします。確かにその国の規制には引っかかりにくくなるし、広く売れるようになる面もありますが、本来持っていたキャラクターの魅力を削ぐことにもつながりかねない。このような問題に直面したとき、言われるがままに表現を変えるのは最悪な対応で、かえって日本のアニメや漫画のコンテンツの良さを押しつぶしてしまう恐れもあります。だから、国が様々な形で支援をしたりお金を出したり関わっていく時には、コンテンツの中身には手を出さないようにすることが大切だと思います 。
ーコンテンツ産業を巡っては、生成AIによる脅威も話題になっています。この点についてご意見を伺えますでしょうか。
生成AIそのものへの懸念は理解しています。しかし、その存在自体を消し去ることはできませんから、どう付き合っていくかを考えなければなりません。たとえば、背景画をAIに描かせてクリエイターの作業負担を減らすなど、有益な使い方ができますし、実際私もAIで政策チラシを作ったこともあります。ただやはり問題があるとすれば、AIが誰かの創作物を学習に使っても、当然には原作者にはお金が還元されない形になっていることです。繰り返しになりますが、これ以降AIをなくすことはもうできないので、現在のAIの仕組みの中でどう収益を上げていくかを考えなければなりません。
少し昔の話になりますが、かつて、アメリカでは日本のアニメを違法配信するサイトがあり、会員から月額の会費を集めて大きな収益を上げていました。日本の権利者がそのサイトに対して何をしたかというと、正規のライセンスを与える代わりにライセンスフィーを払わせて、適法な事業としてアニメ配信できるようにしました。結果として、日本のアニメをアメリカで正規に配信する動きが非常に円滑になったのです。
だから、作られてしまった仕組みに対して「ダメだ、ダメだ」と言うだけでなく「この中でいかに収益を上げるか」という視点でも考えることが重要なのです。「AIが出力したものは尊重するから、きちんと対価を支払う仕組みを築くべきだ、クリエイターに対価を支払っていないAIなんか俺らは認めない」という意識をファンダムの中で形成することが、最終的にみんなの利益になるのではないでしょうか。
ーコンテンツ拡大のため、日本独自でプラットフォームを持つのはどうですか。
これは難しい問題で、NetflixやAmazonなどはとにかくタイトルを数多く抱えたいので、お金に糸目をつけないケースもあります。だから、海外のプラットフォームと組むことで収益が大きくなる可能性はあります。日本独自のプラットフォームをゼロから構築するのか、海外のプラットフォームを活用するのか、さまざまな意見があると思います。
いずれにせよ、国家としての意思を明確にすることが大切です。半導体の分野では何兆円という単位で投資をしていますが、コンテンツ産業では数百億円くらいの規模感しかありません。本当に伸ばしていくなら人員をそろえて、予算も集中投下する必要があります。しかし、日本はどうしても予算含め、各省庁の動きがバラバラで、横断的に動ける人がいません。だからこそ、各省庁に散らばっているコンテンツに関する予算や人員を一つにまとめて「コンテンツ庁」を作り、この分野に政府が本気でコミットする意思を示すことができれば、コンテンツ産業もさらなる拡大に向けて前進すると信じています。