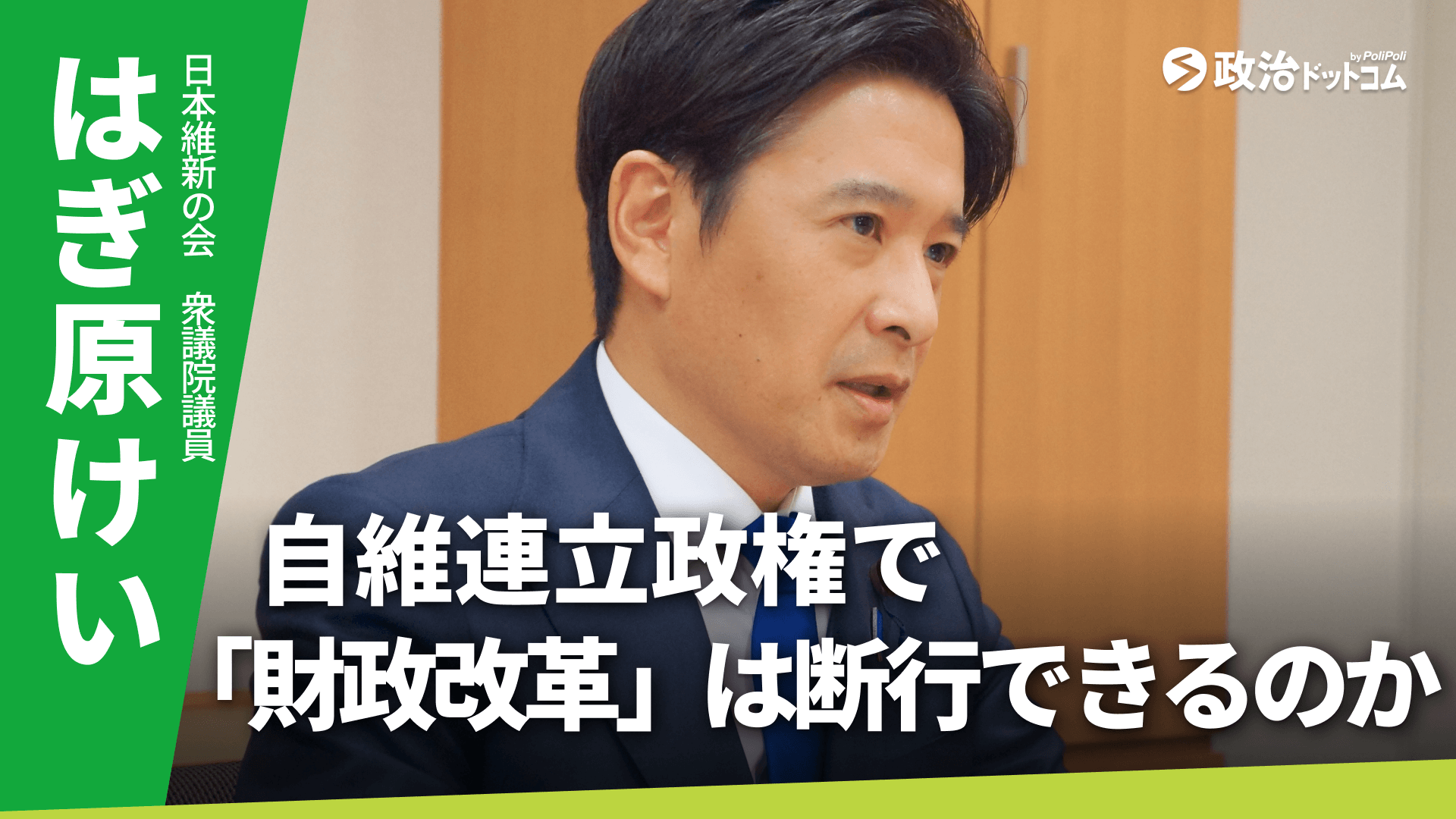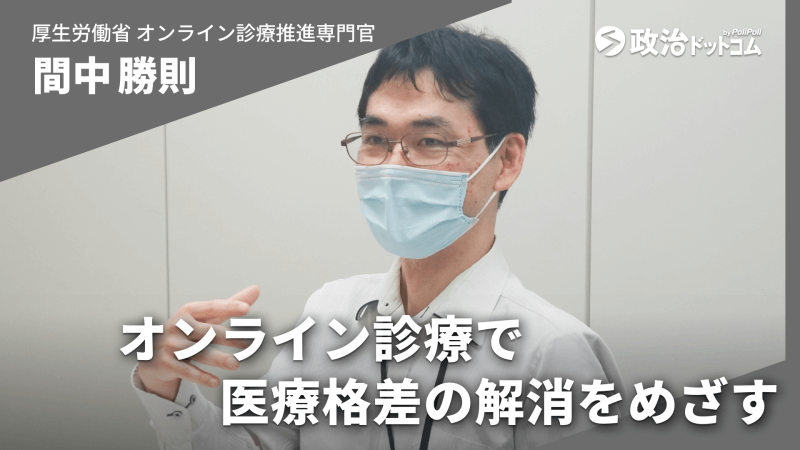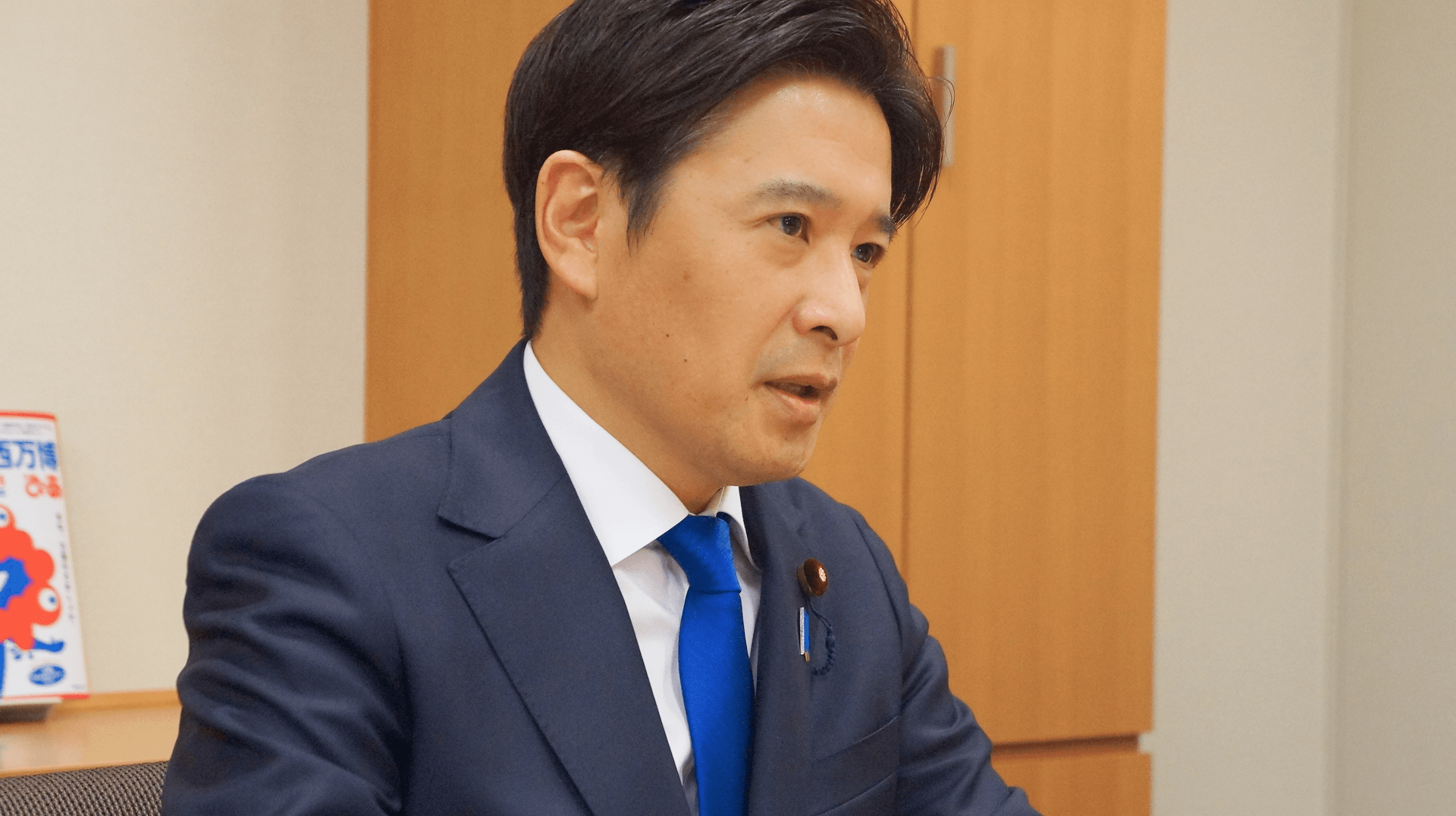
萩原 佳 はぎはら けい 議員
1977年大阪府生まれ、茨木市育ち。監査法人勤務を経て、公認会計士・税理士として茨木市で会計事務所を開業。
2017年より茨木市議会議員を2期務める。
2024年の第50回衆議院議員選挙で初当選(1期)
現在、衆議院財政金融委員会理事、党税制調査会事務局長を務める。
自民・維新連立政権が発足し、その政策合意文書には柱の一つとして「経済財政関連施策」が盛り込まれました。今後の財政運営の舵取りに国民の大きな注目が集まっています。
今回のインタビューでは、国民生活に直結するガソリン税の暫定税率廃止や租税特別措置の見直しなどの政策を、党の中心となって立案されているはぎ原けい議員にお話を伺いました。積極財政を掲げる自民党との連立政権において、日本維新の会はどのような役割を果たしていくのか。そして、政策が実現した時、私たちの暮らしは具体的にどう変わるのか。その核心に迫りました。
(取材日:2025年11月6日)
(文責:株式会社PoliPoli 大森達郎 )
「変わらない地元」への疑問。会計士から政治家を志した原点
―公認会計士・税理士という、政治と異なるキャリアから、なぜ政治家を志したのでしょうか?
学生の頃から、漠然とですが、一番人の役に立つ仕事は「政治」だろうと考えていました。ただ、当時は自分には関係ない世界だとも思っていました。その後、会計士・税理士として独立し仕事をしていましたが、自分や家族、顧客のことだけを考えて働く日々に、「このままでいいのかな」という思いもどこかで抱えていました。
転機となったのは30代後半です。私の地元は大阪府茨木市なのですが、1970年の万博の時に再開発されて以来、私が小学校の時から駅前の風景が全然変わっていなかったんです。時代が進む中で、なぜ私たちの町は変わらないのか。その疑念を持った時に、市議会議員選挙があると知りました。
他の人が変えてくれるのを待つより、自分の会計や税務のキャリアは他の議員にはない経験ですし、地元に貢献できるのではないかと思い、挑戦したのが始まりです。
―市議会議員から、国政へ挑戦されたのはなぜですか?
茨木市政の仕事をしている中で、国政を変えなければ地域を良くすることができないと感じる場面が多くありました。地方行政はもちろん、税制や財政の実務を知っているからこそ、なおさら強く課題を感じたのです。それならば、より自分の力を生かせるのは国政ではないかと考え、チャレンジしました。
結果として、自分のスキルは国政において貢献できていると感じています。国会議員全体を見ても、会計や税務の実務経験者は多くはありません。官庁の皆様は優秀な制度設計のプロですが、どうしても「現場の痛み」や「商売の苦労」と異なる視点を持っているところもあると感じます。現場の視点をかけ合わせることで、より良い政策が作れると考えています。

―会計士・税理士の視点から見て、日本の財政金融政策における最大の課題は何だとお考えですか?
「少なすぎる収入に対して、多すぎる支出がある」ことが常態化していることだと思います。長年の政策の積み重ねの中で、現在の不健全な経営状態をより改善していく必要があります。
その一因として、国家財政にも民間企業や家計のような「経営感覚」をより取り入れる必要があると感じています。税収の確保だけでなく、どうやって経済を成長させていくかという視点や、現場の実情に即した資金の流れを作る視点が必要です。一つの商品が売れるまでの現場の苦労や工夫、そういった感覚を政策に反映させていくことが大切だと考えています。
与党の中の野党として。維新が果たすべきブレーキとアクセルの役割
―自維連立政権の誕生により、野党から与党としての役割に変わりました。心境の変化はありますか?
役割が大きく変わっていると実感しています。今までは法案が出た後に議論をする立場でしたが、今はその法案が出る前の、立案段階から関わることになりました。より機密性の高い情報も増え、他党の議員の方々とのコミュニケーションの質も変わり、与党としての重責を肌で感じているところです。
―今回の歴史的な自維連立政権の政策合意をどのように評価されていますか?
非常に大きな一歩だと評価しています。特に意義深いのは、これまで自民党が「改革工程に乗せているのに、様々なしがらみがある故に先送りにしてきた課題」を、この政策協議の中で前に進めることができるという点です。たとえば、OTC類似薬の保険適用見直しなどもそうですが、できない理由を探すのではなく、期限を区切って実行に移す。「課題として取り組む」と合意文書に明記させたことは、実務者として非常に価値を感じています。

―はぎ原議員は税制調査会事務局長として実務面から支えてこられました。特に「経済財政政策」の分野で、こだわった点はどこでしょうか?
まず、合意文書の構成そのものです。文書の一番はじめに「経済政策」、中でも国民の生活に大きく関わる物価高対策を持ってきたこと。これは党として強く提案させていただきました。国民生活がインフレで苦しんでいる今、まずやるべきは生活に直結するコストを下げることです。だからこそ、「ガソリン税の暫定税率廃止」を経済政策のトップに掲げました。もちろん、これは各党が長年取り組んでこられたテーマでもあります。そこに我々が加わったことで、改革の機運をより加速できたのではないかと考えています。
―ガソリン減税の合意に至るまで、交渉が難航していたと伺っています。
調印式では代表者たちが笑顔でサインをしていましたが、そこに至るまでは相当なすり合わせがありましたし、私もその厳しさを肌で感じていました。
協議の中で、我々は単に「減税したい」と主張したわけではありません。出来ない理由ではなく、できる理由。そして、実務的な観点を重視し、自民党側、そして、公明党を始めとする野党側との合意点を探り続けました。
事務局長として私が特にこだわったのは、「順序」です。国民の皆様にご負担をお願いする前に、まず徹底した歳出改革を行う。政策効果の薄い事業はやめる。その上で財源が足りなければ議論する。
ガソリン税の暫定税率廃止をはじめとした「12本の矢」にも、この「身を切る改革」の哲学を、埋め込むことができたのではないかと考えています。
―積極財政を掲げる自民党政権の中で、維新はどのような役割を担っていくのでしょうか?
我々はよく「緊縮財政」と誤解されますが、決してそうではありません。我々が目指しているのは、「無駄なものをなくして、次世代に投資をしよう」ということです。
たとえば、「租税特別措置」の見直しです。特定の分野に対する優遇措置が、時代の変化に合わせて本当に必要なのか、政策目的は達成されたのではないか。これは、費用対効果の観点から検証を行うことができます。維新はしがらみがない分、フラットな目線でこの予算はより効果的な分野へ回せるのではないか、と考えています。
無駄な支出には「ブレーキ」をかけ、次世代への投資や成長戦略には「アクセル」を踏む。単なるアクセル役ではなく、財政規律と成長のバランスを監視し、コントロールする役割。それが、実務に強い維新が連立政権で果たすべき、最大の責任だと考えています。
お金の使い道が「投資」か「浪費」かという視点を持つ
―合意した政策を実現するために、今後どのような道筋を描いていますか?
前提として「魔法の杖」はありません。
維新の強みは、吉村代表や藤田共同代表などの若いリーダーの下で「意思決定が早い」こと、そして「地道な物事を一歩一歩、着実に進めていく」という実務能力の高さです。魔法の杖を求めるのではなく、民間と同じように、着実に進める。そのために、政策の進捗状況を確認する実務者協議の場なども作っていきます。
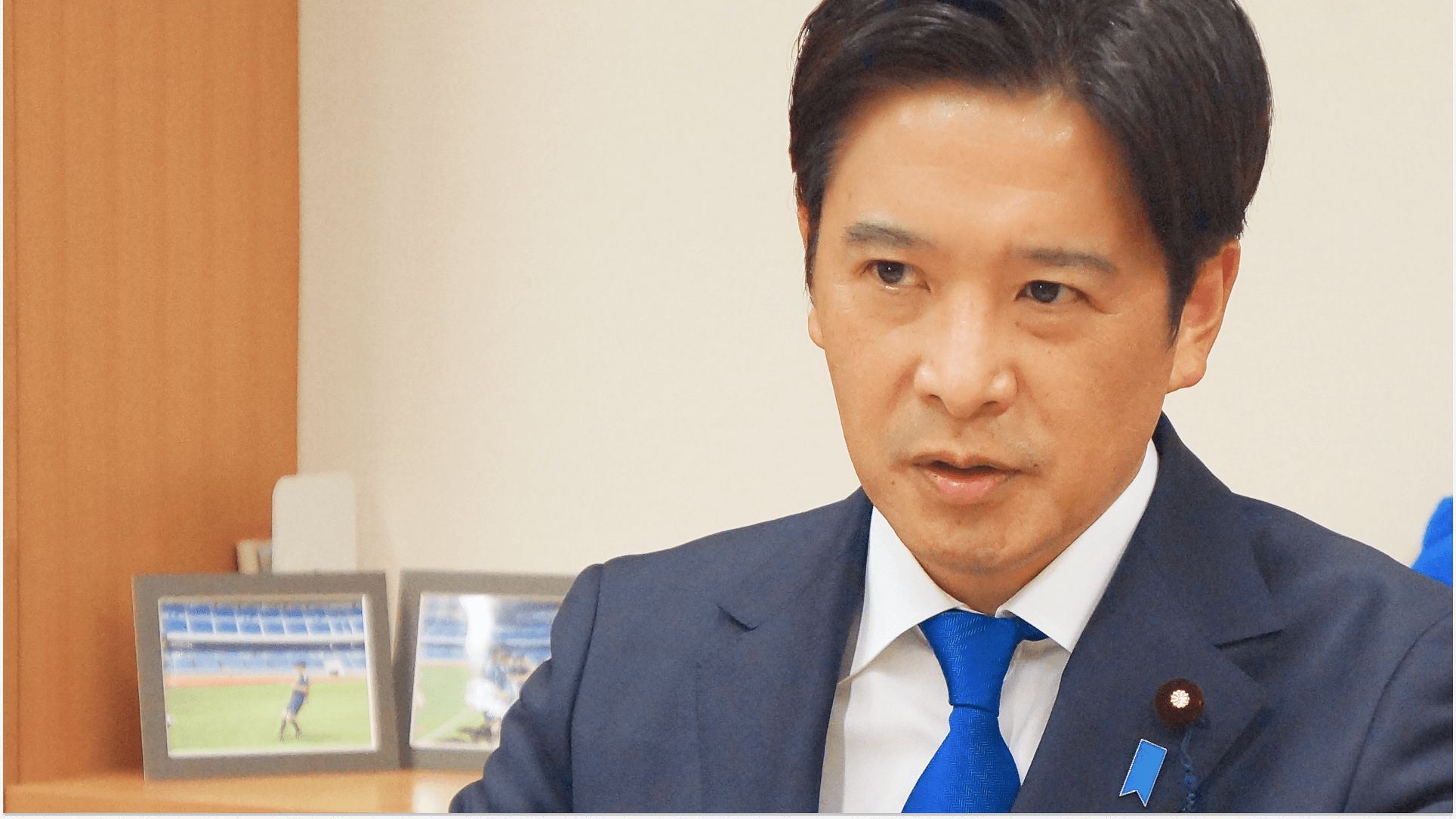
―最後に「財政」について、注目してほしい点は何でしょうか?
「財政」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、要はそのお金の使い道が、将来の役に立つ「投資」なのか、それとも消えてなくなるだけの「浪費」なのかという視点を持つことが大切です。
たとえば、手元に100万円あるとします。これを将来の仕事のために、高性能なパソコンや機材を買うのに使うなら、それは未来の利益を生み出す「投資」になります。でも、単に贅沢品を買って消費してしまうだけなら、それは「浪費」です。国の税金も同じです。子どもたちの教育無償化にお金を使うことは、将来の日本を支える人を育てる「投資」です。一方で、変化すべき古い業界を延命させるだけの補助金は「浪費」と言えるでしょう。
難しく考える必要はありません。
金利の話も同様です。身近な例で言えば、今の物価が上がっている時代に「投資は怖いから」と銀行に預金し続けること。これは価値が下がっている日本円に投資しているのと同じことです。物価が上がれば、同じ100万円でも買えるものは減ってしまいますから、実質的に資産は減っていることになります。
ご自身の家計と同じように、国の予算に対しても、これは未来のための投資か、それともただの浪費か、というシンプルな物差しで見ていただければ、政治はもっと身近なものになるはずです。