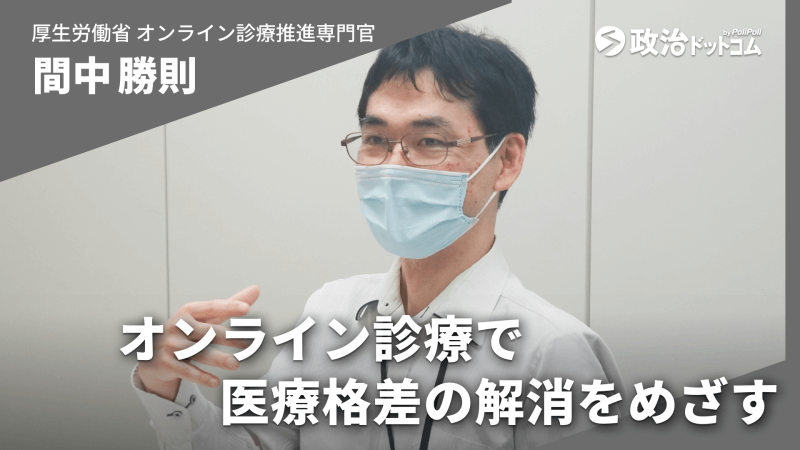草間剛 くさま つよし 議員
1982年生まれ。青山学院大学法学部公法学科、
早稲田大学大学院公共経営研究科を経て、早稲田大学マニフェスト研究所入所。
その後、神取忍参議院議員の公設第一秘書、横浜市議(3期)を経て、
2024年衆議院銀選挙初当選(現在1期目)。
横浜市議を経て昨年の衆院選で衆議院議員に初当選した自民党・草間剛議員は、大学時代から議員立法へのこだわりを持ち続けています。草間剛議員が議員立法にこだわる理由と国会議員の議員立法の実状を、草間議員が横浜市議時代から誘致に尽力した8月に横浜で開催されるアフリカ開発会議(TICAD9)への思いとともに伺いました。
(取材日:2025年3月18日)
(文責:株式会社PoliPoli 児島花生里)
なぜ議員を志したのか?議員立法に興味を抱いた原点について
—草間議員は大学院卒業後、横浜市議を経て昨年の衆議院議員選挙で当選し国政に進出されました。最初に政治を志した経緯を教えてください。
私が政治に興味を持った原点は、小学6年生の社会の授業です。社会では、行政・司法・立法の三権分立を学びますよね。行政は市役所でイメージがわきますし、司法も話題の裁判があればニュース報じられるのでイメージできます。ただ、立法だけはイメージがわきませんでした。先生からは立法は法律を作る所でその法律を作るのが議員の仕事、と説明されました。しかし議員のイメージといえば、当時少年野球をやっていた私にとっては、大会の開会式に来る人、という程度。実際、1990年代の地方議会には議員立法はほとんどなく、国に言われたことを実現するのが主な仕事だったんですね。
しかし、国の事務を地方自治体の首長に実施させる機関委任事務制度が2000年4月の地方分権一括法の施行で廃止され、地方議会も主体性を持って立法の仕事をしなければいけない、と感じたのが大学の頃でした。

—草間議員のプロフィールからは、地方議会そして立法へのこだわりを感じましたが、そんな原体験があったのですね。
大学時代はアメリカンフットボールに熱中しましたが、卒論は明治時代の地方議会制度を書きました。明治の横浜市議会の議事録を読むと、明治時代のほうが今よりも活発な議論が行われていた事実に驚かされ、同時に今の地方議会に疑問を感じました。その後、日本の政治を変えるには地方議会の改革しかないと思い、元三重県知事の北川正恭教授などがいる早稲田大学大学院公共経営研究科に進学しました。院生時代は地方議員の立法を手掛ける活動に注力し、同級生で岩手県江刺市議の佐藤邦夫さんと江刺市議会では最初で最後の議員提案条例となった「えさし地産地消推進条例」の制定に向けた活動を行いました。この条例制定の活動を元に書いた「地方分権時代における地方議会の役割」という論文は、優秀論文の1つに選ばれています。その後も、地方議会改革を実務として進めたい。という思いから、北川教授が所長を務める早稲田大学マニフェスト研究所に就職しました。同研究室で各地の地方議会改革のお手伝いをして、地道に活動を続ける一部の地方議会の姿から議会再生の可能性を確信しました。
日本の政治を変えるには地方議会の改革しかないと思い、地方議会改革を実践するため、地方議会を目指しました。立法府を活性化させて政治を良くしたい、というのが私の思いです。横浜市議時代は7本の議員提案条例を提出しました。
—「共働き・ロスジェネ・子育て世代の代弁者」として子育て政策の全国一律化などを目指されています。当事者としてのおもいなどはありますか。
私は横浜市議会の本会議を立ち会い出産のために休んだ初めての男性議員なんです。
出産のために議会を休んだ女性議員は横浜市議会でも過去何人かいたのですが、男性では私が初めてです。男性議員が立ち会い出産で議会を欠席した例はなく、先輩議員に相談したら、それは絶対に行った方がいいよ、とアドバイスされ、当時の自民党議員の皆さんに説明して行かせていただきました。その後、立ち会い出産での欠席は議会でルール化されたのですが、当事者が政界に入ることでルールは変わると実感しました。この経験からも、様々なバックグラウンドを持つ人がどんどん政治の世界に入るのはよいことだと思っています。

横浜市議として7本の議員提案条例を提出、アフリカ開発会議(TICAD)の誘致にも尽力
—草間議員が横浜市議時代から誘致に尽力したアフリカ開発会議(TICAD)が、今年8月に横浜で開催されます(TICAD9)。開催への思いをお聞かせください。
TICADは、Tokyo International Conference on African Development(アフリカ開発会議)の略であり、アフリカの開発をテーマとする国際会議です。1993年から日本政府が主導して、国連、国連開発計画(UNDP)、世界銀行及びアフリカ連合委員会(AUC)と共同で開催しています。私は横浜市議時代の2015年に日本アフリカ友好横浜市会議員連盟を立ち上げて、事務局長に就任しました。そしてケニアで開催されたTICAD6,チュニジアで開催されたTICAD8にも参加し、今年のTICAD9の横浜誘致を実現しています。また自民党の牧島かれん国際協力調査会長、鈴木貴子TICADプロジェクトチーム座長の下、私が党のプロジェクトチームの事務局長に就任しました。
トランプ政権になってアメリカがアフリカへの様々な支援を打ち切っています。世界中が自国中心主義になっている中で、日本も税金で外国を支援する国際協力の意義を問われる時代です。だからこそ、日本が今までやってきた国際協力を再検証しつつ、アメリカや中国、ロシアとは異なる日本独自の立ち位置で、アフリカに何ができるか新しい戦略が必要と感じています。以前に比べると企業もアフリカへ関心を抱いており、政府が全部やるというより、民間・若手・女性といった方々にもアフリカに関わっていただくことが、日本にとって重要ではないでしょうか。
—若い方などに対し、TICADとどういった関わり方をして欲しい、といった思いや希望はありますか。
TICAD9の期間中は、アフリカの政府関係者が横浜の街にあふれます。その期間に横浜に来ていただきたいですね。アフリカの政府関係者も横浜をよく知っている訳ではありません。ただし食事は取らなければいけないし、その中でラーメンは食べてみたいなどの希望もあり、皆さん横浜の街をウロウロするんです。普通に大臣などの偉い人が街の食堂でご飯を食べています。TICAD9のイベントなどにも積極的に参加して頂くのが理想ですが、まずはTICAD9の期間中に横浜に来て街を歩くだけでも相当楽しめると思います。
アフリカの外交官などが街にあふれており、そのような方々がすぐに捕まるので、イベントで是非ディスカッションなどを試みてください。

国会議員となり永田町で日程に追われ多忙な日々、それでも現場の声を聞き続けたい
—草間議員は昨年10月の衆議院議員選挙で衆議院議員に初当選されました。地方議員から国会議員に立場が変わり様々な環境変化があったかと思いますが、特に立法の観点でどのような変化を感じておられますか。
私は学生の頃から立法にこだわってきましたが、国会は地方議会に比べはるかにたくさん立法しています。なぜなら、日本は議員内閣制なので。与野党問わず様々な法律が作られており、地方議会よりも国会のほうが立法は活性化しています。ただし永田町や国会の中だけで法律を作ると、確かに政策としては妥当かもしれませんが、国民の共感が得られません。様々なステークホルダーを巻き込んで法律や政策を作ることが大切です。共感を得られる政策をやっていくことが、政治離れを少しでも止める手段だと思っています。
ただし、国会議員はとにかく時間がありません。市会議員の時はまだ色々な現場に行く余裕があったのですが、国会議員になってから、平日はほぼ永田町にいます。私は横浜に住んでおり、毎日横浜から永田町に通っているのですが、日中はほとんど永田町にいるため、現場を知る力は地方議員の頃に比べると落ちていると感じざるを得ません。
—永田町で忙しい理由はどのあたりにあるのでしょうか。
国会の日程ですね、国会の日程をふまえて誰をいつ捕まえるか、というのが本当に重要なのです。今回の衆議院予算委員会の分科会で何度も質問を行いましたが、質問を作る過程で忙しい中でも現場の声を聞きました。しかし、国会で質問するタイミングは極端な場合、急に翌日入るなど緊迫した日程でやっています。このため、ゆっくりと現場を見ている時間がありません。上手にやれば、現場の声も取らずに永田町だけで質問を作ることができてしまいます。忙しいからこそ、日頃の活動で現場の声をどう拾っていけるのか、ということが本当に重要です。それをやっていないと、いつか永田町の声だけで現場からかけ離れてしまうのだろうな、と感じています。

格差社会の中でも誰1人取り残さない政治を目指したい
—今後のやりたい政策や、今度どんな日本にしたいかといった大きな方向性について、草間議員の思いをお聞かせください。
本当に国際情勢が大変な状況にあるため、安全保障的にも強い日本を作る必要があります。また、これだけ格差が拡大して苦しんでいる人も多いため、誰1人取り残さない政治を行う必要があります。また先ほども申しましたが、永田町だけでやらない、ということも本当に重要です。現場の声を聞く政治をやっていく必要があります。
—最後に読者に対するメッセージをお願いします。
こちらの記事を読んでいるのは、どちらかというと政治に関心がある方だと思います。政治に関心があって、このような記事をご覧になっているなら、もう一歩踏み込んで“政治とどう関わるか”という段階に進んでいただきたいです。もう一歩踏み込む方が増えれば増えるほど、この国は良くなると私は思います。読者の方には、政治に対し一歩踏み込む勇気をほんの少し持っていただくことをお願いしたいですね。