
藤田 文武 ふじた ふみたけ 議員
1980年大阪府寝屋川市生まれ。
高校教員、留学、会社経営等を経て、2019年大阪12区にて初当選(現在3期)
2021年〜2024年日本維新の会幹事長、2025年共同代表に就任
2025年7月に実施された第27回参議院議員選挙の結果を受け、日本維新の会は党の今後を占う重要な分岐点に立っています。初の国会議員団代表選挙を経て、藤田文武議員が吉村洋文代表とともに新たなリーダーとして選出されました。
「原点に返り、捨て身で進む」という力強い決意のもと、藤田議員が新共同代表としてこの難局にどう立ち向かい、党の舵取りを担っていくのか。今後の党運営、そして日本が直面する本質的課題に切り込む政策についてお伺いしました。
(取材日:2025年8月28日)
(文責:株式会社PoliPoli 大森達郎)
「維新らしさ」の喪失。選挙結果を受け止め、原点に立ち返る
ー第27回参議院議員選挙から約1か月が経ちました。藤田議員は、前回の選挙の結果についてどのように受け止めていらっしゃいますか。
大変厳しい結果だったと認識しています。全国比例の獲得票数は438万票と、3年前の785万票から大幅に減らしました。大阪では支援者のみなさまに支えられ、4議席中上位2議席を確保できたものの薄氷を踏むような戦い、大阪以外では非常に厳しい結果でした。
今回の選挙での反省点は、日本維新の会が何を訴え、何を実現するのかということを、もっとシンプルに伝えなければならなかったことです。また、躍進した他党と比較して、我々には攻めの姿勢が足りなかった。来る衆院選に向け、国会活動から党のあり方まで、全てを見直す必要があると考えています。
ーかつて、日本維新の会の幹事長として、2022年に党の「中期経営計画」をまとめられ、第26回参議院議員選挙で12名以上の当選、2023年の統一地方選挙で地方議員数を合計600名、そして次期衆議院議員総選挙で野党第一党を獲得という3つの目標を掲げていました。
このうち2つの目標は達成しましたが、3つ目の衆議院議員選挙については票を取りきれませんでした。どのように課題を分析されていますか。
ご指摘のとおり、2022年の参議院議員選挙、2023年の統一地方選挙までは計画通りの進捗でした。その2022年の参院選では、野党で最大の比例票をいただき、12議席を獲得しました。また、2023年の統一地方選挙では、改選前の1.5倍である600議席を目標に置いていたのですが、結果的に800議席、つまり倍まで議席をいただくことができました。
地方での地道な活動が党の土台として大きな資産となり、党全体としても以前よりとても強くなりました。地方議員が多く誕生し、地方の支部をつくり、全国から意見を集めて政策に反映していく土台があったからこそ、国政選挙では厳しいながらも全国の仲間のおかげで耐え忍ぶことができました。
一方で、直近の国政選挙では何がダメだったのか。私は、日本維新の会はもっとまっすぐに勝負しなければならなかったと思っています。象徴的なのが、政治資金制度改革です。
2024年5月、我々は自民党と実現のための現実的な交渉をして、政治資金制度改革について合意し、一定の改革成果は得ました。しかし、政策活動費の使途公開を10年後としたことに対し「なぜ10年後なのか?」「スッキリと全廃すると言えないの?」という声が多かった。譲歩をして何かの成果を得るという姿勢は、わかりにくかったし、ご納得もいただけなかったのです。
「維新は直球で改革する政党ではなかったのか?」という民意が、選挙結果に繋がったと考えています。
我々は、もう一度原点に立ち返って、この傷んだ日本社会を大構造改革していかなくてはいけない。そのために真正面から一点突破するという政治姿勢を忘れてはならないと、改めて感じています。
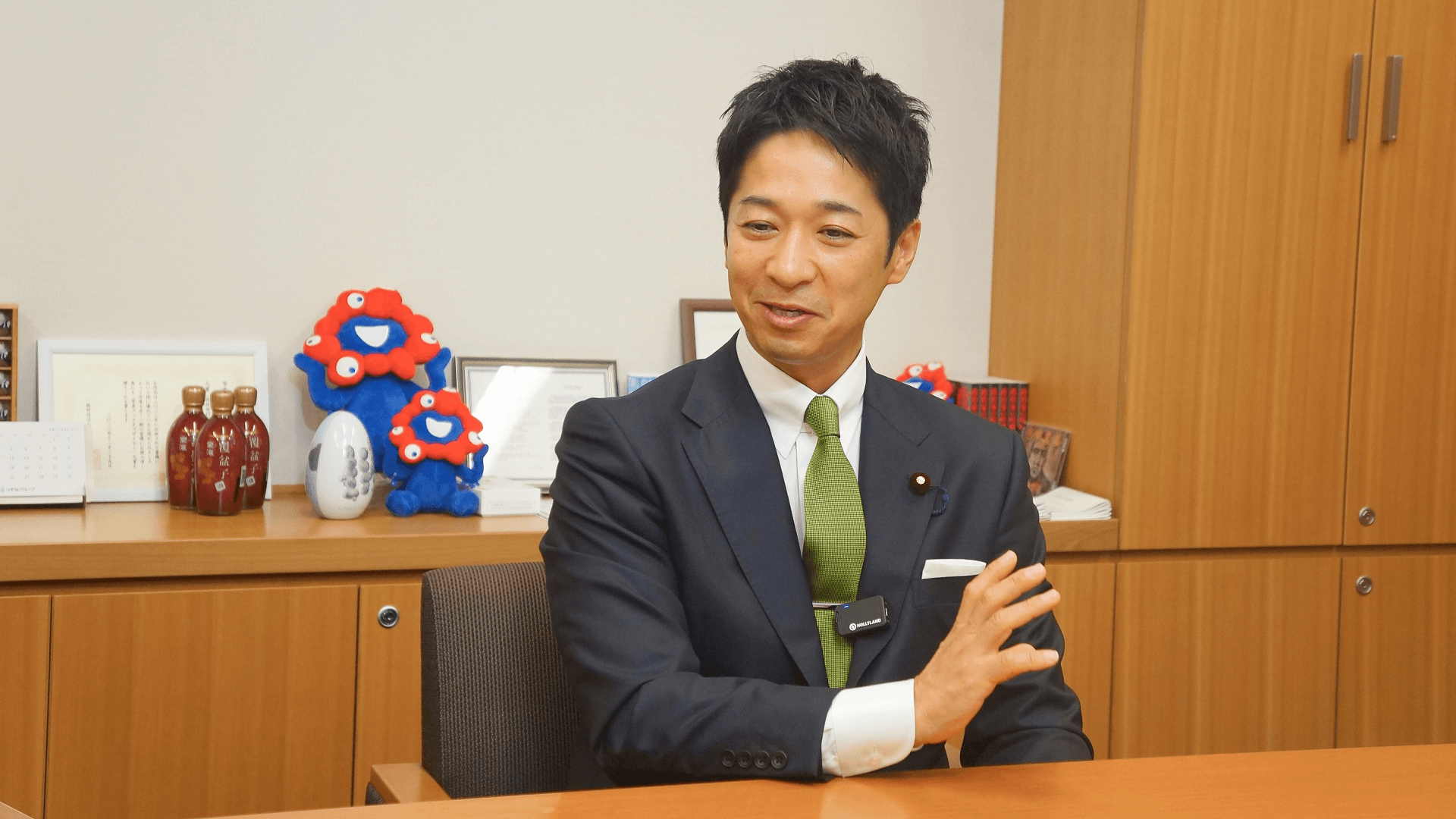
ー立ち返るべき日本維新の会の原点とはなんでしょうか。
私にとって、2012年大阪から全国の維新になるために策定された維新八策が原点としてあります。
大阪で行ってきた政治改革モデルを広げて、国レベルで構造改革をする。身を切る改革を断行し、将来世代のために既得権益と戦う。このシンプルな政治姿勢こそが維新の原点であり、もう一度立ち返るべきところだと思っています。
幹事長退任から8か月、新共同代表選挙に立候補した思い
ー日本維新の会として重要な局面にあるなかで、共同代表選挙選挙に立候補した理由を教えてください。
共同代表選挙に立候補したのは、縁と巡り合わせによるところが大きいですね。2024年の衆院選のあと、選挙敗北の責任を取り、幹事長をはじめ全ての役職を辞しました。共同代表に就任するまでの8か月間は、一兵卒の議員として維新をどう立て直すべきか自問自答し、泥臭くもがいていました。
今回の参院選後、党の立て直しが急務となる中で、自分がその先頭に立って戦いたい。その一心で立候補を決意しました。
ー藤田議員は、共同代表であり、国会議員団代表であるという理解ですが、吉村洋文代表との役割分担はどのような形になるのでしょうか。
共同代表・国会議員団長は、分かりやすく言うと代表を支える党のNo.2であると同時に、国会運営に責任を持つリーダーでもあります。
日本維新の会が特徴的なのは、橋下徹さん、松井一郎さん、馬場伸幸さん、吉村洋文さん、歴代の4人の代表のうち、3人が国会議員ではありません。つまり、国会議員を中心としたピラミッドではなくて、地方から生まれた政党としての特徴の一つと言えるでしょう。
私はこの特徴に価値を感じているのですが、その上で、実務的な話をすると、例えば総理大臣を選ぶ首班指名や、党首討論などを含め、日々の国会の動きにあわせて意思決定していかないといけない場面があり、実務的な国会議員団のリーダーが必要になります。
そのため、党運営においては、吉村代表を徹底的に支え、一致結束するためのNo.2的な仕事をする。そして、国会議員団長として、吉村代表と連携しつつ国会に関する意思決定をスムーズに進め、リーダーとして牽引していく仕事をする。この二つの役割を両立させることが私の役目です。
ー幹事長のときに掲げられた中期経営計画をまた作り直す予定などはありますか。
中期経営計画を作り直すかはまだ決めていません。中期経営計画はあくまで政策を実現するための手段でしかありません。あくまで計画は、数字のコミットや、そこから巻き戻したアクションプランというのを明示することによって、組織をまとめるためのものです。
政局が流動化している中で、計画を中期的にまた長期的に確定できるかというと、非常に難しいということもあるので、柔軟に考えようと思っています。

将来世代へ負担を先送りしない。維新の掲げる国家百年の計
ー7月の参議院議員選挙では、社会保険料の引き下げを訴えました。日本維新の会としての今後の政策の展望について教えてください。
社会保障は医療・介護・年金と幅広い分野なんですが、その中でも日本維新の会は7月の参院選で医療費削減についてターゲットを絞って訴えました。
近年、日本の国民医療費は急激に増加しています。2022年度の国民医療費は47兆円と過去最高を更新し、毎年1兆円ずつ増加しています。さらに、後期高齢者の増加により、医療費の伸び率も上がっていくことが予想されている。
これにより、現役世代の負担が重くなりすぎて、結婚や子どもを経済的な理由で諦める人が増えて、少子化が加速し、消費も冷え込むという悪循環に陥ってしまいます。
私は、医療費の削減を掲げる政党は今の日本に絶対に必要だと考えています。医療費の削減、現役世代の負担軽減という旗を決して下ろしてはなりません。
現時点では、医療費の増大を抑制しないといけないという問題意識については多くの政治家が同じ思いを持っているところですが、具体的にどの部分をどう削るかの議論になれば、既得権の激しい抵抗、さまざまな利害調整があり、簡単には折り合わない。前執行部でもかなり議論を進めて、過剰な病床の効率化によって1兆円の削減に踏み込めるところまできた。しかし、OTC類似薬の保険適用除外をはじめ、医療改革はまだ道半ばです。しかし、これまで議論すらされていなかったところから、粘り強い交渉を進めたことで、ようやく詳細の検討に入ったことは一歩前進です。
国民医療費を年間4兆円削減することが決して簡単でないのは、初めからわかっています。しかし、難しいから放っておいていい、というわけではありません。一歩一歩積み重ねて1兆円、2兆円と積み上げていかなければならないのです。
さらに、負担の構造そのものも変えていかなかればならない。例えば、後期高齢者医療制度によって、75歳以上の高齢者の医療費窓口負担は原則1割となっています。これは、現役世代の保険料からの高齢者への仕送りと、税負担によって支えられています。
本来、保険とは利用が多い人が保険料を多くする仕組みになっているはずです。しかし、今は医療をたくさん受ける高齢者の保険料が安く、現役世代の保険料が高くなっています。セーフティネットとして、能力に応じた負担を、という考え方も大切です。
選挙では耳の痛い話かもしれませんが、国全体の最適解を考え、改革に取り組んでいかなければなりません。
ー参議院選挙では、副首都構想も掲げられています。副首都構想はどういった問題意識が背景にあるのでしょうか。
これは東京一極集中の打破が最大の目的です。東京一極集中を壊し、多極分散型の社会をつくるための一点突破として副首都構想を掲げています。
多極分散型の社会をつくる目的は大きく2つあります。1つは地方に東京と型を並べるような経済圏をつくっていくこと、2つ目は首都機能のバックアップです。
今、日本ではものすごい勢いで人口減少が進んでいる上に、地方から東京に人材と富が流出しています。地方の自治体サービスを受けて育った優秀な人材が東京に流出して、東京で働き納税する。東京に企業の本社が集中する。こうして日本中から富や資源が集中し、東京だけが豊かになっている現状があります。一方で、地方では人が減り、経済はどんどん縮小しています。大阪、愛知、福岡、仙台をはじめ、地方の経済圏を力強く育てていかなければ、日本全体の繁栄はないだろうと考えています。
2つ目の首都機能のバックアップは、首都直下型地震をはじめとする大規模災害やテロなどによる、首都機能のダメージに対するリスクヘッジが必要との問題意識からです。
副首都構想については、国家百年の計としての統治機構改革であり、人口戦略、国土構想を含めた国家のあり方を合わせて議論をしていきたいと考えています。

ー人口戦略に関して、外国人政策に注目が集まっています。藤田議員は「外国人政策と人口戦略調査会」の立ち上げを表明されましたが、外国人政策についてどのようにお考えでしょうか。
前提として日本人の出生数が急激に減少している一方で、外国人の入国数は想定以上に増えています。これにより、将来、国のあり方が大きく変わっている可能性があります。
2024年の日本人の出生数は69万人と、統計開始以来、初めて70万人を下回りました。直近5年の減少率を見ると、2040年代には、現在の半分の35万人しか日本人が生まれない時代に突入する可能性があります。一方で、この3年間で外国人は30万人以上増えています。入国する外国人の数と新しく生まれる日本人の数が逆転する世界が、この10年か15年で起こりえる。これは大きなインパクトです。
では、どうすればいいのでしょうか。私は結論からいうと、在留外国人の増加スピード、全人口に占める外国人比率について、可能な限り最大限抑制すべきだと考えています。
ヨーロッパなどの国の事例を見ると、人口比率が10%を超えると、文化的衝突や犯罪率の増加、社会コストの増大が顕在化する傾向があります。憎しみのエネルギーが右派的な移民排斥運動に繋がってしまうケースもあります。そうした分断や衝突を避けることが政治の使命であるはずです。
現在、全人口に占める外国人比率は3%程度ですが、外国人問題が顕在化している川口市では、外国人比率は7%を超えています。20%を超える市区町村も出始めました。これは、外国人が一定の地域に集中しやすい構造があるからです。特定の地域だけ外国人比率が上がっていくと、その地域の様子も変わり、社会的な混乱も大きくなります。
企業としても、労働者の獲得のため外国人を積極的に採用したいということは理解できますが、国家全体として無秩序に増やしていくことはできません。人口が減少しても経済が発展するモデルへ転換する覚悟を決め、戦略を組み直すことが重要です。
最近話題の外免切替問題や経営管理ビザの要件が甘いことなど、個別のミクロな問題を解決するだけではなく、人口動態の変化を含めた大きな視点で戦略を考えていく必要があると考えています。
ー現在、外国人政策をとりまとめるのはどの省庁になるのでしょうか。
外国人問題は、省庁横断的な問題が多く、同時に国、都道府県、基礎自治体に問題がまたがっています。そのため、2月21日の衆議院予算委員会で、国としての司令塔機能を作ることを提案しました。
石破総理大臣からは、強い問題意識を持っているという答弁があり、7月に内閣官房に外国人問題の司令塔となる組織をつくることを表明し「外国人との秩序ある共生社会推進室」が設置されたことは歓迎しますが、目の前の短期的な問題に対処するだけにとどまらず、国家としての方針や戦略決めていくことこそが本丸であり、今後も国会で議論していきたいと思います。
ー日本維新の会に設置された「外国人政策と人口戦略調査会」の今後の活動について教えてください。
「外国人政策と人口戦略調査会」の会長として、臨時国会までに政策提言を出したいと考えています。勉強会を重ねながら、最終的な提言の形にまとめたいと考えています。
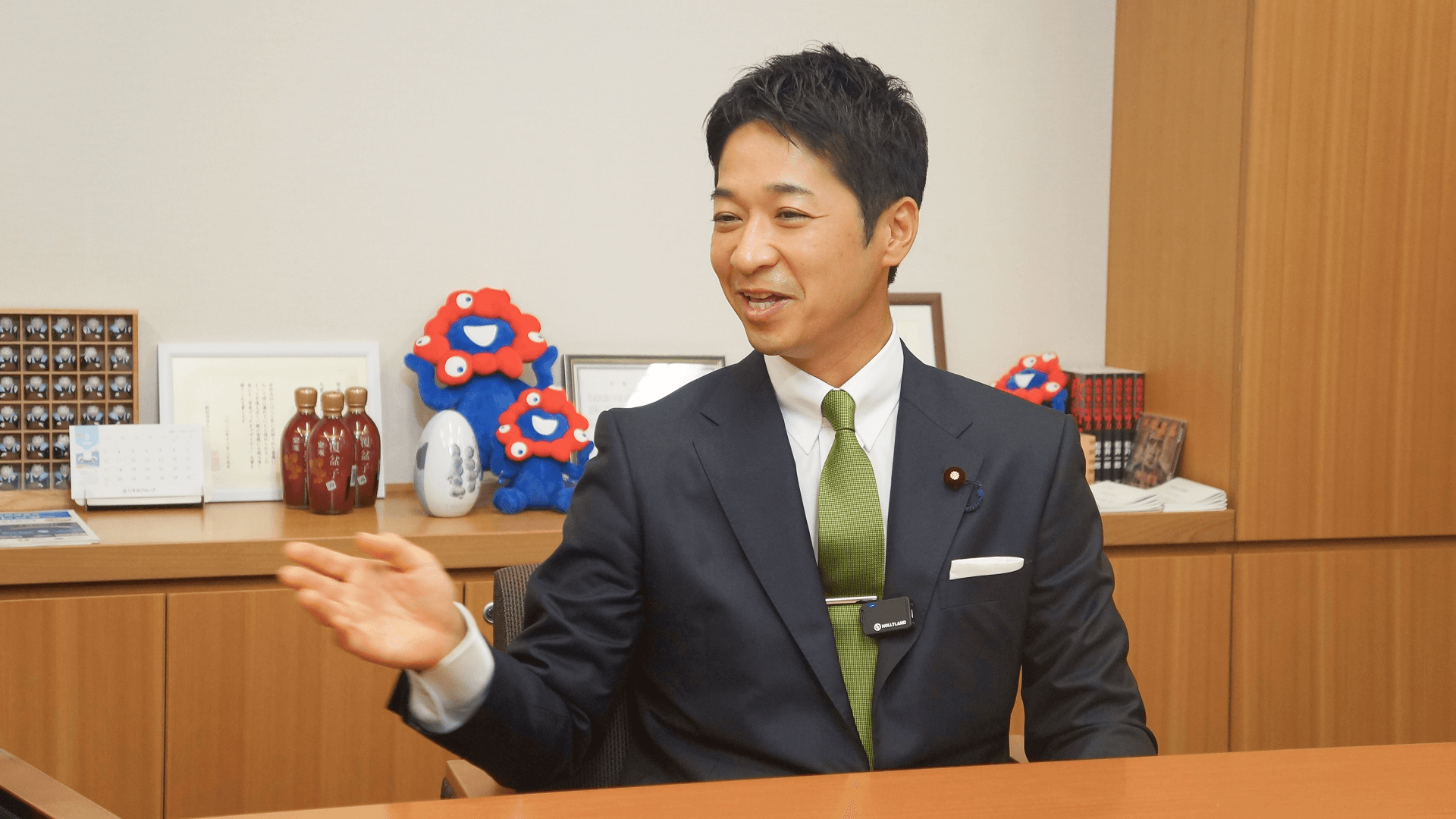
「捨て身」の覚悟で、政策実現へ
ー今後の展望として、党運営や広報において実施していきたいことはありますか。
SNS戦略、インターネット戦略の見直しは急務です。ここ1〜2年で、政治におけるSNS・インターネット戦略の重要性は激変しました。その影響力は広報活動の一部というレベルではなく急速に増大しています。
新興勢力の急伸は、まさにこのネットやSNSの力がなければ考えられなかった象徴的な出来事です。かつて私たちの党は広報がうまいと評されていましたが、この急激なトレンドの変化に乗り遅れてしまい、直近の選挙では戦略的に他党に劣後したと反省しています。
この遅れを取り戻し、最先端の動向を政治運動の手段として捉え直すことは絶対不可欠です。本腰を入れてキャッチアップしていくことが、私自身の重要な仕事だと考えています。
ー日本維新の会の共同代表としての藤田議員の意気込みを教えてください。
日本維新の会が最も大切にすべきなのは、吉村代表が常々語っているように「政策を実現し、公約を必ず守る」という有言実行の姿勢です。この政策実現という一点に、なりふり構わず、そして「捨て身」でこだわることこそが、党の核心だと考えています。
維新の創業者である松井一郎元代表には、「自分たちの政治家の身分にしがみつかんと、とにかく捨て身でやりなさい」という教えを常々いただいてきました。この「捨て身」という言葉が、私の中にすとんと落ち、維新の会の原点を再認識させられました。
維新の会は、党という組織を守るためや、議員という身分にしがみつくために存在するわけではありません。掲げた政策や改革を実現するためならば、あらゆるものを投げ打ってでも突っ込んでいく。その精神こそが「捨て身」なのだと思います。
現在は、どの政党も過半数を持たない「ハングパーラメント」で、多くの少数政党が並び立つ、意思決定の難しい時代です。このような状況だからこそ、自分たちの利益ではなく、国民のために「捨て身」で改革を実現しようとする政党が必要です。
そうした志を持つ政党が集い、切磋琢磨していく政治は健全です。私たちも、この「シンプルな原点」に立ち返り、国民のための政策実現に邁進していきたいと考えています。



















