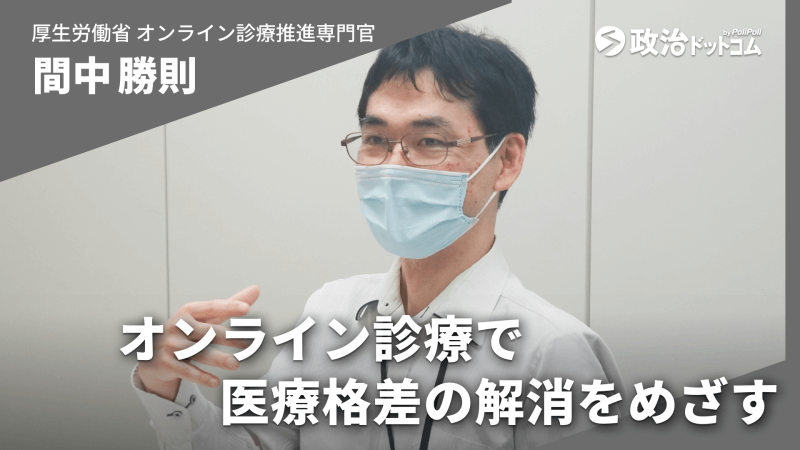中曽根康隆 なかそね やすたか 議員
1982年生まれ。慶應義塾大学法学部を卒業後、米国コロンビア大学大学院で
国際関係学修士号を取得。
JPモルガン証券を経て参議院議員である父の私設秘書に。
2017年の衆議院議員選挙に比例北関東ブロック単独で出馬し初当選。
2021年より群馬1区の衆議院議員として現在3期目。
2021年の第2次岸田内閣にて防衛大臣政務官に就任。
現在、自民党青年局長、党経済安保推進本部事務局長。
2024年に行われた衆議院議員選挙の投票率は戦後3番目に低い53.85%。20代に限れば40%未満で、若者を中心に政治離れが深刻化しています。
今回のインタビューでは元総理大臣を祖父に持ち、現在は自民党の青年局長を務める中曽根康隆議員に、若者の政治参加促進への取り組みや、その先に描く国家ビジョンをお聞きしました。
(取材日:2025年3月13日)
(文責:株式会社PoliPoli 秋圭史)
都心と地方を行き来する中で芽生えた政界進出への意欲

ー祖父も父も政治家という家に育った中曽根議員は、小さい頃から政治家をめざしていたのでしょうか。
祖父が総理大臣になったのが1982年で、ちょうど私が生まれた年なんです。父も私が幼少期に参議院議員になったので、物心ついたときから政治家は一番身近な職業でした。祖父は一緒に住んでいましたが、祖父も父もほとんど家におらず、さみしい思いを抱きつつも政治家という仕事の大変さを肌で感じていました。
私が総理大臣の孫だったこともあり、学校では「孫」と呼ばれ、それがコンプレックスだった時期もありました。「自分には『康隆』という名前があるのに」と思う一方で、「政治家の子として、きちんと振舞わないといけない」というプレッシャーもありました。ただ、高校生のときに1年アメリカへ留学したのを機に、それらの呪縛から解放されました。「もっと自分らしく生きればいいんだ」と。
そこからは逆に自分の立場をもっと活用しようという発想に切り替えて、大学生になってからは父の仕事を手伝うようになりました。父の事務所は群馬県の前橋市にあるのですが、大学が終わったら新幹線で群馬へ向かう日々を送っていました。この活動を通じて、中曽根家が祖父の代から群馬の方々に本当に温かく支えられてきたことを実感しました。ただ、自分が政治家になるかどうかは、まだ明確には考えていなかったと思います。
ー外資系の証券会社に就職されていますが、そこから政治家に転身したきっかけは何だったのでしょうか。
勤務先は東京の丸の内にあり、平日はパソコンのモニターを8台くらい目の前に並べ、ニューヨークや香港と連絡を取りながら業務をこなしていました。一方で、土日は学生時代から続けてきた父のサポートで群馬に通っていました。平日は大都会でパソコンと向き合い、土日は地方で人と向き合う。そんな日々を送っているうちに、証券会社での仕事は「自分じゃなくてもいいのでは?」という感覚が芽生えてきたのです。
さらに、東京は勝手に人が集まる特異な場所で、やはり過疎が進む地方こそ想いを持った人の手が必要だと感じるようになりました。祖父も父も支えてもらった群馬を盛り上げるために、自分も何か還元したい、群馬の力になりたい。そんな気持ちを抱くようになったのです。
防衛費の増額は“勝つ”ためではなく、“抑止する”ため

ー政治家になってから注力された分野のひとつに防衛がありますが、当時どのような視点で防衛政策に携わられていたのでしょうか。
2021年に防衛大臣政務官を拝命しましたが、これは本当に大きな経験でした。全国各地の基地や駐屯地を回って若い自衛官とたくさん話をするなかで、月並みな言葉ですが「平和があるのは当たり前ではない」と痛感しました。私たちが日々平和に暮らしているのは陸海空24万人の自衛官が24時間、365日、任務に就いているお陰なのです。
そして、年間8兆円ものお金をつぎ込んで防衛を維持しているのは、平和を守る上でもっとも大切な「抑止力」を上げるためです。よく誤解される点なのですが、防衛費を増やす目的は「戦争に勝つ」ためではありません。戦って勝つためではなく、あくまで戦争を仕掛けられないように抑止力を高めるための防衛費なのです。
そのためには装備も大切ですが、もっとも大切なのはやはり「人」です。自衛官の処遇を改善し、誇りを持って働ける環境を整えることが安全保障には欠かせません。私が事務局長を務めている自衛官支援議員連盟でも議論しましたが、老朽化した宿舎の新設や僻地での通信環境の改善などに今後も力を入れていきたいと考えています。
多様な意見を政治に反映させるには若者の政治参加が不可欠
ー現在は自民党の青年局長や党の「立候補年齢引き下げ実現プロジェクトチーム」の座長、超党派による「若者政策推進議員連盟」の事務局長を務められています。若者と政治の関わりについてどのようなお考えをお持ちですか。
議連では多くの学生さんから政治に関する意見を聞くのですが、要望として特に強いのが被選挙権年齢の引き下げです。若者の政治離れが深刻化するなか、政治への関心を高め、参加を促すうえで被選挙権年齢の引き下げは有効な手段だと思います。2024年6月には、「被選挙権年齢の18歳への引き下げ」、そして「供託金額の大幅な引き下げ」を盛り込んだ提言を各党の政調会長へ申し入れました。
もちろん、課題はたくさんあります。成人年齢が18歳に引き下げられた一方で、少年法の適用は20歳未満となっており、この点との整合性も考えなければなりません。
乗り越えるべきハードルはたくさんありますが、多様な意見を政治に反映するためには若者の政治参加が不可欠です。3月4日には党の選挙制度調査会の中に「立候補年齢引き下げ実現プロジェクトチーム」を結成し、私が座長に就任しました。青年局においても学生の声を集めているので、プロジェクトチームの議論に反映していきます。当面の目標として、2025年7月の参議院議員選挙での公約入りをめざしています。
自立(自律)した国へ

ー若者の政治参加促進の先にあるビジョンについて教えてください。
若者に限らず国民全体の政治への関心が年々下がっていることを不安視しています。このまま投票率が3割あたりまで下がると、10人のうち7人は投票に行かないことになり、「これで民主主義が成り立つのか?」という疑問が出てきます。より多くの民意が反映された結果として議員が選ばれる、という仕組みを維持していかなければなりません。
ただ、そのためには選挙制度の話だけでなく、しっかりとした国家ビジョンを示すことも必要です。私が特に重視していることとして、「国家安全保障」「エネルギー安全保障」「食料安全保障」の3点があります。国民の命を守る上できわめて重要なこの3点について、日本は海外への依存度が高すぎるのです。
有事の際、国民の暮らしを守るには防衛力を確保しなければなりません。また大規模災害時に、社会活動を止めないためには、国内のエネルギー供給も維持する必要があります。食料を確保して飢餓を防ぐには、急速に減少している農家の経営を守る必要もあります。これらすべてにおいて海外への依存を減らし、ビジョンとして「自立した国」をめざすべきだと考えています。
ービジョンの実現に向けて、国民に伝えたいメッセージはありますか。
国際的な意識調査の「自分は国や社会に貢献できると思うか」という質問で、「そう思う」という回答の割合は日本が圧倒的に低いですよね。これは危惧すべきことだと思っています。これを改善していくためにも、政治を「自分ごと」として捉えていただきたいですね。
その土壌をつくる手段のひとつとして、学校での生徒会活動は有効だと思います。学校が決めたルールに従うのではなく、自分たちで決めたルールを自分たちで守るという経験を通して、社会を動かす一員としての意識を持つことができます。この活動を各学校で強めていくことが、政治への当事者意識を高めるきっかけのひとつになると思います。
今後、人口減少がさらに加速し、経済が縮小する可能性がある中で、いかに幸福度の高い国を作るかが国全体のテーマになってきます。GNH(国民総幸福量)の概念です。国民一人ひとりが当事者意識を持って、自立した豊かな国を作ることが、幸福度を上げる鍵になると信じています。