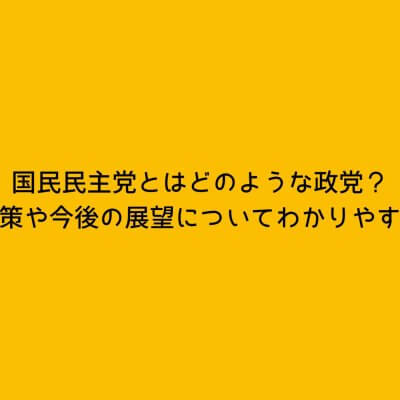自民党の石破茂総裁が9月7日、総裁を辞任する意向を表明しました。これを受け、後任を選ぶ自民党総裁選挙が9月22日告示、10月4日投開票の日程で行われることになりました。
7月の参院選で連立与党が過半数を失うという厳しい選挙結果の責任を取る形となった今回の辞任。政治資金問題で失った国民の信頼を回復し、混迷する政権を立て直すために、新たな自民党のリーダーが求められています。
本記事では、自民党総裁選の概要や仕組み、ルール改定を巡る議論について詳しく説明します。
自民党総裁選とは?
自民党総裁選とは、自由民主党の代表である「総裁」を選ぶ選挙のことを指します。
総裁の役割について、党則では「党の最高責任者であり、党を代表し、党務を総理する」と定められています。また、総裁には党の主要幹部を決定する権限があり、総務会の承認を得て幹事長・政調会長・選挙対策委員長を任命できるほか、副総裁を指名することも可能です。
現在、自民党は国会で多数派を占めているため、総裁選は事実上、内閣総理大臣を決める選挙と同じ意味を持ちます。このため、自民党総裁選は日本の政治において極めて重要な選挙と言えます。
引用:自由民主党党則
参考:日経新聞
自民党総裁選の仕組み
では、誰がどのようにして総裁を選ぶのでしょうか?
自民党総裁選では、自民党所属の国会議員による投票(議員投票)と、全国の党員・党友による投票(党員投票)の2つで構成されています。議員票は国会議員1人につき1票が与えられます。
一方、党員票は全国から集められた投票結果を都道府県ごとに集計したうえで、議員票と同数になるように「総党員算定票」として換算されます。この換算には「ドント方式」という比例配分の方法が用いられます。たとえば、2024年9月の総裁選では議員票が368票だったため、党員票も368票分に換算され、それぞれの候補者に応じて比例配分されました。
このようにして集計された議員票と党員票を合算し、過半数を獲得した候補者が当選となります。
ただし、候補者が3人以上いる場合、1回目の投票で過半数に届かなかったときには、上位2名による決選投票が行われます。この決選投票では、国会議員による投票は引き続き1人1票ですが、党員票は47都道府県連に1票ずつ割り振られます。各都道府県でより多くの支持を得た候補者に1票が与えられる仕組みで、結果として議員票の比重が相対的に高まることになります。
他方で、どのような人が自民党総裁選の候補者となり得るのでしょうか?
自民党総裁選の候補者となるためには、いくつかの条件があります。まず、自民党所属の国会議員であることが必要です。加えて、同じく自民党に所属する国会議員20人の推薦人を確保しなければなりません。
この「推薦人20人の確保」は、実際には大きなハードルとなっています。たとえば2024年の総裁選では、野田聖子元総務相と斎藤健前経済産業相が、推薦人を十分に集めることができず、立候補を断念しました。こうした例からも、総裁選への出馬には、党内での広範な支持が必要であることが分かります。
自民党総裁選を巡る議論
自民党総裁選のルールを巡っては、前回2024年の総裁選後に党内で見直しを求める議論が行われた経緯があります。
特に論点となったのが、決選投票における地方票の扱いです。現在のルールでは、決選投票は国会議員票と47都道府県連に各1票(計47票)が割り当てられます。これに対し、2024年の総裁選後、森山裕幹事長(当時)らが「地方の党員の民意が十分に反映されない」と問題提起し、見直しを求める声が上がりました。
また、前回の総裁選では9人が立候補し、「候補者乱立」と指摘されました。この対策として、立候補に必要な推薦人(現行20人)の引き上げなどが検討されました。
これらの見直し論は2025年3月の党大会に向けて議論されましたが、党内の意見集約には至らず、最終的にルール改正は見送られました。このため、今回の総裁選は現行ルールで実施されることになり、決選投票にもつれ込んだ場合の地方票の行方に改めて注目が集まっています。
まとめ
自民党総裁選は、党の最高責任者を決める重要な選挙です。2024年の衆議院選挙、2025年の参議院選挙で過半数を割り込んだものの、国会で比較第一党である自民党のリーダーは、内閣総理大臣に最も近い存在です。相次ぐ国政選挙での後退と、それに伴う石破首相の辞任。今回の自民党総裁選は、自民党が旧来の体質と決別し、真の党改革を断行できるかの分岐点に立たされていることを示しています。物価高騰や安全保障環境の変化など、内外に課題が山積する中、新総裁は少数与党という厳しい状況で野党との協調も探りながら、国政を前に進めなければなりません。誰がその重責を担うのか、「ポスト石破」に注目が集まっています。