
緒方 林太郎 おがた りんたろう 議員
1973年生まれ。福岡県出身。
外務省を経て、2007年から政治の道へ。
2009年衆議院議員初当選し、現在3期目。
フランス語検定1級を取得するなどフランス語が堪能。
外務省で通商交渉などを担当したのちに国会議員となり、2020年には外交官と国会議員の両方の経験を踏まえ通商分野に関する著書も出版した緒方林太郎議員。現在、院内会派・有志の会に所属しながら、無所属で活動を続けています。民主党政権時、政権与党の議員だった緒方議員が感じた野党の課題とは何か。人口減少と少子化に苦しむ日本が本来議論すべき政策とはどのようなものなのか。政治が逃げずに目を向けるべきこれからの時代の国難との向き合い方についてお伺いしました。
(聞き手・文責:株式会社PoliPoli 秋圭史)(取材日:2024年4月4日)
(1)外交官から政治家へ。通商交渉の現場で感じた野党の課題。
ープロフィールを拝見したところ、東京大学を中退し外務省へ入省されています。どのような経緯があったのでしょうか。
外交官を目指したのは、シンプルに世界を見てみたいという思いが小さなころから強かったからです。私は福岡県北九州市の出身で、それ程外国が身近だったわけではありません。普通のサラリーマン家庭に育ち、子どものころ外国に行ったことはありませんでした。
東京大学に入学後は、周りに官僚を目指す人も多く、外国に行ける仕事を、と外交官を目指すようになりました。当時、国家公務員試験とは別に外務省では外交官試験を行っており、大学3年生でも受験することができました。
そこで受験してみると合格してしまった。外務省で働く上で大学中退であることが不利になるわけではなかったので、そのまま東大を中退し外務省に入省しました。「大学を中退してやる!」と思っていたわけではなく、自然のなりゆきでしたね。ただ外交官になった後に外国に行った際には「なんで中退したんだ」、「最終学歴は高卒か」と聞かれる事があったので、「自分で選んだ道なんだ」と説明するのは少し面倒でした(笑)。
ー外務省入省後はどのようなお仕事をされていたのでしょうか
外務省では数多くの仕事に携わりましたが、比較的経済局でのキャリアが主だったかなと思います。
私が外務省に入省した1994年当時は日米貿易摩擦やWTO(世界貿易機関)の発足など、通商政策が非常に注目されている時代でした。
外交官試験の試験科目は法律と経済が両方あったので、その延長上で国際法と経済の中間領域である通商の分野に関心を持ったのは自然の流れだったかもしれません。
ただ、理論・理屈は頭で分かっていても、通商交渉における日本の立ち位置との関係では非常にもがく事が多かったです。どの国にも強みと弱みはあるのですが、日本ほど分野ごとにスタンスが明確に分かれている国は珍しかったです。自動車では相手国の関税撤廃を訴えながら、農業では自国の関税維持を掲げ、「貿易自由化」、「関税引き下げ交渉」という言葉を使う事すら憚られたのが現実でした。国益を追求して行かなければならないのは当然ですが、その国益とは何だろうかと外交の現場では非常に考えさせられました。
通商交渉を経験する中で、外交は内政の延長にあるものだと改めて痛感しました。内政の様々な利害関係を持ちながら、外交の場でそれらをどう整合的にコーティングして主張していくのかが外交官の腕の見せ所です。
通商外交・通商政策が盛り上がりを見せた時代にその現場で通商交渉に当たることができたのは私にとっても貴重な経験でした。
ーその後、外務省を退職し政治家を目指したきっかけはなんだったのでしょうか。
日本の将来に危機感を覚えたからです。日本の抱える最大の課題は巨額の国債発行と少子化です。現在、国の借金である国債の発行残高は1,000兆円余りで、GDPの2倍を超えています。これは、主要先進国の中で最も高い水準です。
国が借金を抱え込んでいるせいで金利が上げられません。我々は長年の低金利政策に慣れてしまいましたが、金利が低い世の中はやはり盛り上がらない世の中なのです。安倍政権下での超低金利政策は、国債の利払い費を抑えなくてはならないという前提の下で展開されたものです。しかし、デフレ脱却を金融政策だけで実現しようとしたアプローチが的外れだったことはこの10年余の歩みが証明しています。
しかし、今後、予期できない形で金利が上昇する可能性も否定できません。2023年度の国債の利払い費は8.5兆円ですが、もし長期金利が2%となると借り換えが進めば最終的には単純計算で20兆円に拡大します。
国の歳出の多くが国債の利払い費にあてられることも問題ですが、私が懸念しているのは、国の借金が長期的に持続可能なのか、ということです。今は「まだ大丈夫」というマーケットの信頼があるわけですが、借金が更に積み重なれば、その信頼が揺らぎかねません。
市場で日本国債の償還可能性に疑問符が付き、価値が認められなくなれば、円安や急激なインフレが引き起こされ、国民生活に危機的なダメージを与えます。多くの政治家が財政健全化の話題を避けていますが、私は財政健全化こそ重点的に取り組むべき課題だと思っています。
ー外交官であったことは政治家になってどのように活かされていますか?
外交官の経験は政治家になっても大きく役立っていると思います。日本の国際社会における立ち位置、見られ方、そして立ち振る舞い方に関する「相場感」って野党の議員を経験するだけではなかなか身に付くものではないんですよ。私自身、普通に野党で議員生活をしていたら外交に関心を持たなくても特に支障はありません。ただ、それではいけないので常にアンテナを高くして、必死に最新の国際情勢から遠ざからないようにしています。
現在の日本の政治状況は自民党が長らく政権を取り続けている状況にあります。政権に就いていれば、所属議員は政務三役の経験を通じて外交に接する機会が増えていきます。一方、今の野党には外交経験が薄すぎます。
外交関係の処理は内閣の事務として憲法にも定められています。だから政権を取るまでは外交に直接携わる事は無いし、関わらなくてもいいんです。しかし実際に政権を取ったら、その直後から外交の現場に放り込まれます。いきなり、プーチンのような世界の独裁者も相手にしなくてはいけません。
野党の政治家は外交の経験が薄く、民主党への政権交代後、外交の現場に出た議員の顔に「おびえ」が出てしまうのを何度か目の当たりにしました。となると交渉する上でも不利に働いたりするわけです。
これが今の野党に対して期待感が高まらない一つの理由かと思います。国民も今の野党に本当に外交安保ができるのか、疑問に思っているでしょうね。

(2)無所属で選挙に勝ったからこそ見える景色
ー緒方議員は2020年から無所属で活動しています。どのような経緯があったのでしょうか?
無所属になったきっかけは、2017年に落選した後、所属していた政党がなくなったことです。強い意思があって無所属になったというよりは、結果的に無所属になった、そして、その後何処にも行っていない、というのが実際のところです。要するに、既存政党との関係で「何もしなかったらこうなった」というだけです。
私が初めて当選したのは2009年で、当時は民主党に所属していました。当時何を思っていたかというと、お金のニオイのする政策作りからは決別する必要があるという事でした。そういう旧態依然とした政治ではもう駄目なのだと思ったからです。
ただ、当選後、大きな挫折感を味わいました。それは結局民主党も自民党と同じ穴のムジナだったことに気づいたからです。政権をとったあとの民主党議員の多くが、これまで自民党を批判してきたにもかかわらず、企業団体献金を受け取ったり、パーティー券を押しつけたりしているのを目の当たりにしたのです。「自民党が業界と癒着した政治をするのがけしからん。だから、それを止めさせたい。」と私は思っていたのですが、「自民党が業界と癒着した政治をするのがけしからん。自分たちがそれをやりたい。」と思っていた方が結構多かったのには愕然としました。
更に言うと、自民党は業界との付き合い方で経験がたくさんあるからうまく線引きできるのだけど、民主党は経験不足が悪い方向に働き、舞い上がってしまった。偉くなったと勘違いし横柄になったり、過度に業界に忖度したりする場面も散見されました。フタを開けてみれば自民党も民主党も同じだったどころか、より性質が悪かったとすら言えるかもしれません。
これは私にとってすごくショッキングな出来事でした。ただ、今でも当初抱いた青雲の志は持ち続けています。お金のニオイのする政策作りからは決別するなんてのは、きっと青臭く聞こえるのでしょう。それでもその青臭さを持ち続けながら、2回も落選して臥薪嘗胆してきたわけですから、そこは貫いていきたいと思います。
ー逆に無所属でいることのよかったと感じたことはなんですか。
無所属だと活動のウィングが広がるのを実感します。決して当て込んでいるわけではないのですが、無所属になって応援してくれるようになった方も多々おられます。今は国会での質疑でも、自分が信ずる事をそのまま発言していますが、それを色眼鏡無しに評価いただいているという面もあろうかと思います。勿論、国会は団体戦ですからずっと無所属でいるつもりは毛頭ありません。
ー無所属は選挙で大変なイメージがあります。
その通りです。今の公職選挙法は政党中心の選挙制度を志向しているため、無所属の議員にはやや厳しい法制度になっています。ポスターは公営掲示板のみにしか貼れず、ビラの配布数の上限も少ない。当然、政党助成金がなく、企業団体献金も受け取れないため、政治活動をするための資金を集めるのが大変です。もちろん選挙の時の比例復活制度もありません。
2012年の選挙で1回目の落選をしたとき、地元の小さな路地まで入り込み、一軒一軒ごあいさつさせていただきました。地道な活動でしたが、本当にメモリアルな経験です。ただ、2017年に2度目の落選をしたときは更に大変でした。無所属で再チャレンジをするというのは、普通で考えれば無謀以外の何物でもありません。直接的、間接的に「絶対無理」というメッセージを数多く頂きました。今の選挙制度では、無所属は「泡沫」扱いされる事が多いです。
そのような厳しい環境の中、ただただ地元の皆様のお支えを頼りながら、さまざまな制約がある中で、政党の推薦も団体の推薦も一切なく当選することができました。私を国会に送り込んでくれた北九州市の市民のみなさんのおかげです。だからこそ、無所属であることにプライドを持っています。91,000人を超える方から票を投じていただいた事が国会での活動の基盤になっています。
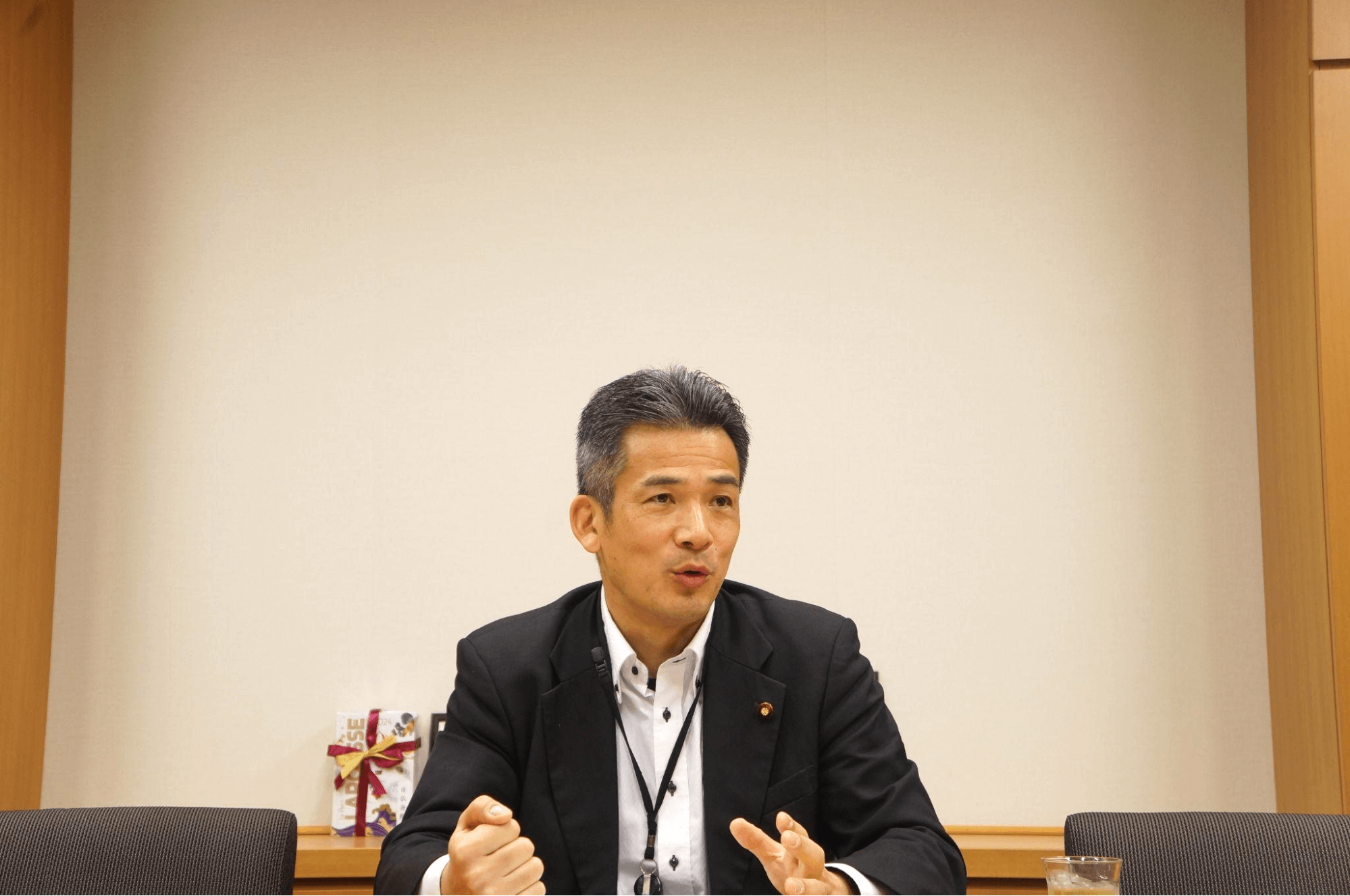
(3)緒方議員の志:国家の礎となって死ぬことが本望
ー政治家を目指したきっかけに日本の財政問題に加え、少子化を挙げていましたが、具体的な解決策について教えてください。
真っ先に行うべきことは、人口減への対応です。生産性の向上で対応するという事を言う方は多いです。しかし、生産性の向上は魔法のステッキではありません。急激な少子化に生産性の向上だけでは対応できない。であれば、国外から労働力を補う方策は考えざるを得ません。よく自治体レベルで「人口の社会増」が語られます。外からの流入が流出を上回る現象です。国家レベルでの社会増は外国から人が入って来ることです。国家レベルで自然増が期待できない中、社会増を語るのはむしろ当然ではないかと思います。
私は第二次ベビーブームの1973年生まれです。私と同じ年に生まれた子どもは210万人もいました。現在の出生数はすでに80万人を下回っています。これから高齢者の数が増えていくなか、介護需要も急拡大します。その際、誰が介護を行うのでしょうか。
自民党は右派からの批判を恐れて、堂々と労働力としての外国人という視点を打ち出す事を避け続けました。これまで「技能実習生」という形で外国人を受け入れていました。当初から労働力として当て込んでいたにもかかわらず、国際貢献の美名の下での技能の伝承というお題目でした。要するに、誰もが嘘だと分かっている事を強弁しながらやって来たのがこれまでの政策でした。実際には労働力なのに、建前は実習生なので、どうしても仕組みに歪みが出ます。当初は労働法制がきちんと適用されませんでしたし、その後も虐待、強制労働、搾取と非難された人権問題が頻発しました。その嘘がもう維持できなくなったので、今の通常国会で根本的な見直しをすることになりました。遅きに失した感を拭えません。
日本はこれから人口が減り、超高齢社会になるのに、国外から労働力としての外国人を入れずにどうするつもりなんだ、と思います。それを「移民」と呼ぶかどうかは言葉の問題だと思います。ただ、このような政策を批判する人の中には「日本が外国に乗っ取られる」と主張する人もいます。しかしよく考えてみてください。これまでの歴史で日本の文化ってそれほどヤワなものだったでしょうか。日本社会、日本文化は堅固だと私は信じています。
地域レベルでは外国の方との共生が進んでいることもあれば、困難が生じているところもあります。文化が違う以上、最初からすべてがスムーズにいくわけではありません。だからこそ、相互理解が必要です。私の地元・北九州市は地理的な影響もあり、いわゆる「在日」の方が多いのですが、本当に素敵な方が多いですよ。先の大戦が終わってからそろそろ80年。もはや「相互理解」、「多文化共生」なんて大上段に構える必要すらありません。
ただ、そのためには日本の国家としての魅力を高め「選んでもらえる国」にするために知恵をしぼる必要があります。今、日本の国力が下がり、円安が進む中、日本は稼げる夢の国ではなくなりつつあります。「オーストラリアの農場で働けば時給2,000円」と競わなくてはならないのです。そのような中、非常に気になっているのが、日本人の内向き感です。自分たち日本人は外に出ずにただ外国人に「ウチに来てください」と言うだけでは説得力がまるでありません。腕組みしていれば、自動的に選んでもらえるほど、日本の置かれた状況は安泰ではありません。この事実自体が国会の中で、必ずしも浸透していないことに危機感を持っています。
ー少子化対策についてはどのようにお考えでしょうか。
現在の岸田政権が行っている子育て支援の充実は福祉としての意味合いはありますが、少子化対策にはならないと考えています。子育て支援は福祉で、少子化対策は社会政策です。現在の「異次元の少子化対策」には社会政策の要素が少なく、子どもは増えないでしょう。無償化、給付増で本当に子どもが増えるのか、私は大いに疑問に思っています。無償化、給付増で子どもを持つ事への安心感が高まり、子どもを持つ動機が高まるという理屈を語る方は国会の中に多いですが、私は問題の本質から目を背けているだけだと思います。それを分かっているのであれば、今の政策で突き進むのは国家への背徳ですし、分かっていないのであればあまりに現実が見えていません。
少子化の最大の原因は、晩婚化や未婚化によって、女性が第一子を儲ける年齢が上がっていることにあると思います。女性が第一子を儲ける年齢を前倒しする事に焦点を当てた政策パッケージを考えるべきだと思います。ライフスタイルの押し付けだという批判はあるでしょう。私も言わずに済むなら、こんなことは言いたくありません。しかし、少子化は日本を恐ろしいレベルで蝕んでいます。批判されてでもやる、という現政権の本気度が見えてこないのが残念でなりません。
ー最後に、政治家として成し遂げたいことを教えてください。
私は、日本の危機を救うために全精力を注ぎたいと思います。このまま少子化と財政の問題を放置すれば、日本に大きな危機が訪れかねません。勿論、そうならないように頑張るわけですが、今後、みんなに嫌われる政策、批判される政策を行わなければならなくなる時が来る可能性は高いです。
将来を考えたときに絶対にやらなくてはならないけれども、それをやったら嫌われる、恨まれる、批判される政策が眼前にあるとします。そのとき、俺にやらせろ、と言いたい。自分が全部をひっかぶる、責任をすべて受ける覚悟です。万人にいい顔をすることはできないし、みんなに愛されなくてもいい。あとは歴史の法廷に立つ覚悟と気概だけを持ちたいです。そして、自分が死ぬ直前に、自分がいたおかげで世界は間違いなくよくなった、という実感を持って人生を終えたいですね。




















