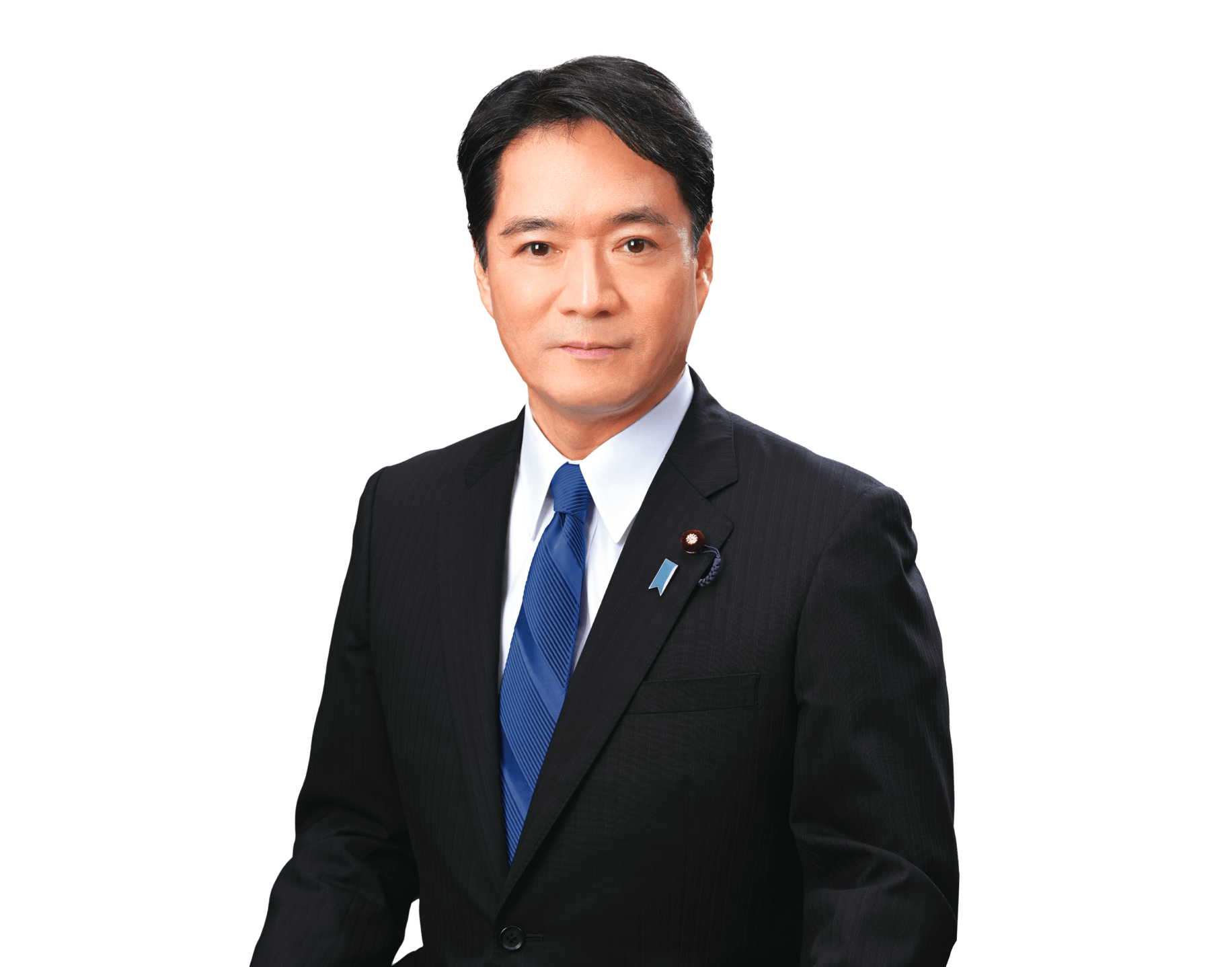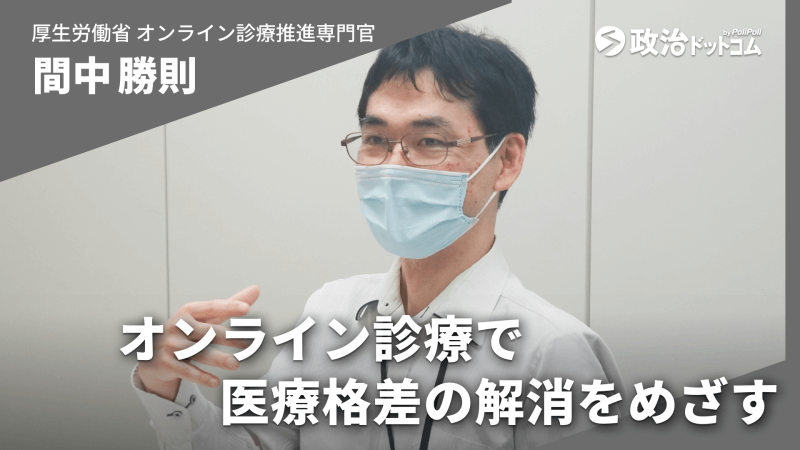尾﨑 正直 おざき まさなお 議員
1967年高知県高知市生まれ。
東京大学経済学部を卒業後、大蔵省(現 財務省)に入省。
2007年財務省を退官し高知県知事選挙に出馬、当選(3期)。
2021年衆議院議員総選挙に自由民主党から立候補し当選(現在2期目)。
現在は自由民主党の副幹事長等を務める。
人口減少や高齢化、災害の激甚化を踏まえた新たな防災対策の必要性が高まるなか、石破政権下において防災政策が重要政策の一つとして掲げられ、防災庁の設置準備が加速しています。今回のインタビューでは、前国土交通大臣政務官であり、現在自民党における「防災体制抜本的強化本部」の事務局長を務める尾﨑正直議員に、地方の現状や課題を踏まえ、今の時代に求められている防災・減災政策について、またご自身の政治家としての原点や今後のビジョンについてもお伺いしました。
(取材日:2024年12月23日)
(文責:株式会社PoliPoli 秋圭史)
地元の英雄・坂本龍馬に憧れ、政治の道を志す
ー大蔵省(現・財務省)の官僚からキャリアをスタートされていますが、まずは大蔵省に入省したきっかけや背景について教えてください。
高知県出身の私は坂本龍馬のように「世のため人のためになりたい」という想いを持ち、政治家になりたいという思いを学生時代から持っていました。とはいえ、まずは政治・行政のことをしっかり勉強しようと考え、行政全体に関わることができる大蔵省に新卒で入省しました。
30代に入るころになると財務省の仕事が面白くなり、政治家になるという想いは薄れていきました。財務省時代は予算編成の仕事が長かったのですが、財政再建の道筋を策定する業務や個別省庁の予算審査にも関与することができ、財政という切り口で行政の様々な分野に関わりました。
インドネシア大使館に赴任する機会にも恵まれ、外交面からも行政に関わりました。さらに第一次安倍政権のときには、官邸で官房副長官の秘書官に就き、グッと政権運営に近い部分に関わったり、とにかく政治行政の様々な分野に関わらせてもらいとてもやりがいを感じていました。
実は36歳くらいの時に高知県知事選挙へ出馬するお誘いを頂戴したこともありました。ただ官僚として働く中で、政治・行政の中枢を知り、面白くなってきた所だったこともあり、すぐさまお断りしたものです。
ーその後、高知県知事選挙に立候補しました。どのような心境の変化がありましたか?
4年後、40歳になったとき、もう一度高知県知事選に出馬してはどうかとお話をいただきました。現職の知事が後継指名した高知県職員の方がギリギリに近いタイミングで出馬をお断りされ、候補者を大急ぎで探しているときだったのです。時間もなく大変だという時に、前回も出馬の相談があった私の元に駆け込みでお話をいただいたという感じですね。
多くの方から熱心に、集中的にお誘いを頂き、私自身も、高知県も過疎化による経済の縮小など大きな危機感を持っていたので、投票日の2ヶ月前ぐらいに出馬を決断しました。いきなりのことだったので、出馬表明してもずっとドタバタしていたことを思い出します。
 高知県知事として「産業振興計画」を世に問う(まだパワーポイントも無い時代(笑))
高知県知事として「産業振興計画」を世に問う(まだパワーポイントも無い時代(笑))
ー県知事選挙では無事当選。当時最年少知事として就任し、3期にわたり高知県知事を務められました。そのなかで感じた現場の実情や、注力した課題などについて教えてください。
先ほども申し上げたように高知県の経済状況は非常に厳しいものでした。全国で有効求人倍率が1.0を超えた2006年も高知は0.42くらいしかなく、高知だけが全国に取り残され景気が低迷している状態だったのです。知事就任後、真っ先にその要因分析に着手したところ、人口減少に伴って高知県内の経済規模も縮小していることがわかりました。経済自体が縮小しているので、いわゆる地産地消をしていても縮小するばかりだったんです。
その対策として地域で作って外で売る「地産外商」の戦略を取りました。地理的に高知では企業誘致に有利ではありません。毎年のように発生する豪雨災害はもちろん、南海トラフ地震による津波の被害想定も大きい。おまけに本州から見ると高知は四国に渡った上でさらに山を越えた地域なので、産業の集積地にするような企業誘致は実現可能性が乏しいのです。ならば「地場の産業を外に売り込んで稼ぐ」戦略に振り切ろうと「地産外商」の戦略を採用した訳です。おかげさまで、一人当たり県民所得は、知事就任時全国でほぼ最下位だったのが、36位ぐらいまで向上させることができました。
ー国政進出に至った背景について教えてください。
高知県知事時代は国会議員になろうとは考えていませんでした。知事としての仕事は3期12年までと決め、その後は特にノープラン。シンクタンクのような行政における政策作りの知見を活かせる職を探そうかなと漠然と考えていました。
ー知事は3期までと決めていた理由は何ですか。
周囲がイエスマンばかりになり、よい仕事ができなくなると考えていたからです。就任当時は最年少ということもあり、ベテランの方を中心に必ずしも県職員の方々が私の話を充分に聞き入れてくれるわけではありませんでした。少しずつ実績を挙げていくと、求心力が高まるようになり、更に進むと、今度は次第に周囲から異論出なくなっていくんです。知事は人事権や予算編成権を持っており、非常に強い存在。長く続けていくなかで権力が集中しすぎることは、逆に危険だと思ったんです。
ーその中で国政に挑戦しようと。
ちょうどそのとき高知2区は自民党が議席を失っており、高知2区から出馬しないかとお声がけを頂くようになりました。自民党高知県連がこのままでは野党に勝てないと危機感を持っていた時期で、野党対立候補と同じ年代の私に白羽の矢がたったというわけです。
産学官民一体となったマクロな視点での防災政策
ー政府では「防災庁」設置の準備が進んでいるようですが、尾崎議員の視点から見て防災政策で注力すべきと考えているポイントについて教えてください。
防災は非常に多岐に渡る政策分野ですが、特に事前防災に力をいれていくべきだと考えています。事前防災は道や堤防などのインフラの強化から始まって、発災直後のオペレーションの改善に向けた平時からの準備に至る迄、幅広い内容を含みます。効率的・効果的な防災対応のための体制構築全般的な議論をしていくべきだと思っています。
ー防災体制抜本的強化本部での議論で、国と地方の連携、あるいは官民での連携の在り方についても意見が上がったと聞きました。このあたりの考え方についても教えてください。
事前防災も発災後対応も対応の主力は自治体です。ただし、過疎化や高齢化が進んでいる地方だけでは対応しきれないこともあるので、ここを国がしっかりバックアップする体制を作る必要があります。もちろん、大型のインフラ整備や防災DXなどのスキル、法制整備等は国が主体的に取り組まなければなりません。
併せて、民間事業者の防災対策も重要です。災害時に重要業務が停止しないようなBCP(Business Continuity Plan、事業継続計画)の策定をはじめ、各事業者自身が事前の対策と発生時の対応を準備する必要があります。国家安全保障の観点も含めて言えば、経済安全保障推進法で指定された重要インフラに関わる事業者の平時からの準備は特に重要だと考えています。
一つ私が強く問題意識を持っているのが、戦後に構築された日本の国土構造の危険性です。戦後の復興期・昭和30年代に臨海型の都市構造が次々と生まれ、海岸沿いに次々と大小のコンビナートが建造されていきました。その後、昭和40年代に入るとプレートの境界面で地震が頻発することを示したプレートテクトニクス理論が科学界において提唱され、日本の工業集積地域は繰り返し襲う巨大地震の想定被害地域に立地していることが事後的に判明したのです。
南海トラフ巨大地震では、これまでの巨大地震とは比較にならないほどの大きな被害が想定されています。昭和の時代に立地した西日本沿岸地域にあるコンビナートや発電所、工場群は大きな影響を受けるでしょう。発災時に大規模火災を起こすのみならず、長期間に亘り、燃料、電力の供給停止を引き起こす可能性が大きい。それは人々の暮らしの安全や安心の根本に関わるリスクだと思っています。今、想定しているBCPが根本から崩れるような事態になる可能性があります。こうした分野の事前防災対策はとても大事なことですし、昭和の時代に形成された国土構造・産業立地を抜本的に見直すことが重要です。先ほど経済安保保障法に言及しましたが、私はいずれ防災安全保障法のようなものが必要になると思っています。
ー日本を俯瞰したマクロな視点で「防災」について考えることが重要ということですね。
おっしゃる通りです。それに加えて災害の型にとらわれないことも重要です。一口に地震といっても、先の能登半島地震と今後予測される南海トラフ地震は、局所型と超広域型で性質が異なる災害です。
また同じ超広域型だとしても、震災による「揺れ」が深刻な被害をもたらすケースもあれば、揺れによって引き起こされる「火災」あるいは「津波」が大きな被害を与えるケースもあります。こうしたさまざまな被害パターンを想定して準備しておくことが重要です。膨大なパターンについて緻密な予測を行うためには、これからの防災DXを始め、最新のテクノロジーの力も借りていかなければなりません。現在実装に向けた準備が進んでいる新総合防災情報システムは、情報を集約し、関係者と共有し、それを使って予測や必要な対応を洗い出すといったことを意識して構築しようとしています。
 選挙の街頭演説にて、防災の重要性を訴える
選挙の街頭演説にて、防災の重要性を訴える
豊かで安全な国を将来に残すために。「防災政策」と「産業育成」の好循環
ー尾﨑議員は日本をどのような国にしていきたいですか。
「豊かな国を将来に残す」、「安全な国を将来に残す」この2つが政治家としての最大の使命だと思っています。いずれも厳しいチャレンジになりそうですが、豊かな国を実現するためには先端産業育成と地方創生が重要です。
先端産業育成については、諸外国が産学官民連携で産業政策に取り組む一方、日本は21世紀以降「官から民へ」を主眼として、そうした産業政策にあまり取り組んできませんでした。今ついに政府としてここに本格的にコミットしようとしています。この取り組みを、国際的競争を意識して加速する必要があります。
もう一つ、地方創生でそれぞれの地域の潜在能力をしっかり活かすこと。地方創生のセンターピンは各地方の実情に即して、各地域の事業者の事業拡大、則ち「地産外商」を行い、それぞれの経済ポテンシャルを最大化させることです。東京一極集中の是正はその結果として付いてくるものです。人口が減少する社会でも各地方の経済を拡大させる政策を諦めずに考え抜くことが重要だと思います。
最後にお伝えしたいことは「豊かさ」と「安全」はリンクし、相互にシナジーがあるということです。防災体制を強化すると同時に防災産業を育成したり、国家安全保障の強化に伴い防衛産業を育成したりすれば、コストセンターがベネフィットセンターとしても機能することとなり、産業の裾野が広がり、経済が活性化します。そして、豊かな産業群と強い経済を持つことは、こうした安全を更に強固なものとします。この「安全と豊かさの好循環」を作るために更に努力を続けたいと思います。