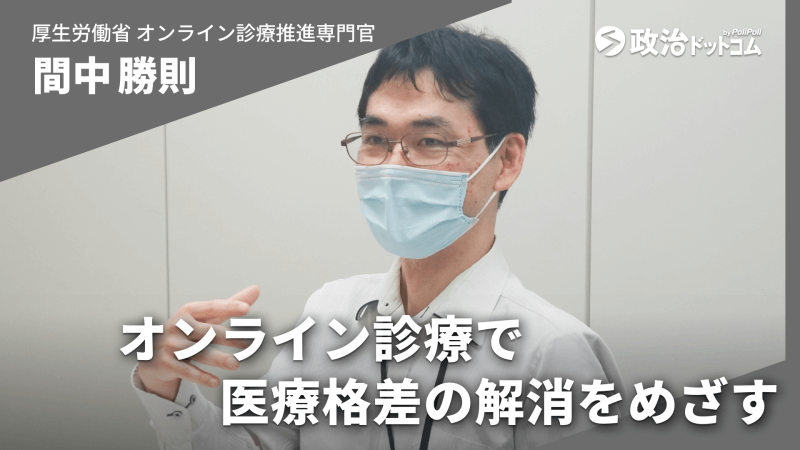仙田晃宏 せんだあきひろ 議員
1982年愛知県大口町生まれ。
明治大学政治経済学部を卒業後、NTTデータに入社。
18年間の勤務を経て政界へ。
2024年衆議院議員選挙に国民民主党から出馬し初当選。
第50回衆議院選挙が2024年10月27日に投開票され、99名の新人議員が誕生しました。『政治ドットコム』では、初当選を果たした国会議員の方々にインタビューし、政治家を志したきっかけや実現したい政策などを深掘りし、政治家の方々をより身近に感じられる記事を配信していきます。
今回のインタビューでは、国民民主党公認候補として立候補し、初当選を果たされた仙田晃宏議員に、政治家を志した原点や会社員時代に感じた問題意識、目の前の政策実現の先にどのような日本を思い描くのかについて、お伺いしました。
(取材日:2025年1月20日)
(文責:株式会社PoliPoli 秋圭史 )
幼い頃に見た祖父の姿、会社員として培った現場感を携えて政治の道へ
ーおじい様が長く地元の町議会議員を務められていたと拝見しました。ご自身も幼少期から政治家になることを意識されていたのですか。
私は愛知県の大口町の出身で、祖父が32年間町議会議員を務めていました。地域のため、町のため、そして人のために働く祖父の姿に感銘を受け、小学生くらいから自分も政治家になりたいという思いをうっすら持っていました。
小さな町でしたので、祖父がよく町役場に連れて行ってくれて、役場の方たちにもかわいがってもらった記憶があります。そのため子どもの頃から政治や行政を比較的身近に感じていました。
当時は政治家になろうとまでは思っていませんでしたが、大学では政治経済学部に入学し、雄弁部にも所属して政治について学びました。

ー民間のIT企業からキャリアをスタートしましたが、どのような経緯だったのでしょうか。
学生時代には、議員事務所でのインターンも、民間企業でのインターンも両方経験しました。そこで感じたのは、やはり世の中の大多数の人はどこかの企業で働く、いわゆる「会社員」であること。政治を志すとしても、企業で働く人たち、普通の会社員たちの気持ちを理解できなければ意味がないと思い、まずは民間企業で働こうと考えました。
その中でも、せっかくなら社会のために働きたいと思い、国のインフラを支えているNTTデータを選びました。
ー18年のNTTデータでのキャリアから政治家に転身したきかっけは何だったのでしょうか。
地方の過疎化を目の当たりにし、日本の将来に危機感を抱いたことがきっかけです。NTTデータでは、地域金融機関の営業からキャリアをスタートしました。日本全国を巡るなかで、地方では駅前にも本当に人がいない。このままでは地方の縮小が進み、結果的に国全体が縮小していく。これはどうにかしなければならないなと感じました。
人口減少に伴い、地域の金融機関も合併を繰り返しています。私は、いずれ県などの自治体も合併を考えていかねばならないのではないかと思います。
そんな問題意識を持つなかで、政治の道に進むことを決めたのは新型コロナウィルスがきっかけでした。それまで対面でしてきたコミュニケーションがどんどんオンラインに移行していく中で、NTTデータという会社としては、IT化で便利に効率的に、ということに貢献できたのですが、私個人の想いとしては対面でのコミュニケーションを非常に重視していました。
そこのギャップが生まれたタイミングで、自分は世の中に対して何ができるのだろうかと、政治に関する塾に入りながら改めて考えた結果、政治家に転身する決意をしました。
ー安定した大手企業から政治家に転身に対して、周囲の反応はいかがでしたか。また国民民主党からの出馬に至った背景も教えてください。
周りからは、NTTデータという一部上場企業の安定をなぜ捨てるのかという声は多かったです。しかし、成長やチャレンジの機会として応援してくださる方もいました。また妻も私が政治の世界に興味があることを知っていたので私の決断を応援してくれて。本当に感謝しています。
国民民主党を選んだのは、党の方針や政策への共感からです。「対決より解決」というスローガンもそうですし、当時から給料を上げるという政策を掲げている点にも共感しました。
会社員時代は管理職もしていたのですが、若い優秀な人がどんどん辞めてしまう背景に、外資系が提示する給料に勝てないという要因があることに気づきました。
昔は海外から日本に出稼ぎに来てくれていたのが、今は逆に日本が外に稼ぎに行くような現状に危機感を持っています。
人がどんどん外に出ていけば日本の産業空洞化がどんどん加速するので、やはり働く人の給料を底上げすることが重要だと考えています。

IT企業での経験を活かし、まずは地方×スタートアップでイノベーションを!
ー仙田議員が掲げる政策に「岐阜県をデジタル特区に」があります。まずはこちらについて聞かせてください。
端的に言ってしまうと、現在トヨタ自動車が静岡県裾野市で実施している「ウーブン・シティ」が一つのゴールの姿かなと思っています。すべての情報が繋がって連動して動いていくという社会を実現したいです。
現在、ウーブン・シティは、企業敷地内、つまり私有地であるため好きなように実証実験ができますが、やはり公共用地でできないと限界があると思っています。
そうした時に、岐阜県の山間部は人口よりもシカやイノシシが多いと言われるくらい土地もあり、人口密度も低いので、自動運転やドローンの実証にうってつけなのではないかと考えています。
ーNTTデータでのご経験がそうした政策立案にも活きてきそうですか。
通信による効率化、例えばバーチャル市役所のような構想であったり、防災におけるデータ連携など、NTTデータが強みを持っている分野の経験は活かせる部分があると思います。
意外と党内にもIT系の人材は少ないので、そうした観点からも貢献できたら良いですね。
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会にも抜擢されていますが、そうしたIT知見が背景なのでしょうか。委員会ではどのような観点に注力していきたいですか。
自分の強い希望を党に受け入れてもらった結果です。委員会の中で注力したい政策は2点あります。一つは東京一極集中の打破です。言わずもがな、東京にどんどんヒト・モノ・カネが集中する一方で地方が形骸化していってしまうので、本社機能の地方移転に対する税制優遇や、テレワーク推進など、地方と都市部の実情に即した法整備をする必要があります。
もう一つはスタートアップや起業家の応援です。大学での起業も含めて、若い起業家やスタートアップを税制や補助金で応援し、投資していく。各県・地方でもそうしたスタートアップに対する評価をして投資を促せるような仕組みを作っていきたいです。岐阜県の近くでいうと、愛知県の「STATION Ai」のようなオープンイノベーション拠点なども良い例だと思います。
「Japan As No.1」を取り戻すために、まずは手取りUPから景気の循環を作る
ー今後、国民民主党をどのような党に育てていきたいか聞かせてください。
今回の選挙で大きく議席を伸ばし、注目いただいていますが、まだ28議席で全体の中で決して大きいわけではありません。
まずはどんどん仲間を増やしていくことだと思います。
それは国会議員だけでなく、県や市議会も含めて、国民民主党の旗を掲げてくれる仲間を地方にも増やしていくことが大事だと思います。
一方で、今後党が大きくなっていくと、今の理念や信念に必ずしもフィットしない方も増えてきて、カルチャーが薄まってしまう可能性もありますが、「大きい党だから」ということではなく、これまでのように議席が少なかったとしても政策やビジョン、方針に心から共感して参加してくれるような仲間を見つけていくということを大事にしていきたいです。
この軸はぶらさない、変えないということを言い続けていきたいです。
ーご自身として、政策の実現を通じてどのような日本にしていきたいかをお伺いさせてください。
「Japan As No.1」を取り戻したいです。
先にも述べましたが、日本からどんどん人や産業が外に出て行ってしまう流れをどうにか変えて、もう一度Japan As No.1を目指さなければならない。
言わずもがな、経済政策に注力し、まずは手取りを増やして使えるお金を増やし景気の循環を作っていく、消費喚起をしていくところから着手していきたいです。

ー最後に読者へのメッセージをお願いします。
政治は皆さまが思っているよりももっと身近なものだと思います。給食費の無償化のような話はもちろん、今日私のところにいらした地元の支援者の方は「子どもの通学路を何とかしてほしい」とおっしゃっていましたし、そういう身近な課題も含めて政治とつながっています。
学生の方であれば、まずは自分のアルバイトの給与明細をよく見てみてください。
明細で天引きされている「社会保険料とは何だ?」というところが既に政治とつながっています。一度見てもらったら「税金高すぎ!」と気づくと思います。ぜひそうした身近なところから政治に関心を持ち始めていただければと思います。