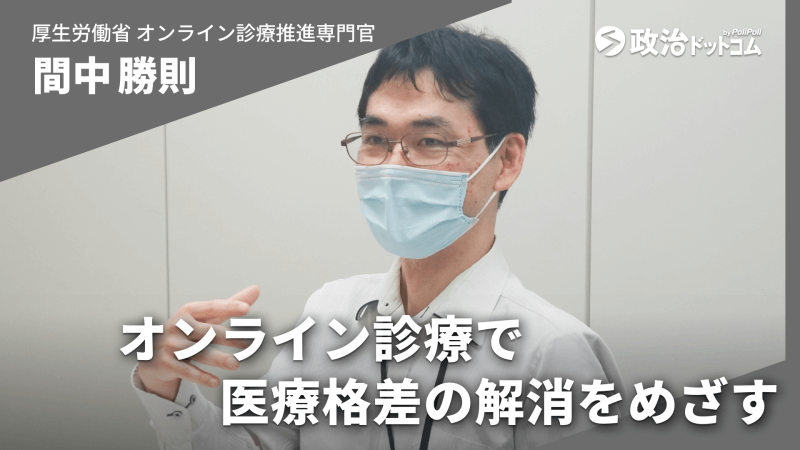浮島智子 うきしま ともこ 議員
2歳半でバレエを始め、19歳で香港ロイヤルバレエ団に招聘。
香港、アメリカなどでのプリンシパルダンサーとしての活動を経て、
1998年に日本で劇団「夢」サーカス設立。
2004年参議院議員選挙で初当選、2012年衆議院議員選挙で初当選(5期)。
文部科学副大臣などを歴任し、2024年9月に党市民活動委員長就任。
好きな言葉は「やればできる」。
小中学校の不登校児童が全国で30万人を超える一方、教員不足や長時間労働などの課題が深刻化する教育現場。現在その解消に向けて不登校児童の受け皿の整備や教員の処遇改善など、さまざまな制度改革が進められています。
今回のインタビューでは、バレリーナから政治家へ異色の転身を果たし、文化芸術や教育を軸に子どもたちのための政策に注力する浮島智子議員に、その思いをお伺いしました。
(取材日:2024年12月26日)
(聞き手・文責:株式会社PoliPoli 井出光 )
文化芸術を通じて「心の復興」を支援
ー政治家になる前、浮島議員はバレリーナとして活躍されていたと伺いました。
バレエを始めたのは2歳半のときです。19歳で香港ロイヤルバレエ団からの招聘を受け、それから約13年半にわたって活動しました。その間、香港とアメリカのバレエ団でプリンシパルダンサーやカルチャースクールの経営を務めさせていただきました。
ーバレエを辞めたのち、日本で劇団を主宰されています。どのような背景があったのでしょうか。
大きな転機となったのは、1995年の阪神・淡路大震災です。当時、ニューヨークにて活動していたのですが、震災のニュースに衝撃を受け、バレエ団を退団し帰国したんです。「ごみ拾いだけでもいいから何か役に立ちたい」という思いで神戸を訪れたのですが、多くの仮設住宅で暮らす被災者の方々を見て「復興の力になろう」と決意し、日本に戻ってきました。
被災地で「自分に何ができるだろう」と考えたとき、やはり私の原点であるバレエ、ダンスを通じてみんなを元気にしたいと思ったんです。宝塚やバレエの友人にもお声がけし、ルミナリエの前で躍らせていただきました。
その後も子どもたちにダンスを教えたり、ミュージカルを企画したり、さまざまな活動を続ける中で「心の復興」を深く考えるようになりました。道路や橋はお金を出せば元に戻りますが、心の復興は目に見えません。しかし、これこそが最も重要なものです。
そこで次に取り組んだのが、劇団の創設です。1998年に劇団「夢」サーカスを設立し、震災で両親を亡くした子どもたちをはじめ、希望する方は誰でも参加できるようにしました。衣装や道具の制作など、運営はすべてボランティアで、本当に多くの方が協力してくださいました。親を亡くして暗い気持ちになっていた子たちが、活動を通じて少しずつ前向きになっていく姿を見て「芸術ってこんなにも人の心を強くするんだ」と改めて実感したのを覚えています。東日本大震災の後には東北でも公演を行い、被災地の方々と絆を深めてきました。
ー2004年に参議院議員選挙に立候補し、初当選されています。出馬のきっかけは何だったのでしょうか。
2001年に、現在の文化芸術基本法の前身である「文化芸術振興基本法」が成立しました。その際に「法律はできたものの、舞台芸術を理解している人がいないと具体的な政策を実行できないので協力してほしい」と公明党からオファーをいただいたのです。一緒に活動していたボランティアのみんなに相談したら「私たちも芸術で元気になったので、政党に関係なく応援します」と言っていただいたので、立候補する決断をしました。

当選当初から、子どもたちに本物の文化芸術に触れてもらうための取り組みには力を入れてきました。学校にアーティストが来てパフォーマンスを行う「本物の舞台芸術体験事業」に関しては、2009年度に実施校を3倍に増やすことができました。
ただ、この事業では学校に来ることができない不登校児などは観ることができません。そこで新たに取り組んだのが、18歳以下を対象に、採択された公演のチケットを上限3万円まで無料にする「劇場・音楽堂等の子供鑑賞体験支援事業」です。2021年度に公明党の提案で始まり、23年度には7万人を超える子どもが鑑賞しました。
いじめで不登校になっていた児童の一人は、この事業を利用して祖父母と何度も公演を観に行き、心に変化が生まれて学校に行けるようになったそうです。だから、外に出て何かを体験するというのは、本当に大切なことだと思います。
「公教育の再生」に向けて教育現場を変える
ー浮島議員は文化・芸術だけでなく教育分野の政策にも注力しています。
芸術に関わってきた人間として日本の教育のあるべき姿を考えたとき、「人と人が向き合い、目と目を見て心で感じる教育」、そして「体験を通じて学ぶ教育」が大切だと思っています。
昔は家庭でも近所でも「悪いことしちゃいけないよ」「ちゃんと帰ってきたら靴を揃えなさい」など言ってくれる大人がいましたよね。それが今はなくなりつつあるのと、いじめが陰湿化していることに心を痛めています。
ー教育分野では、今どのような課題を感じていますか。
まず、不登校の子どもたちがかつてなく増えていることです。不登校の児童は小中学生を合わせて30万人以上に増えていますが、具体的な対策が見つかっていない状況です。そこで、「公教育の再生」という概念を提唱しました。子どもたち一人ひとりが持つ才能や個性に光を当て、それぞれの「好き」を伸ばしていける教育の実現を目指しています。
従来の一方的なレクチャー形式の授業で、よく理解できないまま点数で評価される学校って、通いたくなくなるじゃないですか。そうではなくて、しっかりと基礎教育を大事にしながらも、個々の「好き」を伸ばせる学校が理想だと思うのです。実際に、不登校児童向けに特別な教育課程で授業を行う「学びの多様化学校(不登校特例校)」では、そうした取り組みを実践し、子どもたちもイキイキしています。
ある不登校の児童はゲームが大好きで、教師が「ゲームも勉強だから一生懸命やってみたら」とその興味を後押ししました。その生徒は卒業後、ゲーム関連の会社に就職。店長を任された後、子会社の社長にまでなったそうです。
不登校の子どもたちも含め、全ての子どもたちは夢中になれるものを必ず持っている。それをどのように引き出してあげられるかが、鍵です。ただ、科学技術、文化芸術、スポーツなど、子どもが興味を持つものは多岐にわたるため、それを教えるために各分野の専門家による指導が必要です。現在、文部科学省と議論していますが、教員免許を持たない方でも特別免許を交付して授業ができる制度を検討しています。

また、教師のなり手不足が深刻です。公教育の再生には教師たちの働き方改革と処遇改善が不可欠です。
2024年12月23日に、私が部会長を務める公明党 文部科学部会が「教員の働き方改革と処遇改善に向けた緊急提言」を文部科学大臣へ提出しました。提言には処遇改善として学級担任や生徒会担当といった職責を正しく評価するための新しい役職の創設や、やむを得ず勤務時間外に行う業務に対する新たな手当、教職調整額の引き上げなどを盛り込みました。
また働き方改革としては、国や地方自治体、地域社会が一体となって取り組む「緊急改革期間」の設定、勤務間インターバルの導入や支援人材の拡充、教科担任制の拡大などを要望しました。この「処遇改善」と「働き方改革」は両輪として一緒に進めていくことが大切です。
私は教員の業務を「やらなくていいこと」「やってもやらなくてもいいこと」「やらないといけないこと」の3つに分類し、やらなくていいことをどんどん削っていく提案をしました。先述の「学びの多様化学校」では教師が子どもたちの教育に集中できる環境があるので、みんなイキイキしているんです。一方、一般の学校では付随する業務が多すぎて、児童生徒への教育に十分に集中できていません。この状況の改善のためにも、必要のない業務を洗い出して削る努力が必要なのです。

2024年5月には「チーム学校推進法案」を議員立法で出そうと意見をまとめました。これは教職員のみで学校を運営するのではなく、複雑化・多様化する教育課題に地域社会全体で取り組み、公教育の再生を図ることを目的としたものです。2015年3月に予算委員会で初めて「チーム学校」を打ち出し、法案をまとめましたが、衆議院の解散によって廃案になってしまいました。今回の通常国会で必ず実現したいと考えています。
やさしい社会を築くのは「1人」を大切にする気持ち
ー今気になっていることや、今後取り組みたいことについて教えてください。
一番気になっているのは、子どもたちのスマートフォンの利用です。最近は子どもたちもスマートフォンの決済アプリでお買い物をしているのを見て驚かされます。現金をほとんど触らず、金銭感覚が身につくのでしょうか。さらには、家族で食事に来ても全員が別々にスマートフォンを見ていて、家族の会話がない。スマートフォンの登場によって、なにか大切なものが失われつつあるように思います。
また、SNSを使っていじめが陰湿化していることに強い危機感を抱いています。「LINEの返事が遅い」というだけでいじめが始まるなど、辛いですよね。オーストラリア議会が16歳未満のSNS利用を禁止する法案を可決しましたが、日本でも大人が何か対策を考えないと、苦しむ子どもが増える危険性があります。
ー最後に、読者にメッセージをお願いします。

皆さんにお願いしたいことが一つあります。それは、「1人の人でいいから、身近な人に声をかけてあげてほしい」ということです。自分の心に余裕がないと、他者に優しくすることは難しい。だから私も劇団のメンバーにはずっと「全員を幸せにしようとしなくていいよ。でも学校に行ったら、自分の両隣と前後に座っている友達には声をかけてあげよう。それで何か悩んでいたら共有して、話をしよう」と伝えてきました。
若い方々にもお願いしたいのは、SNSが重要になっている昨今、やはり生身の対話を重視した生活も忘れないでほしいということ。そして家に帰ったらスマートフォンを置いて、家族と話をしてほしいということ。たわいのない会話で構いません。そこから心の交流をどんどん広げていってほしいです。人と人とのふれあいが強固になれば、人の喜びや心の痛みがわかる人がもっと増えると信じています。