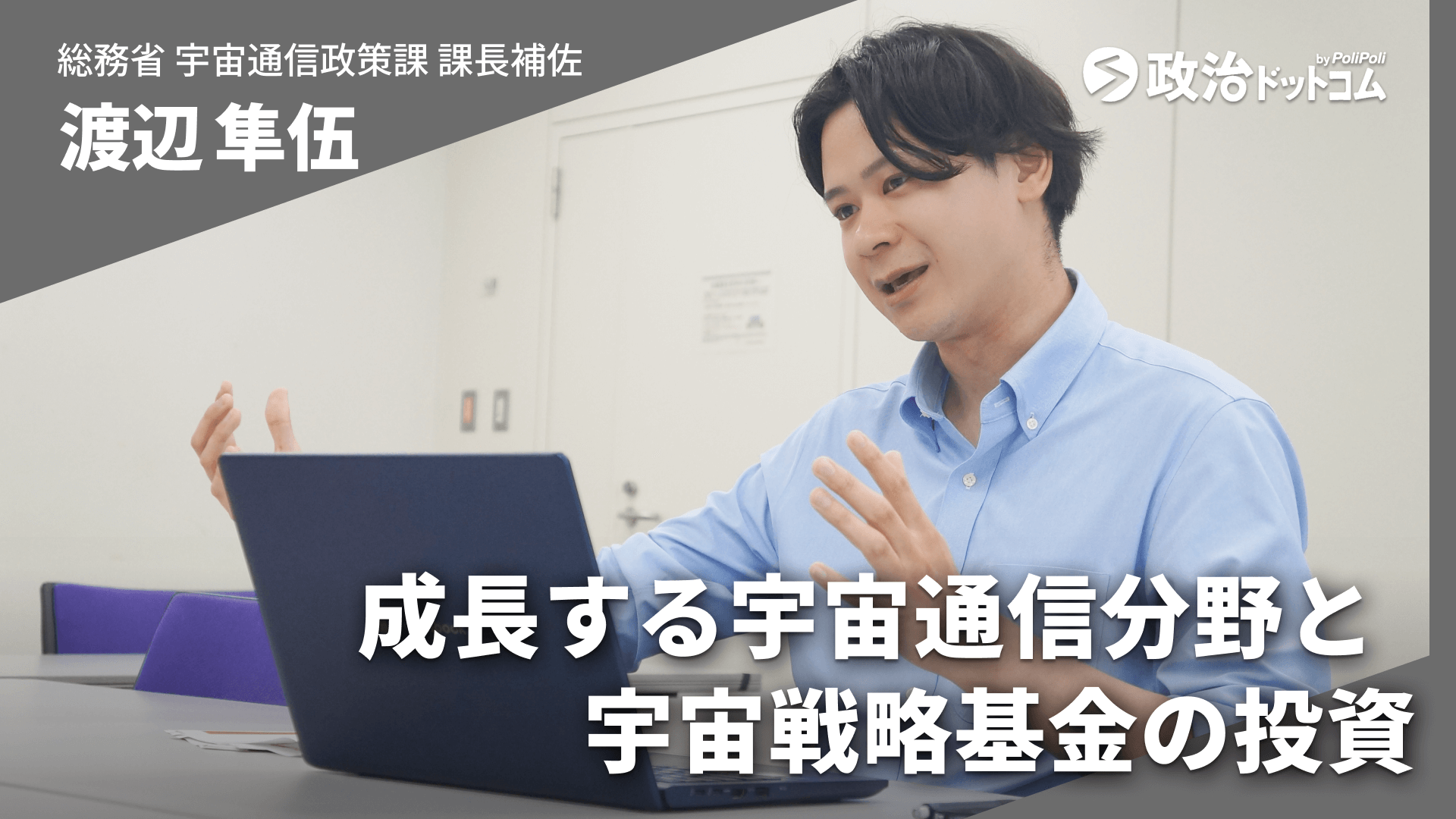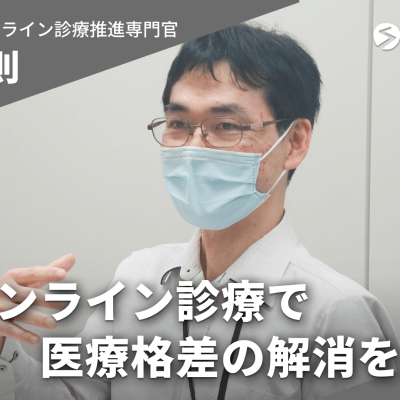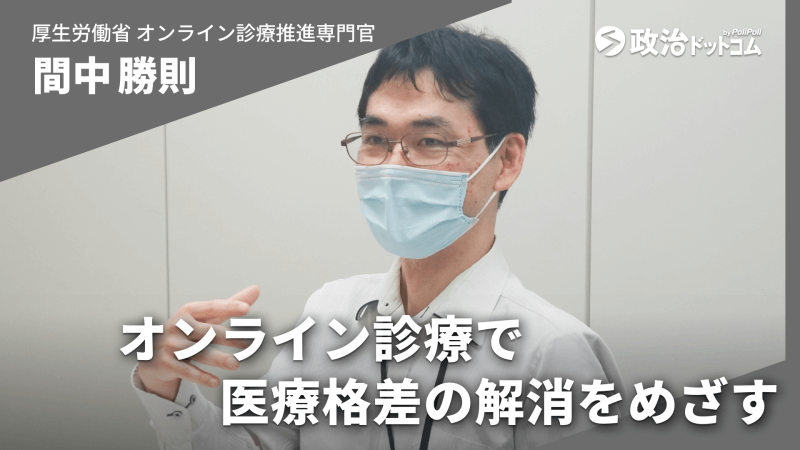宇宙は儲かるものではない、という時代を脱して宇宙は成長市場に転じており、宇宙分野の注目度が高まっています。成長市場ながら米国勢が強い宇宙市場について、総務省はどのような対応をしているのでしょうか。今回は総務省国際戦略局宇宙通信政策課の渡辺隼伍課長補佐に、宇宙通信分野を中心とする宇宙政策の方向性や2024年に設立された宇宙戦略基金について、また、宇宙政策を手掛けるやりがい等をお聞きしました。
(取材日:2025年8月28日)
(文責:株式会社PoliPoli 秋圭史 )
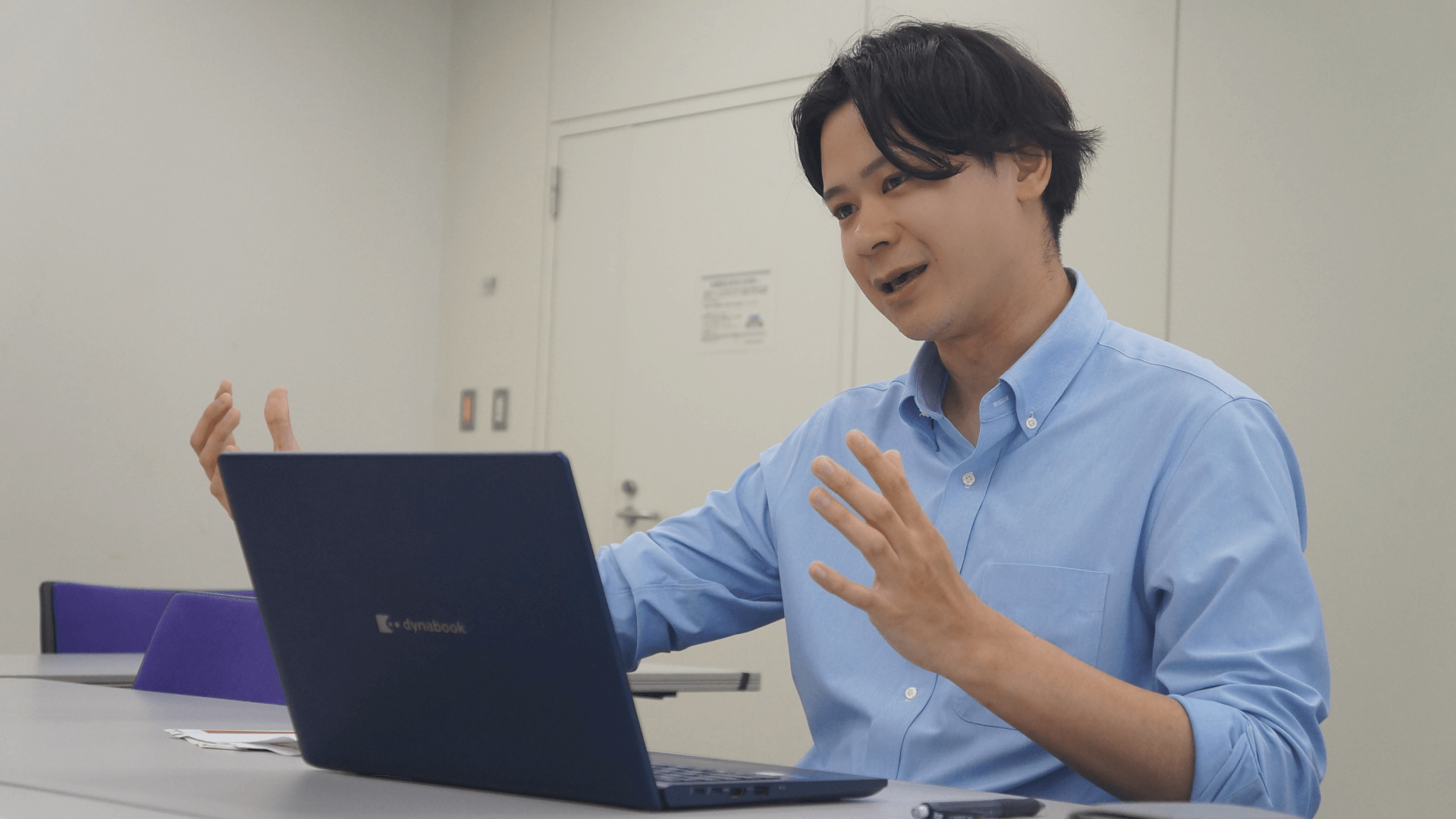
渡辺 隼伍
総務省 宇宙通信政策課 課長補佐。
2019年に総務省入省後、QRコード決済推進など情報通信政策に携わった後、デジタル庁にて人事・広報施策の立ち上げを担当。通信規制見直しの法改正の業務を経て、現在は宇宙通信分野の政策企画に従事。
宇宙分野の政策における総務省の役割
─宇宙分野の政策は非常に幅が広いため、各省庁で役割分担をしていると思います。その中で、総務省はどのような役割を担っているのでしょうか。
総務省は宇宙分野の政策について、衛星通信とも呼ばれる宇宙通信分野で中心的な役割を果たしています。ただし、宇宙通信は知られていない部分も多いので、最初に基本的なところからお話をさせてください。
通信というのは、距離が離れた人同士で話ができる仕組みです。東京と大阪など、遠方の人と会話ができるのは、地中に通信用の線が通っているからです。携帯電話は近くの基地局まで無線でつないで、そこから先は地中に埋まっている光ファイバー経由で通信する仕組みです。一方、光ファイバーが引かれていない地域は、携帯電話があってもつながりません。日本は人口の9割9分の方が携帯電話を使える状態ですが、面積ベースでは未だ6~7割に留まる状態です。現実問題として、山の上や離島などに光ファイバーを敷設するのは難しいので、解決策として出るのが、宇宙を経由すればいいじゃないか、という発想です。地上から何万kmも上空にある衛星を経由して通信ができるようになる、ここが宇宙通信を理解する上で一番大切な部分です。
─宇宙分野は近年、急速に注目を集めるようになりました。宇宙市場についてどのような見方をしておられるのでしょうか?
これまでは宇宙政策は儲かるものではない、という前提だったのですが、産業化が進み市場が成長していることが明らかになっています。様々な予測があるものの、現在は約3,300億ドルの市場規模があると言われており、2035年には2倍以上の7,500億ドルになるとの予想です。また、そのうち3分の1は通信分野です。今後成長する宇宙業界、その中でも3分の1を占める宇宙通信分野において、日本の事業者や日本の技術が勝ち進むことが、法人税等を含む税収増にもつながります。宇宙通信産業の育成を通じて、我が国を活性化することが我々の大きな目標です。
成長する宇宙市場で日本企業が勝つための政策について
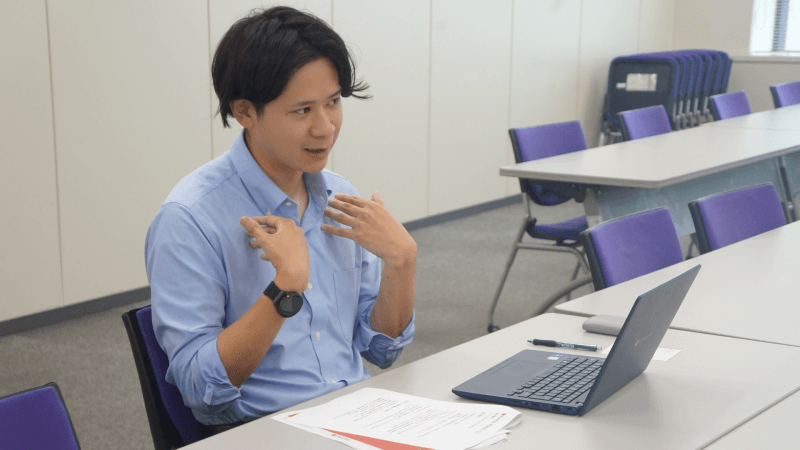
─成長が進む宇宙市場で日本企業が勝つための戦略を教えてください。
日本は以前から衛星通信に関して研究開発の蓄積もあり、優れた技術があります。例えばスカパーJSATという会社がありますが、同社はアジア最大の衛星通信企業であり、宇宙業界で確たる地位を築いています。一方、近年はスターリンク、最近ではアマゾンの衛星打ち上げプロジェクトがありますが、彼らはケタ違いの資本力で破壊的なビジネス展開をしています。どういうことかと言えば、日本がこれまでやってきたような、衛星を1つ打ち上げて日本全体をカバーしよう、というものではなく、小型衛星を何百機・何千機と打ち上げて、一気に世界中でサービスを展開します。彼らにより業界構造が様変わりし、業界のエコシステム(生態系)が変化しています。そのような環境であり、日本の生き残り策はシビアに考えざるを得ません。
このような破壊的なビジネスが出てきた背景の一つには、米国ではNASA等が民間企業に相当規模の資金を投じたことで、民間企業が大きく成長したことがあります。世界的に官民一体となった宇宙開発競争が発生しており、日本においても、JAXAを産官学の結節点として民間企業や大学の研究開発支援を戦略的に行うため2024年に宇宙戦略基金を設立しました。この基金を用いて、10年で有望な民間企業・大学等に1兆円を投資して、研究開発をしっかり頑張っていただこう、という取り組みを行っています。そこでは、我が国として強い分野や、民間企業が自らやっていきたい、こういった研究開発をしたい、と手が挙がったテーマを支援しています。
日本がこれまで手掛けてきた、光通信分野は可能性のある分野です。衛星通信は衛星と地上との間を通信するものですが、その通信手段について“電波か光か”という議論があります。日本は光ファイバーで元々強い技術を持っていたこともあり、光でつなぐ技術革新がかなり進んでおり、そういった進んでいる分野を拾い上げながら政策を進めています。正面から勝負してスターリンクに勝つようなことは考えておらず、この分野なら勝てる、という分野を中心に取り組むのが総合的な考え方です。
─KDDIはスターリンクと提携して、4月から衛星ダイレクト通信を始めています。
衛星ダイレクト通信は、スマホから直接衛星通信を使えて、利用者が特別な準備を必要としないので、一気に衛星通信が身近になる可能性を秘めています。山間部や離島などこれまでつながりにくかった地域でも携帯電話がつながるようになり、災害時での活用も含め、利便性は高く大いに期待しています。その上で、現状では、海外事業者の衛星通信インフラの上で成り立っている状況であり、通信インフラが国民生活にとって重要なインフラであることを考えれば、日本としても衛星ダイレクト通信のインフラを持つことが必要だと思っています。
─宇宙通信分野において日本としての独立性はどの程度大切なのでしょうか?
日本にとって宇宙通信分野の独立性がどれくらい大切かについて、2つの観点でご説明します、1つ目はデータ主権に類似の考え方です。例えば海外企業によるクラウドサービスは海外にサーバーがあるため、日本人が使うデータは海外経由にならざるを得ないことがあります。それは経済安全保障上問題があるのではないか、という議論がありますが、宇宙通信分野も同様です、宇宙からの通信を受信する先が海外だけ、という状態であってはならないと思います。日本の事業者が宇宙との間で通信を行い、日本で送受信できる自律性の確保は非常に重要です。
もう1つは、月や火星探査に関係する話です。月面での人類の活動には、地球と月との間の通信が欠かせません。先日、ispace社の機体が月に着陸しようとして実現に至りませんでした。同社の機体も地球と通信をしているから機体の状態が分かり、地上から機体のコントロールができる訳です。その時の月と地球との通信の重要性は言うまでもありません。しかし、今アメリカではトランプ政権下で、NASAの関連予算や月の探索予算が削減されるとの報道が出ています。日本の持続的な宇宙開発のためには、月と地球の間の通信も日本側で提供できる環境を維持する必要があります。それにより、月面での活動の自由度も確保されるのではないでしょうか。
─宇宙分野は他の分野以上に官庁と民間企業の連携が大切かと思いますが、状況はいかがでしょうか。
そうですね、宇宙通信産業のエコシステムを大切にしなければならないと考えています。また、最近はありがたいことに、業界のプレイヤーが増えています。元々は、一部の大手企業だけ、という業界だったのですが、近年はスタートアップの参入が増えており、2024年にスタートアップで一番人が流入した業界は宇宙分野だったそうです。
ただし連携に絡めて言えば、この流れを実際の市場獲得や市場拡大につなげていくためには、技術のシーズ(種)とニーズの両者を接続するのが、非常に重要です。例えば、モノ作りに対する支援で言うと、公的支援を受け、5年、10年かけて凄い技術ができたものの、最後になって、結局誰が買うのか?誰が使うのか?、というユーザーの視点が抜けていてはもったいない訳です。そうではなく、技術を開発する側のベンダーと利用する側のオペレーターが一緒になって技術開発を進めて欲しい、と我々は思っています。ただし、これは我々がお願いしているだけではなく、民間企業の側も既に気付き始めているようで、両者がうまく接続できればよいなと思っています。
宇宙分野の盛り上がりを無駄にしないことが大切
─宇宙分野の政策について今後の展望を教えてください。
先ほど自律性の話が出ました。宇宙分野が拡大し、海外事業者がどんどん市場を拡大していく中で、日本の事業者にもぜひ頑張ってほしい、という思いを持っています。繰り返しになりますが、現状では、衛星ダイレクト通信も海外事業者の衛星通信インフラの上で成り立っている状況であり、通信インフラが国民生活にとって重要なインフラであることを考えれば、日本としても衛星ダイレクト通信のインフラを持つことが必要だと思っています。
技術開発については、宇宙戦略基金が6,000億円まで予算化されており、目標の1兆円に向けて勝てる技術を拾い上げていくことも重要な課題です。技術の種は多いので、様々な方と意見交換しながら有望な技術を見つけていきたいです。直近で取り組みたいのは、自動運転など自動車産業と通信産業を連携させることや、今は利用されていない他の産業での衛星通信の利用です。これらの技術開発やアンテナ設計、通信方式の研究もしっかり応援したいですね。
─宇宙戦略基金の役割は大きいですね。
業界として本当に宇宙分野は盛り上がっていますが、資金的には民間のベンチャーキャピタルが投資しているものの、個人的に民間銀行や公的な金融機関の資金はまだ流入していないと感じています。宇宙戦略基金が公的なリスクマネーとしての役割を果たした上で、民間のビジネス展開がうまくいくよう頑張っていただくことを期待しています。
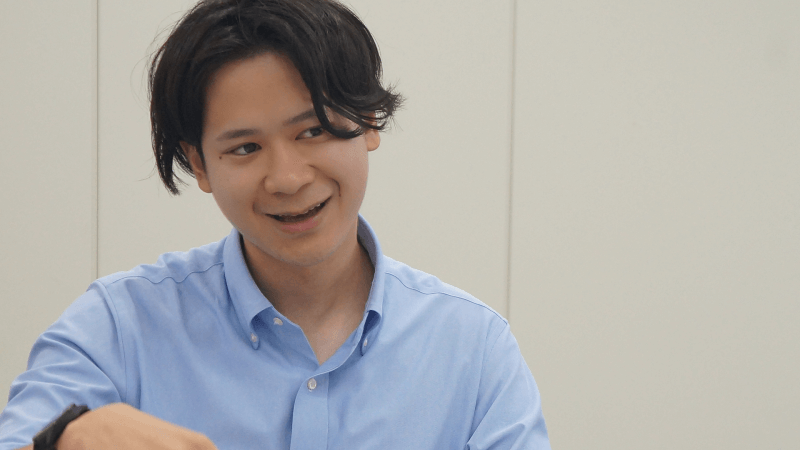
─最後に宇宙通信の分野を通して社会を変革していく、やりがいと大変さの両面を教えてください。
個人的にも宇宙は子供の頃からワクワクする分野でした。宇宙が人々に夢を与える力を本当に感じています。日本人の宇宙飛行士が月に行く時代も今後来ると思うのですが、宇宙通信によってその様子のライブ配信が実現することを期待したいですね。月面の活動などをリアルタイムで見ることができれば、社会現象となり日本全体が盛り上がるでしょう。その状態が非常に大切で、また日本の技術力を示す良いきっかけになると思います。そこに向けて活動できること、それを先導できることは、本当にやりがいを感じています。
一方、大変なところは、難しい事柄をどのようにわかりやすく伝えられるか、という部分です。宇宙の専門家だけで仕事をしている訳ではないので、政治家の方や一般の方も含めて宇宙開発の意義をしっかり伝えなければなりません。宇宙の魅力を分かりやすく伝えて、仲間を増やし、理解してもらうこと。そこが課題でもあり難しい部分です。
いずれにしても宇宙分野は今非常に盛り上がっています、この盛り上がりを無駄にしないことが本当に大切だと感じています。