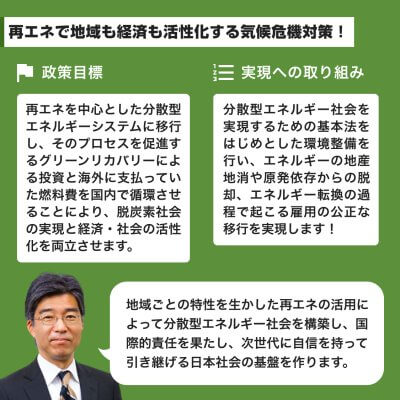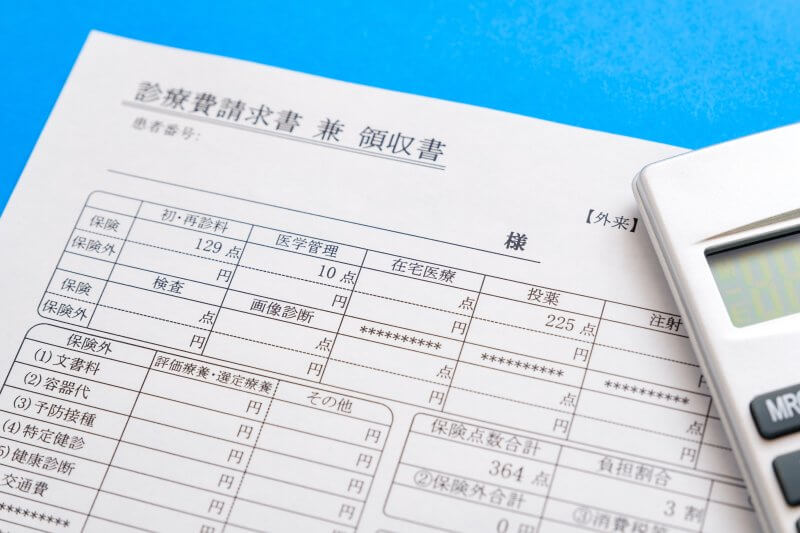「特定外来生物」とは、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす、または及ぼすおそれのある外来生物のうち、規制・排除の対象として指定された生物のことです。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」で具体的な種類が指定されています。
今回は特定外来生物について以下の通り解説します。
- 「特定外来生物」とは
- 「外来種」や「未判定特定生物」との違い
- 特定外来生物が及ぼす3つの悪影響
- 海外起源の外来種はどのようにして日本にやって来たのか
- 日本の取り組み
- 世界の取り組み
1、特定外来生物とは?
 特定外来生物とは、以下全ての条件に当てはまる生物を指します。
特定外来生物とは、以下全ての条件に当てはまる生物を指します。
- 海外由来の外来種(人間によって日本に持ち込まれた種)
- 侵略的外来種(生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす種、または及ぼすおそれがある種)
- 外来生物法により指定された種
個体だけではなく卵、種子、器官なども含まれます。
種類も哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類、クモ形類、植物、甲殻類など様々です。
具体例としてはタイワンザル、アライグマ、ヒアリ、カミツキガメなどが挙げられます。
参考:どんな法律なの? | 日本の外来種対策 | 外来生物法
2、「外来種」や「未判定外来生物」との違い
特定外来生物とよく似た言葉について説明します。それぞれ言葉の定義が微妙に異なります。
(1)外来種と侵略的外来種
「外来種」とは、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことを指します。
“もともとその地域にいなかったにも関わらずそこにいる生物”と聞くと、渡り鳥などをイメージするかもしれませんが、自然の力で移動する生物は外来種に当たりません。
あくまでタイワンザルなど、人間によって海外やその他地域から新たな地域に持ち込まれた生物を指します。
ここで注意したいのが、外来種には海外由来の外来種だけではなく国内由来の外来種もあるという点です。
例えば台湾から日本に持ち込まれた生物はもちろん外来種に当たりますが、沖縄にしか生息していなかった生物が北海道に持ち込まれた場合も外来種に当たるのです。
このような外来種の中でも、特に自然環境に大きな影響を与える種を「侵略的外来種」と呼びます。
例としては、以下が侵略的外来種に当たります。
- 沖縄本島に持ち込まれた「マングース」
- 小笠原諸島に入ってきた「グリーンアノール」
特定外来生物に該当するのは「海外由来の外来種」のうち、「侵略的外来種」なのです。
(2)未判定外来生物
「未判定外来生物」とは、特定外来生物と似ていますが、定義上は別の生物です。
海外由来の外来種である点は同じですが、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすおそれがあるが「実態がよく分かっていない種」である点に違いがあります。
未判定外来生物は輸入できますが、事前に環境大臣と農林水産大臣に届け出なければなりません。
参考:どんな法律なの? | 日本の外来種対策 | 外来生物法
3、特定外来生物が及ぼす3つの悪影響

(1)生態系への悪影響
外来種が入ってきた場合にまずリスクとして考えられるのは、在来種(もともとその地域にいる種)への悪影響です。
在来種の数を減らしてしまったり、場合によっては絶滅に追いやってしまったりする可能性さえあります。また、在来種と交雑することで雑種を産み、在来種の遺伝的な独自性が損なわれる場合もあるのです。
例えば、小笠原諸島のみに生息する希少な昆虫類が、ペットとして持ち込まれた特定外来生物「グリーンアノール(別名:アメリカカメレオン)」に捕食されています。個体数が激減している種もあり、大きな問題となっています。
(2)人への悪影響
種によっては毒を持っているものもあるので、そのような生物との接触があれば人間が病気になる可能性もあります。
本来であれば日本に存在しなかった生物が新たに入ってくることで、新たな病気の発症・感染リスクが高まる可能性があります。
2014年に東京都でも発見された 特定外来生物「セアカゴケグモ」を例に挙げると、咬まれた場合にその強い毒性から全身症状に苦しめられる場合があります。
(3)農林水産業への悪影響
外来種がその地域にある農作物を食べたり、畑を踏み荒らしたりするなど直接的な影響がある可能性があります。
例えば、東京都では特定外来生物「アライグマ」などが原因で農作物に被害が出た、という都民の相談が近年で増加しています。
被害はスイカなどの農作物だけではなく、生態系や住居などの生活環境にも及んでいます。
参考:外来生物が及ぼす被害|東京都環境局「気をつけて!危険な外来生物」
4、海外起源の外来種はどのようにして日本にやって来たのか
日本に存在する海外起源の生物は、わかっているだけでも約2000種あります。
明治以降、人間の移動や物流が活発になったことで、多くの動物や植物が輸入されるようになりました。展示用、飼育用、食用、研究用など目的は様々です。
一方で、貨物や乗り物に紛れ込んだり、付着したりして意図せず海外から持ち込まれてしまったものもあります。
農作物や家畜、ペットなども含むので、今の私たちの生活に欠かせない外来種も多くあります。
5、日本の取り組み

(1)外来生物法
「外来生物法」は正確には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」です。
特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的として制定され、2005年に施行されました。
生物の多様性を守り、人の生命・身体を保護し、農林水産業の健全な発展に寄与することで、国民生活の安定・向上を目指しています。
問題を引き起こす海外起源の外来生物を「特定外来生物」として定義し、具体的な個体名を指定しています。
特定外来生物に指定された生物は、飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取り扱いにおいて規制がかけられています。法律で規制することで、特定外来生物の防除を行っているのです。
参考:どんな法律なの? | 日本の外来種対策 | 外来生物法
(2)「外来種被害予防三原則」の周知
外来種による被害を予防するために重要なことは3つあります。
- 入れない(悪影響を及ぼすおそれがある外来種を「入れない」)
- 捨てない(飼養・栽培する外来種は適切に管理して「捨てない」)
- 拡げない(既にいる外来種を他の地域に「拡げない」)
外来生物法では上記を「外来種被害予防三原則」として掲げ、国民への周知活動を行っています。
また、登山者の増加に伴う外来植物の分布拡大対策でも、この予防三原則が取り入れられています。
具体的には、以下のような取り組みを行っています。
- 外来植物の防除を目的にした事業の導入
- 生態系に悪影響を及ぼす可能性がある外来植物の除去
- 外来植物種子除去マットの設置
外来種は「人間が持ち込む」という特徴から、生活と密接に関わりを持つことが多いです。だからこそ、国民一人一人の理解と適切な対応が重要であり、三原則は日頃から意識すべき原則と言えるでしょう。
(3)「自然公園法」などの活用
自然公園法など既存の法令を活用し規制の強化をしています。
- 自然公園法および自然環境保全法の改正(「生物の多様性の確保」を目的規定に追加)
- 海域における保全施策の充実(海域公園地区制度や海域における利用調整地区制度の創設)
- 生態系維持回復事業の創設
- 特別地域などにおける動植物の放出などに関わる規制の強化
- 地方公共団体の条例による国内由来の外来種などの規制
参考:8 国内由来の外来種対策の現状と課題(1) 8 国内由来の外来種対策の現状と課題(2)
6、世界の取り組み

(1)生物多様性条約
国際社会において、外来種問題はすでに10年以上前から深刻な環境問題として認識されています。
1993年には、世界の環境保全を目的とした国際条約「生物多様性条約」が発効されました。第8条において、外来種の侵入防止・駆除などの対策の必要性が明記されています。
生物多様性条約では、批准国に「生物多様性国家戦略」の作成が義務づけられています。外来種問題に対する姿勢と方針を打ち出すだけではなく、具体的な政策の実施まで行わなければなりません。
日本も締結国で、1995年に最初の「生物多様性国家戦略」を策定しました。第六次戦略「生物多様性国家戦略2023-2030」が最新版となっています(2023年現在)。
参考:環境省
(2)レッドリスト
1948年に設立されたIUCN(国際自然保護連合)は”自然を尊び、保全する公正な世界”を目指す、国際的な自然保護ネットワークです。
自然が持つ本来の姿とその多様性を保護しながら、自然資源の公正かつ持続可能な利用を確保することを目的に活動しています。
約1200の政府、機関、非政府組織組織(200を超える政府・機関、900を超える非政府機関)で構成されています。国際的には、このIUCNは「レッドリスト=絶滅のおそれがある野生生物の種のリスト」を作成しています。
2000年には「外来侵入種によって引き起こされる生物多様性減少防止のためのIUCNガイドライン」を採択しました。
また、「世界の侵略的外来種ワースト100」の発表を行うなど、世界中で深刻な問題を引き起こす侵入種をリストアップすることによる問題提起も行っています。
PoliPoliで公開されている環境関連の取り組み
誰でも政策に意見を届けることができる、政策共創プラットフォーム『PoliPoli』では、再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策について、以下のような政策が掲載されています。
あなたの願いや意見が政策に反映されるかもしれないので、是非下記のリンクからコメントしてみてください。
PoliPoli|再エネで地域も経済も活性化する気候危機対策!
(1)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策提案者
| 議員名 | 田嶋 要 |
| 政党 | 衆議院議員・立憲民主党 |
| プロフィール | https://polipoli-web.com/politicians/JskZ6HJLEgwWJZkKTVZN/policies |
(2)再エネで地域も経済も活性化する気候危機政策の政策目標
- 再エネを中心とした分散型エネルギーシステムに移行し、そのプロセスを促進するグリーンリカバリーによる投資と海外に支払っていた燃料費を国内で循環させることにより、脱炭素社会の実現と経済・社会の活性化を両立させます。
(3)実現への取り組み
実現への取り組みは以下の通りです。
- 分散型エネルギー社会を実現するための基本法をはじめとした環境整備を行い、エネルギーの地産地消や原発依存からの脱却、エネルギー転換の過程で起こる雇用の公正な移行を実現します!
この政策の詳細をより知りたい方や、政策の進捗を確認したい方は下記リンクからご確認ください。
まとめ
今回は特定外来生物について詳しくご紹介しました。
特定外来生物と外来種の概要に加えて、特定外来生物と外来種が及ぼす悪影響や、日本と世界の外来生物対策についてもおわかりいただけたのではないでしょうか。
人間の活動が原因で持ち込まれた外来種が、自然環境や私たちの暮らしを脅かす可能性があることを、恐ろしく感じた方もいらっしゃるでしょう。生活と密接に関わる分野だからこそ、正しい知識を得て必要な行動を取りたいものです。
本記事が少しでもあなたのお役に立てば幸いです。