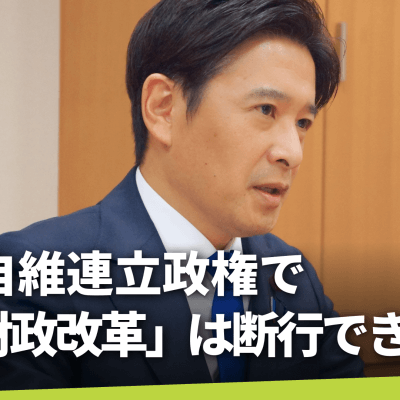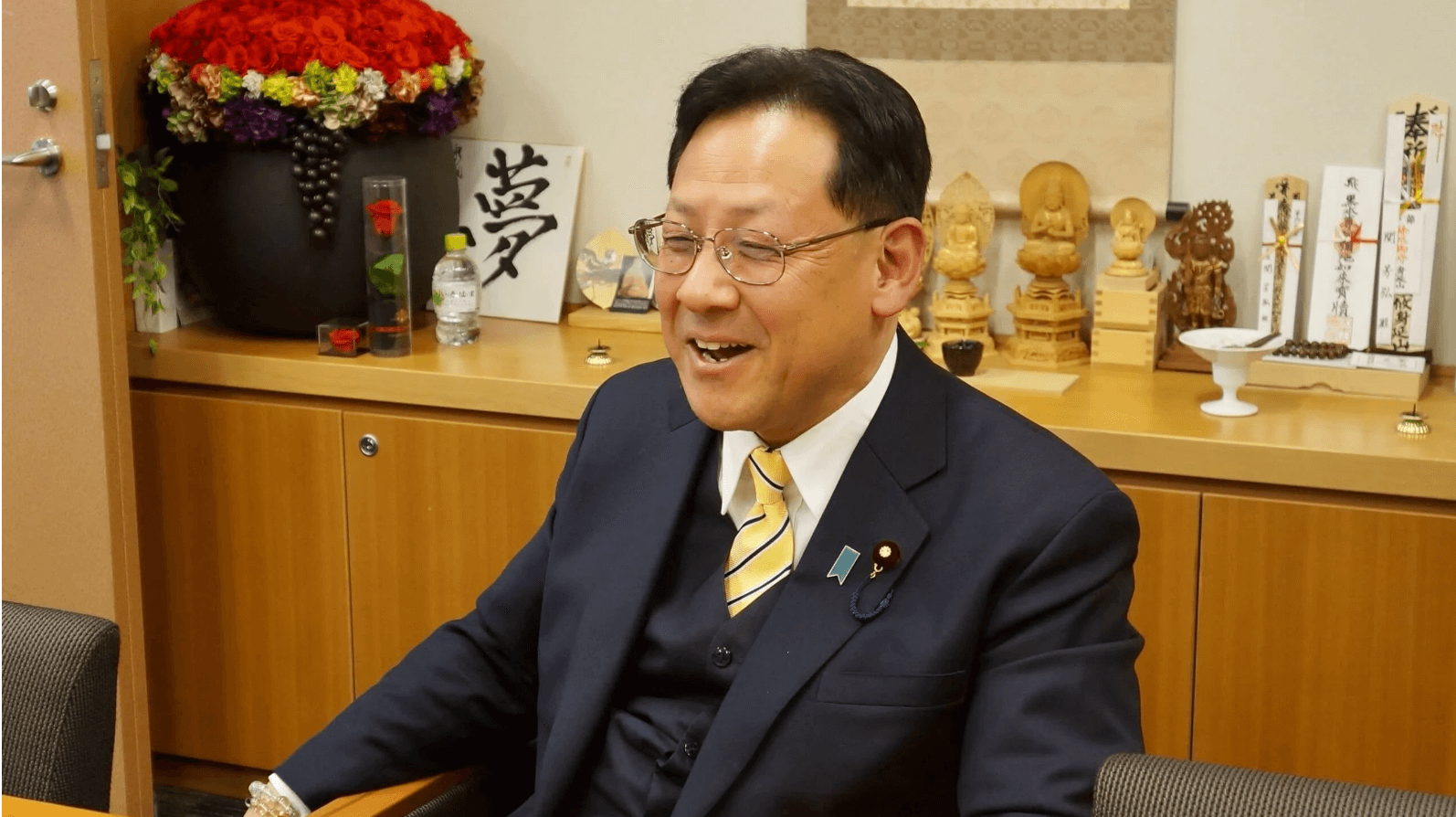
関芳弘 せき よしひろ 議員
1965年徳島県出身。関西学院大学在学中に松下政経塾に合格内定するも、住友銀行(現・三井住友銀行)に就職。
2005年の衆議院議員選挙で初当選(6期)。
自民党副幹事長、経済産業副大臣、環境副大臣などを歴任し、
2024年に党広報戦略局長に就任。
趣味はスポーツ全般、囲碁・将棋・読書・生き物観察。
かつて世界トップに君臨していた日本の国際競争力は「失われた30年」の間に大きく減退。半導体製造やAI開発でも海外に主導権を握られ、「技術の国・日本」の復権は国全体の課題となっています。
今回のインタビューでは、銀行から政治の世界へフィールドを移し、経済産業副大臣などを歴任してきた関芳弘議員に、半導体産業を中心とした日本の産業技術力の再興に向けたビジョンについて聞きました。
(取材日:2025年2月26日)
(文責:株式会社PoliPoli 井出光 )
「仕事は人のためにするもの」父の言葉を胸に銀行員から政治家へ
ー関議員が政治家を志したきっかけは何だったのでしょうか。
私は徳島県の小松島市という港町で育ち、父は魚市場に勤めていました。毎朝2時に起き神棚と仏壇を拝み、3時には家を出てオートバイで1時間かけて出勤するという生活。水を扱うので、冬には手や足があかぎれだらけでしたが、体調を崩して熱を出しても仕事を休まないような人でした。
その父から子どもの頃から言われていたのは「仕事というのは人のためにするものだ」という言葉です。この言葉はずっと頭に残っていました。
大学生になり、就職活動の時期を迎え「なんの仕事をしようか」と悩んだときに、「人のために一生懸命生きる仕事がしたい」という思いが漠然とありました。「政治家になって、困っている人を助ける法律を作ったり、相談に乗ったりするような仕事が自分に向いているのでは」と考えるようになったのです。
友人の父親が後藤田正晴 元官房長官の後援会会長だったり、大物議員の秘書の方が知り合いだったり、姉がウグイス嬢をやっていたりと、元々政治の世界は身近なものではあったんですよね。その中で、政治家になるためにはどうしたらいいか、と調べていたら、当時松下幸之助さんが立ち上げた松下政経塾のニュースを目にしました。これだ、と思い入塾試験を受験したところ、高い倍率をくぐり抜けて、受かることができました。

ところが、合格の報告を家族にしたところ、父親が入塾に猛反対しましてね。
「世間の人が、毎日毎日朝から晩まで汗を流し働いている中で、その人の汗や涙や心とか苦しみが理解できるようになったら、政治家でもなんでも勝手にやったらええわ」「ただ、その経験もしない学生の分際で政治家になるなんて」と。
反対されたことには驚きましたが、その通りだ、と腹に落ちました。松下政経塾に行って「せっかく合格をいただきましたが辞退します」とお伝えし、当時の住友銀行(現 三井住友銀行)に入社したのです。
ー銀行には16年勤められましたが、印象に残っていることはありますか。
提案型の営業の面白さを学びました。法人営業で年間約5000億円の企業売上金の新規入金獲得を達成するなど、実績も積むことができました。
顧客である企業から頼まれたことだけに応えるのではなく、自分も一員として「どうしたら売れるか」を一緒に悩み、売上に貢献できる提案をすれば、新たな融資の依頼や口座開設につながります。それができるのも銀行の仕事の醍醐味でした。
また、さくら銀行との合併にグループ長として関わった際には、急ピッチで業務を進めなければならない中でいかにチームワークを効率的に発揮させるか、ということを実践しました。機能する組織の作り方や、仕事に全力を注ぐ気概など、すべてが今につながっています。
ー銀行員として活躍されていた中、政治家への転身を決めた理由は何ですか。
ひととおり経済の動かし方や組織づくり、人付き合いなどについて経験を積み、40歳という人生の節目を迎えたとき、昔から志していた政治家を再び目指そうと決意しました。
ちょうどその頃、自民党で党改革実行本部長を務めていた安倍晋三さんが候補者の公募制度を新設したこともあって、チャレンジする決心がつきました。
当時は小泉政権下で、郵政民営化をめぐる議論が紛糾していた時期でした。そんな最中での公募だったため、応募から半年ほど音沙汰なく「落ちたんだろうな」と諦めかけていました。
ところが、2005年8月、小泉総理が「郵政解散」(衆議院解散)を断行した直後、突然「選挙に出ますか」と電話が舞い込んできたのです。急遽、兵庫3区からの出馬が決まりました。投票日はわずか1ヶ月後に迫っていて、しかも一人も知り合いのいない選挙区での挑戦となったのです。

務めていた銀行の副頭取からは「それは希望ではなく無謀だ」と言われ、「絶対に今回の当選は無理だろうから、次の4年を見据えて経験を積んできなさい」と送り出されました。3日で業務の引き継ぎを済ませ銀行を退職。兵庫へ向かう新幹線のホームには30人ほどの同僚がかけつけてくれました。「片道切符万歳!」と送り出してくれましたね(笑)。
右も左もわからないまま選挙戦を走り抜け、小泉総理の改革の力もあって与党が圧勝しました。私自身も選挙終盤の2週間で支持率が急に伸び、思いがけず当選を果たしました。まさに「100年に1回の風にたまたま乗れた」という感覚でした。
日本の産業技術力を再び世界一に戻すエコシステムづくり
ー政治家になって、特に注目されてきた分野は何でしょうか。
大きな目標としては、やはり昔から父に言われてきた「人助け」をすることでした。その上で、銀行勤務の経験を活かし、経済の分野で貢献したい考えてきました。細かい政策は多岐に渡りますが、私の政治活動の核心には「日本の経済を強くしたい」という強い思いがあります。
その中でも特に重要視しているのが産業技術力です。ヨーロッパの機関が発表している国際競争力ランキングでは、1990年代には1位だった日本が、現在は30番台まで転落しています。この地位を再び1位に返り咲かせることが、政治家としての私の夢です。
ー特に半導体関連の政策を推進されていますね。
そうですね。日本の競争力を再び押し上げるために必要なのは、やはり技術力を徹底的に鍛えること、そしてその優位性を長期的に維持することです。
現在のグローバルビジネスにおける「チョークポイント(choke point:ここが断たれるとサプライチェーンの流れが止まるという急所のこと)」がまさに半導体であり、日本が再び世界的な優位性を確立できる分野だと確信しています。

ただ、国会議員は日々さまざまな会議や面談に追われ、専門分野を深く学ぶ時間の確保が難しいのも実情です。私は幸いにも、銀行時代にホストコンピューターの刷新を担当したことがあり、そこで培った知識が今の半導体関連政策の立案に大いに役立っています。
現在、自民党の中小企業・小規模事業者調査会で幹事長を務めていますが、2月も半導体製造工場のサプライチェーンに日本の中小企業を効果的に組み込むための戦略について議論を重ねました。「熊本のTSMCは3兆円規模、北海道のラピダスは5兆円規模の投資だ」という議論をする前に、半導体製造の各工程を理解することが必要です。製造プロセスを理解しなければ、中小企業にどのような支援体制が必要なのか具体的な道筋が見えてきませんからね。
ー半導体で日本が主導権を握るために必要な視点は何でしょうか。
好例として、半導体製造に欠かせない「露光装置(ステッパー:半導体回路を焼き付ける装置)」を世界で唯一製造できるオランダのASMLというメーカーがあります。彼らは30年かけて何千社ものサプライヤーを集め、巧みに組織化してエコシステムを築き、現在の地位を確立したのです。
私たちも、半導体製造工程のどこか1つでもいいから「日本の技術なしでは半導体が作れない」という強みを持つべきです。そのための包括的なエコシステムの構築が急務です。これは単なる産業政策ではなく、国家の経済安全保障を確保する上で不可欠な要素だと考えています。
「世の中を変える」という気概を持って仕事に夢を託す

ー日本が再び国力を高めていくために必要な心がまえを教えてください。
半導体産業に限らず、あらゆる分野において「新しい技術を創造するんだ」「世の中を変えることに挑戦するんだ」という志を、政治家や官僚、大企業だけでなく社会全体で持つことが大切です。
国を前に進めるのは、この記事を読んでいる一人ひとりです。「私自身が社会をより良くしていくんだ」という気概を持ってほしいのです。
若い頃に読み入った司馬遼太郎さんの名著「竜馬がゆく」の中で、坂本龍馬は混迷する時代を見据え「自らが変革を起こしてやる、この国を前に進めていく」と決意します。まさにこのような気概こそが、今の日本に求められているのではないでしょうか。
ー会社の規模や分野に関係なく、それぞれが持つ力を最大限に高めていくことが大切なのですね。
その通りです。小さな町工場でも、実は世界No.1の精密技術を誇る企業が日本には数多く存在します。大企業であれ中小企業であれ、自分たちの仕事に誇りと夢を託して、「この業界でトップを目指すんだ」くらいの志を持てば、組織全体、社会全体も元気になりますよね。
必ずしも巨大な市場を狙う必要はありません。ニッチな領域でもいいのです。そこで最高峰を目指し、チーム一丸となって挑戦する。そうすれば、毎日の仕事もエキサイトして充実したものになるはずです。それが技術立国・日本の復活への第一歩になると信じています。