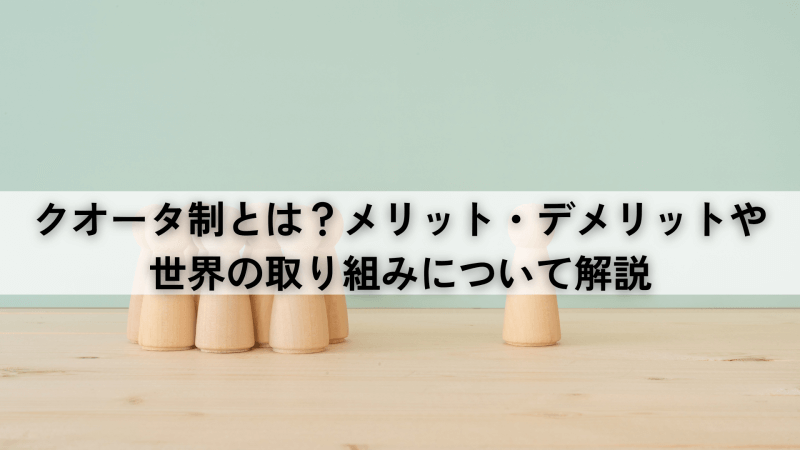プログラム規定説とは、憲法によって人権が保障されている事柄に関して、それがあくまで国の指針や努力義務でしかないとする考え方のことです。
しかしこれだけではまだイメージがつかないと思われます。
憲法第25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とあります。
では国民が国に対し「我々が健康で文化的な最低限度の生活を営むための施策(減税など)を実施して下さい」という具体的訴訟(裁判のこと)を起こせるのかというと、判例(過去の裁判例)ではそうではありません。
憲法25条をめぐる判例では、国民が国に対し人々が健康で文化的な最低限度の生活を営めるよう「努力することを求められる権利」はあるが、具体的な措置を行うように「訴訟を起こして要求できる権利」ではない(法的権利性が無い)という判決が過去に出されています。
これが憲法25条におけるプログラム規定説です。
しかしこれだけでもまだわかりづらいですね。
そこで本記事では
- プログラム規定説の必要性
- 法的権利性
- 統治行為論との違い
- プログラム規定説に関する判例
以上のことについてご紹介していきます。
本記事がお役に立てば幸いです。
社会権について詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

社会権とは?4つの権利を判例・学説と共にわかりやすく解説
1、プログラム規定説とは?なぜ必要なのか

これは当然のことですが、憲法に書かれたすべての権利について国民が訴訟を起こせるようになってしまったら、社会は混乱してしまいます。
前述でも取り扱いました通り「私たちが健康で文化的な生活ができていない!」という主張の下、訴訟が幾つも起きてしまうような状況には問題があると言えますね。
政策実行のために作った法律が「この法律があることで文化的な最低限度の生活が侵害される」という国民の訴訟提起によって違憲とされ無効になっていては、国政が停滞し、それは回り回って国民にも悪影響が出かねません。
具体的には、国の行う公共事業(災害対策やインフラ整備)が行われなくなるといったことが考えられます。
そこでプログラム規定を導入して、国の負担を減らすようにしたのです。
日本国憲法では第25条(生存権)と第29条(財産権)がプログラム規定に関わります。
(1)日本国憲法第25条のプログラム規定
憲法第25条の全文は次のとおりです。
第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない
引用:日本国憲法
ここに書かれてある権利のことを「生存権」といいます。
憲法第25条は、国民に裁判で請求できる具体的権利を与えているわけではない、と解されています。
ただし国は、生存権を立法によって具体化する義務を負っています。
例えば生活保護法は、国がその義務を具現化したものであり、生活保護法第1条には次のように書かれてあります。
「生活保護法第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」
引用:生活保護法
憲法第25条がプログラム規定であることは、学説(大学法学部の教授らの説)でも有力とされ、判例でも憲法第25条がプログラム規定であることがほぼ確定しています。
判例については「4、プログラム規定説に関する判例」で紹介します。
生存権については以下の関連記事でも詳しく解説しています。
(2)日本国憲法第29条のプログラム規定
憲法第29条の全文は次のとおりです。
第1項 財産権は、これを侵してはならない
第2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める
第3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる
引用:日本国憲法
憲法29条とプログラム規定説で問題になるのは、第3項です。
第3項を額面通り受け取ると、私有財産が公共のために用いられた場合、「国などから」「金銭的な」補償が受けられる、となるでしょう。
しかし、第3項はプログラム規定である、という学説があります。
そうなると、公共のために私有財産が用いられた人は、裁判で憲法29条を根拠として、その「金銭的な」補償を請求することができなくなります。
それでは、公共のために私有財産が用いられた人の損害が大きくなることから、「憲法第29条第3項にプログラム規定説を適用することは適当でない」という学説もあります。
2、法的権利性|抽象的権利説と具体的権利説

憲法第25条(生存権)については「法的権利性」も問題になります。
法的権利性とは、「法」を根拠として「権利」を主張できるということです。
また法的権利性は、抽象的権利と具体的権利の2つがあり、その違いには「裁判規範性」の有無があります。
裁判規範性が無いものを根拠に訴えを起こすことはできません。
憲法第25条においては「抽象的権利しかない」とする説と「具体的権利がある」とする説があり、学説では、憲法第25条については抽象的権利説が有力です。
2つの説について見ていきましょう。
(1)抽象的権利説
抽象的権利説とは、それ自体では裁判規範性を有していない(訴えを提起できない)という考え方です。
もし憲法第25条が抽象的権利であれば、国民は「憲法第25条があるから」という理由で訴訟を起こすことはできません。
ただ、憲法第25条があるので、国は生存権に関する法律をつくらなければなりません。
こうした法律が作られれば、国民はその法律を根拠にして訴訟を起こすことができます。
抽象的権利説では、具体的な法律(生活保護法など)ができて初めて裁判規範性が生まれるのです。
(2)具体的権利説
具体的権利説とは、それ自体が裁判規範性を持っているという考え方です。
これによると、国民は「憲法25条があるから」という理由で訴訟を起こすことができます。
国が生存権に関わる法律をつくらなくても、憲法第25条を根拠に提訴できます。
ただ学説では、憲法第25条に具体的権利があるとする説は有力ではありません。
3、統治行為論との違い

プログラム規定説は、統治行為論との対比で論じられることがあります。
統治行為論とは、国家統治に関する高度な政治性を有する国家の行為については、裁判所による司法審査の対象にならない、という考え方です。
例えば、外交問題について裁判所が司法審査を行って、それで大きな損害が生じたとします。
こういった場合、日本の裁判所は責任を負うことができません。
外交問題は、高度な政治性を有する国家の行為に関することなので、国民によって選挙で選ばれた人など(政治家など)が対処すべきです。
つまり、外交問題は統治行為論に当てはまります。
「裁判所で争えない」という点で、「プログラム規定説」と「統治行為論」は似ていますが、両者は次の点で大きく異なります。
- プログラム規定説は「国民の権利」と「訴訟」の関係について定めている
- 統治行為論は「国家統治」や「政治」に焦点を当てている
- 統治行為論は、裁判所が違憲審査を回避するために用いることが多い
違憲審査とは、裁判所が憲法に違反するかどうか審査することです。
4、プログラム規定説に関する判例

憲法第25条のプログラム規定説に関する判例として「朝日訴訟」、「食糧管理法違反事件」、「堀木訴訟」を紹介します。
(1)朝日訴訟
朝日訴訟は、原告(訴えを提起した人)が厚生大臣(現、厚生労働大臣)を相手取り、憲法第25条(生存権)などの内容について争った行政訴訟です。
原告は当時、月600円の生活保護(生活扶助と医療扶助)を受けていました。
その後、原告の兄が原告に月1500円の仕送りをしたことから、市は原告に「1500円のうち、600円は原告が受け取り、残り900円は医療費として、原告が入居していた療養所に納めよ」と命じました。
原告は訴訟の中で月600円では、憲法第25条で定める「健康で文化的な最低限度の生活」を送ることができないため、「月600円の生活保護」は憲法違反である、と主張しました。
地裁は原告が勝訴しましたが、高裁は原告の請求を棄却しました(原告敗訴)。
最高裁判決が出る前に原告が亡くなってしまったことから訴訟は終了し、決着はつきませんでした。
ただこのとき最高裁は「念のため」として、憲法第25条の生存権は「直接個々の国民に具体的な権利を与えたものではない」としました。
つまり、憲法第25条を根拠に訴訟を起こすことはできない、としたのです。
最高裁のこの「念のため」の見解は、プログラム規定説のリーディングケースと呼ばれている「食糧管理法違反事件」での判断を基にしています。
参考:裁判例結果詳細 生活保護法による保護に関する不服の申立に対する裁決取消請求
(2)食糧管理法違反事件
食糧管理法違反事件では、同法に違反して「やみ米」を購入、運搬して起訴された被告が、次のように主張しました。
当時、米は国が管理して配給していました。その配給以外で手に入る米のことを「やみ米」と呼んでいました。
- 配給米だけでは、健康で文化的な最低限度の生活は送ることができない
- したがって、やみ米の購入、運搬は、憲法第25条で保障された生存権の行使である
- それを禁じた食糧管理法は違憲である
被告は以上のように訴えていましたが、これに対し最高裁は被告の上告を棄却しました(被告敗訴)。
その際の根拠も憲法第25条は「個々の国民に権利を付与しているわけではない」とするものでした。
(3)堀木訴訟
堀木訴訟の原告は、視力障害を持った女性でした。
原告は障害福祉年金を受給していて、離婚後に子供を養育することになったことで、知事に児童扶養手当の給付を請求しました。
しかし、当時の法律では、障害福祉年金と児童扶養手当の併給(一緒に受け取ること)は禁止されていたため、知事はこの請求を退け、原告はこの処分を不服として提訴しました。
地裁では、原告が勝訴しました。
地裁は憲法第25条第2項を根拠に、社会保障施策において差別的な取り扱いをしてはならない、としました。
しかし高裁は原告を敗訴としました。理由としては、「社会保障施策は立法の裁量が認められる」というものをあげました。
最高裁は高裁判決を支持し、原告の敗訴が確定しました。
その根拠は「憲法第25条はプログラム規定である」とする内容でした。
プログラム規定説に関するQ&A

Q1.プログラム規定説の意味は?
プログラム規定説とは、憲法によって人権が保障されている事柄に関して、それがあくまで国の指針や努力義務でしかないとする考え方のことです。
Q2.プログラム規定にかかわる憲法は?
日本国憲法では第25条(生存権)と第29条(財産権)がプログラム規定に関わります。
Q3.プログラム規定説はなぜ必要?
憲法に書かれたすべての権利について国民が訴訟を起こせるようになってしまうことを防ぐためです。
まとめ

プログラム規定説は理解しづらい内容といえるでしょう。
憲法第25条には、生存権が明記されており、その権利が国民のものであることは明らかなのに、その権利を根拠に訴訟を起こせないのは不可解だ、という風に考える人も少なくないからです。
しかし、もしプログラム規定説がなければ、訴訟が乱立してしまいます。
政治的な観点からすると、プログラム規定説には高い合理性があるといえそうです。
公共の福祉に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

公共の福祉とは?人権が制限されるパターンと憲法との関係を簡単に解説