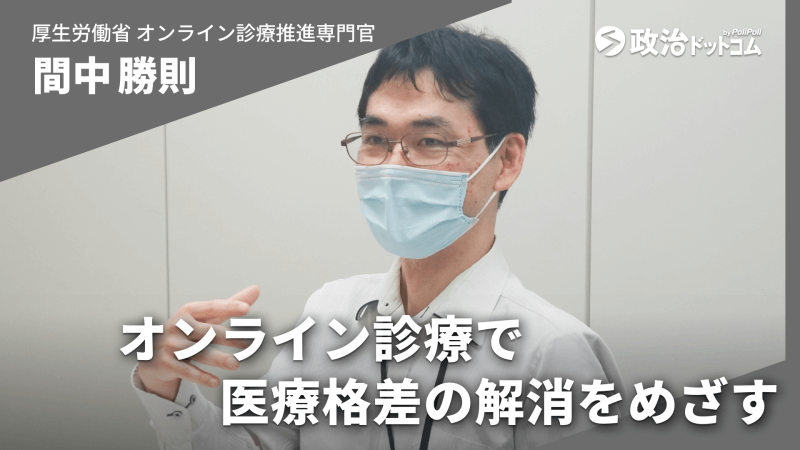田中昌史 たなか まさし 議員
1965年、北海道札幌市生まれ。
清恵会第二医療専門学院を卒業し、理学療法士の資格を取得。
病院、日本理学療法士協会活動を経て、2012年日本理学療法士連盟の会長に就任。
2023年より参議院議員(1期)
世界各地で保健医療体制の脆弱さが顕在化するなか、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)の達成に向けた日本の役割が、あらためて注目されています。
今回のインタビューでは、理学療法士の職能団体・政治連盟で長年政策支援に尽力され、UHCを支えるリハビリテーションと地域包括ケアシステムの推進に積極的に取り組んでこられた田中昌史議員に、超高齢社会をリードする日本が直面する課題と、持続可能な社会の構築に向けた政治家としての展望や、今後注力したい政策についてお話を伺いました。
(取材日:2025年5月27日)
(文責:株式会社PoliPoli 児島花生里 )
現場の疲弊を救い、地域での生活を支える
ーまず、立候補されるまでには職能団体と政治連盟の両輪で長年ご活躍されてきました。ご自身が国会議員に立候補されたとき、どのような思いがあったのでしょうか。
立候補の動機は二つです。第一に、医療・介護従事者の処遇改善です。求人倍率は30倍、40倍と高止まりなのに、医療・介護従事者の賃金は30年間ほとんど上がっていません。
さらに、公定価格なので、経験1年目でも30年目でも請求できる金額は変わらない。経営者は、従業員の給料を上げたくても上げられないんです。これでは若い医療・介護従事者が安心してキャリアを築けず、現場が疲弊する一方です。社会保障の根幹を担う専門職が将来に希望を持てる制度を整えなければ、医療・介護そのものが立ちゆかなくなる――その思いが私を政治に駆り立てました。
第二に、「施設から地域」へという大転換です。30~40年前、私たち医療職は病院内で患者のケアを完結する働き方が当たり前でした。しかし本来のゴールは、自宅や地域で本人が自分らしく暮らせることなんです。
理学療法士として参加した学会シンポジウムで、都議会議員や地域住民代表から「どうか地域に来て、現場を見てください」と強く求められた瞬間、施設中心の仕組みを変えねばという思いが決定的になりました。専門職が生活の現場に赴き、在宅や地域社会で力を発揮できる法制度を形にする。現場第一で培った経験を、国の制度に反映させる使命を感じて立候補しました。

ー「地域包括ケアシステム」を推進するなかで、「政治家でしかできないこと」とはどんなことだとお考えになったのでしょうか。
医療・介護には多様なステークホルダーがいます。専門性を極めること自体は素晴らしいのですが、専門領域に閉じこもると「一人の生活をトータルに支える」という視点が抜け落ちる恐れがあります。そこで政治家の出番です。
制度設計の土台で「医療・介護福祉の本質は何か」を明確に打ち出し、皆が同じコンパスで進めるよう合意をつくる。制度が「ここがゴールだ」とはっきり示さないと、現場は個別最適の積み重ねになり、最終的な目標を見失いがちです。だから私は、法制度の前段階で徹底的に議論し、「生活の回復」という共通目標を共有するプロセスを重視しています。
ー多くの難しい調整を行うなかで「ここだけは外せない」という理念はありますか。
当事者が希望を持てるか――これを外すわけにはいきません。支援を受ける人も支える人も、どんな思いで、どんな未来をみて、お互いに支え、支えられるのかということが大事です。みんなが「ありがたい、明日も頑張ろう」と思える仕組みでなければ政策に意味はない。形だけの制度ではなく、現場で「支える力」が本当に笑顔になっているかどうかを確認し、必要なら制度を躊躇なく修正する。それが私の揺るがぬ軸です。
日本の知見を世界のUHCへ — 超高齢社会の経験を羅針盤に
ー今年はUHCナレッジハブ設立やTICAD 9開催など国際保健が注目されています。日本のリハビリテーションを含めた医療がUHCにどう関係するのでしょうか。
日本は世界の先頭を走る超高齢社会です。介護保険制度や地域リハビリテーション体制はまだ課題も多いですが、先進国として最初に壁にぶつかり、試行錯誤しながら乗り越えてきた実績があります。たとえば新しい地域医療構想では、「できるだけ早くリハビリを提供し、在宅や地域へ戻る」仕組みが強調されました。障害克服や生活能力の回復を優先し、介護が要らなくなることを目指す――これこそUHCの理念です。
経済発展が進むアフリカやアジアでは、労働災害、生活習慣病、女性の健康問題が顕在化しつつあります。日本が経験してきた課題を、彼らはこれから正面から受け止める。日本の知見や制度設計は、こうした国々がUHCを実現するための羅針盤になります。
ー医療DXの国際展開で注目している点はありますか。
率直に言えば、日本の医療DXはまだ道半ばです。ただマイナ保険証の普及で、診療・投薬情報を本人がポータルサイトで把握できる基盤は整いつつあります。将来的にはAIが組み合わさり、セルフメディケーションを後押しする仕組みが構築されるでしょう。
日本は皆保険の手厚さゆえに「自分の健康は自分で守る」という文化が定着しづらい面がありますが、諸外国では最初から自己管理が前提です。DXを使ってセルフメディケーションを促進するモデルは、むしろ海外のほうが受け入れられやすいようにも感じています。
日本が培ったシステムを輸出し、海外で磨き直し、セルフメディケーションなど「自分の健康は自分で作っていく」という風土を逆に日本も取り入れていくという流れを作れるとよいと思っています。
ーリハビリ関連の機器や医療へのデジタル技術の導入で、いま注目している動きはありますか?
東南アジアでは、診察室から検査環境までを一体化した医療コンテナを活用したモバイルクリニックも登場しています。日本企業も医療関係機器を供給していますが、現状は情報が散在し、患者さんや利用する側の方にとっては「どの機器が自分に最適か」が分かりにくい状態となっています。
各社がそれぞれ支店や代理店を構えても、利用者が得るのは断片的なカタログ情報にとどまり、現地ニーズを十分に満たせません。私は産学官連携の横断団体を整え、機器・教育・評価をパッケージで提供する仕組みを政治の力で後押ししたいと考えています。
具体的には、リハビリテーションや医療関連機器、生活支援機器などを扱う事業者が結集し、統一プラットフォームを通じて機器仕様・適応疾患・導入コストを一括提示する。現地には教育拠点を設け、障害の種類や生活状態から「どの機器が適用になるか」を即時判断できる評価判断力を育成する研修なども必要かもしれません。これにより利用者は一か所で包括的情報を得られ、企業側も重複投資を避けながら市場を拡大できるようになります。
国内にも「日本理学療法機器工業会」のような団体がありますが、個々のプレイヤーが経済産業省へ独自に陳情するだけではスケール感に乏しい。業界がまとまって国際展開の共通フレームを示し、政府が規格・補助・外交ルートでバックアップすることで、医療関係機器のワンストップ輸出モデルを確立できると確信しています。
ー日本で持続的な介護、福祉を実現するうえで、いちばん重要だと思うのは何ですか?
私は何事にも「リハビリテーション」の視点が重要だと思っています。
能登半島の生活復興も、刑務所からの社会復帰も、介護現場の支援も本質は同じ――一人ひとりの可能性を最大限に引き出すプロセスです。医療だけにとどまらず、誰もが自分の最良の状態へ到達できる仕組みを整えることが、持続可能な介護・福祉を築く第一歩だと考えます。
人材不足を語る前に、まず「悪くしない」ことが重要です。病気にならない、障害を重度化させない、予防の観点から地域の介護予防や保健活動を強化し、DXを活用してセルフマネジメントを後押しする土壌をつくる。
次に、もし発症・受傷しても速やかに回復へ導く。ここでリハビリテーション専門職を積極的に投入し、軽度の要支援・要介護者を生活自立へ戻す。状態が改善すれば介護は不要になり、限られた介護士リソースを中重度の要介護者へ振り向けられるようになります。
最後に、障害が残る方々へ尊厳のある暮らしを保障する。健康維持と生活支援の質を高め、最終段階まで自律と尊厳を保てる環境を整えることが不可欠です。ところが現行制度では、本人の状態や可能性を適切に把握し、その人に合ったサービスを提供できているか疑問が残ります。たとえば、手動車椅子で20メートル漕げる方に「もっと訓練して100メートルを目指そう」と長年リハビリを続けるより、電動車椅子で買い物に行き、自分で調理して食べる方が運動量も生活満足度も高いことを科学的データも示しています。
本人の体力・生活背景・社会参加を総合的に評価し、支援機器や自助具を柔軟に導入する発想が欠かせません。目的は「歩かせること」ではなく「生きたいように生きる力」を取り戻すことだからです。
こうした判断を現場で支えるには、専門家・家族・当事者が対話し、地域全体で支える環境づくりが重要です。本来できることが制度上の壁で封じられ、生活範囲が狭められている人を一人でも減らしたい。電動車椅子や自動車を使って行きたい場所へ行き、働きたい人が働ける――そうした「希望を持って暮らせる仕組み」が当たり前になる社会を目指します。
要するに、人材不足を量の議論だけで終わらせず、「予防・回復・尊厳」の三層で専門職の力を最適配置し、支援機器も含めた最良の組み合わせを追求することが、介護・福祉を持続させる鍵だと確信しています。
「当たり前のことを当たり前にできる社会」を目指して
ー最後に、読者へのメッセージをお願いします
私は「当たり前のことを当たり前にできる社会」をつくりたい。身体的・社会的・経済的な制限に縛られず、自分らしく地域で暮らせること。このことを実現するために、土台となる健康を守りたい。
子どもの頃から健康教育とセルフメディケーションを徹底し、病気や障害があっても安心して支え合える制度を整える。そして支える側──医療・介護・福祉の現場で働く人たち──が笑顔で働ける環境と公正な評価を保証しなければ、支え合いは長続きしません。
日本人には「お互いさま」の文化があります。国民負担率が48%に迫り、物価も上がるなかで、「もう支えきれない」と感じる人が増えている。しかし誰もがいつか支えられる側になる。だからこそ、働く人が希望を持ち、安心して暮らせる経済基盤を築き、「支える力を笑顔に」できる社会を実現したい。
島国である日本が持つ連帯の強さを次世代に引き継ぎ、誰もが「明日は我が身」と互いを尊重し合える国をつくる――そのために、これからも現場第一で政策に取り組み続けていきます。