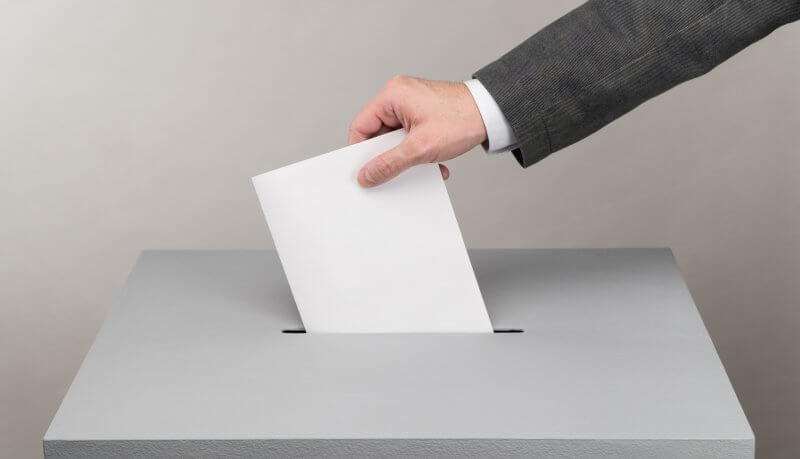石破首相は2025年4月、公立高校受験における「単願制」の見直しに向け、関係省庁に検討を指示しました。受験生が複数校を志望順位付きで登録するなどの「デジタル併願制」を導入する方針ですが、その狙いはどのようなものなのでしょうか。導入の背景や現在検討されている制度について、詳しく解説します。
「デジタル併願制」とは
デジタル併願制とは、受験生が複数の公立高校を志望順位付きで出願し、共通試験(学力検査)や内申点などをもとに、デジタルシステムが自動で合格先を決める仕組みです。
・受験生は志望校を第1志望、第2志望…と順位をつけて提出
・共通試験を受ける(試験は1回のみ)
・試験結果+内申点などのデータをシステムが処理
・合格可能な学校の中から、最も志望順位が高い学校に自動で合格決定
デジタル併願制には、以下のようなメリットが挙げられます。
・複数の学校で別々に受験しなくてよい(受験回数が減る)
・難関校にも挑戦しやすくなる(すべり止めも同時に志望できるため)
・合否判定をシステムで一元管理でき、学校の負担が減る
・公立校受験のハードルが下がり、公立離れを防ぐ効果が期待される
デジタル併願制導入の背景には、私立高校の授業料実質無償化で私立人気が高まる中、公立高校の魅力を高めたいという背景があります。米ニューヨーク市の高校入試や、日本の保育所入園調整でも似た仕組みが使われており、1回の試験で複数校への合否がまとめて決まり、志望順に自動で割り振られることで、受験生の負担軽減と難関校受験へのハードルを下げることが狙いです。
政府は意欲ある自治体での試行実施を進め、全国展開を目指す方針です。
公立高離れ防止?受験生の現状
近年、日本では「公立高校離れ」が進行しており、私立高校への進学者が増加しています。この傾向の背景には、少子化による生徒数の減少や、私立高校の魅力向上、政府の授業料無償化政策などが影響しています。
受験生の現状
・多くの都道府県で、公立高校の受験は「単願制」(1校のみ受験可能)
・受験機会が限られ、難関校挑戦へのハードルに
公立高校の在学者数の減少
文部科学省の「令和5年度学校基本統計」によれば、2023年度の高等学校在学者数は約291万9千人で、前年度から約3万8千人減少しました。
この減少は、少子化に伴う15歳人口の減少が主な要因とされています。内閣府の資料によると、15歳人口は令和11年(2029年)には100万人を下回り、令和19年(2037年)には約78万人になると予測されています。
私立高校の魅力と進学者の増加
私立高校は、特色ある教育や設備の充実、進学実績の向上などにより、受験生や保護者からの支持を集めています。
また、政府の授業料無償化政策により、私立高校の経済的負担が軽減され、進学のハードルが下がったことも、私立高校への進学者増加の一因とされています。
参考:文部科学省 報道発表 、文部科学省_人口減少時代における高等学校就学者の 学習権保護の仕組みの構築
デジタル併願制の利点と課題
高校授業料無償化により私立高校の人気が高まる中、公立高校への進学を促し「公立離れ」を防ぐ狙いですが、石破首相が「単願制」見直しを指示した一方、阿部文科相は慎重姿勢を示しています。
政府の方針
・石破首相が「単願制」の見直しを指示
・成績・志望順位をもとに合格先を割り振る「デジタル併願制」導入を検討中
(共通試験+内申点などをシステムで一括判定)
阿部文科相は会見で、「デジタル化による受験生の利便性向上、教職員の負担軽減は必要」としながらも、「併願制にはメリットがある一方、生徒の多様な個性・能力が十分に評価できるか課題もある」と述べており、「自治体と意思疎通を図り、丁寧に導入を検討する」としています。
まとめ
阿部文科相の述べている通り、デジタルで合格先を割り振る方式は、人柄や得意分野など、「その生徒ならではの良さが十分に伝わらないこともあるかもしれない」という懸念もあるようです。
一人ひとりの良さがちゃんと見えるかどうかが、制度の導入にあたっての課題といえます。デジタル併願制度の導入にあたっては、受験生や保護者、学校現場の声に丁寧に耳を傾けながら、公平で柔軟な仕組みとして実現できるかが問われています。