常任理事国とは、国際連合の安全保障理事会において、恒久的に理事国である国(国連憲章が改正されない限り)を指します。
国連憲章では、
- アメリカ
- イギリス
- フランス
- ロシア
- 中国
の5か国が常任理事国として定められています。
日本は常任理事国ではありませんが、非常任理事国に選ばれる回数が多いため、安全保障理事会の活動自体には深く関わっています。
そこで今回は常任理事国について、以下のとおりご紹介します。
- 常任理事国の概要
- 安全保障理事会の概要
- 常任理事国が有する拒否権とは何か
- 国際連合安全保障理事会決議の事例
本記事がお役に立てば幸いです。
1、常任理事国とは
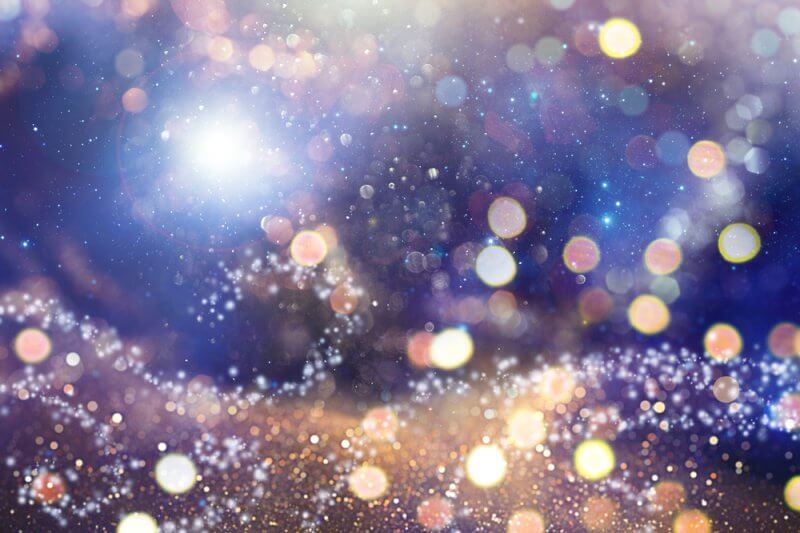
まずは常任理事国の概要についてご説明します。
すでにご説明した通り、常任理事国とは「国際連合」の「安全保障理事会」において、恒久的に理事国である国です(国連憲章が改正されない限り)。
国連憲章では常任理事国に関する定めがあり、
- アメリカ
- イギリス
- フランス
- ロシア
- 中国
の5か国が常任理事国となっています。
では、そもそも「国際連合」や「安全保障理事会」とは何なのでしょうか。
常任理事国の具体的な説明に入る前に、まずは両者の概要についてご説明します。
(1)そもそも国際連合とは
そもそも国際連合とは、平和維持(戦争防止)と社会の発展を目的として1945年に作られた世界的な機関です。
もともと、国際連合の前身となる機関に「国際連盟」があったのですが、国際連盟は結果的に失敗に終わりました。
国際連盟は第一次世界大戦後の1920年、史上初の国際平和機構として設立されましたが、1939年の第二次世界大戦開戦を防げなかったのです。
つまり国際連合は、国際連盟の失敗を糧にして設立された機関なのです。
「戦争の惨害」を終わらせるという強い決意のもとに、国際連合の活動指針となる国際憲章に定められた目的と原則を受け入れた国々が参加しています。
2021年4月時点では、193か国が国際連合に加盟しています。
(2)安全保障理事会とは
次に、国連にある組織「安全保障理事会」に関してご説明します。
国際連合には以下6つの主要機関があり、それぞれ様々な活動を行っています。
- 総会
- 安全保障理事会
- 経済社会理事会
- 信託統治理事会
- 国際司法裁判所
- 事務局
主要機関の1つが安全保障理事会(安保理)であり、国際の平和と安全の維持について主要な責任を有しています。
安全保障理事会の具体的な活動、審議内容は以下の通りです。
- 国連平和維持活動(PKO)の設立
- 多国籍軍の承認
- テロ対策、不拡散に関する措置の促進
- 制裁措置の決定
参考:安保理 国際連合広報センター
(3)安全保障理事会を構成する常任理事国と非常任理事国について
先ほどご紹介した安全保障理事会について、参加国は以下2つのグループに分かれており、
- 常任理事国:5か国(任期の定めがない)
- 非常任理事国:10か国(任期2年、再選不可)
合わせて計15の国で構成されています。
今までご説明した通り、日本は常任理事国に含まれていません。
ただし、非常任理事国には国連加盟国中最多となる11回選ばれたことがあり、安全保障理事会と深く関わりがあると言えます。
非常任理事国は地域別に議席数が割り振られており、現行の制度では以下の通りです。
- アフリカグループ:3議席
- アジア・太平洋グループ:2議席
- 東欧グループ:1議席
- ラテンアメリカ・カリブグループ:2議席
- 西欧・その他グループ:2議席
なお、2021年時点の非常任理事国は任期別に以下のとおりです。
- エストニア、ニジェール、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チュニジア、ベトナム(2021年末まで)
- インド、アイルランド、ケニア、メキシコ、ノルウェー(2022年末まで)
このように、常任理事国と非常任理事国では、任期の有無に違いがあります。
常任理事国が恒久的に理事国である一方、非常任理事国は全加盟国による秘密投票によって選出されるプロセスが必要で、かつ選ばれたとしても再選不可、毎年半数が改選されています。
もう一つの大きな違いは「拒否権」の有無です。
通常、決議の採択は多数決の原則で進められますが、常任理事国が1か国でも反対票を投じた場合は、決議が採択されません。
これは常任理事国だけが持つ権利ですので、大きな違いと言えるでしょう。
詳しくは「3、常任理事国が有する拒否権について」でご説明します。
参考:国際連合広報センター
2、安全保障理事会の審議
続いて、審議の進め方についてご説明します。
安全保障理事会には一定の会期があるわけではないので、必要に応じて随時開催される形をとります。
公開で行われる公式会合の他に、非公式協議も開催されています。
以下で詳しく見ていきましょう。
(1)公式会合
公式会合は傍聴可能な会議です。
国連本部内の安保理議場で行い、原則として公開されているので議事録も取られます。
そのため他の国も参加できますが、あくまで傍聴のみで、決議の際に投票権はありません。
なお、席順はアルファベット順で決まっています。
会合における議長も同様に、英語のアルファベット順に月番で決まっています。
また、会議の公用語としては
- 英語
- フランス語
- ロシア語
- スペイン語
- 中国語
- アラビア語
の6か国語が認められています。
(2)非公式協議
非公式協議は、名前の通り非公開で行われる協議のため、議事録などの記録は残りません。
参考:外務省
3、常任理事国が有する拒否権について

先ほど少し触れましたが、常任理事国と非常任理事国の大きな違いは「拒否権」の有無です。
拒否権は、常任理事国である5か国のみが持っています。
通常、決議の採択は多数決の原則で進められ、安全保障理事会に参加している15か国が一票ずつ投票して決めます。
ただし採択の条件は、決議の内容によって以下の通り少し異なります。
- 手続き事項に関する決定:9か国以上の賛成投票が必要
- 実質事項に関する決定:常任理事国の全ての同意投票を含む、9か国以上の賛成投票が必要
ここで、拒否権の話に戻りますが、常任理事国が1か国でも拒否権を行使した(=反対票を投じた)場合は、決議が採択されません。
たとえ他の14か国が全て賛成投票していたとしても、決議が採択されないのです。
それだけ大きな権利を持っているということが言えます。
ただし常任理事国が棄権または欠席した場合には、拒否権を行使した(=反対票を投じた)とはみなされません。
つまり公に賛成票を投じなくとも、棄権または欠席をすることで、拒否権を行使することなく決議の採択に影響しないような対応は行えるということです。
なお、過去には実際に拒否権を行使した常任理事国もありますが、各国から反発が上がった事例があります。
強い権利である拒否権の有無も含めて、安全保障理事会全体の改革の必要性に関して議論が続いています。
4、国際連合安全保障理事会決議の事例
最後に、安全保障理事会の審議において、実際に決議が行われた事例をご紹介します。
2017年11月、北朝鮮が新型大陸間弾道ミサイル(ICBM)を発射するという事態が起きました。
これを受けて安全保障理事会は同年12月22日、北朝鮮に対する追加制裁決議案を全会一致で採択したのです。
具体的な追加制裁の内容は以下の通りです。
- 北朝鮮への石油精製品輸出を、年間50万バレルに制限する
- 北朝鮮の海外出稼ぎ労働者に対して、24か月以内の本国送還を求める
既存の経済制裁を加味すると、今回の輸出品目の制限は、北朝鮮への輸出がほぼ全て禁止になったと言える事態でした。
北朝鮮経済が大きな影響を受けることは必至であり、安全保障理事会において大きな意味を持つ決議となった事例の一つです。
5、現在の常任理事国の動向
各常任理事国の現在の動向を以下に示します。
アメリカ: バイデン政権下で、多国間主義への回帰を掲げて国連への関与を強化しています。ただし、国内の分断や新興国との競争が、アメリカのリーダーシップに影響を及ぼしています。また、近年では新興技術の規制や気候変動問題など、新しい国際課題への対応が求められています。トランプ政権下ではより一国主義的な傾向になり、国連における活動を軽視する可能性があります。
中国: 一帯一路構想を通じて地政学的影響力を拡大していますが、台湾や南シナ海問題をめぐる緊張が続いており、国際社会との対立が顕著です。また、中国の経済成長が減速している中で、その影響力をいかに維持するかが課題となっています。
ロシア: ウクライナ侵攻による国際的な孤立が進む中でも、エネルギー資源を武器に一定の影響力を保持しています。しかし、その行動は国際的な批判を招いており、信頼性の低下が避けられません。
フランスとイギリス: フランスは気候変動対策やアフリカでの活動に注力し、EU内でのリーダーシップを追求しています。一方、イギリスはEU離脱後、新たな国際的役割を模索しています。これらの国々は共に国際課題への対応を強化しており、常任理事国としての役割を再定義しようとしています。
これらの動向は、常任理事国制度の現状とその限界について再考を促す契機となっています。特に、各国が直面する課題は、国連の意思決定構造全体の再評価を求める声を強めています。
6、日本の常任理事国入りの背景と課題
日本は長年、常任理事国入りを目指しています。その理由の一つは、国際社会における影響力の向上です。日本は国連分担金の主要拠出国であり、国際平和維持活動(PKO)や人道援助においても積極的に貢献してきました。これらの実績は、日本が常任理事国としてふさわしい候補であることを示しています。
さらに、日本は平和憲法に基づく平和的な外交政策を掲げ、戦後一貫して軍事的拡張を避けてきました。このような立場は、国際社会において日本を信頼できるパートナーとして位置づける要因の一つとなっています。
しかし、日本の常任理事国入りにはいくつかの課題があります。まず、国連憲章の改正が必要であり、これは常任理事国全員の同意と国連加盟国の3分の2以上の賛成を必要とします。この手続きの複雑さが、大きな障壁となっています。また、中国や韓国をはじめとする近隣諸国からの反対も根強く、これが地域的な合意形成を困難にしています。
さらに、国際社会全体で常任理事国制度そのものの改革が議論されています。冷戦後の世界情勢の変化に伴い、新興国の台頭や多極化した国際秩序に対応するため、制度の見直しが求められています。このような状況の中で、日本が常任理事国入りを実現するためには、他国との協力を深め、信頼を構築することが不可欠です。
まとめ
今回は常任理事国の概要に加えて、審議の進め方や拒否権について開設しました。
常任理事国は恒久的に安全保障理事会に参加する立場であり、拒否権という強い権利を有します。日本は非常任理事国という立場ではあるものの、多くの任期を務めていることから常任理事国と同様に、世界の平和と安定のために議論を尽くしています。
『ポリスタ』で公開されている安全保障関連の動画
『ポリスタ』は、自民党議員と若手の有識者が政策に関するディスカッションや対談を行うクロストーク番組です。是非以下の動画もチェックしてみてください。


















