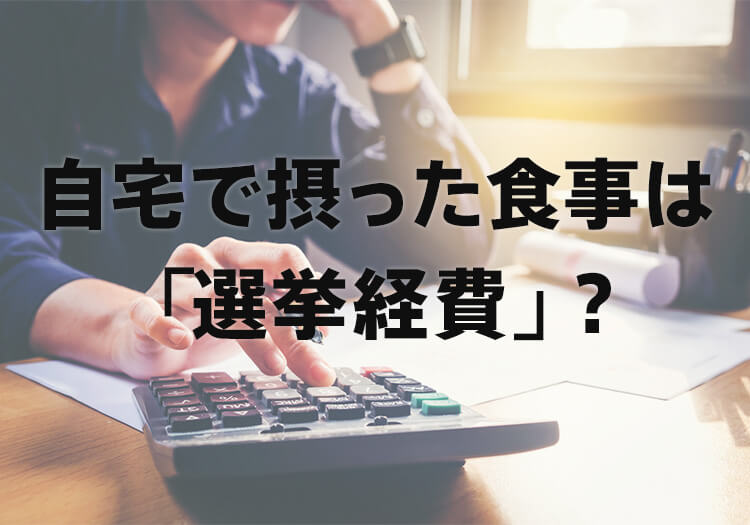 投稿日2020.12.7
投稿日2020.12.7
自宅で摂った食事は「選挙経費」? 最高裁までもつれ込んだ大騒動
当選の恩人への感謝の気持ちが仇に
選挙期間中、運動員が自宅で食べる食事に対して選挙費用を支払っても良いものか。
当時、衆議院議員選挙法第97条では、選挙事務長や選挙委員が、選挙運動の際に必要とした飲食物や、遠方への出張の際の交通費・宿泊費などに関しては、選挙費用として認められると定められていまし...
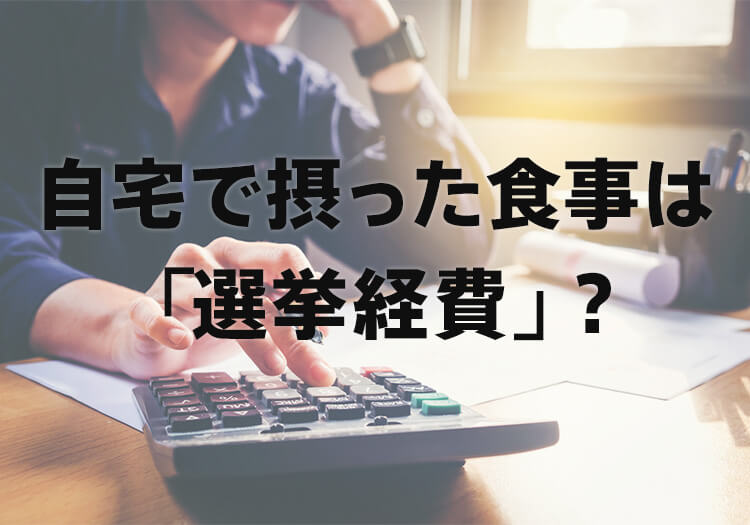 投稿日2020.12.7
投稿日2020.12.7
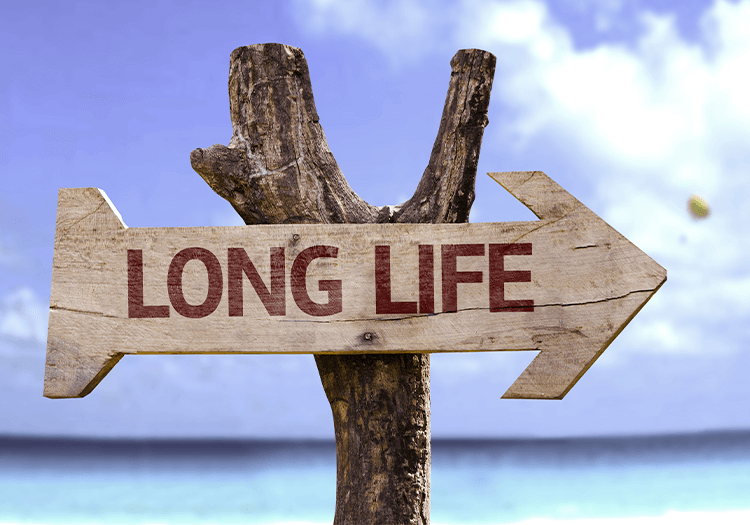 投稿日2020.12.7
投稿日2020.12.7
 投稿日2020.12.7
投稿日2020.12.7
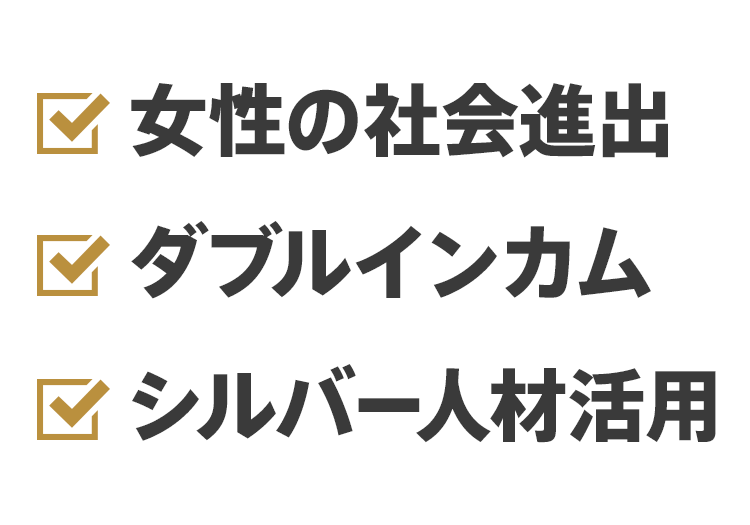 投稿日2020.12.7
投稿日2020.12.7
 投稿日2020.12.7
投稿日2020.12.7
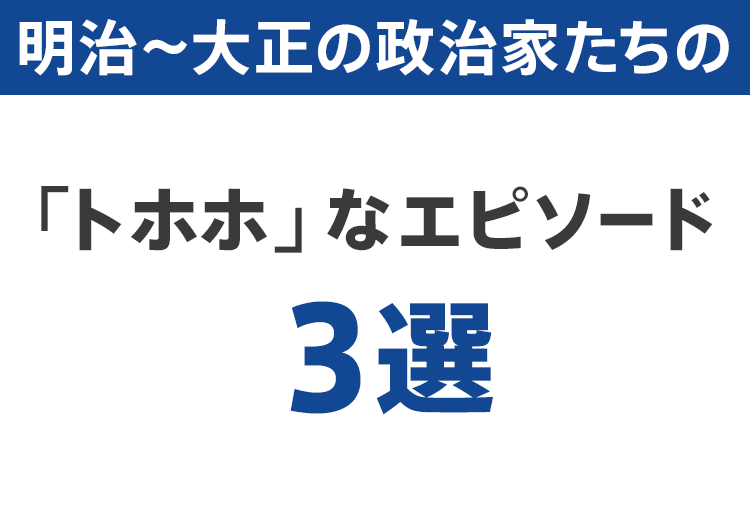 投稿日2020.12.7
投稿日2020.12.7
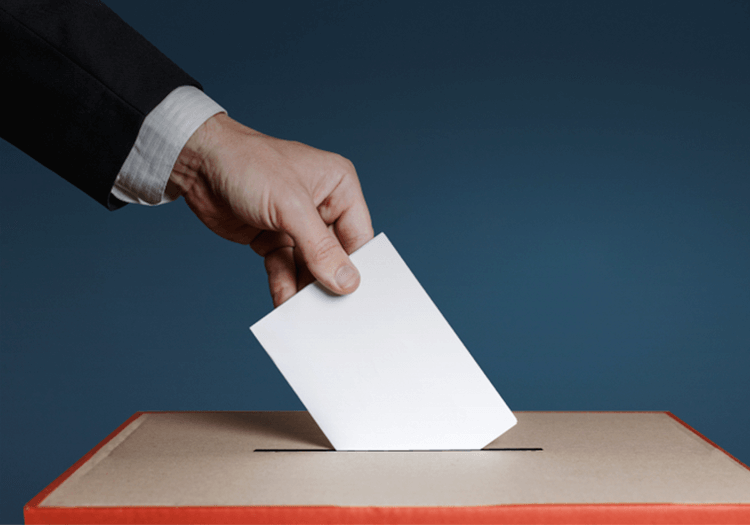 投稿日2020.12.7
投稿日2020.12.7
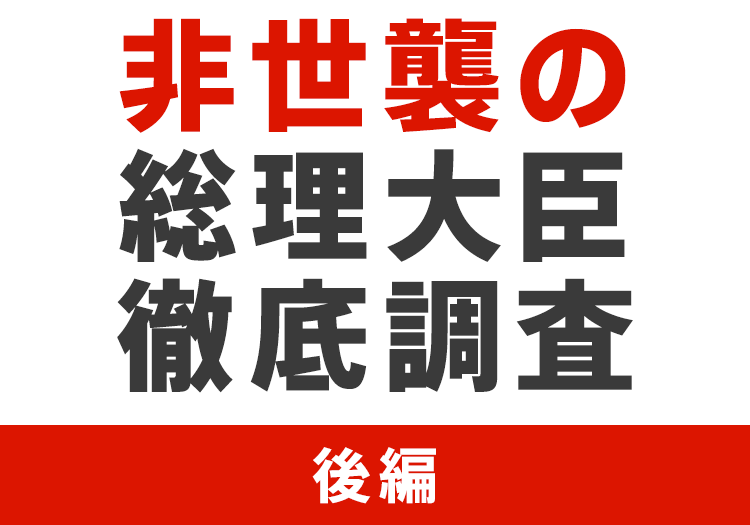 投稿日2020.12.7
投稿日2020.12.7
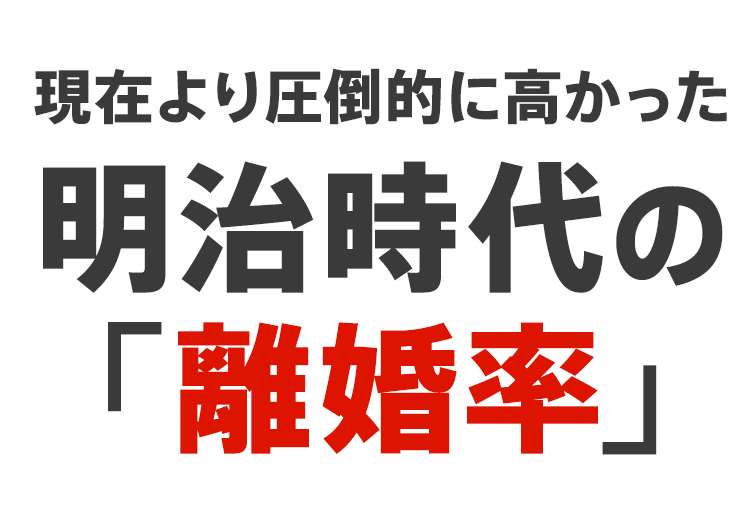 投稿日2020.12.7
投稿日2020.12.7
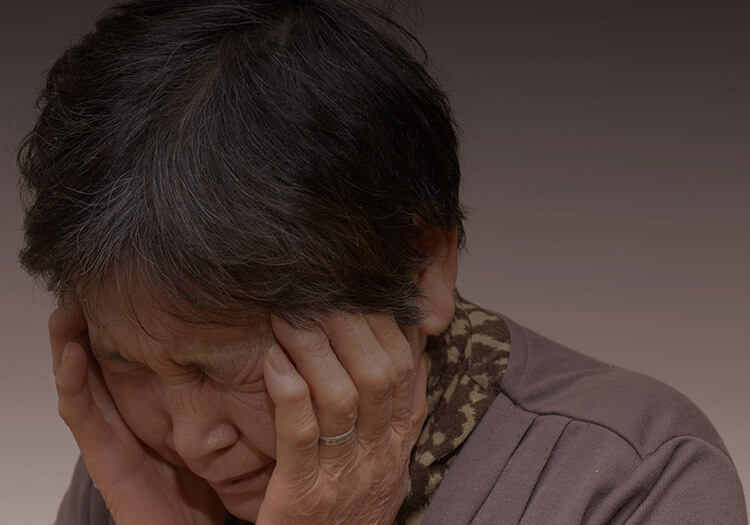 投稿日2020.12.7
投稿日2020.12.7